『蜘蛛の糸』の読書感想文を書く皆さん、こんにちは。
芥川龍之介の不朽の名作『蜘蛛の糸』は、仏教的な世界観を背景にした短編小説で、多くの教科書にも掲載されている児童文学の傑作。
カンダタという罪人が蜘蛛の糸を伝って地獄から脱出しようとする物語は、人間の利己心と救済というテーマを深く描いています。
この記事では、読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいる私が『蜘蛛の糸』の読書感想文の書き方から例文まで、小学生・中学生・高校生それぞれのレベルに合わせて詳しく解説していきます。
書き出しから題名の付け方まで、コピペやパクリに頼らない独自の感想文が書けるよう、具体的なタイトル例も含めてサポートしていきますよ。
『蜘蛛の糸』の読書感想文で触れたい3つの要点
『蜘蛛の糸』の読書感想文を書く前に、まずは物語の核となる重要なポイントを整理しておきましょう。
以下の3つの要点について、読みながら「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切です。
- カンダタの利己心が引き起こした悲劇
- 小さな善行の持つ力と意味
- お釈迦様の視点から見た人間の姿
これらの要点について考えを深めることで、単なるあらすじの紹介ではなく、自分なりの解釈や感想を含んだ読書感想文を書くことができるんです。
メモを取る時は「なぜそう感じたのか」「自分の体験と重なる部分はあるか」「現代社会とのつながりは何か」といった視点で書き留めておくと良いでしょう。
感想文では「どう感じたか」が最も重要な要素になるため、物語を読みながら自分の心に浮かんだ素直な気持ちを大切にしてくださいね。
カンダタの利己心が引き起こした悲劇
『蜘蛛の糸』で最も印象的な場面は、カンダタが
「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼって来た。下りろ。下りろ。」
■引用:芥川龍之介 蜘蛛の糸(青空文庫)
と叫ぶシーンでしょう。
彼は地獄から抜け出すチャンスを目前にしながら、他の罪人たちを蹴落とそうとした瞬間、糸が切れて再び地獄に落ちてしまいます。
この場面からは、人間の利己心がいかに自分自身を破滅に導くかが描かれています。
カンダタの行動を読んで、皆さんはどのような感情を抱いたでしょうか。
「当然の結果だ」と感じる人もいれば、「人間らしい反応だ」と共感する人もいるかもしれません。
また、「もし自分だったらどうしただろう」と考えることも重要です。
現代社会でも、競争が激しい環境では他人を蹴落とそうとする心理が働くことがあります。
受験競争や就職活動など、身近な例と結びつけて考えることで、より深い感想を書くことができるでしょう。
カンダタの選択について自分なりの考えを持つことが、説得力のある読書感想文につながりますよ。
小さな善行の持つ力と意味
物語の冒頭で、カンダタがかつて小さな蜘蛛を助けたという善行が紹介されています。
これは取るに足らないような些細な行為でしたが、お釈迦様の目に留まり、救いのきっかけとなりました。
この設定から、どんなに小さな善行でも大きな意味を持つ可能性があることが示されています。
日常生活の中で、皆さんも人知れず小さな親切をしたことがあるのではないでしょうか。
道端で転んだ人を助けたり、落とし物を届けたり、友達の悩みを聞いてあげたり。
そんな経験を思い出しながら、善行の意味について考えてみてください。
一方で、善行を行う動機についても考察する価値があります。
カンダタは蜘蛛を助けた時、後に救われることを期待していたわけではありませんでした。
純粋な気持ちから出た行動だったからこそ、お釈迦様に認められたのかもしれません。
現代社会では「見返りを求めない善行」の難しさも感じられます。
SNSで善行を自慢したり、評価を求めたりする風潮もある中で、真の善行とは何かを考えることは意義深いでしょう。
お釈迦様の視点から見た人間の姿
『蜘蛛の糸』では、お釈迦様が極楽から地獄を見下ろすという構図が印象的です。
物語の最後、カンダタが再び地獄に落ちた後、お釈迦様は悲しそうな顔をして立ち去ります。
この描写から、慈悲深い存在でありながらも、人間の愚かさに対する深い悲しみが伝わってきます。
お釈迦様の心情について考えることで、人間という存在の本質に迫ることができるでしょう。
また、極楽と地獄という対比的な世界観も重要な要素です。
蓮の花が美しく咲く極楽の平安と、苦しみに満ちた地獄の対比は、人間の行いがもたらす結果を象徴しています。
現代的な視点から見ると、これらの世界観をどのように解釈するかも興味深いテーマです。
宗教的な教えとしてではなく、人間の心の在り方を表現した比喩として捉えることもできます。
お釈迦様の視点に立って人間社会を見た時、どのような問題が見えてくるでしょうか。
環境問題や格差社会など、現代の課題と重ね合わせて考えることで、作品の普遍的なメッセージを感じ取れるはずです。
※『蜘蛛の糸』の意味や芥川龍之介が伝えたいことはこちらで解説しています。


『蜘蛛の糸』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】カンダタから学んだ大切なこと
私は『蜘蛛の糸』を読んで、人の心の怖さと優しさについて深く考えさせられた。
この物語の主人公カンダタは、たくさんの悪いことをして地獄に落ちた人だった。
でも、昔に小さな蜘蛛を助けたことがあったので、お釈迦様が蜘蛛の糸を垂らして助けようとしてくれた。
最初にこの場面を読んだ時、私は「どんなに小さな優しさでも、きっと誰かが見ていてくれるんだな」と思った。
学校で友達が困っている時に手伝ったり、道で転んだ人を起こしたりする時も、誰も見ていないように思えるけれど、そんな小さな親切も大切なんだと感じた。
けれど、カンダタは糸を登っている途中で、他の人たちが後から付いてくるのを見て「この糸は俺のものだ」と叫んでしまった。
その瞬間、糸が切れてカンダタは再び地獄に落ちてしまった。
この場面を読んだ時、私は胸がドキドキした。
カンダタの気持ちも分かるような気がしたからだ。
自分だけが助かりたいと思うのは、人間なら当然の気持ちかもしれない。
でも、その気持ちが強すぎると、せっかくのチャンスまで失ってしまうのだと学んだ。
私も普段の生活で、友達と遊んでいる時に自分だけが得をしようとしたり、テストの答えを教えてほしいと言われた時に断ったりすることがある。
そんな時は、カンダタのことを思い出して、みんなで幸せになれる方法を考えるようにしたいと思った。
お釈迦様が最後に悲しそうな顔をして立ち去ったのも印象的だった。
きっと、カンダタが他の人たちと一緒に登ってくれば良かったのにと思っていたのだろう。
私たちも、困っている人がいたら一緒に頑張ろうという気持ちを持つことが大切だと感じた。
『蜘蛛の糸』を読んで、小さな優しさの大切さと、みんなで助け合うことの重要性を学んだ。
これから友達や家族と接する時は、自分だけではなく、みんなが幸せになれるように行動していきたいと思う。
『蜘蛛の糸』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】利己心という名の罠
芥川龍之介の『蜘蛛の糸』を読んで、私は人間の心の複雑さと、利己心がもたらす悲劇について深く考えさせられた。
この作品は短い物語でありながら、人間の本質を鋭く描いた名作だと感じる。
物語の主人公カンダタは、殺人や放火を繰り返した重罪人だが、たった一度だけ小さな蜘蛛を助けたことがあった。
その善行を思い出したお釈迦様が、彼を救うために蜘蛛の糸を垂らすという設定に、私は最初驚きを感じた。
なぜなら、カンダタの悪行と比べれば、蜘蛛を助けた行為はあまりにも小さなものだからだ。
しかし、この設定から学べることは大きい。
どんなに些細な善行でも、それは確実に価値のあるものだということだ。
現代社会では、大きな成果や目に見える結果ばかりが評価されがちだが、人知れず行う小さな親切にも意味があるのだと改めて思った。
私も日常生活で、電車で席を譲ったり、落とし物を届けたりすることがあるが、それらの行為も決して無駄ではないのだろう。
しかし、物語の核心は、カンダタが糸を登る途中で見せた利己的な行動にある。
他の罪人たちが後から登ってくるのを見て、「この蜘蛛の糸は己のものだぞ」と叫んだ瞬間、糸は切れてしまった。
この場面を読んだ時、私は複雑な感情を抱いた。
一方では、カンダタの行動は理解できる部分もある。
必死に登ってきた糸が重みで切れそうになれば、誰でも不安になるだろう。
自分だけでも助かりたいと思うのは、人間の本能的な反応かもしれない。
しかし、まさにその利己的な心こそが、せっかくの救いの機会を台無しにしてしまったのだ。
この点について考えると、現代社会の様々な問題とも重なって見える。
受験競争では、他人を蹴落としてでも自分が合格したいと思う人がいる。
就職活動でも、同じような心理が働くことがある。
しかし、『蜘蛛の糸』が教えてくれるのは、そうした利己的な行動は自分自身を破滅に導くということだ。
もしカンダタが他の罪人たちを受け入れ、一緒に登ろうと声をかけていたらどうだったろう。
もしかすると、全員が救われていたかもしれない。
協力し合うことで、より大きな力を生み出せるという可能性もあったのではないだろうか。
お釈迦様の描写も印象深い。
物語の最後、カンダタが再び地獄に落ちた後、お釈迦様は悲しそうな顔をして立ち去る。
この表現から、慈悲深い存在でありながらも、人間の愚かさに対する深い失望が感じられる。
お釈迦様は決してカンダタを罰したわけではない。
カンダタ自身の選択が、自らの運命を決めたのだ。
この点から、私たちの日々の選択がいかに重要かということを学んだ。
『蜘蛛の糸』を読んで、私は自分の行動を見直すきっかけを得た。
友人関係でも、家族との関係でも、つい自分の利益を優先してしまうことがある。
しかし、この作品が教えてくれるのは、真の幸せは他者と分かち合うことから生まれるということだ。
利己心という罠に陥らず、周りの人たちと協力し合いながら生きていきたいと思う。
小さな蜘蛛を助けたカンダタの優しさを忘れずに、日々の生活の中で善行を積み重ねていく。
そして、その善行を独り占めするのではなく、みんなで幸せになれる道を選んでいきたい。
『蜘蛛の糸』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】救済と利己心―現代に響く普遍的メッセージ
『蜘蛛の糸』を読んで、人間の本質に関する深い洞察に驚かされた。
表面的には宗教的な救済の物語だが、その奥には現代社会にも通じる普遍的なテーマが隠されているのだ。
殺人や放火を繰り返した重罪人でありながら、たった一度だけ小さな蜘蛛を助けたというカンダタの設定は、人間の複雑さを象徴している。
完全に善良な人間も、完全に悪い人間も存在しないという現実を表現しているのだろう。
私たちの日常でも、完璧な人間などいない。
誰もが長所と短所を併せ持ち、時には善行を行い、時には過ちを犯す。
カンダタという極端な設定を通して、芥川はそうした人間の二面性を描き出したのではないだろうか。
蜘蛛を助けた行為がお釈迦様の目に留まり、救いのきっかけとなる展開には、小さな善行の持つ力強さを感じた。
現代社会ではSNSで善行をアピールしたり、見返りを求めたりする風潮もある中で、カンダタの純粋な動機から出た行動は、真の善行とは何かを考えさせてくれる。
私も日常生活で、電車で席を譲ったり、ごみを拾ったりするが、それらの行為も決して無意味ではないのだと改めて確信した。
しかし、物語の真の核心は、カンダタが見せた利己的な行動とその結果にある。
蜘蛛の糸を登る途中で、他の罪人たちが後から付いてくるのを見て、「この蜘蛛の糸は己のものだぞ」と叫んだ瞬間、糸は切れて彼は再び地獄に落ちてしまう。
この場面のカンダタの反応は理解できる部分もある。
必死の思いで登ってきた糸が、大勢の重みで切れそうになれば、誰でも恐怖を感じるだろう。
自分だけでも助かりたいと思うのは、生存本能として自然な反応かもしれない。
しかし、まさにその利己的な心こそが、せっかくの救いの機会を台無しにしてしまったのだ。
この描写は、現代社会の様々な問題と重なって見える。
受験競争では、限られた合格枠を巡って激しい競争が繰り広げられる。
就職活動でも、他人を蹴落とそうとする心理が働くことがある。
経済活動においても、利益の独占といった問題が存在する。
『蜘蛛の糸』が示すのは、そうした利己的な行動は自分自身を破滅に導くということだ。
もしカンダタが他の罪人たちを受け入れ、「みんなで一緒に登ろう」と声をかけていたらどうだったろう。
糸の強度が問題なら、順番に登るという方法もあったかもしれない。
協力し合うことで、より良い解決策を見つけられた可能性もある。
この点から考えると、現代社会においても競争だけではなく、協力の重要性が見えてくる。
環境問題や貧困問題など、地球規模の課題は一国だけでは解決できない。
個人レベルでも、友人関係や家族関係において、お互いを思いやる心が不可欠だ。
お釈迦様の描写も深い意味を持っている。
物語の最後、カンダタが再び地獄に落ちた後、お釈迦様は悲しそうな顔をして立ち去る。
この表現から、慈悲深い存在でありながらも、人間の愚かさに対する深い失望が感じられる。
重要なのは、糸を切ったのはカンダタ自身の利己的な行動だったことだろう。
これは、人間の運命は他者によって決められるものではなく、自分自身の選択によって決まるということを示している。
現代的な視点から見ると、これは個人の責任と自由意志の問題とも言える。
私たちは日々様々な選択を迫られるが、その一つ一つが将来の自分を形作っていく。
カンダタの例は極端だが、小さな選択の積み重ねが人生を大きく左右することは確かだ。
極楽と地獄という対比的な世界観も、現代的に解釈することができる。
これらを文字通りの来世の世界として捉えるのではなく、人間の心の状態を表現した比喩として見ることもできる。
利己的な心に支配された状態を地獄、他者への思いやりに満ちた状態を極楽と考えれば、この物語は現代人にとっても身近なテーマとなる。
『蜘蛛の糸』を読んで、私は自分の日常的な行動を見直すきっかけを得た。
友人関係でも、部活動でも、家族との関係でも、つい自分の利益を優先してしまうことがある。
しかし、この作品が教えてくれるのは、真の幸せは他者と分かち合うことから生まれるということだ。
競争社会の中で生きる私たちにとって、利己心を完全に排除することは難しいかもしれない。
しかし、その利己心をコントロールし、他者への思いやりを忘れずに生きることは可能だ。
小さな蜘蛛を助けたカンダタの優しさを見習い、日々の生活の中で善行を積み重ねていく。
そして、その善行を独り占めするのではなく、周りの人たちと共に幸せになれる道を選んでいきたい。
『蜘蛛の糸』が発表されてから長い年月が経つが、この作品が持つメッセージは色褪せることがない。
むしろ、個人主義が進む現代社会においてこそ、この物語が投げかける問いは重要性を増していると感じる。
利己心という罠に陥ることなく、他者との連帯を大切にしながら生きていくことの重要性を、この作品は私たちに教えてくれるのだ。
振り返り
この記事では、『蜘蛛の糸』の読書感想文について、小学生から高校生まで各段階に応じた書き方と例文をご紹介してきました。
芥川龍之介の短編小説が持つ深いメッセージを理解し、それを自分なりの言葉で表現することで、説得力のある感想文を書くことができるでしょう。
重要なのは、物語のあらすじを説明するだけではなく、「自分がどう感じたか」を中心に書くことです。
カンダタの利己心、小さな善行の意味、お釈迦様の視点という3つの要点を参考にしながら、皆さん自身の体験や考えと結びつけて感想を深めてください。
コピペやパクリに頼ることなく、自分だけの独創的な読書感想文を書くことで、きっと先生や審査員の心に響く作品を完成させることができるはずです。
皆さんの感想文が素晴らしい作品に仕上がることを心から願っています。
※『蜘蛛の糸』のあらすじや面白い点を解説した記事はこちらです。


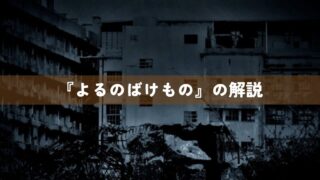



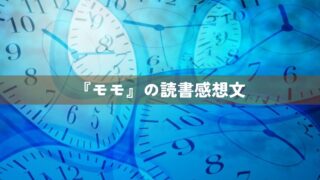
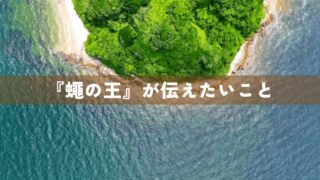



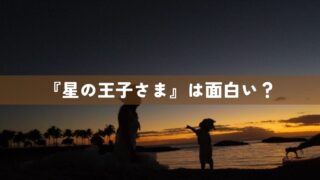

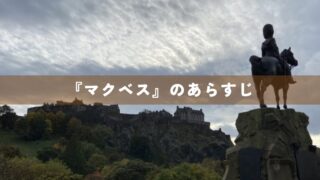





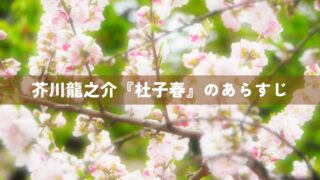
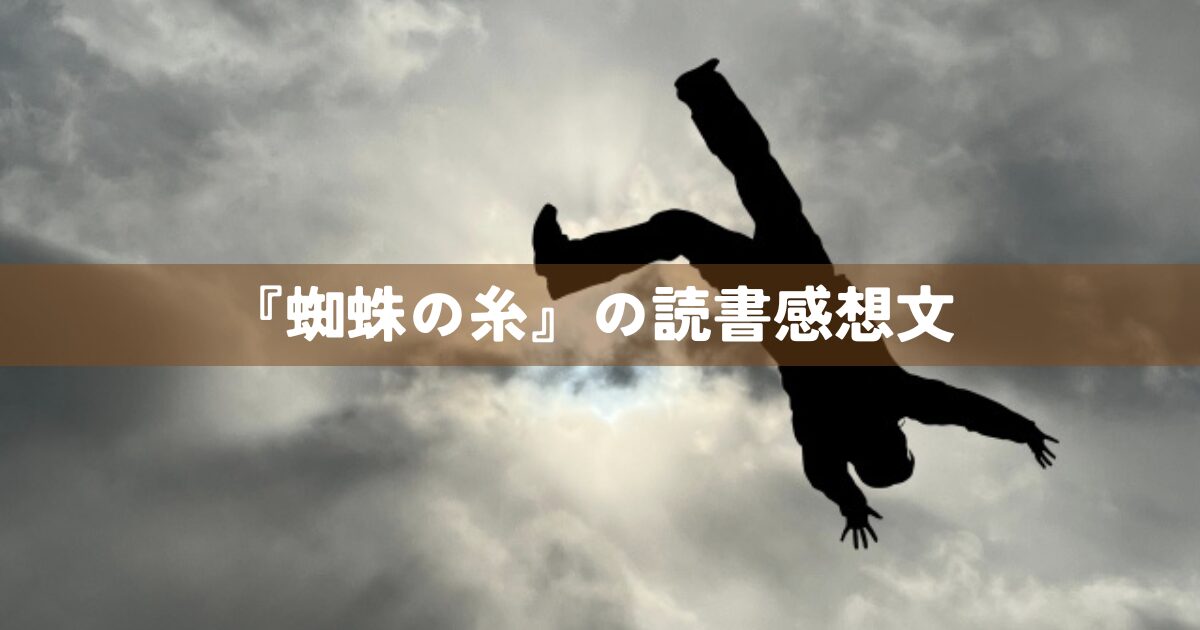
コメント