『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
田沢五月さんが書いたこの作品は、2011年の東日本大震災で被災した岩手県山田町の大沢小学校の子どもたちが、避難所となった学校で「海よ光れ!」という学校新聞を発行し続けて被災者を励ました実話を描いたノンフィクション作品ですね。
2024年には青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にも選ばれた、素晴らしい本です。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
パクリではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、テンプレートに頼らずしっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文で書くべき3つのポイント
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文を書くときに、必ず触れておきたいポイントが3つあります。
- 震災の中で「自分にできること」を考えて行動した子どもたちの姿
- 困難な状況でも希望を失わずに人を励まそうとする心の強さ
- ノンフィクション作品だからこそ伝わる現実の重みと感動
これらのポイントについて、皆さんが「どう感じたか」をメモしておくことが大切ですよ。
感想文は単なるあらすじの羅列ではなく、皆さん自身の心の動きや考えを表現するものですから、まずは自分の気持ちをしっかりと整理することから始めましょう。
メモするときは、「なぜそう感じたのか」「自分だったらどうするか」「今の自分の生活とどう関係するか」という視点で書き留めてみてください。
この「どう感じたか」が感想文の核となる部分だからです。
それでは、これらの3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
震災の中で「自分にできること」を考えて行動した子どもたちの姿
この作品の一番の見どころは、大沢小学校の子どもたちが震災という未曾有の困難に直面したとき、「自分たちに何ができるだろう」と真剣に考えて行動に移したことです。
避難所となった学校で生活する中で、子どもたちは掃除や水汲み、肩もみ隊の結成など、できることから始めていきました。
そして何より素晴らしいのが、学校新聞「海よ光れ!」を発行し続けて、被災者やボランティアの人たちを励まし続けたことですね。
皆さんはこの子どもたちの行動をどう感じたでしょうか。
同じ年頃の子どもたちが、大人でも心が折れそうになる状況で、誰かのために何かをしようと考えて実行に移す姿は本当に心を打ちます。
「もし自分がその立場だったら」ということを考えながら読むと、より深い感想が書けるはずです。
また、この子どもたちの行動から「主体性」や「思いやり」の大切さについても考えてみてください。
誰かに言われたからではなく、自分たちで考えて行動することの意味や、困っている人のことを思う優しい心について、皆さん自身の体験や考えと重ね合わせて感想をまとめてみましょう。
困難な状況でも希望を失わずに人を励まそうとする心の強さ
「海よ光れ!」というタイトルには、荒れた海が再び光り輝くことを願う子どもたちの強い希望が込められています。
津波で大きな被害を受けた海の町で、子どもたちがこのような前向きな言葉を選んだことに、私たちは何を感じるでしょうか。
普通なら絶望してしまいそうな状況でも、希望を捨てずに未来を信じる心の強さがここに表れていますね。
しかも子どもたちは、自分たちのためだけでなく、周りの大人たちや被災者の人たちを元気づけようとしていました。
自分だって辛いはずなのに、誰かを励まそうとする優しさと強さには本当に感動します。
皆さんも今まで生きてきた中で、辛いことや悲しいことがあったと思います。
そのときにどうやって乗り越えたか、誰かに支えてもらった経験はあるか、逆に誰かを励ました経験はあるか、そんなことを思い出しながら読むと、この子どもたちの行動がより深く心に響くでしょう。
また、新聞に書かれた感謝の言葉や励ましのメッセージが、実際に多くの人の心を温めたという事実も重要なポイントです。
言葉の持つ力、人とのつながりの大切さについても考えてみてください。
ノンフィクション作品だからこそ伝わる現実の重みと感動
この作品がフィクション(作り話)ではなく、実際に起こったことを記録したノンフィクションだということが、読む人に特別な感動を与えます。
実際に新聞の写真が掲載されていたり、当時の子どもたちの声が収録されていたりすることで、リアリティがまったく違いますね。
東日本大震災から10年以上が経った今、この出来事を知らない世代も増えています。
でもこの本を読むことで、震災がどんなものだったのか、その中で人々がどう支え合ったのかを知ることができます。
皆さんにとって、この実話を読むことはどんな意味があったでしょうか。
震災という現実の重さを感じると同時に、人間の強さや優しさも感じられたのではないでしょうか。
また、2020年に大沢小学校が閉校になったという事実も、時の流れと地域の変化を物語っています。
でも子どもたちが残した「海よ光れ!」の精神は、この本を通じて多くの人に受け継がれていくのです。
過去の出来事を風化させず、未来に語り継いでいくことの大切さについても考えてみてください。
皆さん自身が、この本を読んで何を学び、それをどう生かしていきたいと思ったかを書くことで、とても深みのある感想文になるはずです。
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文のテンプレート
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文のテンプレートをご用意しました。
ステップ1~6までの項目に自分が感じたことを当てはめていくだけで、十分な文字数がある立派な読書感想文が完成しますよ。
ステップ1:作品紹介を書く
- この本のタイトルと作者名を書く
- 本のテーマや内容を簡単に説明する
(例)「『海よ光れ!』は、東日本大震災の被災地で、子どもたちが学校新聞を作りながら被災者を励ました実話を描いたノンフィクションです。」
ステップ2:心に残ったことを書く
- 作品の中で特に印象に残った場面や出来事を1~2つ具体的に挙げる
- そこで感じたことや学んだことを書く
(例)「子どもたちが困難な避難所生活の中でも、明るく元気に新聞作りを続けていた姿が心に残りました。」
ステップ3:「自分にできること」を考える
- 震災の中で子どもたちが見つけた「自分にできること」について触れる
- 自分も困った時や周りが苦しい時にできることを考え、書く
(例)「私もみんなのために何かできることを考えて、助け合いの気持ちを大切にしたいです。」
ステップ4:希望や励ましの心の強さについて書く
- 困難な状況でも希望を失わず、人を励まそうとする気持ちの大切さを述べる
- その気持ちから学んだことを書く
(例)「どんなにつらくても、希望を持ち続けることや、周りの人を励ますことの強さに感動しました。」
ステップ5:ノンフィクションの重みと感動について書く
- 実話だからこそ伝わる現実の重さやリアルさについて書く
- 読んで感じた感動や考えさせられたことを書く
(例)「ノンフィクションだからこそ、震災の苦しさや子どもたちの勇気がリアルに伝わり、胸に深く響きました。」
ステップ6:まとめと自分の今後の決意を書く
- 本を読んで感じたこと、学んだことのまとめを書く
- 自分がこれからどうしたいか、どんな人になりたいかを書く
(例)「この本を読んで、人を思いやる気持ちや希望を忘れずに頑張る大切さを学びました。私も困っている人を助けられる人になりたいです。」
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】希望の光を灯した子どもたち
私は『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』を読んで、同じ小学生の仲間たちのすごさに心を打たれた。
2011年の東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県山田町で、大沢小学校の子どもたちが学校新聞『海よ光れ!』を作り続け、被災者を励ましたという。
一番感動したのは、子どもたちが「自分たちに何ができるか」を真剣に考えて行動したことだ。避難所となった学校で掃除や水汲み、肩もみ隊を作って大人たちを助けた。そして何より素晴らしいのは、新聞を作り続けたことである。
私だったら、家が津波で流され学校で避難生活をすることになったら、きっと泣いてばかりいたと思う。でも大沢小学校の子どもたちは違った。辛い状況でも希望を捨てず、周りの人を元気づけようとしたのだ。
『海よ光れ!』というタイトルにも、荒れた海が再び輝いてほしいという強い願いが込められている。この前向きな気持ちに、私は深く感動した。
また、この本がノンフィクション、つまり実話だということも重要だ。実際の新聞や子どもたちの言葉が載っているから、その時の気持ちや様子がリアルに伝わってくる。私は震災をテレビや教科書で学んだことはあったが、同世代の子どもたちがどんな体験をしたのかは知らなかった。この本を読んで、震災の大変さと同時に人と人とのつながりの温かさも学ぶことができた。
子どもたちの感謝の言葉や励ましのメッセージが、多くの人の心を支えたのだと思う。私も普段の生活で困っている友達に声をかけたり、家族に感謝を伝えたりしたい。小さなことでも誰かのためになるはずだ。
大沢小学校は2020年に閉校になったが、「海よ光れ!」の精神はこの本を読む私たちに受け継がれている。災害はいつ起こるか分からないが、大切なのは希望を失わず支え合うことだと学んだ。
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』は、同世代の子どもたちの強さと優しさを教えてくれる大切な本である。
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】言葉の力で希望を紡いだ子どもたち
私は『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』を読んで、同じ世代の子どもたちが見せた勇気と思いやりに深く感動した。
この作品は、2011年の東日本大震災で被災した岩手県山田町の大沢小学校で、子どもたちが学校新聞「海よ光れ!」を発行し続け、被災者を励ました実話を記録したノンフィクションである。
作者の田沢五月さんが丹念に取材して書き上げたこの本から、私は震災の現実と人間の強さについて多くのことを学んだ。
特に心を打たれたのは、子どもたちが困難な状況の中で「自分たちに何ができるか」を真剣に考え、行動に移したことだ。避難所となった学校での生活は、電気も水道も満足に使えない過酷なものだった。それでも掃除や水汲み、肩もみ隊など、できることから始めていた。そして何より素晴らしいのは、学校新聞を継続的に発行したことだ。この新聞は情報伝達にとどまらず、感謝や励ましの言葉を届ける大切な役割を果たした。
私は普段、困ったことがあると大人に頼ってしまう。しかしこの子どもたちは自ら考え、周りの人のために行動した。その主体性と責任感には本当に頭が下がる思いだった。
また印象的だったのは、絶望的な状況でも希望を失わず、むしろ人を励まそうとした心の強さである。「海よ光れ!」という題には、荒れた海が再び輝くことを願う気持ちが込められていた。悲しみや怒りに支配されてもおかしくない中で、なぜ前向きな言葉を選べたのか。それは個人の悲しみを越えて地域全体を思いやっていたからだろう。自分たちも被災者でありながら、他の人や支援者を思う優しさに心を打たれた。
私は中学生になり少しずつ社会を考えるようになったが、まだ自分のことで精一杯だ。この子どもたちの行動を知り、もっと広い視野で「自分にできること」を考えたいと思った。
この本がノンフィクションであることの意味も大きい。実際の新聞の写真や子どもたちの声が収録されており、その場の雰囲気が生々しく伝わってくる。震災についてはテレビで見た程度で、同世代の子どもが何を体験し、どう感じたかは知らなかった。この本を通して、震災は今も人々の心に刻まれている現実だと実感した。
さらに考えさせられたのは言葉の力である。子どもたちのメッセージは多くの人を勇気づけた。文字として残された言葉は時を越えて届き続ける。普段の何気ない言葉にも人を励ます力があるのだと改めて感じることになった。
最後に、この本は防災や地域のつながりについても考える機会を与えてくれた。大沢小学校は2020年に閉校したが、子どもたちが作った新聞とそこに込められた思いは永遠に残る。災害は予告なく訪れるが、必要なのは物質的備えだけでなく、心の備えと人との絆である。普段から家族や地域との関係を大切にし、助け合える関係を築くことの大切さを学んだ。
『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』は震災の記録であると同時に、人間の強さと優しさを描いた感動的な作品である。この本を読んで、私も困難に負けない強い心と、周りを思いやる優しい心を持ち続けたいと強く思った。
振り返り
ここまで『海よ光れ!3・11被災者を励ました学校新聞』の読書感想文について詳しく解説してきました。
この作品は、震災という困難な状況の中で子どもたちが見せた勇気と思いやりを描いた、とても読み応えのある本でしたね。
読書感想文を書くときは、まず自分がどう感じたかを素直に受け止めることが大切です。
そして今回お話しした3つのポイントを参考にしながら、皆さん自身の体験や考えと重ね合わせて書いてみてください。
パクリやコピペに頼るのではなく、皆さんの心に響いた部分を大切にして、自分の言葉で表現することが一番重要ですよ。
きっと皆さんにも、心に残る素晴らしい感想文が書けるはずです。がんばってくださいね。
※『海よ光れ』のあらすじはこちらでご紹介しています。



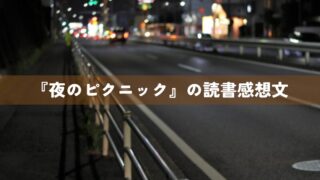

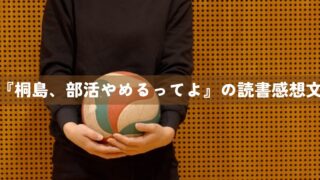

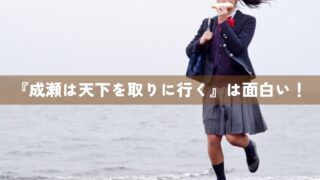





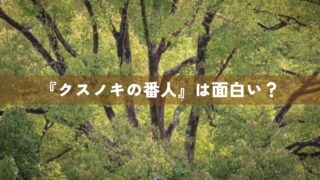

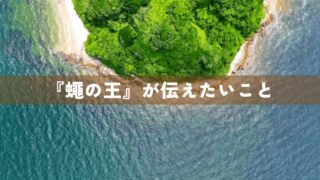



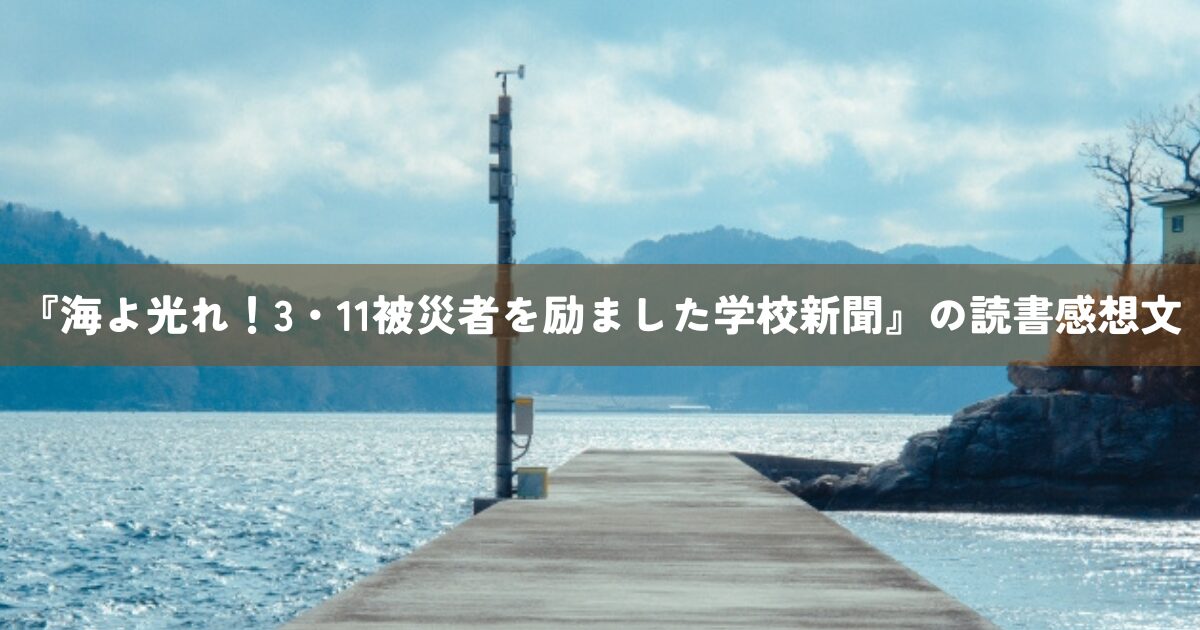
コメント