『そして、バトンは渡された』の読書感想文を書こうと考えている学生のみなさん、こんにちは。
この記事では、2019年本屋大賞を受賞した瀬尾まいこさんの感動作『そして、バトンは渡された』の読書感想文の書き方について、詳しく解説していきますよ。
『そして、バトンは渡された』は、血のつながらない家族の間で育った17歳の少女・森宮優子の成長を描いた物語です。
3人の父親と2人の母親に育てられた主人公が、家族の愛情を「バトン」として受け継いでいく姿は、多くの読者の心を打ちました。
この記事では、読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く際の要点から具体的な例文まで、中学生・高校生の皆さんが参考にできる内容を提供していきます。
書き方のコツや題名の付け方、書き出しの工夫まで、コピペではない自分だけのオリジナルな感想文が書けるようサポートしますね。
『そして、バトンは渡された』の読書感想文で触れたい3つの要点
『そして、バトンは渡された』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要な要点が3つあります。
これらの要点について、読みながら「自分だったらどう感じるか」「どの場面が印象に残ったか」をメモしておくと、感想文を書く時にとても役立ちますよ。
メモの取り方としては、付箋を使って気になった場面にマークを付けたり、ノートに「ページ数と一緒に感じたこと」を書き留めておくのがおすすめです。
なぜ「どう感じたか」が大切なのかというと、感想文は作品の解説ではなく、あなた自身の心の動きを表現する文章だからですね。
まずは以下の3つの要点を確認してみましょう。
- 「バトン」に込められた象徴的な意味
- 血のつながりを超えた家族の愛情の形
- 主人公・優子の心の成長プロセス
それでは、それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
「バトン」に込められた象徴的な意味
この物語で最も重要なキーワードが「バトン」です。
タイトルにもなっているこの言葉は、単なる運動会の道具ではありません。
物語全体を通して、愛情や想い、人生そのものが次の人へと受け継がれていく様子を表現した深い意味を持っています。
優子は幼い頃から様々な親に育てられてきましたが、それぞれの親が彼女に何かしらの「バトン」を渡していきます。
料理の技術だったり、音楽への愛情だったり、生きる姿勢だったり。
形は違えど、すべてが「愛情という名のバトン」なのです。
あなたも家族や周りの人から何かしらの「バトン」を受け取った経験があるはずです。
そのエピソードと重ね合わせて感想を書くと、より深みのある文章になりますよ。
どんな小さなことでも構いません。
お母さんから教わった料理のコツや、お父さんから聞いた人生のアドバイスなど、身近な体験を思い出してみてください。
血のつながりを超えた家族愛
優子には3人の父親と2人の母親がいますが、そのすべてが血のつながった家族ではありません。
それでも、どの親も優子を心から愛し、大切に育てていきます。
現代社会では様々な家族の形がありますが、この物語は「家族とは何か」という根本的な問いを投げかけています。
血縁関係がなくても、毎日一緒に過ごし、お互いを思いやる気持ちがあれば、それは立派な家族なのです。
特に印象的なのは、現在の義父である森宮壮介の優子への接し方です。
彼は優子の好きな料理を作り、悩みを聞き、いつも温かく見守っています。
血のつながりがないからこそ、より意識的に愛情を注いでいるのかもしれませんね。
あなた自身の家族関係と比較してみてください。
家族の中で「当たり前」になっている愛情表現について、改めて考えるきっかけになるでしょう。
また、友達や先生など、血のつながりはないけれど家族のように大切な人がいれば、その関係についても触れてみると良いですね。
主人公・優子の心の成長プロセス
物語は優子の17歳の日常から始まりますが、彼女の過去の体験も丁寧に描かれています。
何度も環境が変わる中で、優子がどのように自分のアイデンティティを築いてきたかが重要なポイントです。
高校生活では、ピアノの演奏や友人関係、恋愛など、等身大の悩みを抱えながらも前向きに歩んでいきます。
特に卒業式でのピアノ伴奏のエピソードは、優子の成長を象徴する場面として印象的です。
最初は技術不足に悩みながらも、周りの人の支えと自分の努力で乗り越えていく姿は、多くの読者の心を打ちます。
あなたも学校生活の中で、何かに挑戦した経験があるでしょう。
部活動でも勉強でも、最初はうまくいかなかったけれど、努力と周りのサポートで成長できた体験があるはずです。
そのような個人的な体験と優子の成長を重ね合わせることで、感想文により深みと説得力が生まれます。
また、優子が様々な困難を乗り越える過程で身につけた強さや優しさについて、自分だったらどう感じるか、どう行動するかを考えてみてください。
※『そして、バトンは渡された』で作者の瀬尾まいこさんが伝えたいことはこちらで考察しています。

『そして、バトンは渡された』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】つながりの温かさ
『そして、バトンは渡された』を読み終えた時、私の心には今まで感じたことのない温かさが広がっていた。主人公の森宮優子は、私と変わらない年齢なのに、3人の父親と2人の母親に育てられるという複雑な家庭環境で生きている。最初は「かわいそう」だと思ったが、読み進めるうちに、優子は私よりもずっと豊かな愛情に包まれて育っていることに気づいた。
この物語で一番印象に残ったのは「バトン」という言葉の使い方だった。普通は運動会のリレーを思い浮かべるが、この小説では愛情や思い出、人生そのものがバトンとして次の人に渡されていく。優子が親たちから受け取ったのは、料理の作り方や音楽への愛、困った時の対処法など、形は違ってもすべてが愛情という名のバトンだと理解した。
私も家族から様々なバトンを受け取っていることに気がついた。母から教わった掃除のやり方、父から聞いた「努力は必ず報われる」という言葉、祖母から受け継いだ手芸の技術など、当たり前だと思っていたことが実は大切なバトンだった。優子の物語を通し、家族からもらった多くのものに改めて感謝の気持ちを持った。
また、血のつながりがない家族でも、深い愛情で結ばれることができるのだと知って驚いた。義父の森宮壮介は血がつながらなくても優子を心から大切にしている。好きな料理を作り、悩みを聞き、まるで本当の父親のようだ。むしろ、血がつながっていないからこそ、より意識的に愛情を注いでいるのかもしれない。
私の家族は父と母と私の3人で、いわゆる普通の家族だと思っていた。でも優子の家族を見て、家族にはいろいろな形があっていいのだと知った。大切なのは血のつながりではなく、お互いを思いやる気持ちなのだ。友達にも複雑な家庭環境の子がいるが、その子のことを今まで以上に理解できそうだ。
高校でのピアノ伴奏の場面では、優子の頑張りに心を打たれた。最初は不安だったが、練習を重ね、周囲の支えもあって最後までやり遂げた。私も去年の文化祭でクラスの出し物の責任者を任され、自信がなく不安だったが、みんなの協力で成功させることができた。優子の気持ちがよく分かる。
この小説を読んで、私は「家族」という言葉の意味を深く考えるようになった。血のつながりがあってもなくても、お互いを大切に思えばそれは立派な家族だ。そして人は生きている間に様々な人から愛情というバトンを受け取り、やがて自分が誰かに渡していく。その温かいつながりの中で成長していくのだと思う。
これからの人生で、私も優子のように様々なバトンを受け取り、いつかは渡す側になるだろう。その時は、家族や友達、先生から受け取った温かいバトンを、しっかりと次の人に渡していきたい。『そして、バトンは渡された』は、そんな大切なことを教えてくれた素晴らしい小説だった。
『そして、バトンは渡された』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】愛情のリレー
『そして、バトンは渡された』を読み終えた時、私の心は静かな感動に包まれていた。瀬尾まいこが描いた17歳の森宮優子の物語は、家族とは何か、愛情とはどのように受け継がれていくものなのかという根本的な問いを私に投げかけた。この小説は単なる家族小説ではない。人生そのものが愛情のリレーであることを教えてくれる、深い洞察に満ちた作品だった。
物語の中で最も印象的だったのは、「バトン」という言葉に込められた象徴的な意味である。タイトルにもなっているこの「バトン」は、運動会で使う道具ではなく、人から人へと受け継がれる愛情や思い、人生の知恵そのものを表している。優子は幼い頃から3人の父親と2人の母親に育てられてきたが、それぞれの親が彼女に異なる形のバトンを渡していく。実父からは音楽への愛を、継母からは自由に生きることの大切さを、そして現在の義父からは日常生活の温かさを受け取った。
私はこの描写を読みながら、自分自身が今まで受け取ってきたバトンについて考えた。母から教わった「人に迷惑をかけないこと」という価値観、父から学んだ「最後まで諦めない姿勢」、祖母から受け継いだ「手作りの温かさ」など、意識していなかった多くのものが実はバトンだったのだと気づかされた。これらのバトンは形としては見えないが、確実に私の人格や行動の基盤となっている。
また、血のつながりを超えた家族の愛情の描き方に深く心を打たれた。優子の現在の義父である森宮壮介は、血縁関係がないにもかかわらず、優子を実の娘のように大切にしている。彼が優子の好きな料理を作り、進路について真剣に話し合い、時には厳しく叱る姿は、血のつながりなど関係なく、真の家族愛とは何かを示している。血縁があっても愛情が薄い家族がある一方で、血のつながりがなくても深い絆で結ばれた家族が存在することを、この小説は教えてくれる。
現代社会では、離婚や再婚により複雑な家族構成を持つ家庭が増えている。私の周りにも、ステップファミリーの友人がいるが、この小説を読むまでは、そうした家庭環境を「複雑で大変そう」としか捉えていなかった。しかし、優子の家族を見ていると、血のつながりの有無に関係なく、お互いを思いやる気持ちがあれば、それは十分に家族として機能することが分かる。むしろ、意識的に愛情を注ぐからこそ、より深い絆が生まれるのかもしれない。
主人公・優子の心の成長プロセスも、この小説の重要な要素である。彼女は複雑な家庭環境にありながら、決して被害者意識を持たない。それどころか、様々な親から受け取った愛情を糧にして、自分らしい人生を歩もうとしている。特に印象的だったのは、高校の卒業式でピアノ伴奏を務める場面である。最初は技術不足で不安に感じていた優子が、練習を重ね、周りの支えもあって最後まで演奏をやり遂げる姿は、彼女の精神的な成長を象徴している。
私もこの場面を読みながら、高校1年の時に生徒会選挙に立候補した経験を思い出した。人前で話すことが苦手だった私は、演説の準備に何日もかかり、当日も緊張で手が震えていた。しかし、クラスの友人たちが応援してくれたおかげで、最後まで自分の思いを伝えることができた。優子のピアノ演奏と私の演説は規模も内容も全く違うが、不安を乗り越えて成長する気持ちは同じだった。この共感により、優子の心境がよく理解できた。
さらに、この小説を読んで気づいたのは、愛情のバトンは一方通行ではないということである。優子は様々な親からバトンを受け取るだけでなく、彼女自身も周りの人にバトンを渡している。友人への思いやり、義父への感謝の気持ち、そして将来に向けた希望など、優子が持つ温かさは確実に周りの人に影響を与えている。これこそが、人生が愛情のリレーである証拠だと思う。
私たちは生きている間に、意識的であれ無意識的であれ、常に誰かからバトンを受け取り、誰かにバトンを渡している。家族から受け取る愛情はもちろんのこと、友人からの励まし、先生からの指導、時には見知らぬ人からの小さな親切も、すべてがバトンなのかもしれない。そして、私たちはそれらのバトンを自分なりに解釈し、新たな形にして次の人に渡していく。
この小説を読んで、私は自分の将来について改めて考えるようになった。将来、結婚して家庭を持った時、私はどのようなバトンを家族に渡すことができるだろうか。また、職業を通じて社会とどのような関わりを持ち、どのような影響を与えることができるだろうか。優子のように、受け取った愛情を大切にし、それを次の世代に確実に渡していける大人になりたいと思う。
『そして、バトンは渡された』は、家族の形の多様性を描きながら、愛情の普遍性を教えてくれる作品である。血のつながりの有無に関わらず、人と人とのつながりの中で私たちは成長し、そして次の世代にバトンを渡していく。この温かい循環こそが、人生の本質なのかもしれない。私もこの小説から受け取ったバトンを、いつか誰かに渡せる日を楽しみにしている。
振り返り
今回の記事では、『そして、バトンは渡された』の読書感想文の書き方について詳しく解説してきました。
この小説は血のつながりを超えた家族愛と、愛情が人から人へと受け継がれていく様子を美しく描いた作品です。
記事で紹介した3つの要点を意識しながら、あなた自身の体験や感情と重ね合わせることで、オリジナリティあふれる感想文が完成するでしょう。
中学生向けと高校生向けの例文を参考にしながら、自分なりの題名や書き出しを工夫してみてください。
コピペではなく、あなただけの感想文を書くことで、読書の喜びもより深く味わえるはずです。
きっとあなたにも素晴らしい読書感想文が書けますよ。頑張ってくださいね。
※『そして、バトンは渡された』の読書感想文の作成に便利なあらすじや読みどころ、ストーリーの疑問点の解説などはこちらの記事が参考なります。



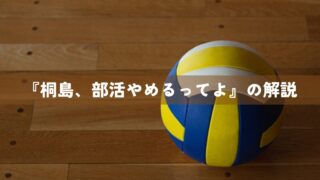





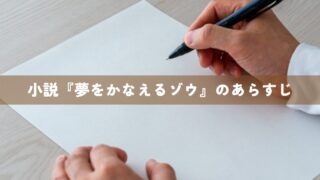



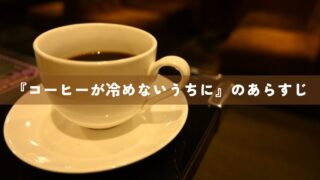






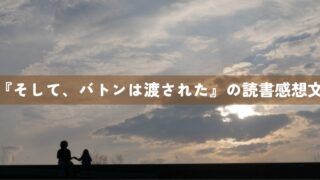

コメント