『神様のカルテ』の読書感想文を書く予定の学生の皆さん、今回はこの素晴らしい小説の感想文の書き方について詳しく解説していきますよ。
『神様のカルテ』は夏川草介さんが描く感動的な小説で、第10回小学館文庫小説賞を受賞し、2010年には本屋大賞2位にも輝いた名作。
信州松本の地方病院で働く内科医・栗原一止の物語は、医療現場のリアルな描写と人間ドラマが絶妙に組み合わさった作品となっています。
この記事では、年間100冊以上の本を読む私が『神様のカルテ』の読書感想文を書く際の要点から、中学生・高校生向けの例文まで、コピペではない本格的な書き方を丁寧にお教えします。
書き出しから題名の付け方まで、感想文作成のすべてをカバーしていますよ。
『神様のカルテ』の読書感想文で触れたい3つの要点
『神様のカルテ』で読書感想文を書く際に、ぜひ触れてほしい重要な要点が3つあります。
これらの要点について「自分はどう感じたか」をメモしながら読み進めることで、感想文の土台となる材料を集めることができますよ。
メモの方法は簡単です。
読書中に心に響いた場面や考えさせられた出来事があったら、付箋に「ここで私は○○だと感じた」「主人公の行動を見て△△について考えた」といった具合に、素直な気持ちを書き留めておくんです。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は小説の内容を説明するレポートではなく、あなた自身の心の動きを表現する文章だからです。
以下の3つの要点を意識して読み進めてくださいね。
- 医師としての葛藤と使命感
- 人間関係と支え合いの重要性
- 命の重みと生きる意味の考察
それでは、それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
医師としての葛藤と使命感
主人公の栗原一止は、地方病院の内科医として多忙な日々を送っています。
大学病院からの誘いを受けながらも、目の前の患者さんたちとの関わりの中で自分なりの答えを見つけていく姿が描かれているんですね。
一止の葛藤は、単に職場を変えるかどうかという問題ではありません。
最先端の医療技術を追求するか、それとも患者一人ひとりに寄り添う医療を選ぶかという、医師としての根本的な価値観に関わる選択なんです。
この部分を読んでいて、あなたはどんなことを考えましたか?
「仕事に対する情熱とは何か」「自分が将来働く時にはどんな価値観を大切にしたいか」といった点について、自分なりの考えをメモしておくと感想文に活かせるでしょう。
また、一止が患者さんたちと向き合う真摯な姿勢から、責任感や使命感について学んだことがあれば、それも大切な感想の材料になります。
人間関係と支え合いの重要性
物語の中で特に印象深いのが、一止を取り巻く人々との温かい関係性です。
同僚の医師や看護師たち、そして患者さんたちとの交流が、一止の心の支えとなっている様子がていねいに描かれています。
特に安曇さんという癌患者との関係は、医師と患者という枠を超えた人間同士のつながりを感じさせてくれますね。
過酷な医療現場においても、人と人とのつながりがいかに大切かということが伝わってくる場面が多く登場します。
ここで考えてほしいのは、あなた自身の人間関係についてです。
家族や友人、先生方との関係の中で、支え合うことの大切さを実感した経験はありませんか?
また、誰かを支えたり、逆に支えられたりした時の気持ちを思い出しながら読むと、より深い感想が生まれるはずです。
一止と周りの人々の関係を見ていて「こんな関係性を築きたい」「こんな風に人に接したい」と感じたことがあれば、それも立派な感想になりますよ。
命の重みと生きる意味
『神様のカルテ』では、生と死という重いテーマが扱われています。
終末期の患者さんたちとの関わりを通じて、命の尊さや限りある時間の中でどう生きるかということが問いかけられているんです。
安曇さんをはじめとする患者さんたちが、病気と向き合いながらも前向きに生きようとする姿は、読者に深い感動を与えてくれます。
一止もまた、患者さんたちから多くのことを学び、医師としてだけでなく一人の人間として成長していく過程が描かれています。
この部分を読んでいて、あなたは生きることについてどんなことを考えましたか?
「今の自分の生活をどう見直したいか」「大切にしたいものは何か」「将来どんな人生を送りたいか」といった点について、素直な気持ちを整理してみてください。
また、家族や友人の大切さを改めて感じたり、日常の小さな幸せに気づいたりしたエピソードがあれば、それも感想文に盛り込める貴重な材料になります。
物語の中で描かれる生死の場面は決して暗いものではなく、むしろ生きることの素晴らしさを教えてくれる内容になっています。
そこから感じ取ったメッセージを、あなた自身の言葉で表現することが大切ですね。
『神様のカルテ』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】心に響いた医師の物語
『神様のカルテ』を読んで、私は医師という仕事について深く考えさせられた。
主人公の栗原一止は、地方の病院で内科医として働いている。
毎日とても忙しく、時には3日も寝られないこともあるという過酷な環境だ。
それでも一止は、一人ひとりの患者さんと真剣に向き合おうとしている。
私はこれまで、医師は病気を治すことだけを考えている職業だと思っていた。
しかし、この本を読んで、医師も私たちと同じように悩んだり迷ったりしながら働いているのだということがわかった。
一止には大学病院から誘いがある。
最新の医療技術を学べる環境で働くチャンスだ。
でも一止は、今の病院で働き続けるか、大学病院に行くかで悩んでいる。
この葛藤を読んでいて、私は将来の進路について考えた。
私もいつか、自分の進む道を選ばなければならない時が来る。
その時に、一止のように自分が本当に大切だと思うことを基準に決められるだろうか。
特に心に残ったのは、安曇さんという患者さんとの関わりだ。
安曇さんは重い病を患っているおばあちゃんで、看護師さんたちにも愛されている優しい人だ。
一止は安曇さんと話をする中で、医師として、そして一人の人間として多くのことを学んでいく。
私は安曇さんの穏やかで前向きな姿勢に感動した。
病気で苦しい状況にありながらも、周りの人を思いやる気持ちを忘れない。
このような人になりたいと心から思った。
また、一止と同僚の医師や看護師との関係も印象的だった。
お互いを支え合いながら、過酷な仕事を乗り越えていく姿が温かく描かれている。
私の学校生活でも、友達や先生方との関係がとても大切だと改めて感じた。
一人では乗り越えられないことも、みんなで協力すれば乗り越えられることがある。
この本を読んで、私は命の大切さについても深く考えた。
私たちは普段、自分が生きていることを当たり前だと思っている。
でも、命は決して当たり前ではなく、とても貴重なものなのだ。
安曇さんのように、限られた時間の中でも精一杯生きようとする姿を見て、私も今の毎日をもっと大切にしたいと思った。
家族や友達との時間、勉強できる環境、健康でいられることなど、すべてがありがたいことなのだと気づかされた。
『神様のカルテ』は、医療現場の物語でありながら、読者に生きることの意味を問いかける作品でもある。
一止の成長を通じて、私も自分なりの答えを見つけていきたいと思う。
将来、どんな職業に就くとしても、一止のように誠実で思いやりのある人間でありたい。
そして、困っている人がいたら手を差し伸べられるような、優しい心を持ち続けたい。
この本から学んだことを忘れずに、これからの学校生活を送っていこうと思う。
『神様のカルテ』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】医師の葛藤から学んだ人生の選択
私が『神様のカルテ』を手に取ったきっかけは、将来的に医療関係の仕事に就きたいと考えているからだった。
少しでも医療の知識が得られればいいと考えたからだ。
しかし、実際に読み進めていくうちに、この作品は単なる医療現場の描写を超えた、人生そのものについて考えさせられる物語であることがわかった。
主人公の栗原一止は、信州松本の地方病院で内科医として働いている。
彼の日常は想像を絶する忙しさで、「24時間365日」という看板のもと、3日も寝ずに働くことが珍しくない過酷な環境だ。
それでも一止は、専門外の診療も含めて幅広く患者に対応し、一人ひとりと真剣に向き合おうとしている。
私は一止の姿を見ていて、職業に対する責任感とは何かということを深く考えた。
私たち高校生は将来の進路を決める重要な時期にある。
大学受験や就職活動を控えて、多くの選択肢の中から自分の道を選ばなければならない。
一止が大学病院からの誘いを受けて悩む姿は、まさに私たちが直面している問題と重なって見えた。
最先端の医療技術を学べる大学病院と、患者との距離が近い地方病院。
どちらにもそれぞれの価値があり、どちらを選ぶかによって一止の人生は大きく変わってしまう。
私は一止の葛藤を通じて、人生の選択において何を基準にすべきかを考えさせられた。
世間的な評価や待遇の良さだけで判断するのではなく、自分が本当に大切だと思う価値観に従って選択することの重要性に気づけた気がする。
特に印象深かったのは、安曇さんという末期の患者との関わりである。
安曇さんは残念ながら「手遅れ」の状態でありながら、優しく穏やかで看護師たちからも愛されている。
大学病院では「手遅れ」の患者は受け入れてもらえないが、地方病院では最期まで患者に寄り添う。
この対比を通じて、医療における技術的な治療と人間的なケアの両方の大切さが描かれている。
私は安曇さんとのやり取りを読んでいて、生きることの意味について深く考えさせられた。
私たちはつい、長く生きることや成功することばかりを重視してしまいがちだ。
しかし、安曇さんのように限られた時間の中でも、周りの人に愛情を注ぎ、感謝の気持ちを忘れずに生きることの方が、よほど価値があるのではないだろうか。
また、一止を取り巻く人間関係の温かさも心に残った。
同僚の医師や看護師たちとの何気ない会話、お互いを支え合う姿勢、時にはユーモアを交えながら過酷な現実を乗り越えていく強さ。
これらの描写を読んでいて、人と人とのつながりがいかに大切かを実感した。
私たち高校生の生活でも、友人関係や家族との関わりが大きな支えになっている。
受験勉強で疲れた時、悩みがある時、一人では乗り越えられないことも、周りの人たちの支えがあるから頑張れる。
一止と周りの人々の関係を見ていて、私も今の人間関係をもっと大切にしたいと思った。
『神様のカルテ』を読んで最も考えさせられたのは、命の重みについてである。
私たちは普段、自分の命や時間を無限にあるもののように感じている。
明日も明後日も当然やってくるものだと思い込んでいる。
しかし、安曇さんのような患者さんたちと向き合う一止の姿を見ていて、命の有限性と尊さを改めて認識した。
私は今、受験勉強に追われる日々を送っている。
時には勉強が嫌になったり、将来に不安を感じたりすることもある。
でも、この本を読んで、今この瞬間に学べることの幸せ、家族や友人と過ごせる時間の貴重さを感じた。
一止が患者さんたちから学んでいるように、私も日常生活の中で多くのことを学び続けたい。
また、一止の医師としての使命感も印象的だった。
彼は単に病気を治すだけでなく、患者さんの心に寄り添おうとしている。
技術的な治療と人間的なケアの両方を大切にする姿勢から、どんな職業においても専門性と人間性の両方が重要であることを学んだ。
私も将来、どのような道に進むとしても、技術や知識だけでなく、相手の気持ちを理解し、思いやりを持って接することを忘れたくない。
『神様のカルテ』は、医療現場を舞台にしながらも、普遍的な人生のテーマを扱った作品だった。
一止の選択と成長を通じて、私も自分なりの価値観を見つめ直すことができた。
これから大学受験、そしてその先の人生において様々な選択を迫られることになるが、一止のように自分の信念に従って歩んでいきたい。
そして、安曇さんのように、限られた時間の中でも精一杯生き、周りの人に愛情を注げる人間でありたいと思う。
この本は、命と向き合うことの大切さ、そして人と向き合うことの尊さを教えてくれた。
私の人生の指針になるような一冊に出会えたことに感謝したい。
振り返り
今回は『神様のカルテ』の読書感想文の書き方について、要点の整理から具体的な例文まで幅広く解説してきました。
この記事でお伝えした3つの要点を意識しながら、あなた自身の素直な感想を大切に文章を組み立てていけば、きっと心に響く感想文が完成するはずです。
中学生も高校生も、まずは物語を読みながら「自分はどう感じたか」をメモすることから始めてみてくださいね。
あなたの感性で捉えた『神様のカルテ』の魅力を、自分らしい言葉で表現してみましょう。
※『神様のカルテ』の簡単なあらすじはこちらの記事にまとめています。


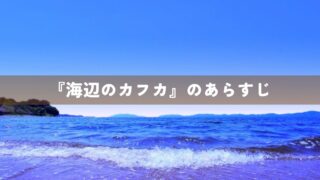

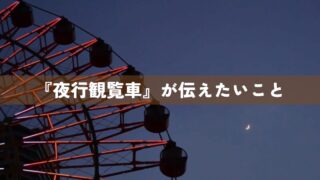




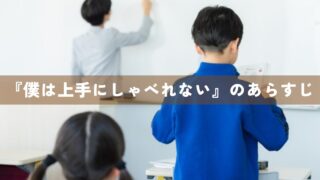



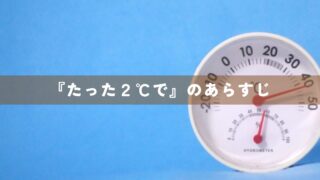

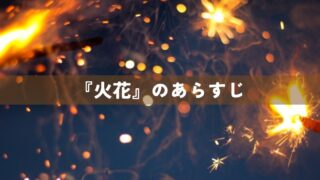


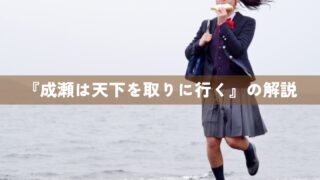

コメント