『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
宮沢賢治の代表作である『セロ弾きのゴーシュ』は、チェロの演奏が下手な主人公ゴーシュが動物たちとの交流を通じて成長していく心温まる物語ですね。
この童話は賢治が亡くなった翌年の1934年に発表された作品で、努力と成長をテーマにした名作として多くの人に愛され続けています。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生・高校生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文で触れたい3つの要点
『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文を書く際に必ず押さえておきたい要点が3つあります。
- 努力と成長の物語
- 音楽の力と表現の重要性
- 自然との調和と謙虚な姿勢
これらの要点について「自分はどう感じたか」をメモしながら読み進めることが大切ですね。
感想文を書く前に付箋やノートを使って、心に残ったシーンや印象的だった場面を書き留めておきましょう。
「なぜそう思ったのか」「自分の体験と似ている部分はないか」といった具体的な理由も一緒にメモしておくと、後で感想文を書くときにとても役立ちますよ。
これら3つの要点を軸にして感想文を構成すると、読み手に伝わりやすい文章が書けるでしょう。
それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
努力と成長の物語
『セロ弾きのゴーシュ』の最も重要なテーマは、主人公ゴーシュの努力と成長の軌跡です。
物語の冒頭でゴーシュは楽団の中でも特に技量が劣るチェリストとして描かれ、楽長から厳しい叱責を受け続けています。
しかし彼は諦めることなく、毎晩遅くまで一人で練習を重ねる姿勢を見せるのです。
この努力の過程で重要なのは、ゴーシュが単に技術的な練習だけでなく、動物たちとの交流を通じて音楽の本質を学んでいく点ですね。
最初は猫に対して乱暴な演奏をしてしまいますが、次第に相手の気持ちに寄り添った演奏ができるようになっていきます。
皆さんも部活動や勉強で思うようにいかない経験があると思いますが、ゴーシュのように継続的な努力を続けることで必ず成長できるというメッセージが込められているのです。
この部分を読んだとき、「自分も諦めずに頑張ろう」と思ったか、それとも「ゴーシュは偉いな」と感じたか、素直な気持ちをメモしておくといいでしょう。
音楽の力と表現の重要性
『セロ弾きのゴーシュ』では音楽が持つ特別な力について深く描かれています。
楽長からゴーシュが指摘されるのは技術的な問題だけでなく、「感情が伝わらない」という表現力の不足でした。
動物たちとの交流を通じて、ゴーシュは音楽が単なる技術ではなく、心を込めて演奏することで相手に何かを伝える手段であることを学んでいきます。
特に印象的なのは、野ネズミの親子との出会いで、ゴーシュの演奏が病気を治す力を持っていることが明らかになる場面ですね。
これは音楽の持つ癒しの力を象徴的に表現したものと考えられます。
また、かっこうとのやり取りでは正確な音程の大切さが描かれ、狸の子との練習ではリズム感の重要性が示されます。
皆さんが音楽を聴いたり演奏したりするとき、どんな気持ちになるか思い出してみてください。
音楽には確かに人の心を動かす不思議な力があることを、この物語は教えてくれているのですね。
自然との調和と謙虚な姿勢
宮沢賢治の作品に共通するテーマとして、自然との調和があげられます。
『セロ弾きのゴーシュ』でも、動物たちがゴーシュの良き教師となることで、自然から学ぶことの大切さが描かれているのです。
最初のゴーシュは動物たちを邪魔者として扱い、特に猫に対しては激しい演奏で苦しめてしまいます。
しかし物語が進むにつれて、動物たちの指摘や要求に耳を傾け、謙虚に学ぶ姿勢を身につけていくわけですね。
かっこうから正確な音程を学び、狸の子からはリズム感を教わり、野ネズミからは音楽の癒しの力を発見します。
この過程でゴーシュは、人間だけでなく自然の生き物たちからも学ぶべきことがあるという謙虚な気持ちを持つようになるのです。
現代の私たちも、自然を大切にし、周りの人や生き物から謙虚に学ぶ姿勢を忘れてはいけないということを、この作品は教えてくれています。
動物が好きな人、自然に触れることが多い人は、特にこの部分に共感できるのではないでしょうか。
皆さんも動物や自然から何かを学んだ経験があれば、それをゴーシュの体験と重ね合わせて感想文に書いてみるといいですね。
※『セロ弾きのゴーシュ』で宮沢賢治が伝えたいことはこちらで考察しています。

『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】ゴーシュから教わったこと
私は『セロ弾きのゴーシュ』を読んで、努力することがとても大切だということを教えられた。
ゴーシュは最初、チェロがとても下手で、楽団の練習では楽長に怒られてばかりだった。でも彼は諦めずに、毎晩遅くまでたった一人で練習を続けることをやめなかった。
私もピアノを習っているが、難しい曲になると嫌になってしまって、つい練習をさぼってしまうことがある。だからゴーシュの姿を思い出すと、自分が頑張り続けることができていないことを反省してしまう。
物語で一番印象に残ったのは、夜中に動物たちが次々とゴーシュの家にやってくる場面だ。最初に来た三毛猫は生意気で、ゴーシュは怒って激しい曲を弾いてしまった。でもその後にやってきたかっこうや狸の子、そして野ネズミの親子に対しては、ゴーシュはだんだんと優しく接するようになっていった。
特に、野ネズミの赤ちゃんの病気をゴーシュの演奏で治すことができた場面は、音楽の持つすごい力を強く感じた。音楽はただ人を楽しませるだけでなく、苦しんでいる人の心を癒やし、元気にしてくれる力もあるのだと知った。私が通っている音楽教室の先生も、「心を込めて演奏することが一番大切」といつも言っている。
ゴーシュも動物たちとの交流を通して、ただ技術を磨くだけでなく、演奏に心を込めることの大切さを学んだのだと思う。最後の音楽会でゴーシュが「印度の虎狩り」を演奏して、観客から大きな拍手をもらった場面は本当に嬉しかった。
努力を続けてきたゴーシュが、ついにまわりから認められた瞬間だったからだ。この物語を読んで、私も諦めずに毎日の練習を大切にしようと思った。
難しい曲でも、ゴーシュのようにコツコツと努力を重ねれば、きっと上達できるはずだ。そして技術だけでなく、聞いてくれる人のことを思い浮かべながら、心を込めて音を届けられるようになりたい。
動物たちがゴーシュの先生になったように、私も家族や友だち、先生など、周りの人たちから色々なことを素直に学び、成長していきたいと思う。
『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】音楽が繋ぐ心の成長
『セロ弾きのゴーシュ』を読んで、私は努力の意味について深く考えさせられた。
主人公のゴーシュは町の活動写真館でチェロを弾いているが、技術が未熟で楽長から厳しく叱責される日々を送っている。
しかし彼は決して諦めることなく、毎晩遅くまで一人で練習を重ねる姿勢を貫いた。
私は部活動でバスケットボールをしているが、思うようにシュートが決まらない時期があった。
その時は練習が嫌になり、時には休んでしまうこともあった。
ゴーシュの姿を見て、継続することの大切さを改めて実感した。
物語の中で最も印象深かったのは、動物たちとゴーシュの交流場面である。
最初に訪れた三毛猫に対して、ゴーシュは苛立ちを露わにし、激しい「印度の虎狩り」を演奏して猫を苦しめてしまう。
この場面は、技術ばかりに囚われて音楽の本質を見失っている状態を表していると感じた。
しかし、その後に訪れるかっこう、狸の子、野ネズミの親子との出会いを通じて、ゴーシュは次第に変化していく。
かっこうとのやり取りでは、正確な音程の重要性を学んだ。
人間の耳には同じように聞こえるかっこうの鳴き声も、実際には微妙な音程の違いがあることを知り、楽器の調律について理解を深めた。
狸の子との練習では、リズム感の大切さを教わった。
小太鼓を叩く狸の子から、「ここのところがぼんやりしてる」と指摘され、自分の演奏の粗さに気づかされた。
そして野ネズミの親子との出会いは、音楽の持つ癒しの力を発見する重要な場面だった。
ゴーシュの演奏で病気の子ネズミが元気になった時、彼は初めて音楽の真の力を実感したのではないだろうか。
この経験を通じて、私は音楽が単なる技術の披露ではなく、人の心に寄り添い、癒しを与える力を持っていることを学んだ。
ゴーシュの成長過程で特に感動したのは、彼の謙虚な姿勢の変化である。
最初は動物たちを邪魔者として扱っていたが、次第に彼らの指摘に耳を傾け、素直に学ぼうとする姿勢を見せるようになった。
これは私たち人間にとっても大切な教訓だと思う。
自分より劣っていると思う相手からも学ぶべきことがあり、謙虚な心を持つことで成長できるのだ。
最後の音楽会でゴーシュが「印度の虎狩り」を演奏し、聴衆から拍手を受ける場面は、彼の成長の集大成として描かれている。
この曲は物語の冒頭で三毛猫を苦しめるために使った曲と同じだが、その演奏の質は全く異なっている。
技術的な向上はもちろん、心を込めて演奏することを覚えたゴーシュの成長が表現されていると感じた。
『セロ弾きのゴーシュ』を読んで、私は努力を続けることの大切さと、周りから謙虚に学ぶ姿勢の重要性を学んだ。
また、何かに打ち込むときは技術だけでなく、心を込めることが最も重要だということも理解できた。
この物語の教えを胸に、これからも部活動や勉強に真摯に取り組んでいきたいと思う。
『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】音楽を通して見つけた真の成長
宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』を読み終えて、私の心には主人公ゴーシュの成長過程が強く残された。この作品は単なる音楽上達の物語ではなく、人間としての内面的成長を描いた深みのある作品だと感じている。
物語の冒頭で描かれるゴーシュの状況は、現代を生きる私たちにも通じる普遍的な悩みを抱えている。技術的な未熟さゆえに周囲から厳しく批判され、努力しているにも関わらず思うような結果が得られない状況は、多くの人が経験する挫折感そのものだ。
私自身も受験勉強において、どれだけ時間をかけて勉強しても成績が伸びない時期があり、ゴーシュの置かれた状況に強く共感した。
楽長から「表現に乏しい」「感情が伝わらない」と指摘される場面は特に印象深い。技術的な練習だけでは到達できない領域があることを示唆しており、真の上達には心の成長が不可欠であることを暗示している。
このような内面的成長が音楽にどう影響を与えるのかという問いは、芸術に限らず、人生全般に通じる普遍的なテーマだと思う。
動物たちとの交流が始まる場面から、物語は本格的な成長の軌跡を描き始める。最初に訪れた三毛猫に対するゴーシュの対応は、彼の内面の粗暴さを露呈している。
「印度の虎狩り」を激しく演奏して猫を苦しめる行為は、技術に対する劣等感や周囲への不満を動物にぶつけているように見えた。この場面で私は、困難に直面した時の人間の醜さを見た気がして、複雑な気持ちになった。
しかし、その後の動物たちとの関わり方の変化が、ゴーシュの人間的成長を物語っている。かっこうとの出会いでは、正確な音程について学ぶだけでなく、相手の立場に立って考えることの重要性を知った。
最初は「鳥に教わるなんて」というプライドが邪魔をしていたが、次第にかっこうの指摘を素直に受け入れるようになる過程は、謙虚さを身につける成長の軌跡として読み取れた。
私も友人からの助言を素直に受け入れられない時があるが、ゴーシュの変化を見て、他者からの意見に耳を傾ける大切さを改めて感じた。
狸の子との練習場面では、リズム感という音楽の基本要素について学ぶと同時に、年下や経験の浅い相手からも学ぶべきことがあるという重要な教訓が描かれている。「ここのところがぼんやりしてる」という狸の子の率直な指摘に対し、ゴーシュが怒ることなく謙虚に受け止める姿勢は、真の成長を示していると思った。
現代社会では年齢や立場にこだわって、目下の人からの意見を軽視してしまうことが多いが、この場面は学びに境界線はないことを教えてくれている。
野ネズミの親子との出会いは、音楽の持つ本当の力を発見する重要な転換点だった。ゴーシュの演奏で病気の子ネズミが元気になるという出来事は、音楽が単なる娯楽や技術の披露ではなく、人の心に寄り添い、癒しを与える力を持っていることを象徴的に表している。
この場面で私は、自分が将来就きたい職業について考えさせられた。どのような仕事であっても、技術的な側面だけでなく、人の心に触れる何かを提供できることが重要なのではないだろうか。
また、自分の持っている力が、誰かの支えになったり、希望になったりする可能性があることを、この物語はやさしく教えてくれている気がした。
物語全体を通じて描かれるゴーシュの変化は、単なる技術向上以上の意味を持っている。最初は自己中心的で、動物たちを邪魔者として扱っていた彼が、次第に相手の気持ちに寄り添い、謙虚に学ぶ姿勢を身につけていく過程は、真の人間的成長を表している。
最終的な音楽会での成功は、この内面的成長があったからこそ達成できたものだと感じた。
「印度の虎狩り」という同じ曲を演奏しながら、物語の冒頭と結末では全く異なる意味を持つことも印象深い。最初は怒りや不満をぶつける手段として使われた曲が、最後には聴衆の心を動かす美しい演奏となる変化は、ゴーシュの内面的変化を音楽で表現した巧妙な構成だと思った。
宮沢賢治が描く自然観も、この作品の重要な要素の一つだ。動物たちがゴーシュの教師となることで、自然と人間が対等な関係で学び合うことの大切さが示されている。
現代社会では人間中心の考え方が強いが、この作品は自然から謙虚に学ぶことの重要性を教えてくれている。
『セロ弾きのゴーシュ』を読んで、私は努力の本当の意味について深く考えさせられた。単に技術を磨くだけでなく、心を成長させ、他者への思いやりを持つことが真の上達につながることを学んだ。
また、学ぶ機会はどこにでもあり、謙虚な姿勢を保つことで人間として成長し続けることができるという大切な教訓も得られた。
この作品から得た気づきを胸に、これからも様々な出会いや経験を通じて成長していきたいと思う。
そして、自分が関わるすべてのことにおいて、ただ結果を求めるのではなく、そこに至る過程や心のあり方を大切にしながら前に進んでいきたい。
振り返り
『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つの要点(努力と成長、音楽の力、自然との調和)を軸にすることで、読み応えのある感想文が書けるはずです。
小学生の皆さんは素直な気持ちを大切に、中学生の皆さんは自分の体験と重ね合わせながら、高校生の皆さんはより深い考察を加えて書いてみてください。
大切なのは、物語のあらすじを説明するのではなく、「自分はどう感じたか」を中心に書くことです。
皆さんも必ず心に響く素晴らしい読書感想文が書けるはずです。
宮沢賢治の温かいメッセージを受け取って、自分なりの言葉で表現してみてくださいね。
※『セロ弾きのゴーシュ』のあらすじはこちらで簡単に短くご紹介しています。

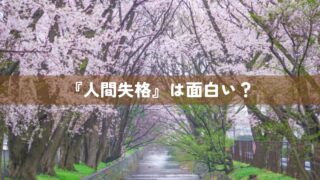





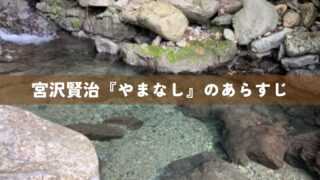



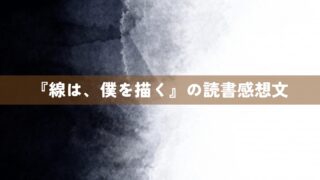

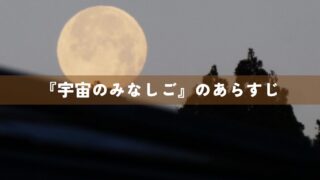

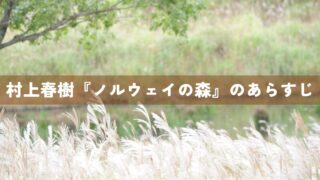


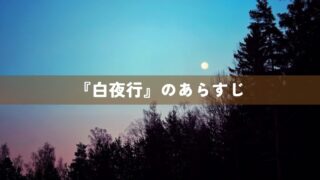

コメント