『よるのばけもの』の読書感想文を書く予定の高校生や中学生のみなさん、こんにちは。
住野よるさんの『よるのばけもの』は、夜になると怪物に変身してしまう主人公の安達と、いじめられながらも笑顔を絶やさないクラスメイト矢野さつきの交流を描いた青春小説。
住野よるさんの3作目となるこの作品は、『君の膵臓をたべたい』で多くの読者の心を掴んだ作家が放つ、深い人間ドラマとなっています。
この記事では、年間100冊以上の本を読む私が『よるのばけもの』の読書感想文の書き方を、例文を交えながら詳しく解説していきます。
題名の付け方や書き出しのコツがばっちり分かるので、コピペしないでも立派な読書感想文が完成しますよ。
『よるのばけもの』の読書感想文で触れたい3つの要点
『よるのばけもの』の読書感想文を書く際には、以下の3つの要点を必ず押さえておきましょう。
- 主人公安達の二面性と自己受容のテーマ
- 矢野さつきの笑顔に隠された真実
- ささやかな勇気が持つ深い意味
これらの要点について読みながら「自分だったらどう感じるか」「どんな経験と重なるか」をメモしておくことが大切です。
感想文は単なるあらすじの紹介ではありません。
あなた自身の心に響いた部分や、共感した場面、疑問に思った点などを記録しておくことで、オリジナリティのある感想文が書けるようになります。
それでは、3つの要点を詳しく見ていきましょう。
主人公安達の二面性と自己受容のテーマ
安達は昼間の「俺」と夜の怪物になった「僕」という、全く異なる二つの人格を持っています。
昼間の安達は、クラスメイトの目を気にして波風を立てないよう振る舞う、ごく普通の高校生です。
一方、夜の怪物になった安達は、誰にも邪魔されずに自由に行動できる本当の自分を表現しています。
この設定は、私たちが日常で経験する「学校や職場での自分」と「家や友人といるときの自分」という使い分けを象徴的に描いたものです。
読者の多くが「本当の自分ってなんだろう」「どっちが本物の自分なんだろう」という疑問を抱いたことがあるでしょう。
安達の葛藤を通して、自分らしさとは何か、社会の中で自分を偽ることの苦しさについて考えを深めてみてください。
あなた自身も、場面によって違う自分を演じた経験があるはずです。
そんな体験と重ね合わせながら、安達の心情に共感した部分をメモしておきましょう。
矢野さつきの笑顔に隠された真実
クラス全員からいじめを受けている矢野さつきは、常ににんまりと笑っている不可解な存在として描かれています。
周囲からは「頭がおかしい」と思われていた彼女の笑顔でしたが、実は恐怖や不安を隠すためのものだったという真実が明かされます。
「怖いと無理に笑っちゃう」という矢野のセリフは、多くの読者の心に深く刺さる部分です。
また、井口をいじめから救うために自分が身代わりになるという矢野の行動は、単なる奇行ではなく他者への深い思いやりの表れでした。
この展開は、見た目だけで人を判断することの危険性や、一人ひとりが抱える事情の複雑さを教えてくれます。
あなたも周りの人を「この人はこういう人だ」と決めつけてしまった経験があるのではないでしょうか。
矢野の真実を知ったとき、どんな気持ちになったか、自分の経験と照らし合わせて考えてみてください。
ささやかな勇気が持つ深い意味
物語の結末で安達が取る行動は、世界を変えるような大きなものではありません。
矢野の挨拶に「おはよう」と返すという、本当に小さな一歩です。
しかし、この行動こそが物語の核心であり、最も勇気のいる選択でした。
安達は夜の「僕」として矢野の秘密を知りながら、昼の「俺」としてその知識を活かすことを決意します。
これは、孤独だった二つの世界をつなぐ、とても意味深い行動です。
日常生活で「正しいことをしたいけれど、周りの目が気になって行動できない」という経験は、多くの人が持っているでしょう。
安達のささやかな勇気について、どう感じたかをしっかりメモしておいてください。
また、あなた自身が似たような場面で勇気を出せた体験や、逆に出せなかった体験があれば、それも感想文に活かせる大切な材料になります。
※『よるのばけもの』を通して作者が伝えたかったことはこちらで考察しています。
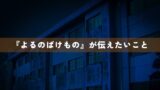
『よるのばけもの』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】本当の自分を見つける勇気
『よるのばけもの』を読んで、私は「本当の自分」について深く考えさせられた。
この物語は、夜になると怪物に変身する安達と、いじめられながらも笑顔を絶やさない矢野さつきの出会いを描いている。
最初、安達の設定を知ったとき、私は非現実的で「ありえない」と思った。
しかし読み進めるうちに、安達の変化を自然なこととして受け入れるようになってしまった。
昼間の安達は「俺」として、クラスのみんなに合わせて生活している。
みんなと同じように振る舞い、目立たないようにして、波風を立てないことを最優先にしている。
でも夜の怪物になった「僕」は、誰にも気を使わずに自由に行動できる。
この二つの人格は、私たちが普段経験していることと同じだと思った。
私も学校では「みんなに嫌われないように」と気を使って、本当に言いたいことを我慢することがある。
でも家では家族に甘えたり、一人のときは好きなことを思いっきりやったりしている。
安達の二面性は、私たちの心の中にある「本音と建前」を表しているのだと感じた。
一番印象に残ったのは、矢野さつきの笑顔の真実だった。
いつもにんまり笑っている彼女を、最初は「変な人」だと思っていた。
なぜいじめられているのに笑っていられるのか、理解できなかった。
しかし「怖いと無理に笑っちゃうの」という矢野の言葉を読んだとき、胸が苦しくなった。
彼女の笑顔は、恐怖や不安を隠すためのものだったのだ。
この場面で私は、人を見た目だけで判断してはいけないということを強く感じた。
私も今まで、クラスメイトのことを「あの子はこういう性格だから」と決めつけていたことがあった。
でも本当は、みんなそれぞれに事情があって、表面に見えない気持ちを抱えているのだと気づいた。
矢野が井口を守るために自分が身代わりになったエピソードも心に残った。
彼女の行動は一見すると理解できないものだったが、実は深い優しさからきていた。
自分が傷つくことを覚悟で、他の人を守ろうとする矢野の勇気に感動した。
そして物語の最後、安達が矢野の挨拶に「おはよう」と返すシーンが一番印象深かった。
たった一言の挨拶だが、これがどれほど勇気のいることかがよく分かった。
クラスのみんなが矢野を無視している中で、一人だけ挨拶を返すのは簡単なことではない。
でも安達は、夜の「僕」として知った矢野の本当の気持ちを、昼の「俺」として受け止めることを選んだ。
この行動は、二つに分かれていた安達の心を一つにつなげる、とても大切な一歩だったと思う。
『よるのばけもの』を読んで、私は自分らしく生きることの難しさと大切さを学んだ。
みんなに合わせることも時には必要だが、本当の自分を見失ってはいけない。
そして困っている人がいたら、小さなことでもいいから手を差し伸べる勇気を持ちたい。
安達のように、ささやかでも意味のある一歩を踏み出せる人になりたいと思った。
『よるのばけもの』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】二つの世界をつなぐ小さな勇気
『よるのばけもの』を読み終えたとき、私の心には今まで感じたことのない複雑な感情が渦巻いていた。
住野よるさんのこの作品は、表面的には「夜に怪物に変身する高校生」という非現実的な設定で始まるが、そこに描かれているのは私たち自身の姿であり、現代社会が抱える深刻な問題だった。
主人公の安達が抱える二面性は、私にとって他人事ではなかった。
昼間の「俺」として振る舞う安達は、クラスメイトの目を気にして、常に周囲に合わせることを優先している。
一方、夜の怪物になった「僕」は、誰にも邪魔されずに本当の自分でいられる時間を過ごしている。
この設定を読んだとき、私は自分自身の日常を思い浮かべずにいられなかった。
学校では「みんなに嫌われないように」「浮かないように」と常に気を使い、本当に言いたいことを飲み込んでしまうことが多い。
でも家に帰れば、家族の前では素の自分でいられるし、一人の時間には好きなことに没頭できる。
安達の二つの人格は、私たちが日常的に経験している「建前の自分」と「本音の自分」の使い分けを、極端な形で表現したものだと感じた。
しかし、この作品の真の価値は、そこに矢野さつきという存在が加わることで発揮される。
最初に矢野のことを知ったとき、私は正直なところ理解に苦しんだ。
なぜいじめられているのに、いつもにんまりと笑っていられるのか。
なぜそんなに空気を読まない行動を取り続けるのか。
私の中にも、矢野を「変わった人」として距離を置こうとする気持ちがあった。
だからこそ、「怖いと無理に笑っちゃうの」という矢野の告白は、私の心を強く揺さぶった。
彼女の笑顔は喜びの表現ではなく、恐怖や不安を隠すためのものだったのだ。
この真実を知ったとき、私は自分の浅はかさを痛感した。
人の表情や行動の裏には、外からは見えない事情や感情があることを、頭では理解していたつもりだった。
しかし実際には、私も周りの人たちを表面的な情報だけで判断していたのだ。
矢野が井口を守るために自分を犠牲にした行動も、私に大きな衝撃を与えた。
井口が矢野の消しゴムを拾ったことで無視の対象になったとき、矢野は井口をビンタして、再び自分にいじめの矛先を向けさせた。
この行動は一見すると理解しがたいものだったが、実は深い思いやりから生まれていた。
自分が傷つくことを覚悟で、他者を守ろうとする矢野の勇気と優しさに、私は強く心を動かされた。
そして何より印象深かったのは、物語の結末で安達が取った行動だった。
安達は世界を救うヒーローにはならなかった。
矢野を完全にいじめから救うこともできなかった。
彼がしたのは、矢野の挨拶に「おはよう」と返すという、本当に小さな行為だった。
しかし、この一言がどれほど重要な意味を持つかを、私は物語を通して深く理解した。
クラス全員が矢野を無視する中で、一人だけ挨拶を返すことの勇気。
夜の「僕」として知った真実を、昼の「俺」として行動に移すことの困難さ。
安達のこの選択は、二つに分裂していた彼の世界を一つにつなげる、決定的な瞬間だった。
私自身を振り返ってみても、正しいことをしたいと思いながら、周りの目を気にして行動できなかった経験が数多くある。
いじめを見て見ぬふりをしたり、困っている人がいても声をかけられなかったり。
そんな自分の弱さを認めながらも、安達の勇気ある一歩に強く励まされた。
『よるのばけもの』は、私に「本当の自分とは何か」という問いを投げかけた。
社会の中で生きていく以上、ある程度の使い分けは必要かもしれない。
しかし、本音と建前があまりにもかけ離れてしまうと、安達のように自分が二つに分裂してしまう危険性がある。
大切なのは、どちらの自分も偽りではなく、状況に応じて使い分けながらも、核となる部分は一貫していることなのだろう。
また、この作品は他者理解の重要性も教えてくれた。
表面的な行動や表情だけで人を判断するのではなく、その裏にある事情や感情に思いを馳せること。
自分とは違う価値観や行動様式を持つ人を、すぐに排除するのではなく、理解しようと努めること。
これらの姿勢が、より良い人間関係を築く基盤になると感じた。
そして最も重要なのは、小さくても行動を起こす勇気だ。
安達の「おはよう」という一言は、矢野の孤独を完全に解消したわけではないかもしれない。
しかし、その一言が矢野にとって、そして安達自身にとって、大きな意味を持ったことは間違いない。
私たちの日常にも、そうした小さな勇気を必要とする場面がたくさんある。
困っている人に声をかけること、間違いを指摘すること、自分の意見を正直に伝えること。
どれも簡単なことではないが、そうした一歩一歩の積み重ねが、より良い世界を作っていくのだと思う。
『よるのばけもの』を読んで、私は自分自身と向き合う貴重な時間を得た。
これからも、本当の自分を見失わずに、他者への理解と共感を忘れずに、そして小さな勇気を大切にして生きていきたい。
振り返り
『よるのばけもの』の読書感想文について、書き方から例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つの要点を参考にしながら、あなた自身の体験や感情と重ね合わせて感想文を書いてみてください。
大切なのは、物語のあらすじを説明することではなく、読んだあなたがどう感じたか、何を考えたかを正直に表現することです。
中学生向けと高校生向けの例文も参考にしながら、あなたらしい言葉で『よるのばけもの』への思いを綴ってください。
コピペは絶対にしてはいけませんが、構成や発想のヒントとして活用していただければ幸いです。
きっと素晴らしい読書感想文が書けるはずですよ。
※『よるのばけもの』の読書感想文の作成に役立つあらすじと考察記事がこちらです。









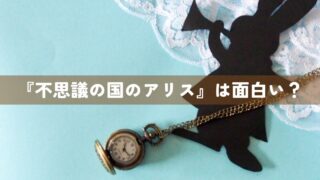
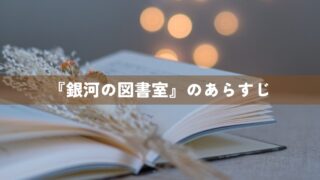









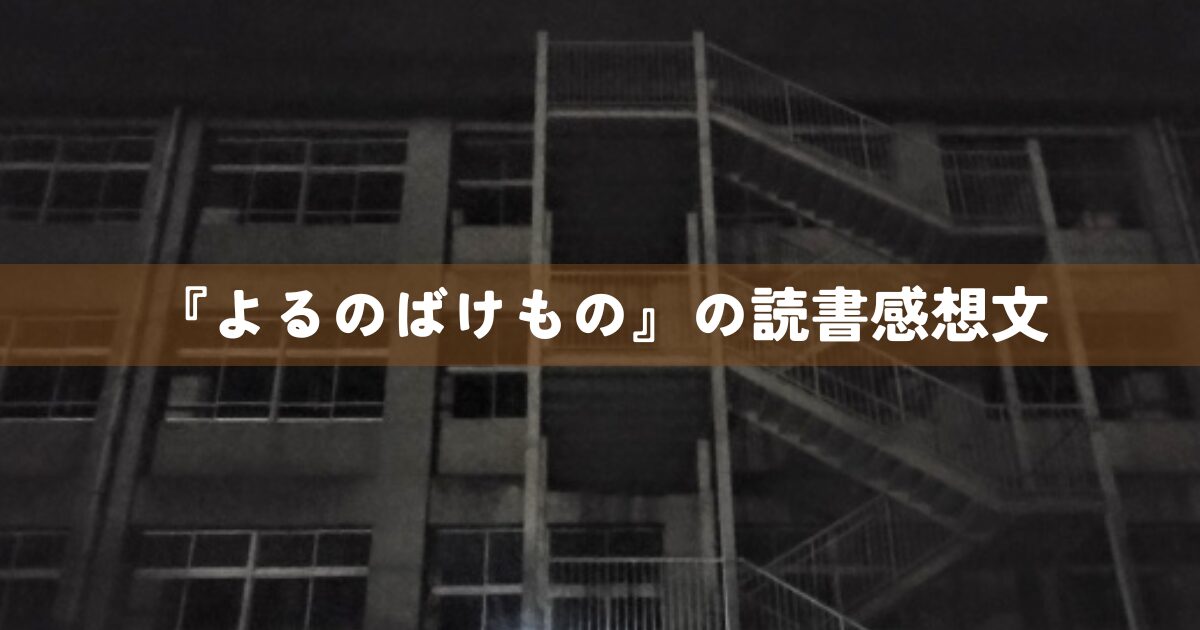
コメント