『図書館がくれた宝物』の読書感想文を書く予定の小学生のみなさん、こんにちは。
戦時下イギリスを舞台にした心温まる物語『図書館がくれた宝物』は、ケイト・アルバス作、櫛田理絵翻訳による2023年の話題作ですね。
第70回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にも選ばれた注目の一冊。
1940年のロンドンを舞台に、疎開先で生きる3人きょうだいと図書館との交流を描いた感動的なストーリーとなっています。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、『図書館がくれた宝物』の読書感想文の書き方から例文、小学生のみなさんがコピペしないでも素晴らしい感想文を書けるよう丁寧に解説していきます。
書き出しのコツやテンプレートも用意していますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
『図書館がくれた宝物』の読書感想文に書くべき3つのポイント
『図書館がくれた宝物』の読書感想文を書く時に押さえておくべき重要なポイントを3つ紹介しますよ。
まず、この小説を読んだ時にどんな気持ちになったか、どの場面が印象に残ったかを読みながらメモしておくことが大切です。
感じたことをその場で書き留めておけば、あとで感想文を書く時にとても役立ちますからね。
それでは、感想文で必ず触れるべき3つのポイントを見ていきましょう。
- 戦争という厳しい時代の中での子どもたちの成長と絆
- 図書館と本が持つ特別な力と意味
- 困難な状況でも希望を失わない心の強さ
これらのポイントを中心に、自分なりの感想や体験談を織り交ぜて書いていけば、きっと素晴らしい読書感想文が完成しますよ。
それでは、各ポイントについて詳しく解説していきますね。
戦争という厳しい時代の中での子どもたちの成長と絆
『図書館がくれた宝物』の舞台は1940年、第二次世界大戦が始まったばかりのイギリスです。
12歳のウィリアム、11歳のエドマンド、9歳のアンナの3人きょうだいは、両親も祖母も亡くし、知らない土地への疎開を余儀なくされました。
現代を生きる私たちには想像しにくい厳しい状況ですが、この3人がどのように支え合い、成長していったかに注目してみてください。
特に長男のウィリアムが弟と妹を守ろうとする責任感や、エドマンドの前向きさ、アンナの優しさなど、それぞれの個性が困難な状況でどう発揮されるかが見どころですね。
また、血のつながった家族だけでなく、疎開先で出会う大人たちとの関わりも重要なポイントになります。
家族の絆とは何か、本当の温かさとは何かについて、あなた自身の経験と照らし合わせて考えてみてください。
普段、兄弟姉妹とケンカをすることがあっても、本当に困った時にはお互いを支え合う気持ちがあることを実感したことはありませんか。
そんな体験があれば、きっと3人きょうだいの気持ちがよく分かるはずです。
図書館と本が持つ特別な力と意味
タイトルにもなっている「図書館がくれた宝物」という言葉には、とても深い意味が込められています。
3人きょうだいにとって図書館は、単に本を読む場所ではありませんでした。
つらい現実から逃れることができる特別な場所、心の避難所のような存在だったのです。
本を読んでいる間だけは、疎開先での寂しさや不安を忘れることができる。
物語の世界に入り込むことで、勇気や希望をもらうことができる。
このような「本の力」について、あなたはどう感じましたか。
あなたにも、悲しい時や落ち込んだ時に読んで元気をもらった本はありませんか。
好きな物語に夢中になって、時間を忘れてしまった経験はありませんか。
そんな体験があれば、きっと3人きょうだいが図書館で感じた特別な気持ちが理解できるでしょう。
図書館という場所の温かさ、司書さんの優しさ、そして本そのものが持つ不思議な力について、具体的なエピソードを交えて書いてみてくださいね。
困難な状況でも希望を失わない心の強さ
『図書館がくれた宝物』で最も感動的なのは、3人きょうだいが様々な困難に直面しながらも、決して希望を諦めなかった点です。
疎開先で冷たい扱いを受けたり、理不尽な目に遭ったりしても、お互いを信じ、未来への希望を持ち続けました。
この強い心はどこから来るのでしょうか。
それは、家族への愛情、そして本や図書館から得られる知識と勇気、そして何より「諦めない気持ち」だったのではないでしょうか。
あなたも今まで生きてきた中で、つらいことや困ったことがあったと思います。
でも、それを乗り越えてきたからこそ、今のあなたがいるわけですね。
家族や友だち、先生に支えられたこともあるでしょう。
好きな本や映画に励まされたこともあるでしょう。
そんな経験と3人きょうだいの体験を重ね合わせて、「希望を持つことの大切さ」について書いてみてください。
また、この物語を読んで、あなた自身がどんな希望や夢を持つようになったかも書けるといいですね。
『図書館がくれた宝物』の読書感想文のテンプレート
読書感想文を書くのが苦手なみなさんのために、簡単に使えるテンプレートを用意しました。
このテンプレートに沿って書けば、きっとスムーズに感想文が完成しますよ。
- 【書き出し】この本を読んだきっかけと第一印象を書く
- 【あらすじ】物語の設定と主人公について簡潔に説明する
- 【印象的な場面】一番心に残った場面とその理由を書く
- 【自分との関連】主人公の体験と自分の体験を比較する
- 【メッセージ】この本から学んだことや感じたメッセージを書く
- 【まとめ】この本を読んで変わった自分の気持ちや考えを書く
「『図書館がくれた宝物』というタイトルを見て、(自分がどう感じたか)と思った。読んでみると、(第一印象)だった。」
「この物語は、1940年のイギリスで、(主人公の説明)が(どんな状況に置かれたか)という話だ。」
「私が一番心に残ったのは、(具体的な場面)のところだ。なぜなら、(理由)だからだ。」
「私も(主人公と似たような体験)をしたことがある。その時、(自分がどう感じたか)だった。」
「この本を読んで、(学んだこと)ということが分かった。特に、(具体的な内容)は大切だと思う。」
「『図書館がくれた宝物』を読んで、私は(どう変わったか)。これからは、(今後どうしたいか)と思う。」
それぞれの部分に自分の言葉と体験を入れて書けば、オリジナルの感想文になりますよ。
『図書館がくれた宝物』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】図書館がくれた本当の宝物
『図書館がくれた宝物』を読み終えて、私の心は温かい気持ちでいっぱいになった。
最初はタイトルを見て、図書館で宝石でも見つける話なのかなと思っていた。
でも読んでみると、本当の宝物はもっと大切なものだということが分かった。
この物語は、1940年のイギリスが舞台だ。
12歳のウィリアム、11歳のエドマンド、9歳のアンナの3人きょうだいは、両親と祖母を亡くし、知らない土地に疎開することになった。
戦争という恐ろしい時代に、まだ子どもの3人だけで生きていかなければならない状況は、想像しただけでも胸が苦しくなる。
私が一番印象に残ったのは、3人が図書館で本を読んでいる場面だ。
疎開先では冷たい扱いを受けることも多く、居場所がないように感じていた3人にとって、図書館だけは安心できる特別な場所だった。
本を読んでいる間は、つらい現実を忘れて、物語の世界で冒険することができる。
私も、嫌なことがあった時に好きな本を読むと、気持ちが楽になることがある。
だから、3人の気持ちがとてもよく分かった。
特にウィリアムが弟と妹を守ろうとする姿に感動した。
まだ12歳なのに、家族のために一生懸命頑張る姿は立派だと思った。
私にも弟がいるが、普段はケンカばかりしている。
でも、この本を読んで、家族って本当に大切な存在なんだと改めて感じた。
困った時にはお互いを支え合うのが家族なんだということを、3人きょうだいが教えてくれた。
また、図書館の司書さんや村の人々の優しさにも心を打たれた。
最初は冷たく見えた人たちも、3人のことを理解してくれるようになる。
人との出会いや温かさがどれほど大切かということも、この物語から学んだ。
『図書館がくれた宝物』の本当の宝物は、本そのものだけではなく、家族の絆、人との出会い、そして希望を失わない強い心だったのだと思う。
3人きょうだいは図書館で多くの本に出会ったが、それ以上に大切なものを見つけることができた。
私もこれからは、つらいことがあっても希望を忘れずに頑張りたいと思う。
そして、家族や友だちをもっと大切にしていきたい。
この本は、私にとって本当に特別な一冊になった。
『図書館がくれた宝物』の読書感想文の例文(1200字の小学生向け)
【題名】本が教えてくれた家族の意味
『図書館がくれた宝物』を読み始めた時、私は戦争の話だから重くて暗い内容なのかなと思っていた。でも、読み進めるうちに、この物語には深くて温かいメッセージが込められていることが分かった。タイトルにある「宝物」とは何なのか、それを考えながら最後まで読み通すことができた。
物語の舞台は1940年のイギリス、第二次世界大戦が始まったばかりの時代だ。主人公は12歳のウィリアム、11歳のエドマンド、9歳のアンナの3人きょうだい。両親を幼い頃に亡くし、面倒を見てくれていた祖母も亡くなり、3人は疎開先の村で新しい生活を始めることになった。
想像もつかない厳しい状況に置かれた3人だが、お互いを支え合い懸命に生きていく姿に深く感動した。特に印象に残ったのは、3人が図書館で過ごす時間だ。疎開先では居場所を見つけられず、時には冷たい扱いを受けることもあった彼らにとって、村の図書館は安らげる唯一の場所だった。本に囲まれて読書をしている時だけは、つらい現実を忘れることができた。物語の世界に入り込み、主人公と冒険したり困難を乗り越えたりすることで、現実を生きる勇気をもらっていたのだ。
私も読書が大好きで、よく図書館に通っている。嫌なことがあった時や落ち込んだ時に、お気に入りの本を読むと心が落ち着く。本の中の登場人物が頑張っている姿を見ると、私も頑張ろうという気持ちになる。だから3人が図書館で感じていた特別な気持ちが分かった。図書館は本を借りる場所ではなく、心の支えを見つける大切な場所なのだと実感した。
また、長男のウィリアムが弟と妹を守ろうとする責任感にも心を打たれた。まだ12歳という年齢でありながら、家族のために一生懸命考え行動する姿は本当に立派だった。私にも年下の弟がいるが、普段は些細なことでケンカをしてしまう。だが、この物語を読んで、家族の絆がどれほど大切かを考えるようになった。お互いを思いやり、困った時に支え合うからこそ本当の家族になれるのだと3人が教えてくれた。
そして最も感動したのは、3人がどんなにつらい状況でも希望を失わなかった点だ。未来が見えない不安な日々の中でも、いつか状況が良くなることを信じ前向きに生きる姿勢は、現代を生きる私たちにも大切な教訓だと思う。私も今まで、テストで悪い点を取った時や友だちとケンカをした時など落ち込むことがあった。そんな時は「もうだめだ」と諦めそうになることもある。だが、この本を読んで、困難な状況でも希望を持ち続けることの大切さを学んだ。
『図書館がくれた宝物』というタイトルの本当の意味は、本そのものではなく、本を通して得られる知識や勇気、そして人とのつながりや家族の絆だったのだと思う。3人きょうだいは図書館で多くの「宝物」を見つけた。私もこれから読書を通してもっと学び、成長していきたい。そして家族や友だちとの関係を大切にしながら、希望を持って毎日を過ごしていこうと思う。この本は、私の心に深く響く特別な一冊になった。
振り返り
『図書館がくれた宝物』の読書感想文について、書き方のポイントからテンプレート、実際の例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つのポイント(戦時下での子どもたちの成長と絆、図書館と本の特別な力、困難でも希望を失わない心の強さ)を押さえれば、きっと素晴らしい感想文が書けるはずです。
大切なのは、物語を読んで自分が本当に感じたことを素直に書くことですよ。
テンプレートや例文は参考程度に使って、あなただけのオリジナルな感想文を完成させてくださいね。
読書感想文を書くのは最初は難しく感じるかもしれませんが、コツを掴めばきっと楽しくなります。
この記事が、みなさんの読書感想文作成の手助けになれば嬉しいです。
頑張って素敵な感想文を書いてくださいね。
※『図書館がくれた宝物』のあらすじはこちらでご紹介しています。


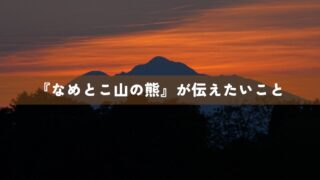
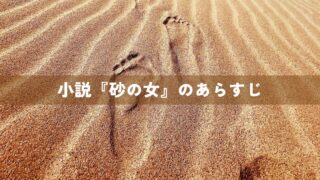



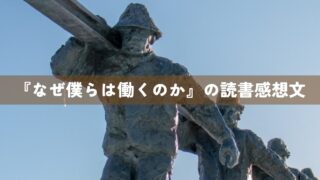
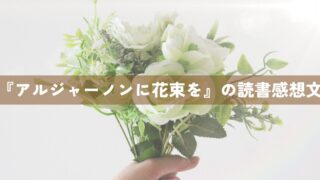


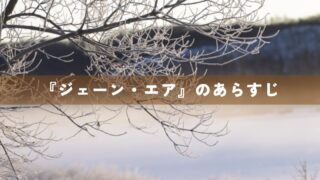

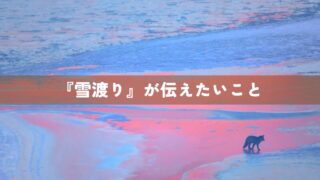

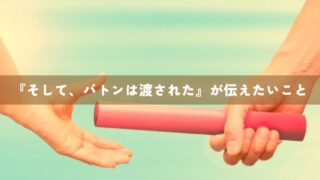



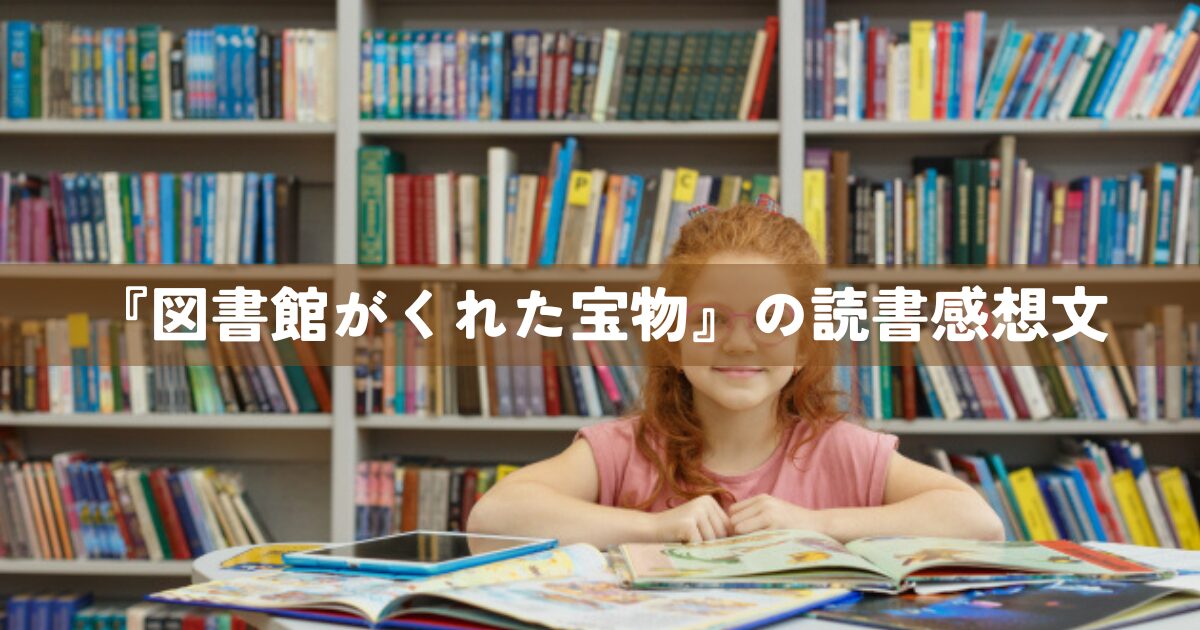
コメント