『注文の多い料理店』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
宮沢賢治の代表作『注文の多い料理店』は、西洋料理店を舞台にした不思議で怖い童話です。
この作品は賢治が生前に出版した唯一の童話集の表題作で、『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』と並ぶ名作として親しまれています。
小学校の国語の教科書にも掲載されているので、多くの方がご存知でしょう。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文の書き方から例文まで、小学生・中学生・高校生それぞれのレベルに合わせて詳しく解説していきますよ。
題名や書き出しのコツ、コピペではない自分だけの感想文を書くポイントもお伝えします。
『注文の多い料理店』の読書感想文で触れたい3つの要点
『注文の多い料理店』の読書感想文を書く際は、以下の3つの要点を意識してメモを取りながら読み進めましょう。
- 「注文」という仕掛けと物語のユーモア
- 自然・人間への警告や教訓性
- 怖さと安心の対比、心の動き
これらの要点について「どう感じたか」を具体的にメモしておくことが大切です。
例えば「怖いと思った場面」「驚いた瞬間」「考えさせられた内容」など、自分の素直な気持ちを言葉にしてみてください。
感想文は物語の内容を説明するだけでは不十分で、あなた自身の感情や考えを表現することが最も重要ですよ。
「注文」という仕掛けと物語のユーモア
『注文の多い料理店』の最大の魅力は、「注文」という言葉の二重の意味にあります。
二人の紳士は最初、レストランの「お客様への注文(要求)」だと思って従っていました。
しかし実際は、山猫が人間を料理するための「注文(発注)」だったという恐ろしい真実。
この言葉遊びのような仕掛けが、物語に独特のユーモアとスリルを生み出しています。
読みながら「あれ、なんか変だな」と感じた瞬間や、真実に気づいた時の衝撃をメモしておきましょう。
宮沢賢治の巧妙な文章テクニックに対して、あなたはどんな印象を持ちましたか。
自然・人間への警告や教訓性
『注文の多い料理店』には、自然を軽んじる人間への厳しい警告が込められています。
二人の紳士は山で迷子になり、連れていた猟犬も不可解な死を遂げてしまいます。
それでも彼らは金銭的な損失ばかり気にして、命の重さを理解していません。
この傲慢さが、山猫軒という恐ろしい罠にはまる原因となっているのです。
現代社会でも、人間が自然を支配できると思い込んでいる場面がたくさんありますよね。
物語を読んで、自然との向き合い方について何を感じたかメモしてみてください。
怖さと安心の対比、心の動き
物語の展開とともに変化する二人の心情描写も見どころです。
最初は軽い気持ちで注文に従っていた紳士たちが、だんだん不安を感じ始めます。
そして真実を知った瞬間の絶望的な恐怖から、猟犬に救われる安堵まで。
この感情の振れ幅が、読者にも強いインパクトを与えます。
あなたはどの場面で一番怖いと感じましたか。
また、最後に助かった時はどんな気持ちになったでしょうか。
自分の心の動きを振り返ってメモしておくと、感想文に深みが出ますよ。
※『注文の多い料理店』で宮沢賢治が伝えたいことや物語の疑問点の考察はこちらの記事がくわしいです。


『注文の多い料理店』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】山猫軒で学んだこと
私は宮沢賢治の『注文の多い料理店』を読んで、とても驚いた。
最初は二人の紳士が山で迷子になって、たまたま見つけたレストランに入る話だと思っていた。
でも読み進めていくうちに、だんだん変な感じがしてきた。
「髪をとかしてください」「靴の泥を落としてください」という注文はまだわかるが、「金属のものを全部外してください」「体にクリームを塗ってください」という注文は明らかにおかしい。
私は読みながら「なんでこんな変な注文ばかりなのかな」と不思議に思った。
そして最後の部屋で「体に塩をもみ込んでください」という注文を見た時、やっと気がついた。
二人の紳士は料理を食べるお客さんではなく、山猫に食べられる料理だったのだ。
この真実を知った時、背中がゾクゾクして本当に怖くなった。
私は『注文の多い料理店』を読んで、人間の勝手さについて考えさせられた。
二人の紳士は山で狩りをして、動物を殺そうとしていた。
でも自分たちが殺される立場になった途端、泣き出してしまった。
これはとても身勝手なことだと思う。
動物だって生きているのに、人間の楽しみのために殺されるのは可哀想だ。
また、二人の紳士は自然を甘く見ていたから、こんな怖い目にあったのだと思う。
山は人間のものではないし、動物たちの住む場所を荒らしてはいけない。
自然を大切にしない人間には、きっと自然からの仕返しがあるのだろう。
最後に猟犬が現れて二人を助けた場面では、少しホッとした。
でも二人の顔はくしゃくしゃのままで、元に戻らなかった。
これは「悪いことをした罰」なのかもしれない。
私は『注文の多い料理店』を読んで、命の大切さと自然への感謝を忘れてはいけないと思った。
人間だけが偉いわけではないし、他の生き物にも優しくしなければならない。
この物語は怖い話だったけれど、とても大切なことを教えてくれた。
これからは動物や自然を大切にして、傲慢にならないよう気をつけたい。
『注文の多い料理店』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】人間の傲慢さと自然への畏敬
私は宮沢賢治の『注文の多い料理店』を読み、人間の傲慢さと自然の恐ろしさについて深く考えさせられた。
この物語は一見すると奇妙でユーモラスな童話だが、その奥には現代社会にも通じる重要なメッセージが隠されている。
物語の主人公である二人の紳士は、都会から山奥へハンティングにやってきた裕福な男性だ。
彼らは自然を単なる娯楽の場として捉え、動物の命を軽視している。
連れていた猟犬が不可解な死を遂げても、経済的な損失しか気にしない彼らの態度には、人間の身勝手さが表れている。
私はここで、現代の環境破壊や動物の乱獲問題を連想した。
人間は長い間、自然を征服できる存在だと思い込んできたが、実際は自然の一部に過ぎないのではないだろうか。
山猫軒での一連の「注文」は、物語の最大の仕掛けである。
最初は親切なサービスだと思っていた注文が、実は自分たちを料理するための準備だったという恐ろしい真実。
この逆転の構造は、私たちが当たり前だと思っている日常が、実は危うい基盤の上に成り立っていることを示唆している。
二人の紳士が注文を素直に受け入れていく様子は、現代人が便利さや快適さに慣れて、危険性を見落としてしまう姿と重なる。
私も普段、食べ物や電化製品を何の疑いもなく使っているが、その裏側で何が起きているか深く考えることは少ない。
最も印象的だったのは、真実に気づいた瞬間の二人の反応だ。
今まで狩る側だった彼らが、逆に狩られる立場になった時の絶望と恐怖。
「顔がくしゃくしゃになるほど」の恐怖は、死への直面を表している。
この場面で私は、生と死の境界線の曖昧さを感じた。
人間は他の生き物の命を奪って生きているのに、自分の命が危険にさらされると途端に怯えてしまう。
この矛盾こそが、宮沢賢治が描きたかった人間の本質なのかもしれない。
しかし物語は絶望で終わらない。
死んだはずの猟犬が現れて二人を救う結末には、希望と救済のメッセージがある。
これは自然が持つ慈悲深さの象徴だと私は解釈した。
自然は人間に厳しい試練を与えるが、同時に救いの手も差し伸べてくれる。
ただし、二人の顔は元に戻らなかった。
これは過ちの代償として残る傷跡であり、彼らが学んだ教訓の証しでもある。
『注文の多い料理店』を読んで、私は自分の生活を見直すきっかけを得た。
毎日食べている肉や魚も、元は生きていた動物たちだ。
その命をいただいていることへの感謝を忘れてはいけない。
また、自然環境を破壊する行為についても、もっと関心を持つべきだと思った。
宮沢賢治がこの物語に込めたメッセージは、100年近く経った現在でも色あせていない。
むしろ環境問題が深刻化している今だからこそ、より重要な意味を持っている。
私たちは自然の一部として謙虚に生きていかねばならない。
傲慢さを捨て、他の生き物や自然環境への敬意を忘れずにいたい。
『注文の多い料理店』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】文明社会への警鐘と人間性の本質
宮沢賢治の『注文の多い料理店』は、表面的には奇想天外な童話でありながら、その内側には現代文明社会への鋭い批判と人間性の本質に関する深い洞察が込められている。
私はこの作品を読み、人間の傲慢さと自然への畏敬、そして真の豊かさとは何かについて考えさせられた。
物語の冒頭から、二人の紳士の人物像は明確に描かれている。
彼らは都市部の裕福な階層に属し、「ハンティング」という娯楽目的ではるばる山奥までやってきた。
彼らにとって自然は征服すべき対象であり、動物の命は金銭的価値でしか測られない。
猟犬が不可解な死を遂げた時も、「いくらくらいの損害だろう」と経済的な計算しかしない彼らの反応は、現代の資本主義社会における人間の価値観を象徴している。
私はここに、物質的豊かさを追求するあまり、生命の尊厳を見失いがちな現代人の姿を重ね合わせた。
山猫軒での一連の出来事は、この物語の核心部分である。
「注文の多い料理店」という看板の二重の意味は、言語の持つ多義性を巧みに利用した宮沢賢治の文学的技巧を示している。
客に対する「注文(要求)」と、料理としての人間への「注文(発注)」という意味の転換は、読者に強烈な衝撃を与える。
しかし私が最も注目したのは、二人の紳士がこの異常な状況を合理化し続ける心理的メカニズムである。
彼らは明らかに不自然な注文に対して、「電気を使う料理があるから金属は危険」「西洋料理だから身だしなみが重要」といった理由づけを行う。
この自己欺瞞的な思考パターンは、現代社会における様々な問題への対処法と類似している。
私たちも日常生活において、不都合な真実から目を逸らし、都合の良い解釈を採用してしまうことがある。
環境破壊や社会格差といった深刻な問題に対しても、直視することを避け、表面的な理由で正当化してしまう傾向がある。
『注文の多い料理店』の二人の紳士は、まさにそうした現代人の縮図なのではないだろうか。
彼らの滑稽さや愚かしさは、読者に笑いを誘うと同時に、鋭い自己反省を促してくる。
真実が明らかになった瞬間の二人の反応は、人間の本質的な脆さを露呈している。
今まで狩る側として君臨していた彼らが、一転して狩られる側になった時の絶望的な恐怖。
この立場の逆転は、人間が生態系の頂点に立っているという思い込みがいかに脆弱な基盤の上に成り立っているかを示している。
私はここで、人間の文明がどれほど自然環境に依存しているかを改めて実感した。
気候変動や生物多様性の損失といった現代的課題を考えると、私たち人間もまた自然界の一員に過ぎず、生態系のバランスが崩れれば存続できない存在なのだ。
そして、人類が自然を「管理できる」と錯覚していること自体が、最大の過信であるようにも感じた。
しかし宮沢賢治は、単に人間の愚かさを糾弾するだけでなく、救済の可能性も示している。
死んだはずの猟犬が現れて二人を救う結末は、自然の持つ寛容さと慈悲を表現している。
この犬たちは、利害関係を超えた純粋な忠誠心によって主人を守った。
彼らの行動は、打算的な人間関係とは対照的な、無償の愛の象徴である。
私はこの場面に、人間と自然が本来持つべき調和的な関係性のヒントを見出した。
このような動物との絆は、私たちが失いつつある「命とのつながり」の感覚を呼び覚ましてくれる。
ただし、二人の顔が元に戻らなかったという結末は重要な意味を持つ。
これは過ちの代償として残る永続的な傷跡であり、彼らが体験した恐怖と学んだ教訓の証しでもある。
真の学びは、表面的な理解ではなく、身体的・精神的な体験を通じて刻み込まれるものなのだ。
私自身も、この物語を読むことで、日常の当たり前を見つめ直すきっかけを得た。
毎日食べている食事も、誰かの労働と自然の恵みによって成り立っている。
また、便利な現代生活の裏側で、どれだけの資源が消費され、どれだけの環境負荷が生じているかについても意識するようになった。
一見するとただの風変わりな童話のように見えるこの作品が、ここまで現代的なテーマを内包していることに驚き、深く感動した。
『注文の多い料理店』が発表されてから約100年が経過したが、この作品のメッセージは現代においてむしろ切実性を増している。
グローバル化が進み、テクノロジーが発達した現代社会においても、人間の根本的な問題は変わっていない。
物質的豊かさを追求するあまり精神的豊かさを見失い、自然環境を破壊し続ける現代文明に対して、宮沢賢治は100年前から警鐘を鳴らしていたのだ。
私はこの作品を通じて、真の豊かさとは何かについて深く考えるようになった。
それは単なる物質的な充足ではなく、自然や他者との調和的な関係性の中で得られる精神的な満足なのではないだろうか。
今後は消費者として、また社会の一員として、より責任ある選択を心がけていきたい。
『注文の多い料理店』は、私にとって人生観を見つめ直す貴重な機会を与えてくれた作品である。
振り返り
今回は『注文の多い料理店』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
小学生から高校生まで、それぞれの年齢に応じた表現方法や着眼点を示すことで、皆さんの感想文作成をサポートできたと思います。
大切なのは、物語の内容をただ説明するのではなく、あなた自身が「どう感じたか」を素直に表現することです。
宮沢賢治の込めたメッセージを理解しつつ、現代の視点から自分なりの考えを述べることで、オリジナリティのある感想文が完成します。
今回紹介した3つの要点や例文を参考にしながら、ぜひあなただけの『注文の多い料理店』読書感想文を書いてみてください。
きっと素晴らしい作品が出来上がりますよ。
※『注文の多い料理店』の読書感想文を書くのに役立つ記事がこちら。


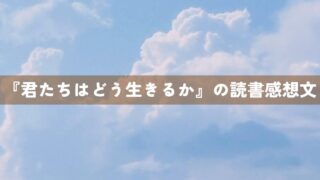
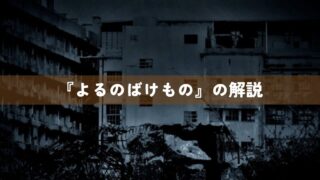



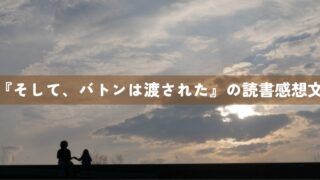
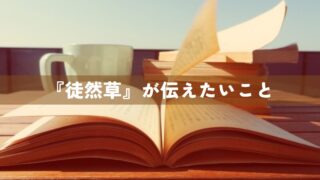

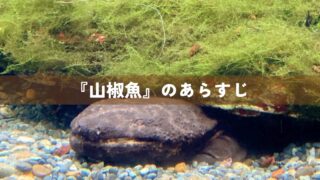

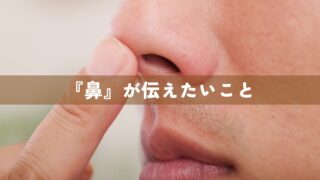


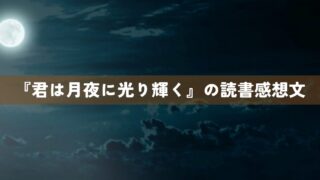

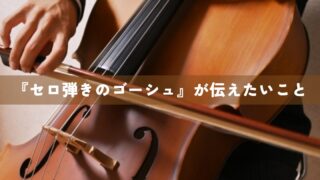
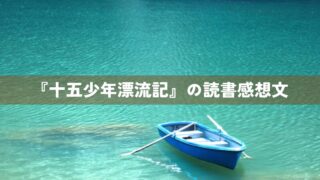
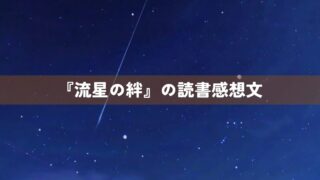
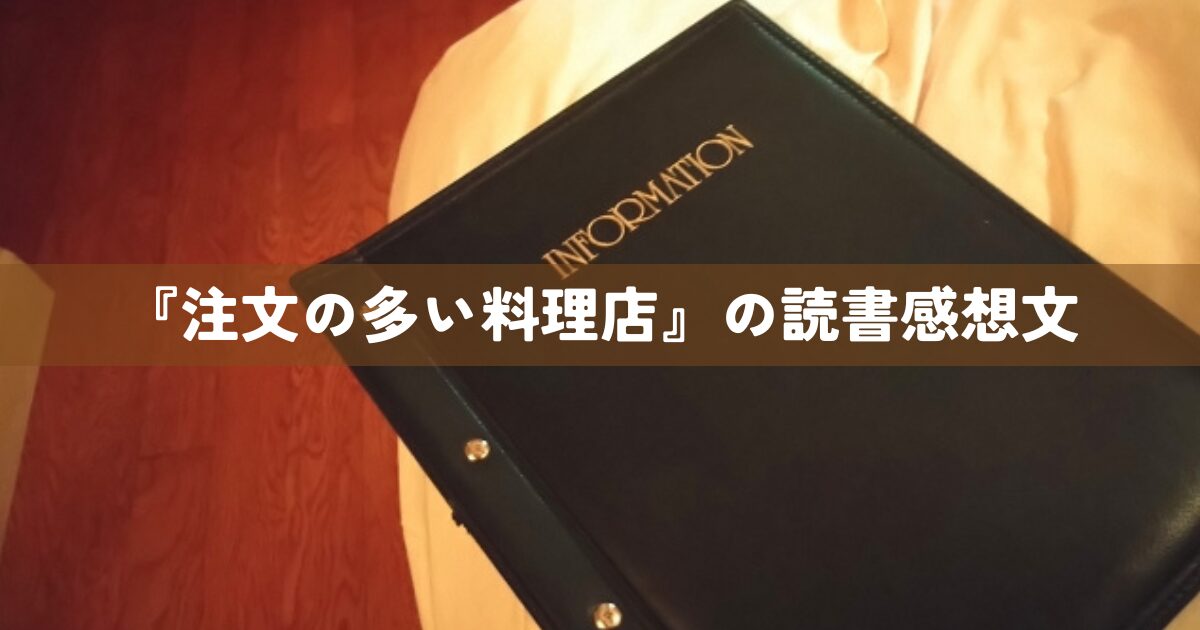
コメント