『ドグラ・マグラ』のあらすじを簡単に・ネタバレありで紹介していきますね。
夢野久作の代表作『ドグラ・マグラ』は、日本探偵小説三大奇書の一つとして知られる、構想・執筆に10年以上をかけて1935年に刊行された不朽の名作です。
年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、簡単なあらすじから私の読んだ感想まで、丁寧に解説していきますよ。
『ドグラ・マグラ』のあらすじを簡単に短く(ネタバレ)
『ドグラ・マグラ』のあらすじを詳しく(ネタバレ)
大正15年11月20日、見知らぬ病室で目覚めた「わたし」は自分の記憶を失っていた。九州帝国大学医学部の若林教授から、ここは精神病科の病棟であり、一ヶ月前に自殺した奇人天才・正木博士の実験台にされていると告げられる。「わたし」は自分が呉一郎という人物で、婚約者である従妹のモヨ子を絞殺した容疑者だと知らされる。
若林教授は正木博士の遺志を継ぎ、「わたし」に記憶を取り戻させるため、博士の残した5つの文書を読ませる。その中には「心理遺伝」という理論や、呉家に伝わる絵巻物の秘密が記されていた。呉家には死んだ美しい妻の姿を写し取ろうとして発狂した先祖の伝説があり、モヨ子殺害事件もその「心理遺伝」による再現ではないかと示唆されていた。
文書を読み終えた「わたし」の前に、死んだはずの正木博士が現れる。博士によれば今日は10月20日で、窓の外には自分にそっくりな青年の姿が見える。博士は自らが犯人であることを告白し、呉一郎が「心理遺伝」の実験台だったと明かす。博士と若林は学生時代からのライバルで、呉家の秘密に興味を持ち、一郎の母に言い寄って実験のお膳立てをしたというのだ。
混乱した「わたし」が一度部屋を出て戻ると、そこには10月20日付の号外があり、正木博士の自殺と患者・呉一郎による惨殺事件の報道が載っていた。自分が呉一郎であるかもしれないと気づき始めた「わたし」が駆け出したとき、闇の中に呉家の先祖・呉青秀の姿を見る。時間軸が交錯し、主人公の正体と真実は謎のまま物語は終わる。
『ドグラ・マグラ』のあらすじを理解するための用語解説
『ドグラ・マグラ』の複雑な世界観を理解するために、重要な用語を整理しました。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ドグラ・マグラ | 長崎地方の方言で、 元々は切支丹バテレンの幻魔術を指す言葉。 現在では「戸惑い」「混乱」を意味し、 作品の世界観を象徴する。 |
| 脳髄論 | 正木博士の論文で 「脳髄は物を考える処に非ず」と主張。 脳は単なる情報交換所であり、 近代の脳髄崇拝を批判する内容。 |
| 胎児の夢 | 胎児が母体内で数十億年の生物進化を反復し、 その夢を見るという理論。 エルンスト・ヘッケルの反復説を下敷きにした 正木博士の論文。 |
| 心理遺伝 | 正木博士の説で、 刺激により祖先の記憶が蘇るという理論。 呉一郎の殺人行為の原因として説明される。 |
| 九相図 | 呉青秀が描いた 愛妻の死体が腐敗していく様子を描いた絵巻物。 呉家の男子を発狂させる引き金となる重要なアイテム。 |
これらの用語は作品の核心的なテーマと密接に関わっており、物語の理解に欠かせない概念です。
『ドグラ・マグラ』を読んだ感想
正直に言うと、『ドグラ・マグラ』を読み終えた時の感想は「やばかった!」の一言に尽きます。
この作品は本当に読者を選ぶ小説で、最初の数十ページで挫折しそうになりました。
でも、読み進めていくうちに、この異常な世界観にどんどん引き込まれていったんです。
特に印象的だったのは、主人公の「わたし」の正体が最後まで明かされないこと。
普通の小説なら、謎は解決されて、真犯人が明かされて、すっきりと終わるじゃないですか。
でも『ドグラ・マグラ』は違う。
読み終わっても、「結局、何が真実だったんだ?」という疑問が残り続けるんです。
これが夢野久作の狙いなんでしょうね。
読者自身を混乱に陥れ、現実と幻想の境界を曖昧にする。
まさに「ドグラ・マグラ」という言葉の通り、読んでいる私たちも「戸惑い」「混乱」の中に放り込まれるわけです。
正木博士の論文「脳髄は物を考える処に非ず」や「胎児の夢」なんて、読んでいて鳥肌が立ちました。
特に「胎児の夢」の部分は、生物進化の壮大な物語が展開されて、SF要素も感じられましたね。
ただ、正直に言うと、理解できなかった部分も多々あります。
作中作が多すぎて、どこまでが現実でどこからが妄想なのか分からなくなってしまった。
「〇〇〇〇地獄外道祭文」なんて、読んでいて気持ち悪くなってしまいました。
でも、それが作品の魅力でもあるんですよね。
読者を不安定な精神状態に追い込み、物語の世界に完全に没頭させる。
呉家の絵巻物の話も、本当に恐ろしかった。
愛する妻を殺して、その腐敗していく様子を描くなんて、狂気の沙汰です。
でも、その狂気が世代を超えて受け継がれていくという設定が、また恐ろしい。
遺伝や無意識の恐怖を描いた作品として、本当に秀逸だと思います。
私が一番感動したのは、作者の夢野久作が10年以上かけて構想・執筆したという執念です。
これだけ複雑で難解な作品を書き上げる情熱は、本当に尊敬に値します。
読了後は、しばらく現実に戻れませんでした。
それほど強烈な読書体験でした。
確かに読者を選ぶ作品ですが、読み切った時の達成感は格別です。
文学好きなら一度は挑戦してみる価値のある、まさに「奇書」と呼ぶにふさわしい作品だと思います。
※謎が多い『ドグラ・マグラ』を読み解くにはこちらの解説記事がお役に立つはずです。

『ドグラ・マグラ』の作品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 夢野久作 |
| 出版年 | 1935年(昭和10年) |
| 出版社 | 松柏館書店 |
| 受賞歴 | 日本探偵小説三大奇書の一つ |
| ジャンル | 探偵小説、幻想小説、アンチミステリー |
| 主な舞台 | 九州帝国大学医学部精神病科 |
| 時代背景 | 大正15年(1926年) |
| 主なテーマ | 記憶、狂気、遺伝、アイデンティティ |
| 物語の特徴 | 入れ子構造、メタフィクション、論理的解決の回避 |
| 対象年齢 | 高校生以上(内容の難解さと精神的負担を考慮) |
| 青空文庫 | 収録済み(こちら) |
『ドグラ・マグラ』の主要な登場人物とその簡単な説明
『ドグラ・マグラ』の複雑な人物関係を理解するために、主要な登場人物を整理しました。
| 人物名 | 説明 |
|---|---|
| わたし | 物語の語り手で記憶を失った青年。 自分の正体が分からず、呉一郎と同一人物かが最大の謎。 |
| 呉一郎 | 20歳の美青年で物語の鍵を握る人物。 従妹モヨ子と母千世子の殺害容疑者。 |
| 呉モヨ子 | 呉一郎の従妹で許嫁の美少女。 精神を病み、隣室で療養中。 |
| 正木敬之博士 | 九州帝国大学精神病科教授。 「狂人の解放治療」を提唱し、物語の核心となる実験を行う。 |
| 若林鏡太郎教授 | 九州帝国大学法医学教授。 「わたし」に状況を説明し、正木博士の遺志を継ぐ。 |
| 呉青秀 | 呉家の祖先で唐時代の天才画家。 愛妻を殺して腐敗する様子を描いた絵巻物を残す。 |
| 呉千世子 | 呉一郎の母で八代子の妹。 2年前に殺害され、事件の発端となる。 |
| 呉八代子 | 呉一郎の伯母でモヨ子の母。 千世子の姉として事件に関わる。 |
これらの人物たちの複雑な関係性が、『ドグラ・マグラ』の謎めいた世界観を形作っています。
『ドグラ・マグラ』の読了時間の目安
『ドグラ・マグラ』の読了時間について、具体的な目安をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文字数 | 約431,000文字 |
| 推定ページ数 | 約718ページ |
| 読了時間 | 約14時間30分 |
| 1日1時間読書 | 約15日 |
| 1日2時間読書 | 約8日 |
ただし、『ドグラ・マグラ』は非常に難解な作品なので、通常の読書速度よりも時間がかかることを覚悟してください。
内容を理解しながら読み進めるには、上記の時間の1.5倍程度を見込んでおくと良いでしょう。
また、作中作や論文部分で立ち止まることが多いため、読みやすい小説とは言えません。
『ドグラ・マグラ』はどんな人向けの小説か?
『ドグラ・マグラ』は確実に読者を選ぶ作品ですが、以下のような人には強くおすすめできます。
- 難解で実験的な文学作品に挑戦したい人
- 精神の深層や無意識の世界に興味がある人
- 謎が明確に解決されない作品を楽しめる人
- 日本近代文学の「奇書」を読破したい人
- 読書そのものが「体験」「冒険」だと感じる人
- 一度の読書で理解できなくても再読を楽しめる人
- 幻想的で狂気的な世界観に魅力を感じる人
逆に、明快なストーリー展開や論理的な解決を求める人、読みやすさを重視する人には向かないかもしれません。
しかし、文学的な挑戦を求める人にとっては、一生忘れられない読書体験となるでしょう。
あの本が好きなら『ドグラ・マグラ』も好きかも?似ている小説3選
『ドグラ・マグラ』の独特な魅力を感じた方におすすめの、似たテーマや雰囲気を持つ作品をご紹介します。
『黒死館殺人事件』(小栗虫太郎)
『ドグラ・マグラ』と共に日本探偵小説三大奇書の一つに数えられる作品です。
舞台となる「黒死館」で起こる奇怪な連続殺人事件を、探偵が哲学、宗教、医学、神秘学などの膨大な知識を駆使して推理していきます。
『ドグラ・マグラ』と同様に、物語の筋よりも作者が構築した異様な世界観と圧倒的な知識量が前面に出る点が似ています。
難解さと独特な雰囲気を求める読者には、まさにうってつけの作品でしょう。
『虚無への供物』(中井英夫)
こちらも日本探偵小説三大奇書の一つで、現実と幻想の境界が曖昧になる作品です。
主人公が過去の記憶を辿りながら、謎めいた事件の真相に近づいていく構成は、『ドグラ・マグラ』の主人公の記憶喪失からの回復過程と似ています。
メタフィクション的な要素や、読者を混乱に陥れる手法も共通しており、『ドグラ・マグラ』が好きな人なら必ず楽しめるはずです。
『砂の女』(安部公房)
日常を離れた男性が、砂の穴に閉じ込められた女性と共に生活することを強いられる物語です。
閉鎖された空間でのアイデンティティの変容や、脱出不可能な状況での精神の変質というテーマが、『ドグラ・マグラ』の精神病棟という閉鎖空間での主人公の体験と重なります。
不条理な状況下での人間の存在意義を問う哲学的な側面も、『ドグラ・マグラ』の深層心理的なテーマと通じるものがあります。
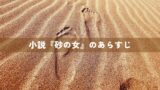
振り返り
『ドグラ・マグラ』は確実に読者を選ぶ作品ですが、その分、読み切った時の達成感は格別です。
記憶、狂気、遺伝、アイデンティティといった重厚なテーマを扱いながら、現実と幻想の境界を曖昧にする独特な構成は、まさに「奇書」と呼ぶにふさわしい作品でした。
夢野久作が10年以上かけて構想・執筆したこの作品は、日本近代文学史においても特別な位置を占める名作です。
簡単には理解できない作品ですが、それこそが『ドグラ・マグラ』の最大の魅力なのかもしれません。


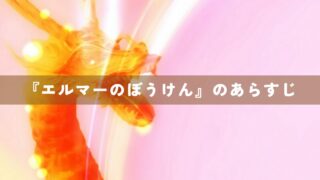
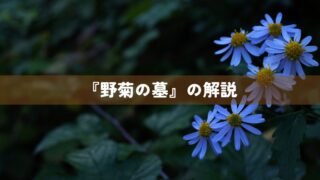


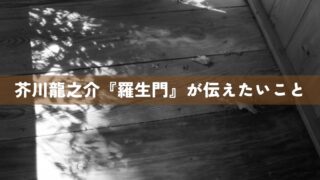
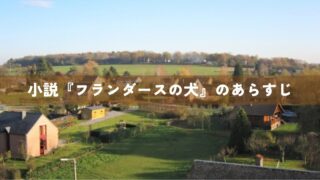

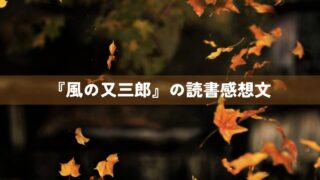


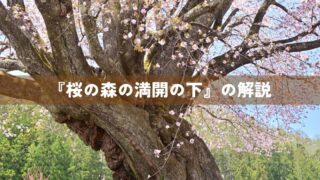





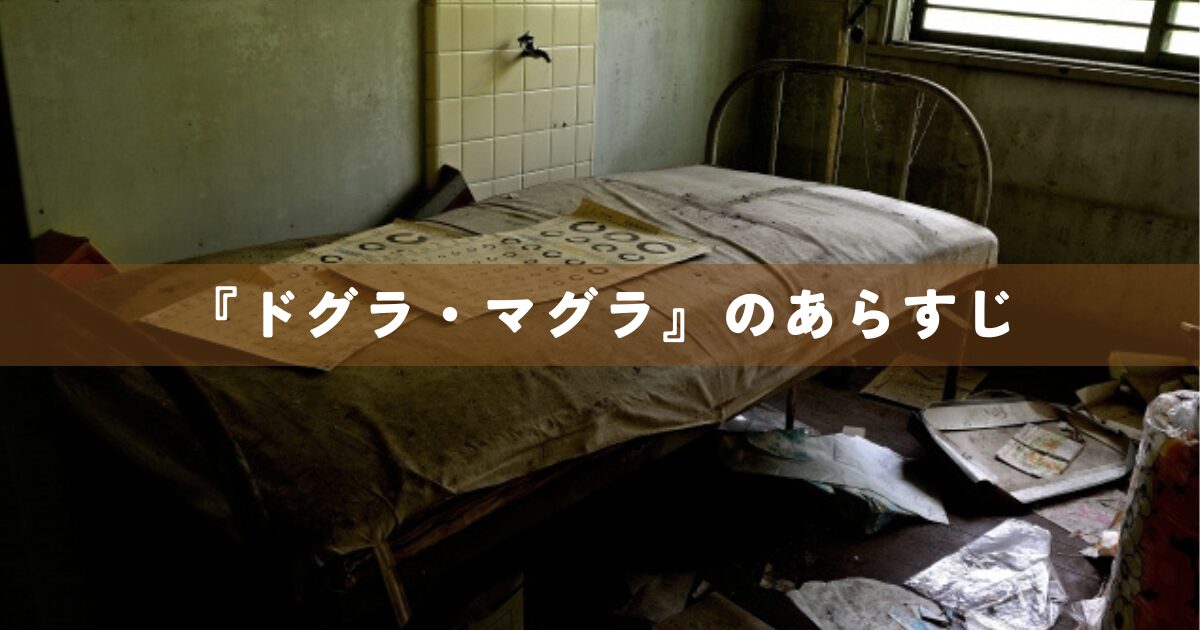
コメント