『逆ソクラテス』の読書感想文を書く予定のみなさん、こんにちは。
伊坂幸太郎さんの短編『逆ソクラテス』は、小学6年生を主人公に先入観との戦いを描いた感動作です。
読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文の書き方から例文まで、コピペではなくしっかりとした内容で、中学生から高校生まで参考になるテンプレートをご紹介していきますよ。
書き出しから題名の付け方まで、丁寧に解説していきます。
『逆ソクラテス』の読書感想文で触れたい3つの要点
『逆ソクラテス』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要なポイントが3つあります。
- 先入観や決めつけの恐ろしさと、それに立ち向かう勇気
- 子どもたちの知恵と友情による「逆転劇」の痛快さ
- 「無知の知」と「逆ソクラテス」の対比が示すメッセージ
これらの要点について「どう感じたか」を必ずメモしながら読み進めてください。
感想文は「あらすじの説明」ではなく「自分の心の動き」を書くものですから、自分の感情や考えの変化を記録することが何より大切なんです。
メモの取り方としては、読書中に気になった場面や印象的なセリフ、そして「なぜそこに心が動いたのか」を簡単に書き留めておくといいでしょう。
それでは、これら3つの要点について詳しく見ていきましょう。
先入観の描写と主人公たちの成長
物語の中心となるのは、担任の久留米先生が持つ「先入観」です。
久留米先生は草壁くんを「できない子」と決めつけ、佐久間さんを「優等生」として扱います。
このような大人の決めつけが、どれほど子どもたちを傷つけるかが生々しく描かれているんです。
あなたも学校生活で、先生や周りの大人から「あの子はこういう子」と決めつけられた経験はありませんか?
また、自分自身も知らず知らずのうちに、誰かを「こういう人」と決めつけてしまったことはないでしょうか?
この部分を読みながら、自分の体験と重ね合わせて感じたことをメモしておくと、感想文に深みが出ますよ。
子どもたちの作戦と友情
転校生の安斎くんが主導する「逆ソクラテス作戦」は、読んでいて本当にワクワクします。
カンニング作戦から始まり、美術館での計画、そして噂作戦まで、子どもたちの発想力には驚かされるはずです。
特に注目してほしいのは、最初は戸惑っていた加賀くんや佐久間さんが、次第に安斎くんの作戦に協力していく過程です。
彼らがなぜ行動を起こすようになったのか、その心の変化について考えながら読んでみてください。
また、草壁くんを助けようとする彼らの友情の深さも感動的です。
あなたなら同じ状況で、安斎くんのような行動を取れるでしょうか?
そんな自問自答をしながら読み進めると、感想文に書くべき内容が自然と見えてくるでしょう。
タイトルに込められた哲学的メッセージ
ソクラテスの「無知の知」とは、自分がいかに無知であるかを自覚することの大切さを説いた言葉です。
しかし、久留米先生は自分がすべてを知っているかのように振る舞い、生徒たちを決めつけてしまいます。
これこそが「逆ソクラテス」の正体なんです。
物語を読みながら、この対比について深く考えてみてください。
私たちの身の回りにも「逆ソクラテス」のような大人はいませんか?
そして、もしかすると私たち自身も「逆ソクラテス」になってしまうことがあるかもしれません。
この気づきこそが、『逆ソクラテス』が私たちに伝えたい最も重要なメッセージだと思います。
※『逆ソクラテス』のあらすじはこちらで詳しくご紹介しています。

『逆ソクラテス』の読書感想文のテンプレート
『逆ソクラテス』の読書感想文を書く際に使えるテンプレートをご紹介します。
このテンプレートに沿って空欄を埋めていけば、しっかりとした感想文が完成しますよ。
ステップ1:書き出しと作品の印象
私は伊坂幸太郎さんの『逆ソクラテス』を読んで、( )と感じた。
この物語は小学6年生が主人公でありながら、( )について深く考えさせられる作品である。
特に印象的だったのは( )の場面で、( )と思った。
ステップ2:先入観について感じたこと
物語の中で久留米先生が草壁くんを「できない子」と決めつける場面を読んで、私は( )と感じた。
なぜなら、私自身も( )という経験があるからだ。
大人の先入観が子どもに与える影響について考えると、( )と思う。
私たちも普段から( )しないよう気をつける必要がある。
ステップ3:主人公たちの行動への共感や驚き
安斎くんたちが考えた「逆ソクラテス作戦」は( )だと思った。
特に( )の作戦は( )で、読んでいて( )した。
もし私が同じ立場だったら、( )だろう。
彼らの友情の深さからは( )ということを学んだ。
ステップ4:「無知の知」と「逆ソクラテス」から学んだこと
ソクラテスの「無知の知」と久留米先生の「逆ソクラテス」を対比させることで、作者は( )ということを伝えたかったのだと思う。
この物語を読んで、私は( )の大切さを学んだ。
今後は( )するよう心がけたい。
ステップ5:まとめと今後への決意
『逆ソクラテス』を読んで、私は( )について改めて考えることができた。
この作品が教えてくれたのは( )ということである。
これからの生活では( )を意識して、( )していきたいと思う。
『逆ソクラテス』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】先入観と戦う勇気
私は『逆ソクラテス』を読んで、先入観の恐ろしさと、それに立ち向かう勇気の大切さを学んだ。
この物語は小学6年生が主人公だが、大人にも通じる深いテーマが描かれている。
この本を手に取った時は、タイトルの意味がよく分からなかった。
しかし、読み進めていくうちに、ソクラテスの「無知の知」とは正反対の「逆ソクラテス」が何を意味するのかが分かってきて、とても興味深く感じた。
物語の中で最も印象的だったのは、担任の久留米先生が草壁くんを「できない子」と決めつける場面である。
久留米先生は草壁くんの可能性を全く見ようとせず、表面的な情報だけで判断してしまう。
この場面を読んで、私は怒りと同時に悲しさを感じた。
なぜなら、私も小学生の時に似たような経験があるからだ。
私は運動が苦手で、体育の時間はいつも消極的だった。
すると担任の先生から「やる気がない」と決めつけられ、頑張っても認めてもらえないことがあった。
その時の悔しい気持ちを思い出しながら、草壁くんの心境を想像すると胸が痛くなった。
一方で、転校生の安斎くんの行動力には本当に驚かされた。
彼が考えた「逆ソクラテス作戦」は突拍子もないものばかりだが、そこには久留米先生の先入観を打ち破ろうとする強い意志が感じられる。
カンニング作戦や噂作戦など、大人から見れば問題のある行動かもしれない。
しかし、安斎くんの目的は友達を救うことであり、その純粋な気持ちに心を打たれた。
特に感動したのは、最初は安斎くんの作戦に戸惑っていた加賀くんや佐久間さんが、次第に協力するようになる過程である。
佐久間さんは先生に信頼される優等生だった。
それなのに、自分の立場を犠牲にしてでも友達のために行動する姿勢は立派だと思った。
私だったら、先生からの信頼を失うのが怖くて、同じような行動は取れないかもしれない。
彼らの友情の深さと勇気から、本当に大切なものは何かを教えられた気がする。
この物語のタイトルである「逆ソクラテス」について考えてみると、とても深い意味が込められていることが分かる。
ソクラテスは「無知の知」、つまり自分が無知であることを知ることの大切さを説いた。
しかし久留米先生は、自分がすべてを知っているかのように振る舞い、生徒たちを勝手に決めつけてしまう。
これこそが「逆ソクラテス」の正体なのだろう。
私たちの周りにも、このような「逆ソクラテス」的な大人はたくさんいる。
そして、もしかすると私自身も、知らないうちに誰かを決めつけてしまうことがあるかもしれない。
この本を読んで、相手のことを本当に理解しようとする姿勢の大切さを学んだ。
『逆ソクラテス』を読んで、私は人を判断する時の危険性について深く考えることができた。
先入観や決めつけは、相手の可能性を奪い、傷つけてしまう恐ろしいものだ。
しかし同時に、安斎くんたちのように勇気を持って行動すれば、そのような理不尽な状況を変えることもできるのだと希望を感じた。
これからの学校生活では、友達を表面的な情報だけで判断せず、その人の本当の姿を見ようと努力したい。
そして、もし理不尽なことがあった時は、安斎くんのように勇気を持って行動できる人になりたいと思う。
『逆ソクラテス』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】「無知の知」が照らし出す現代社会の問題
伊坂幸太郎の短編『逆ソクラテス』を読んで、私は現代社会に潜む深刻な問題について考えさせられた。
この作品は一見、小学生を主人公とした軽快な物語のように見える。だが、そこに込められたメッセージは非常に重要で、私たちの日常生活にも直結する普遍的なテーマが扱われている。特に「先入観」や「決めつけ」の危険性を、ここまで鮮明に描いた作品は珍しいのではないだろうか。
物語の冒頭で、久留米先生が生徒たちにソクラテスの「無知の知」を語る場面がある。皮肉にも、その久留米先生こそが「無知の知」とは正反対の態度を取っている。彼は草壁くんを「できない子」、佐久間さんを「優等生」と決めつけ、その枠から外れた情報を受け入れようとしない。この矛盾した状況が、物語全体のテーマを象徴しているように思えた。
私は久留米先生の姿に、現代社会の大人たちの姿を重ねずにはいられなかった。肩書きや外見、過去の実績だけで人を判断する人は身の回りにも数多く存在し、そのような判断が「正しい」とされてしまうことさえあるのだ。私自身も高校生活で似た経験をした。文系科目は得意だが数学は苦手で、質問に行った時、先生から「君は文系だから数学は諦めなさい」と言われてしまった。その時の悔しさと絶望感は今も忘れられない。草壁くんが受けた仕打ちを読みながら、あの時の感情がよみがえってきた。
一方で、転校生の安斎くんの存在は非常に魅力的だった。彼の「逆ソクラテス作戦」は一見子どもらしい突拍子もない計画に見えるが、その背後には大人社会の矛盾を突く戦略的思考が隠されている。安斎くんは久留米先生の先入観を逆手に取り、その偏見がいかに浅はかで危険かを証明してみせた。
特に印象的だったのは、カンニング作戦が失敗した後、より巧妙な「噂作戦」を考案する場面である。安斎くんは大人の心理を巧みに読み、草壁くんが「ヒーロー」として認識される状況を演出した。この作戦の見事さには感嘆させられると同時に、こうした方法を用いなければ友達を救えない現実の理不尽さに憤りを感じた。
物語の中で最も心を動かされたのは、最初は作戦に戸惑っていた加賀くんや佐久間さんが、次第に協力者となっていく過程である。特に佐久間さんの変化は象徴的だった。彼女は久留米先生から信頼される「優等生」という立場にあり、その立場を失うリスクを承知で協力を決断した。その勇気には頭が下がる思いだった。私は佐久間さんの行動を見て、自分自身の生き方についても考えさせられた。もし友達が理不尽な扱いを受けた時、私は自分の立場を犠牲にしてでも助けることができるだろうか。正直、自信はない。しかし彼女の決断は、本当に大切なものは何かを教えてくれた。
また、草壁くん自身の成長も見逃せない。物語の終盤、彼が久留米先生に「僕は、そうは、思いません」と言い切る場面は胸が熱くなった。長い間「できない子」として扱われてきた彼が、ついに自分の意見を堂々と述べる姿は、人間の尊厳の回復を象徴している。この場面から私は「自分の声を持つことの大切さ」を学んだ。周囲から否定的な評価を受けても、自分自身の価値観を大切にし、勇気を持って表明する必要があるのだと感じた。
物語のタイトル「逆ソクラテス」という言葉は、現代社会の病理を的確に表現している。ソクラテスの「無知の知」は、自分の無知を自覚することで真の知恵に近づけるという教えだ。だが、久留米先生のような「逆ソクラテス」の人々は、自分が全てを知っていると思い込み、新しい情報や異なる視点を拒否する。その態度は個人の成長を阻むだけでなく、他者の可能性まで奪ってしまう。
私たちの社会には、学歴や職業、年収といった外的要素で人を判断する風潮が根強い。しかし『逆ソクラテス』が示すのは、そのような表面的な評価基準がいかに危険で無意味かということである。一人ひとりの人間には無限の可能性が秘められており、それを引き出すには先入観を捨て、相手と真正面から向き合うことが必要なのだ。
『逆ソクラテス』を読んで、私は人間関係における「見る目」の重要性を改めて感じた。久留米先生のような「逆ソクラテス」にならないためには、常に自分の判断を疑い、相手の新しい一面を発見しようとする姿勢が大切だ。そしてもし理不尽な状況に遭遇した時は、安斎くんや佐久間さんのように勇気を持って行動することが求められる。
この作品が教えるのは、真の教育とは知識を一方的に与えることではなく、一人ひとりの可能性を信じて引き出すことだという点である。私も将来、人を指導する立場に就くかもしれない。その時は必ず『逆ソクラテス』の教訓を忘れず、相手の可能性を信じて向き合いたい。また、日常生活においても安易に人を決めつけることなく、常に謙虚な気持ちで相手を理解しようと努力していきたい。
振り返り
この記事では、『逆ソクラテス』の読書感想文を書く際に重要な3つのポイントから、実際の例文まで詳しくご紹介しました。
伊坂幸太郎さんのこの作品は、先入観の危険性という深いテーマを小学生の視点から描いた傑作です。
読書感想文を書く際は、物語のあらすじを説明するのではなく、自分がどう感じたかを中心に書くことが大切ですよ。
ご紹介したテンプレートや例文を参考にしながら、あなた自身の体験や感情を盛り込んで、オリジナルの感想文を完成させてください。
きっと素晴らしい作品ができあがるはずです。

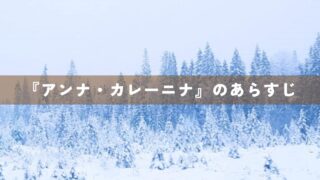

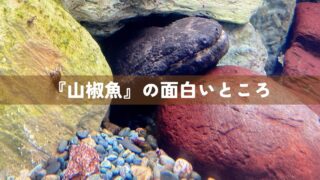

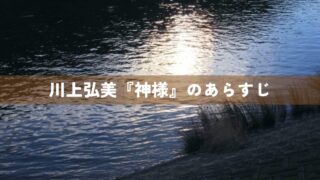









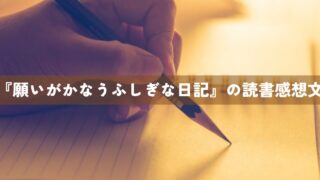
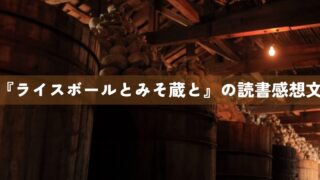

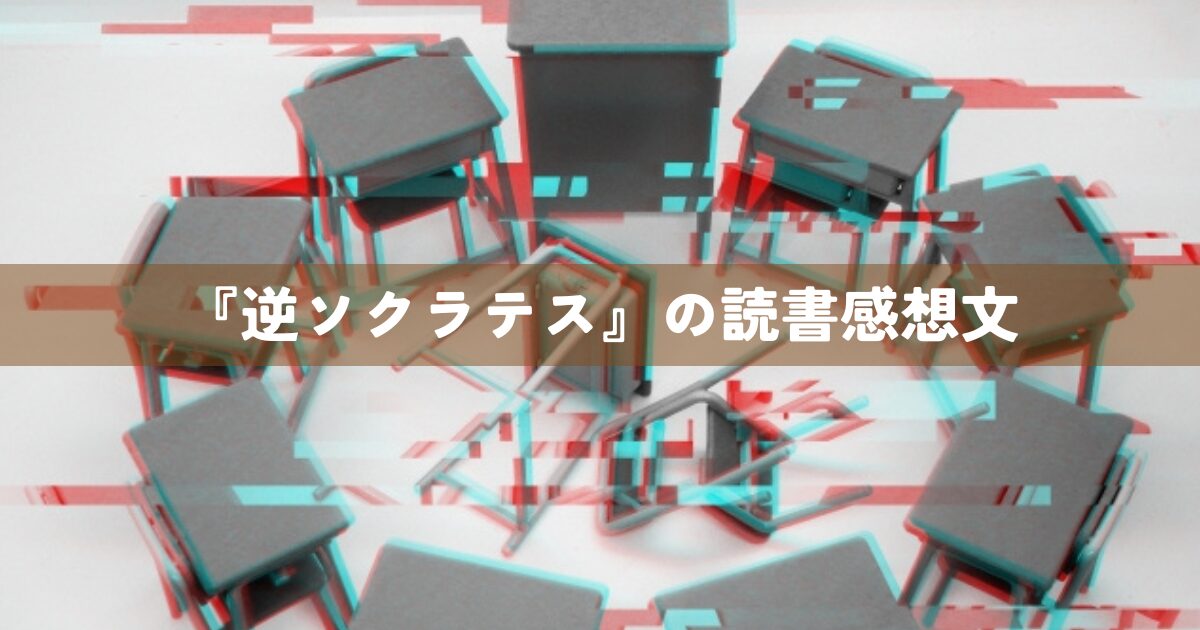
コメント