『「のび太」という生き方』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
横山泰行さんによる『「のび太」という生き方』は、ドラえもんの登場人物であるのび太を通じて人生の生き方を語る自己啓発書として2004年に出版され、多くの読者に愛され続けています。
この作品は単なるドラえもんの解説書ではなく、のび太の「失敗を恐れない生き方」や「ありのままの自分を受け入れる姿勢」から学べる人生の教訓が詰まった深い内容ですね。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、小学生・中学生・高校生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉でテンプレートに頼らない心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『「のび太」という生き方』の読書感想文で触れたい3つの要点
『「のび太」という生き方』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要な要点が3つあります。
- 「ダメな自分」を受け入れることの重要性
- 「他力本願」を肯定的に捉える視点
- 「失敗」を恐れない生き方
これらの要点について「自分はどう感じたか」をメモしておくことが、説得力のある感想文を書く上でとても大切です。
メモを取る時は、各要点を読みながら「自分の体験と似ている部分はないか」「共感できる部分はどこか」「疑問に思う点はないか」といった視点で自分の気持ちを書き留めてください。
感想文で最も重要なのは、あらすじの説明ではなく「あなた自身がどう感じ、何を学んだか」を伝えることだからです。
それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
「ダメな自分」を受け入れることの重要性
のび太は勉強も運動も苦手で、すぐにあきらめてしまう「ダメな人間」として描かれています。
しかし著者の横山教授は、その「ダメさ」を否定するのではなく、むしろ「それが自分である」と受け入れることの重要性を説いています。
現代社会では完璧であることが求められがちですが、この本は「不完全な自分も価値がある」というメッセージを伝えています。
あなた自身も、勉強や部活動で思うようにいかなかった経験があるのではないでしょうか。
そんな時に自分を責めるのではなく、「これも自分の一部だ」と受け入れることで、かえって前向きに取り組める場合があります。
この要点について感想文を書く時は、自分の「ダメな部分」にどう向き合ってきたか、この本を読んでその捉え方がどう変わったかを具体的なエピソードと共に書くと深みが出ますよ。
「他力本願」を肯定的に捉える視点
のび太は困ったことがあるとすぐにドラえもんに頼ります。
一般的に「他力本願」はネガティブな言葉として使われがちですが、著者はこれを「人を頼ることのできる才能」として肯定的に捉えています。
現代人は「一人でがんばらなければいけない」というプレッシャーを感じることが多いですが、実際は周りの人との協力や助け合いが人生を豊かにします。
のび太のように素直に助けを求められることは、実は人間関係を築く上でとても大切な能力なのです。
あなたも友達や家族、先生に助けてもらった経験があるはずです。
その時に感じた感謝の気持ちや、人とのつながりの温かさを思い出してみてください。
感想文では「人に頼ることの大切さ」について、自分の経験を交えながら書くと説得力が増します。
また、今後は積極的に他者との協力を大切にしていきたいという前向きな決意も加えると良いでしょう。
「失敗」を恐れない生き方
のび太は、どんなに失敗しても決して立ち直れないほど落ち込むことはありません。
すぐにまた次のことを始めて、失敗を繰り返します。
この「失敗を恐れないタフさ」が、のび太の最大の強みであると著者は指摘しています。
多くの人は失敗を恐れて行動できなくなることがありますが、のび太は失敗から学びながらも前進し続けます。
これは現代を生きる私たちにとって、とても重要な生き方の指針となります。
あなたも今まで「失敗するかもしれない」という不安で挑戦をためらったことがあるのではないでしょうか。
でも失敗は成長のチャンスでもあります。
感想文では、失敗を恐れて行動できなかった自分の経験や、この本を読んで「失敗してもいいんだ」と思えるようになったこと、失敗から何を学べるかといった視点を書くと良いですよ。
さらに、今後は失敗を恐れずに新しいことにチャレンジしていきたいという気持ちも表現してみてください。
※『「のび太」という生き方』のあらすじや要約はこちらでご覧ください。

『「のび太」という生き方』の読書感想文テンプレート
『「のび太」という生き方』の読書感想文を、小学生でも書けるようにステップバイステップで解説します。
このテンプレートを使えば、800字の感想文を簡単に書くことができます。
ステップ1:書き出し(約100字)
なぜこの本を読んだのか、読む前の「のび太」に対するイメージを書きましょう。
* ぼくは、夏休みの宿題で『「のび太」という生き方』という本を読みました。
* マンガののび太は、勉強も運動も苦手で、ダメなところばかり目立つキャラクターだと思っていました。
* 最初は「のび太のどこがいいんだろう?」と不思議に思いながら読み始めました。
ステップ2:本の紹介と一番心に残ったこと(約200字)
本の内容を簡単に紹介し、特に心に残ったポイントを一つ選びます。
* この本は、いつもダメなのび太が、じつはすごい才能を持っていると教えてくれました。
* その中でも一番心に残ったのは、「**ダメな自分を受け入れること**」という部分です。
* のび太は、テストで0点をとったり、ジャイアンにいじめられたりしても、すぐに「まあいっか」と立ち直ります。それは、自分のダメなところを隠したり、ごまかしたりしないからだ、と書かれていて、とてもおどろきました。
ステップ3:自分の経験と結びつける(約300字)
ステップ2で選んだポイントについて、自分の経験をふり返って書いてみましょう。
* ぼくも、苦手な算数のテストで悪い点をとったとき、お母さんに見せるのがはずかしくて、かくそうとしたことがあります。
* でも、のび太は0点のテストをお母さんに正直に見せて、怒られても、次の日にはまた元気に遊びます。
* この本を読んで、ダメな自分をかくすよりも、ちゃんと向き合うことの大切さを学びました。ダメな自分を認めることが、前に進むための第一歩なんだと思いました。
ステップ4:他のポイントについても書く(約100字)
心に残った他のポイントについても、簡単に触れてみましょう。
* また、のび太はすぐにドラえもんに助けを求めます。
* それは「他人に頼る才能」だと書いてあって、人を頼ることは悪いことじゃないんだと気づきました。
* それに、何度失敗してもくじけないのび太の「失敗を恐れない心」もすごいと思いました。
ステップ5:まとめ(約100字)
この本を読んで、これからどう生きていきたいか、どんな自分になりたいかを書きます。
* この本を読む前のぼくは、ダメなところがない完璧な人になりたいと思っていました。
* でも、今はのび太のように、ダメな自分も受け入れて、失敗を恐れずに色々なことにチャレンジできる人になりたいです。
* そして、困ったときは一人でがんばらずに、まわりの人たちを頼ってみようと思います。
-このテンプレートを参考に、自分の言葉で文章を組み立ててみてください。
のび太から学んだことを自分の生活にどう活かしていきたいか、具体的に書くと、より素晴らしい感想文になります。
『「のび太」という生き方』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】のび太に教えてもらったこと
私は『「のび太」という生き方』を読んで、のび太のことが今までよりもっと好きになった。
のび太はいつも失敗ばかりして、勉強もできず、運動も苦手で、よく友だちにバカにされている。
でも、この本を読んでわかったのは、のび太はすごくがんばっているし、やさしい心を持っているということだ。
のび太は、どんなに失敗しても、くじけずに何度も立ち上がる。
私なら、うまくいかないとすぐにあきらめてしまうけれど、のび太は違った。
算数のテストで0点を取っても、次の日にはまた元気に学校に行く。
それに、のび太は友だちにやさしく、ジャイアンやスネ夫にいじめられても、うらみに思わない。
そんなのび太の性格にとても学ぶことがあった。
この本では、「がんばりすぎないで、自分のペースでいいよ」という考え方が紹介されている。
私もつい、できないことをがんばりすぎて疲れてしまうことがある。
でも、この本を読んだら、自分らしく楽しく生きることの大切さがわかった。
のび太は、ドラえもんにいつも助けてもらっているけれど、それは悪いことではないと書いてあった。
人に助けてもらうことも、人を助けることも、どちらも大事なことなんだと思った。
私も困ったときは素直にお母さんや先生に相談して、友だちが困っているときは手伝ってあげたい。
のび太のように、失敗を恐れずに挑戦して、まわりの人に助けてもらいながら生きていくことが、幸せな人生につながると私は思う。
これからは、もっとのび太のようにやさしくて、前向きな気持ちで毎日をすごしたい。
そして、自分のダメなところも認めながら、でも努力することは忘れずに成長していきたい。
この本を読んでから、私は失敗を「恥ずかしいこと」ではなく、「新しい一歩のきっかけ」として受け止めたいと思うようになった。
『「のび太」という生き方』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】のび太の生き方に学ぶ、ありのままの自分で輝く方法
野比のび太という名前は誰もが知っている。
世間では「ダメな子」の代名詞のように扱われ、実際に『ドラえもん』の劇中では勉強ができず、運動も苦手で、よくジャイアンやスネ夫にいじめられている。
それなのに、彼は40年以上も全国の子供たちに愛されている。
そんなのび太の生き方を横山泰行先生が研究し、書いたのが『「のび太」という生き方』という本である。
この本を読んで、のび太に対しての見方が変わった。
のび太はただの「ダメな子」ではなく、失敗してもあきらめず、やさしさと夢を持って生きる強い子だということがわかったのだ。
のび太は自分の欠点を受け入れながらも、自分らしく生きている。
その姿が私に大きな勇気を与えてくれた。
特に印象に残ったのは、「がんばりすぎなくていい」というメッセージである。
現代社会では、「完璧でなければならない」とか「周りと比べて劣ってはいけない」というプレッシャーが強い。
でも、この本はそうした生き方に疲れた人に「自分なりでいいんだよ」とやさしく寄り添っている。
のび太のように失敗もするけれど、それでも前を向き、自分のペースで夢に向かっていく姿が「のび太メソッド」として説かれているのが心に響いた。
私も中学生になってから、まわりの友達と自分を比べて落ち込むことが多くなった。
テストの点数や部活動の成績で一喜一憂し、うまくいかないと自分を責めてばかりいた。
でも、のび太を見ていると、失敗しても「まあ、いいか」と切り替えて次に進んでいく。
その前向きさが、実は一番大切なことなのかもしれない。
また、のび太がドラえもんや友達に助けられながらも、自分の意志で行動することの大切さも学んだ。
ひみつ道具に頼ることは悪いことではなく、人は一人では生きられないということを、この本はやさしく教えてくれる。
人に頼ることも勇気の一つだと感じた。
私は今まで「人に迷惑をかけてはいけない」と思って、困っていても一人で抱え込むことが多かった。
でも、それは間違いだったのかもしれない。
のび太のように素直に助けを求めて、感謝の気持ちを忘れずにいることが大切なのだ。
さらに、この本を読んで改めて気づいたのは、のび太は決して「弱い人」ではなく、人間らしい強さを持った存在だということだ。
失敗しても立ち上がり、友達を思いやり、どんな状況でも夢を見る姿は、多くの人が忘れかけている大切な生き方を教えてくれる。
私自身、これまで「成功すること」ばかりを目標にしていたけれど、のび太の生き方を知ってからは、うまくいかなくてもそこに学びや意味を見いだせるようになりたいと思うようになった。
この本を読むことで、私は自分の弱さや失敗を恐れず、自分らしく生きることの価値に気づいた。
これからは、周りと比べるのではなく、自分自身の良さを大事にし、のび太のようにやさしさと夢を忘れずに生きていきたいと思う。
完璧でなくてもいい、失敗してもいい、そう思えるようになったことが、この本を読んだ一番の収穫である。
『「のび太」という生き方』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】のび太という生き方から学ぶ人生の本質
「のび太」と聞いて、多くの人は勉強も運動も苦手で、何度も失敗し、友だちにからかわれる”ダメな子”のイメージを思い浮かべるだろう。
私ものび太に対しては「泣き虫・弱虫・いくじなし」とネガティブなワードならいくらでも思いついてしまう。
しかし、『「のび太」という生き方』(横山泰行著)を読んで、その固定観念が大きく変わった。
この本は、のび太の本当の強さや生き方を掘り下げ、彼こそが人生の勝ち組であるという説を提唱している。
のび太の魅力は、「失敗してもくじけず立ち上がる強さ」「人にやさしく思いやる心」「それでいて、自分らしく生きる姿勢」にある。
現代社会には完璧主義や過度の競争が蔓延し、無理に理想を追いかけることが求められているが、本書は「がんばりすぎない」「自分のペースで生きていい」という価値をやさしく説く。
のび太はドラえもんのひみつ道具に助けられることもあるが、それらに頼り切るのではなく、自分の意志で行動し夢を叶えていく。
これは、人はひとりで生きるのではなく、周囲の助けを借りて支え合いながら生きることの重要性を教えてくれる。
私自身、高校に入学してから進路や成績のプレッシャーに押しつぶされそうになることが多かった。
周りの友人たちが優秀に見え、自分だけが取り残されているような気持ちになった。
特に模擬試験の結果が思うようにいかなかった時は、「自分はダメな人間だ」と自己否定に陥ることが多かった。
しかし、この本を読んで、のび太の生き方を知ると、そうした考え方が間違っていることに気づかされた。
のび太は自らの弱さや失敗を受け入れ、それを恥じることなくありのままの自分でいる勇気を持っている。
これは私たちが忘れがちな「自己肯定」の大切なメッセージである。
私は学業や人間関係の悩みから自分を責めがちだったが、この本でのび太の姿を通じて「完璧でなくていい」「失敗しながらも自分のリズムで進めばよい」と気づかされた。
また、のび太の「他力本願」な面についても、新たな視点を得ることができた。
これまで私は、人に頼ることを「甘え」や「弱さ」だと思っていた。
自立することが大人への第一歩だと考え、困っても一人で解決しようとしてきた。
しかし、著者は「人を頼ることのできる才能」として肯定的に捉えている。
確かに、のび太は素直にドラえもんや友人たちに助けを求め、その結果として豊かな人間関係を築いている。
人は一人では限界があり、互いに支え合うことでより大きなことを成し遂げることができる。
この考え方は、私の人生観を大きく変えた。
さらに印象的だったのは、のび太の「失敗を恐れない生き方」である。
のび太は数え切れないほど失敗を重ねるが、それに打ちひしがれることなく、常に新しいことに挑戦し続ける。
この姿勢こそが、彼の最大の強みなのだと著者は指摘している。
私は今まで失敗を恐れるあまり、新しいことに挑戦することを避けてきた。
部活動でも勉強でも、「うまくいかなかったらどうしよう」という不安が先に立ち、積極的に行動できずにいた。
しかし、のび太を見ていると、失敗は成長の機会であり、挑戦しないことの方がもったいないのではないかと思えてきた。
失敗から学び、次に活かすことができれば、それは決して無駄ではない。
のび太の生き方は、子ども向けの単純な話ではなく、大人が人生を考える上でも普遍的な教訓に満ちている。
失敗を恐れずに挑戦し、他人に寛容であり助け合い、自分らしく歩むこと。
これこそが幸福な人生の鍵だと実感した。
そして私は、この本を読み終えた後、自分の過去の失敗を振り返りながら、「あのときの経験が今につながっているのではないか」と思うようになった。
これまで後悔ばかりしていた出来事も、見方を変えれば成長の種だったのだと感じられるようになったのは大きな変化である。
現代社会は効率や結果を重視しがちだが、のび太のようにプロセスを大切にし、人とのつながりを重視する生き方にこそ、本当の豊かさがあるのかもしれない。
完璧さを追い求めて疲れ果てるより、不完全さを受け入れて笑顔で生きる方が、どれほど健やかで人間らしいだろうか。
のび太はまさに、その生き方を体現している。
特に印象的なのは、のび太がどんなに失敗しても決して笑顔を忘れないことだ。
その姿は読者に「大丈夫、きっと乗り越えられる」と静かに励ましを与えてくれる。
この本から得た教訓を胸に、私はどんな困難にも前向きに立ち向かい、ありのままの自分を大切にして夢を追い続けたいと思う。
完璧な人間になる必要はない。
のび太のように、失敗を恐れず、人を大切にし、自分らしく生きていけばいいのだ。
それが、この本が教えてくれた最も重要なメッセージである。
振り返り
今回は『「のび太」という生き方』の読書感想文の書き方について、具体的な例文と共に詳しく解説してきました。
この作品の魅力は、のび太という身近なキャラクターを通じて人生の大切な教訓を学べることにあります。
「ダメな自分を受け入れること」「人に頼ることの大切さ」「失敗を恐れない生き方」という3つの要点を中心に感想文を構成することで、読み手の心に響く作品に仕上がるはずです。
小学生の皆さんは素直な気持ちで、中学生の皆さんは自分の体験と重ね合わせて、高校生の皆さんは将来への思いも込めて書いてみてください。
大切なのは、コピペに頼らず、テンプレート通りではない、あなた自身の言葉で思いを表現することです。
のび太のように失敗を恐れずに、まずは書き始めてみましょう。きっと素晴らしい読書感想文が完成しますよ。
■参照サイト:株式会社アスコム




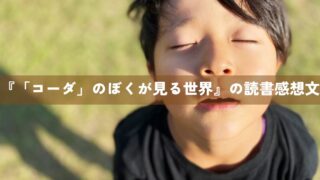
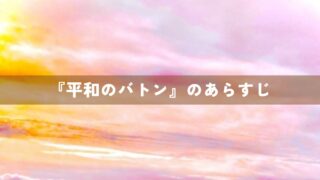
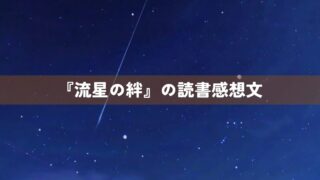




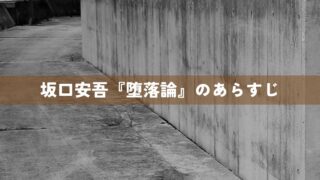







コメント