『宇宙のみなしご』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
森絵都さんの『宇宙のみなしご』は、中学2年生の陽子と弟のリンが屋根のぼりという秘密の遊びを通して、思春期の葛藤や友情、自己発見を描いた青春ストーリーですね。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生・高校生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
テンプレートも用意したので、あなただけのオリジナルな感想文を一緒に作っていきましょう。
『宇宙のみなしご』の読書感想文で触れたい3つの要点
『宇宙のみなしご』の読書感想文を書く際には、この物語の核となる重要なテーマを理解することが大切です。
感想文を書く前に、まず以下の3つの要点について、あなたがどう感じたかをメモしておくことをおすすめします。
- 主人公陽子の心の変化と孤独感
- 「屋根のぼり」が象徴する意味
- 孤独を希望に変えるメッセージ
これらの要点について感じたことをメモする時は、「なぜそう思ったのか」「自分の体験と重なる部分はあるか」「登場人物の気持ちがどう変わったか」という視点で書いてみてください。
感想文では「何が書かれていたか」よりも「それを読んでどう感じたか」が最も重要になります。
あなた自身の気持ちや体験と重ね合わせることで、オリジナリティのある素晴らしい感想文が完成するでしょう。
主人公陽子の心の変化と孤独感
物語の中心にいる陽子は、両親が仕事で忙しく、弟のリンと2人きりで過ごすことが多い中学2年生です。
彼女が抱える「宇宙のみなしご」のような孤独感は、多くの思春期の人が経験する複雑な感情ですね。
陽子の孤独感は、単に一人でいることの寂しさではありません。
周りに人がいても感じる「誰にも理解されない」という心の奥底にある孤独です。
この孤独感から始まり、物語を通して陽子の心がどのように変化していくかに注目してみてください。
特に、キオスクとの出会いや屋根のぼりの体験を通して、陽子が自分の孤独と向き合い、やがて他者とつながる喜びを見出していく過程は感動的です。
あなた自身も、陽子のような孤独感を感じたことはありませんか?
そんな時、どんな気持ちだったか、どうやってその気持ちと向き合ったかを思い出しながら読んでみると、より深い感想が書けるはずです。
陽子の成長過程を通して、孤独は決して恥ずかしいことではなく、誰もが抱える自然な感情だということが伝わってきます。
「屋根のぼり」が象徴する意味
『宇宙のみなしご』で最も印象的なのが、陽子たちが夜中にこっそり行う「屋根のぼり」という秘密の遊びです。
この屋根のぼりは、単なるいたずらや危険な遊びではありません。
日常の息苦しさから逃れ、自分だけの場所を見つけようとする陽子たちの心の表れなのです。
屋根の上は、学校や家庭といった大人が作ったルールから少しだけ離れることができる特別な場所です。
そこで陽子たちは、普段は誰にも話せない本当の気持ちを語り合います。
屋根のぼりが陽子にとってどのような意味を持っていたのか、深く考えてみてください。
現実逃避でありながら、同時に自分自身と向き合うための大切な時間でもあったのではないでしょうか。
また、友達との秘密を共有し、絆を深める場所としての役割も果たしています。
あなたにも、陽子たちの屋根のような「特別な場所」はありますか?
それは物理的な場所かもしれませんし、心の中の場所かもしれません。
そんな自分だけの居場所について思いを巡らせながら、屋根のぼりの意味を考えてみると、きっと素晴らしい感想が浮かんでくるでしょう。
孤独を希望に変えるメッセージ
『宇宙のみなしご』というタイトルは、一見ネガティブな響きを持っていますが、この作品は孤独を否定していません。
むしろ、誰もが心の中に抱える孤独こそが、人と人をつなぐ共通の感情なのだと教えてくれます。
陽子が感じていた「宇宙にたった一人でいる」ような孤独感は、物語の終わりには「みんなそれぞれが宇宙のみなしごなんだ」という気づきに変わっていきます。
孤独は乗り越えるものではなく、共有することでより深いつながりが生まれるものなのです。
この作品から学べるのは、孤独はネガティブなものではなく、誰かとつながるための大切な一歩だということです。
自分の弱さや誰にも言えない心の闇も、それは自分を形作る大切な一部なんですね。
あなたは孤独を感じた時、どんな風に考えますか?
この作品を読んで、孤独に対する見方が変わったでしょうか?
孤独を感じる自分や周りの人たちへの見方がどう変わったか、そんな気づきを書くと、読書体験がより豊かなものになります。
森絵都さんが伝えたかった「孤独は人をつなぐ力になる」というメッセージを、あなた自身の言葉で表現してみてください。
※『宇宙のみなしご』のあらすじはこちらで簡単に短くご紹介しています。

『宇宙のみなしご』の感想文テンプレート
『宇宙のみなしご』の読書感想文テンプレートをご用意しました。
以下の1~5のステップに「自分が感じたこと」を入れ込んでいくと、自然と整った感想文が完成しますよ。
・作品タイトル、作者名、ジャンルを簡単に紹介する。
・なぜこの本を読もうと思ったのか、どんな期待を持って読み始めたかを書く。
・中学2年生の陽子が抱える孤独や不安、家族関係の状況を説明。
・陽子の鋭い観察力や感受性、そして思春期特有の心の揺れ動きを具体的に書く。
・陽子が外の世界や自分、自分の置かれた状況と葛藤しながら少しずつ成長していく様子を書く。
・陽子と弟、仲間たちが夜の屋根にのぼる秘密の遊びで、現実から少し離れられる特別な場所であることを説明。
・この遊びが友情の絆や心の解放、そして自分らしくいられる場所としての象徴であることを考察。
・「宇宙のみなしご」というタイトルと絡めて、広大な宇宙での孤独と輝きのメタファー(隠喩)を述べる。
・物語全体を通じて感じた「孤独でも決して一人ではない」というテーマを書く。
・登場人物たちが支え合い、孤独を力に変えていく姿が希望や勇気を与えてくれることを書く。
・自分自身の経験や考えと照らし合わせて、作品のメッセージが自分の生き方にどのように影響を与えたかを書く。
・全体を振り返り、この作品から得たものや感動したことを簡潔にまとめる。
・今後の自分の生活や考え方にどう役立てたいかを書き添えて締めくくる。
『宇宙のみなしご』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】みんな宇宙のみなしご
『宇宙のみなしご』を読んで、最初はタイトルがちょっとさびしそうだなと思った。
でも読んでいくうちに、主人公の陽子ちゃんの気持ちがよく分かって、私も同じ気持ちになったことがあるなと思い出した。
陽子ちゃんは中学2年生で、お父さんとお母さんがお仕事で忙しく、弟のリンくんと2人でいることが多い。みんな仲良く過ごしているのに、時々「私だけひとりぼっちなのかな」と感じる。私も友達と遊んでいるのに、なぜかさびしくなることがあるから、陽子ちゃんの気持ちがよく分かった。
物語で一番おもしろかったのは、夜中にこっそり屋根にのぼる「屋根のぼり」という遊びだ。危ないからやってはいけないけれど、陽子ちゃんたちにとっては特別な場所なんだと思った。屋根の上では普段言えない本当の気持ちを話せる。学校や家では言えないことも、夜空の下なら素直に言えるのだ。私にもそんな場所があったらいいなと思った。
いじめられっ子のキオスクくんが出てきた時は、最初はこわいと思った。でも、彼も陽子ちゃんたちと同じようにさびしいのだと分かった。みんな違う人だけど、心の奥では似た気持ちを持っていると気づいた時、なんだか温かい気持ちになった。
この本を読んで「宇宙のみなしご」という言葉の意味が分かった。宇宙にたった1人でいるようなさびしさ。でもそれは誰もが持っているから、本当はひとりぼっちじゃない。陽子ちゃんも最後に、みんなが「宇宙のみなしご」なんだと気づく。だから、さびしさも悪いことじゃないと思えた。
私も時々さびしい気持ちになるけれど、それは私だけじゃないと分かって安心した。友達や家族と一緒でも心の奥のさびしさは消えないかもしれない。けれど、その気持ちがあるから人の気持ちを理解し、やさしくできるのだと思う。
『宇宙のみなしご』は、思春期の複雑な気持ちを教えてくれる素敵な本だった。陽子ちゃんのように、自分の気持ちを大切にし、友達とのつながりを大事にしていきたい。
『宇宙のみなしご』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】孤独という共通言語
森絵都さんの『宇宙のみなしご』を読み終えて、まず心に残ったのは、思春期の複雑な気持ちがこんなにも丁寧に描かれていることへの驚きだった。
主人公の陽子が抱える孤独感は、私自身が日頃感じている言葉にならない感情と重なる部分が多く、読み進めるうちに自分の内面を覗き込んでいるような不思議な感覚になった。
陽子は中学2年生で、両親が仕事で忙しく、弟のリンと過ごすことが多い。特別に孤立しているわけではなく友達もいるのに、時々「自分だけが宇宙に放り出されたみなしごのようだ」と感じてしまう。この感覚は私にもよく分かる。クラスの友達と一緒にいても、家族と過ごしていても、ふと「本当にここにいるのかな」と思うことがある。陽子の孤独感は、単なる寂しさではなく「誰にも理解されない」という感覚なのだと思う。
物語の中心となる「屋根のぼり」は、ただの危険な遊びではない。陽子たちにとって屋根の上は、学校や家庭のルールから離れ、本当の自分でいられる特別な場所だ。夜空の下で友達と語り合う時間は、彼らが素直な気持ちを話せる貴重な瞬間なのだろう。私にもそんな場所が欲しいと思った。屋根のぼりは現実逃避でもあるが、同時に自分自身と向き合うための大切な時間でもあった。
印象的だったのはキオスクの存在だ。最初はクラスのいじめられっ子として登場し、陽子たちとは違う世界にいるように見えた。しかし屋根の上で心を通わせるうちに、彼もまた孤独を抱えた一人の人間だと分かってくる。キオスクの変化は、孤独な魂同士が出会うことで生まれる奇跡のようだった。彼は陽子たちによって救われただけでなく、彼自身も陽子たちを変える存在になった。
この作品が問いかけるのは「孤独とは何か」だ。『宇宙のみなしご』というタイトルは最初は悲しく響くが、やがて孤独の悲しさだけを描いていないことに気づく。陽子が「自分は宇宙にたった一人」と感じていた孤独感は、「みんなそれぞれが宇宙のみなしごなのだ」という気づきに変わっていく。誰もが心の奥に孤独を抱えている。その孤独こそが、人と人をつなぐ共通の言語になるのかもしれない。
森さんの文章は、言葉にしにくい感情にぴったりの表現を与えてくれるような優しさがある。思春期の痛みや葛藤を否定せず、それも含めて自分なんだと受け入れる大切さを教えてくれた。読み終えた後、私は自分の孤独について深く考えた。一人でいる時に感じる寂しさも、みんなと一緒にいて感じる孤独感も、それは自分を形作る大切な一部だと思えるようになった。
孤独を消すのではなく受け入れ、誰かと共有することで、もっと深いつながりが生まれるのだろう。『宇宙のみなしご』は、思春期を生きる私たちに自分の心を見つめ直すきっかけを与えてくれる素晴らしい作品だった。陽子のように、自分の気持ちを大切にしながら、他者とのつながりを見つけていきたいと思う。
『宇宙のみなしご』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】孤独という名の架け橋
森絵都さんの『宇宙のみなしご』を読み終えて、思春期という特別な時期の複雑さと美しさを改めて感じた。
この作品は、表面的には中学生の日常を描いた静かな物語だが、その奥には誰もが経験する普遍的な感情が丁寧に織り込まれている。主人公の陽子が抱える孤独感は、現代を生きる多くの人が共感できるリアルなものだ。物語の冒頭から、陽子の心の微細な動きに引き込まれた。
彼女は中学2年生で、友達もいれば家族もいる。特別に孤立した存在ではない。それなのに、ふとした瞬間に「自分だけが宇宙に放り出されたみなしごのようだ」と感じてしまう。この感覚は、私自身が高校生活の中で何度も経験してきたものと重なる。クラスメイトと楽しく話していても、部活動で仲間と汗を流していても、心の奥底に存在する説明のつかない孤独感。それは現代社会で多くの人が抱える根深い問題なのかもしれない。陽子の孤独は単純な寂しさではなく、不安に近いものだと感じた。
物語の象徴的な舞台となる「屋根のぼり」は、この作品を読み解く上で最も重要な要素だろう。夜中にこっそりと家の屋根にのぼる行為は、大人から見れば危険で無意味な遊びかもしれない。しかし陽子たちにとってそれは現実の息苦しさから解放される唯一の方法だった。屋根の上は、学校や家庭といった社会的な枠組みから一時的に逃れることができる聖域だ。そこでは建前も嘘もなく、ありのままの自分でいることができる。私にもそんな場所が必要だと強く感じた。
高校生になると、進路や人間関係に悩むことが増える。大人になることへの不安と期待が入り混じり、自分が何者なのか分からなくなることがある。そんな時、陽子たちの屋根のような逃げ場所があれば、どれほど救われるだろう。屋根のぼりは現実逃避でもあるが、同時に自分自身と向き合うための重要な時間でもある。陽子たちは屋根の上で、普段は誰にも言えない心の奥底の気持ちを語り合う。そこには社会的な役割や期待から解放された、純粋な人間としての交流がある。
キオスクという登場人物の存在も、この物語に深みを与えている。クラスでいじめられている彼は、最初は陽子たちとは全く違う世界にいるように見える。しかし屋根の上での出会いを通して、彼もまた陽子たちと同じように孤独を抱えた一人の人間だということが明らかになる。キオスクの存在は、孤独が決して特別な人だけが抱える感情ではないことを示している。いじめる側もいじめられる側も、人気者もそうでない人も、みんなそれぞれに孤独を抱えて生きている。キオスクと陽子たちとの関係性の変化は、表面的な違いを超えて人間同士がつながる可能性を示唆している。
この作品の最も深いテーマは、孤独の意味を問い直すことにあると思う。『宇宙のみなしご』というタイトルは一見ネガティブな印象を与える。しかし読み進めていくと、森さんが描く孤独は決して絶望的なものではないことが分かってくる。陽子が最初に感じていた「宇宙にたった一人でいる」ような孤独感は、物語の終わりには「みんなそれぞれが宇宙のみなしごなんだ」という普遍的な理解に変化していく。この変化は、孤独を個人の問題から人類共通の普遍的な感覚へとあざやかに転換させてしまう。孤独は乗り越えるべき障害ではなく、人間であることの証明なのかもしれない。そして、その孤独を共有することで、人と人とのより深いつながりが生まれる。
現代社会では、SNSやメッセージアプリによって表面的なつながりは増えているが、本質的な孤独感はむしろ深まっているように感じる。多くの情報に囲まれ、多くの人とつながっているはずなのに、心の奥底では「誰も本当の自分を理解してくれない」という思いを抱えている人が多いのではないだろうか。『宇宙のみなしご』は、そんな現代人の心に寄り添う作品でもある。陽子たちの屋根のぼりのような、真の意味での人間的な交流の大切さを改めて感じさせてくれる。
森絵都さんの文章は、思春期の繊細な感情を驚くほど正確に捉えている。言葉にならない感情に適切な表現を与え、読者の心に深く響く。特に、日常の何気ない場面で感じる違和感や疎外感の描写は、多くの人が「そうそう、まさにそんな感じ」と共感できるものだろう。この作品を読んで、私は自分の孤独感について新しい視点を得ることができた。
高校生になってから感じるようになった漠然とした不安や将来への迷いも、それは成長の過程で必然的に生まれる感情なのだと理解できた。孤独を恥じるのではなく、それを自分の一部として受け入れ、同じような気持ちを抱える人たちとつながっていくことが大切なのだろう。
『宇宙のみなしご』は、思春期を生きるすべての人への応援歌のような作品だった。陽子の成長を通して、孤独な気持ちも自分を形作る大切な要素であり、それがあるからこそ他者への共感や理解が生まれるのだと学んだ。この本が多くの人に読まれ、孤独を感じている人たちの心に光を届けることを願っている。
振り返り
『宇宙のみなしご』の読書感想文について、書き方から具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つの要点を意識することで、あなたの感想文がより深みのある内容になるはずです。
小学生向けから高校生向けまでの例文も参考にして、あなたの学年に合った文体や表現を選んでくださいね。
大切なのは、物語の内容を説明することではなく、読んであなたがどう感じたかを素直に書くことです。
陽子の孤独感に共感したり、屋根のぼりに憧れたり、キオスクとの友情に感動したり、そんなあなた自身の気持ちこそが感想文の主役なのです。
森絵都さんが描いた思春期の繊細な感情は、きっとあなたの心にも響く部分があったでしょう。
その気持ちを大切にして、あなただけの言葉で表現してみてください。
完璧な感想文を書こうとしなくても大丈夫です。
あなたの率直な気持ちを書くことが、最も素晴らしい感想文になります。
『宇宙のみなしご』を通して感じた孤独や友情、成長について、自信を持って書いてくださいね。
あなたにも必ず、心に響く素敵な感想文が書けますよ。



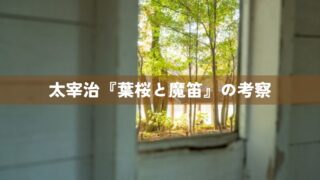

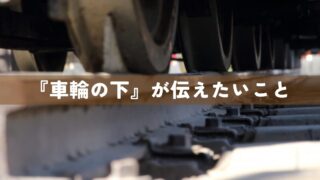


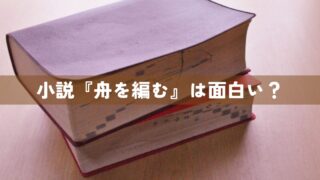
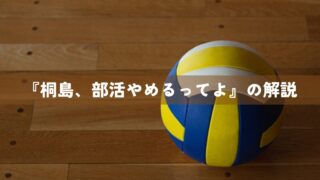








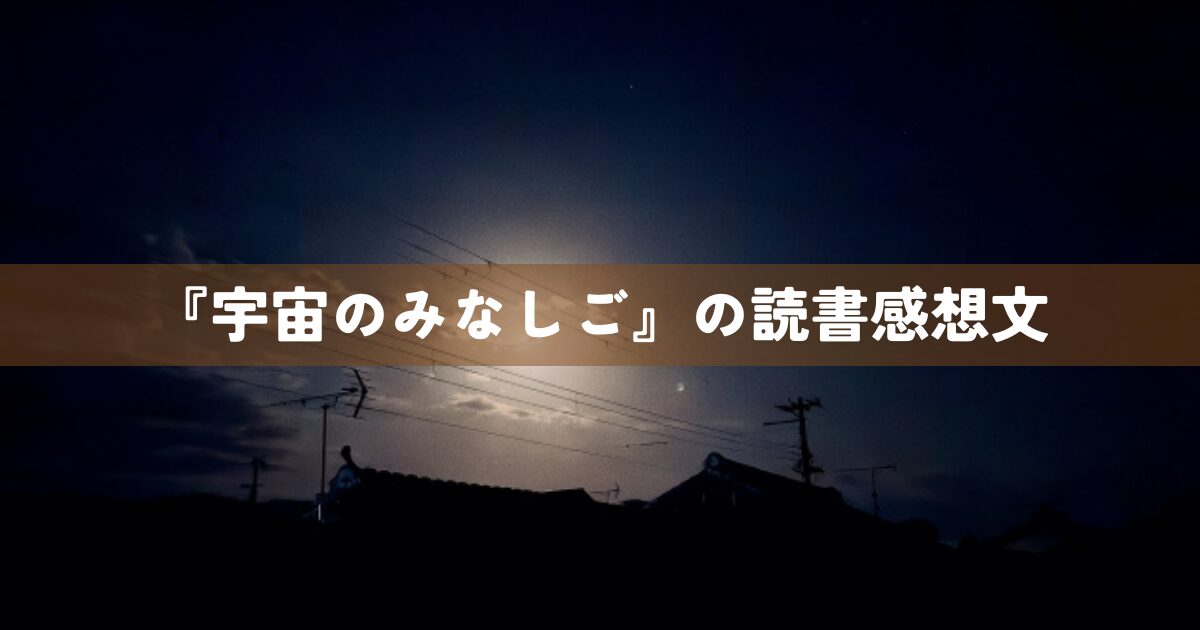
コメント