『かがみの孤城』の読書感想文を書こうと思っている皆さん、こんにちは。
辻村深月さんによるこの感動作は、2018年に本屋大賞を受賞した現代のファンタジー小説です。
不登校に悩む中学生の少女・安西こころが、鏡の向こうの孤城で同じような悩みを持つ仲間たちと出会い、心の成長を遂げていく物語ですね。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいるのですが、『かがみの孤城』は特に印象に残っている作品の一つです。
この記事では、小学生・中学生・高校生それぞれに向けた読書感想文の書き方や例文、そして感想文を書く際の題名や書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではない、あなただけのオリジナルな感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきます。
『かがみの孤城』の読書感想文で触れたい3つの要点
『かがみの孤城』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要な要点が3つあります。
これらの要点について、あなたがどう感じたかをメモしておくことが大切ですね。
- 不登校という現代的な問題と、登場人物たちの心の傷の描写
- 鏡の向こうの孤城というファンタジー設定が持つ意味
- 仲間との出会いと絆、そして現実世界への帰還
メモを取る際は、「なぜそう思ったのか」「自分の体験と重ね合わせてどう感じるか」を具体的に書き留めておきましょう。
感想文では、ただあらすじを書くのではなく、あなた自身の感じたことや考えたことを中心に書くことが何より重要ですよ。
不登校問題と心の傷の描写
『かがみの孤城』の最も印象的な部分は、主人公のこころをはじめとする登場人物たちが抱える不登校の問題です。
こころは同級生の真田美織からのいじめが原因で学校に行けなくなり、家に引きこもってしまいます。
城で出会う他の仲間たちも、それぞれ異なる理由で学校に通えない状況にあるんですね。
アキはバレーボール部での人間関係の問題、マサムネは嘘つき呼ばわりされるいじめ、フウカはピアノのプレッシャーと学校生活への適応困難など、現代の中学生が実際に直面しそうな問題ばかりです。
辻村深月さんは、これらの心の傷を非常に繊細に描写しています。
特に、こころが感じる「自分には何の取り柄もない」という自己否定感や、フリースクールに行こうとした朝に腹痛を起こすストレス反応の描写は、読んでいて胸が苦しくなるほどリアルです。
あなたも学校生活で似たような経験をしたことがあるかもしれませんね。
そんな時の気持ちを思い出しながら、登場人物たちの心情に共感した部分をメモしておきましょう。
また、家族との関係についても注目してください。
こころの母親が娘の腹痛を理解してくれない場面や、リオンの母親が息子をハワイに厄介払いする設定など、大人の無理解や家庭環境の問題も丁寧に描かれています。
これらの描写から、あなたは何を感じましたか。
現代社会の抱える問題について、どのような印象を持ったでしょうか。
鏡の向こうの孤城が象徴するもの
『かがみの孤城』のタイトルにもなっている「孤城」は、物語の重要な舞台です。
この城は現実世界から切り離された特別な空間であり、悩みを抱える子どもたちだけが入ることができる場所として描かれています。
城には厳格なルールがあります。
日本時間の午前9時から午後5時までしか滞在できず、時間を過ぎて一人でも残っていると全員が狼に食べられてしまうという設定ですね。
このルールは一見すると恐ろしいものですが、実は現実世界との適切な距離感を保つための仕組みとも解釈できます。
城の中では、現実世界での肩書きや立場は関係ありません。
みんな同じ「赤ずきん」として平等に扱われ、お互いの悩みを理解し合える仲間として過ごすことができるんです。
オオカミさまが提示する「願いの鍵」を見つけるという目標も、単なるゲーム要素ではなく、子どもたちが自分自身と向き合うためのきっかけとして機能しています。
あなたは、この孤城という設定をどのように受け取りましたか。
現実逃避の場所だと思いましたか、それとも成長のための場所だと感じましたか。
また、もしあなたが同じような城に招かれたとしたら、どんな気持ちで過ごすでしょうか。
城での生活を通じて、登場人物たちが少しずつ心を開いていく過程にも注目してください。
最初は警戒心を持っていたこころが、徐々に仲間たちと打ち解けていく様子は、人間関係の築き方について多くのことを教えてくれます。
仲間との絆と現実への帰還
『かがみの孤城』の最も感動的な部分は、登場人物たちが築いていく友情と絆です。
最初はお互いに距離を置いていた7人の中学生が、城での共同生活を通じて徐々に心を通わせていく過程は、読んでいて温かい気持ちになりますね。
特に印象的なのは、アキがルールを破って城に残ってしまい、みんなが狼に食べられてしまった時の展開です。
こころが仲間たちを救うために奮闘する場面では、彼女の成長と仲間への愛情が如実に表れています。
物語の終盤で明かされる驚愕の真実も、読者に深い感動を与えてくれます。
7人の仲間たちが実は異なる時代を生きていたという設定は、時空を超えた絆の存在を示していて、とても美しい展開だと思います。
特に、オオカミさまの正体がリオンの亡くなった姉・ミオだったという真実は、物語全体に新たな意味を与えてくれますね。
現実世界に戻った後の描写も重要です。
こころが新学年から学校に通う決心をし、転校生のリオンと出会う場面は、城での経験が彼女にとって確実に成長の糧となったことを示しています。
アキが大人になってフリースクールのカウンセラーとして働いている設定も、過去の経験を活かして他者を支える美しい循環を表現していて素晴らしいです。
あなたは、この物語の結末をどのように受け取りましたか。
登場人物たちの成長に感動しましたか、それとも別の感情を抱いたでしょうか。
また、もしあなたが同じような経験をしたとしたら、現実世界でどのように活かしていきたいと思いますか。
これらの要点について、あなた自身の体験や価値観と照らし合わせながら考えてみてください。
感想文では、作品の内容を紹介するだけでなく、あなたがどう感じ、どう考えたかを中心に書くことが大切です。
※『かがみの孤城』を通して作者が伝えたいことはこちらで考察しています。

『かがみの孤城』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】鏡の向こうの友だち
私は『かがみの孤城』を読んで、とても心があたたかくなった。
主人公のこころちゃんは、いじめられて学校に行けなくなってしまった中学一年生だ。
私も時々学校に行きたくないなと思うことがあるから、気持ちがよくわかる。
ある日、こころちゃんの部屋の鏡が光って、その向こうにお城が見えた。
お城の中にはおおかみさまという不思議な女の子がいて、こころちゃんと同じように学校に行けない子どもたちが6人も集まっていた。
リオンくんはかっこよくて優しくて、アキちゃんはお姉さんみたいで頼りになる。
スバルくんは紳士的で、マサムネくんは頭がいいけど少し生意気だ。
フウカちゃんはピアノが上手で、ウレシノくんは食べることが大好きで恋をしやすい。
私は、一人一人が抱えている問題が違うのに、みんなで支え合っているところがすごいなと思った
お城にはルールがあって、夕方5時までに必ず現実の世界に帰らなければいけない。
もし誰か一人でも残っていたら、その日にお城にいた人はみんな狼に食べられてしまうのだ。
一番印象に残ったのは、アキちゃんが時間を過ぎてもお城に残ってしまって、みんなが狼に食べられてしまった場面だ。
こころちゃんが勇気を出してみんなを助けようとするが、私だったら、そんな勇気を出せるかなと考えてしまった。
お話の最後で、おおかみさまの正体がリオンくんのお姉さんだったことがわかった時は、とてもびっくりした。
そして、7人の仲間たちが実は違う時代を生きていたという真実も驚いた。
時代は違っても、同じような悩みを持つ子どもたちがつながっていたなんて、とても素敵だと思う。
最後に、こころちゃんが学校に行く勇気を出して、リオンくんと友だちになれたところが一番嬉しかった。
お城での経験が、こころちゃんを強くしてくれたのだと思う。
私も、困った時は一人で悩まないで、誰かに相談したり助け合ったりすることが大切だと学んだ。
これからは、私も誰かが困っている時は手を差し伸べてあげたいと思う。
『かがみの孤城』は、友情の大切さと、困難に立ち向かう勇気について教えてくれる素晴らしい本だった。
『かがみの孤城』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】孤独から希望へ
『かがみの孤城』を読んで、私は現代の中学生が抱える様々な問題について深く考えさせられた。
主人公・安西こころは、いじめが原因で不登校になった中学一年生だ。彼女の孤独感や絶望感は、同じ中学生である私にとって他人事ではなかった。学校は本来、安全で楽しい場所であるべきなのに、時に残酷な現実を突きつけてくる。
こころが鏡の向こうの孤城で出会った6人の仲間たちも、それぞれ異なる理由で学校に行けない状況にあった。リオンは母親にハワイへ留学させられ、アキは部活内の人間関係、マサムネはいじめ、フウカはピアノのプレッシャー、ウレシノは利用されることへの苦悩、スバルは家庭環境の複雑さを抱えていた。これらはすべて現実に起こりうる問題だと思った。
特に印象深かったのは、大人の無理解についての描写だ。こころの母が娘の不調を理解できなかったり、リオンの母が息子を海外に送り出したりする場面には、大人と子どもの間の深い溝を感じた。子どもの問題を軽視し、大人の都合を優先する現実は確かに存在する。
それでも、この物語は絶望の中に希望の光を見出している。孤城は現実逃避の場所ではなく、自分と向き合い成長する場所として描かれていた。「願いの鍵を探す」という課題は、子どもたちが自分の本当の願いに向き合うきっかけだったのだと思う。
最初は警戒心を抱いていたこころが、少しずつ仲間を信頼していく過程から、人間関係の築き方について多くのことを学んだ。特に感動したのは、アキがルールを破って城に残り、全員が狼に食べられた後の展開だ。こころが仲間を救おうと奮闘する姿には大きな成長が感じられた。
終盤で明かされる「7人は異なる時代を生きていた」という事実は、時空を超えた絆の存在を示していた。さらに、オオカミさまの正体がリオンの亡き姉・ミオだったことは、物語全体に新たな意味を与えた。亡くなった姉が、弟と同じ悩みを抱える子どもたちを救おうとする姿が美しかった。
現実に戻った後、こころが学校に通う決意をし、リオンと再会する場面には希望が感じられた。また、アキが大人になりフリースクールのカウンセラーになっていたことも印象的だった。過去の経験が、誰かを支える力になることを教えてくれる。
私はこの物語を通して、孤独や絶望の中にも誰かとつながれる可能性があることを学んだ。そして、困難な経験も無駄ではなく、将来誰かを助ける力になるのだと理解した。SNSの発達により表面的なつながりが増えた今こそ、心のつながりの大切さが求められていると思う。
『かがみの孤城』は、真の友情や絆が時代を超えて存在することを教えてくれた。私も困った時は一人で抱え込まず、信頼できる人に相談したい。そして誰かが困っていたら、勇気を出して手を差し伸べたいと思う。
『かがみの孤城』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】現代社会の孤独と救済
辻村深月による『かがみの孤城』は、現代日本の教育問題や青少年の心理的困難を繊細に描いた傑作である。本屋大賞を受賞したこの作品は、単なるファンタジー小説の枠を超えて、私たち現代人が直面する孤独や疎外感という普遍的テーマを深く掘り下げている。
主人公の安西こころをはじめとする登場人物たちが抱える問題は、決して特殊なものではない。いじめ、不登校、家庭環境の問題、進路への不安など、これらは現代の中高生なら誰もが経験する可能性のある現実的な困難だ。私自身も高校生として、彼らの抱える心の痛みを身近に感じることができた。
特に印象的だったのは、大人社会の無理解という問題の描写である。こころの母親が娘のストレス性腹痛を理解せず、「甘えている」と判断してしまう場面は、現代社会における世代間のコミュニケーション不足を象徴している。また、リオンの母親が息子を厄介払いのようにハワイに送り出す設定も、子どもの心情よりも体裁や都合を優先する大人の身勝手さを浮き彫りにしている。学校という共同体からはじき出され、家庭でも理解されない子どもたちにとって、居場所を見つけることは極めて困難なのだ。
しかし、『かがみの孤城』の真の価値は、こうした絶望的な状況に対処するヒントを提示していることにある。鏡の向こうの孤城という非現実的な設定は、一見すると現実逃避の象徴のように思えるが、実際は全く異なる機能を果たしている。この城は、現実世界では得られない安全な環境を提供し、傷ついた子どもたちが自分自身と向き合い、他者との関係を再構築するための場として機能しているのだ。
オオカミさまが設定したルールも興味深い。午後5時までに必ず現実世界に戻らなければならないという制限は、この場所が永続的な逃避先ではなく、現実世界に戻るための準備期間であることを示している。また、「願いの鍵」を探すという課題は、子どもたちが自分の本当の願いと向き合うためのメタファーとして機能している。
城での共同生活を通じて、7人の仲間たちは徐々に心を開いていく。現実世界では、肩書きや立場、外見などの表面的な要素が人間関係を規定しがちだが、城の中では純粋に人間性だけで関係が築かれていく。それぞれの個性が自然に発揮され、認め合われる環境がそこにはあった。
物語の転換点となるアキの事件は、物語全体の中でも最も重要な場面の一つである。家庭内の深刻な問題から帰宅を拒んだアキが、ルールを破って城に残り、結果として全員が狼に食べられてしまう展開は、現実の厳しさを改めて突きつけてくる。しかし、この絶望的な状況でこころが示した行動力と勇気は、彼女の大きな成長を物語っている。物語冒頭では自信がなく引っ込み思案だった少女が、大切な仲間のために果敢に立ち向かう姿は、真の友情が人を変える力を持つことを証明している。
物語の終盤で明かされる真実は、読者に大きな感動を与える。7人の仲間たちが実は異なる時代を生きていたという設定は、孤独や困難が時代を超えた普遍的な問題であることを示している。そして、オオカミさまの正体がリオンの亡くなった姉・ミオだったという事実は、死者が生者を救うという美しい物語を生み出している。
現実世界に戻った後の描写も見逃せない。こころが新学年から学校に通う決心をし、転校生のリオンと出会う場面は、城での経験が確実に彼女の人生を変えたことを示している。また、アキが成長してフリースクールのカウンセラーとなり、後輩たちを支える存在になっている設定は、困難な経験が将来の糧となることを象徴している。
私がこの作品から学んだ最も重要なことは、孤独や絶望を感じている時でも、必ず救済の道は存在するということだ。現代社会では、SNSの普及により表面的なつながりは増加しているが、真の意味での心のつながりを築くことは以前よりも困難になっているように感じる。しかし、『かがみの孤城』は、真の友情や絆は時空を超えて存在し得ることを教えてくれた。
また、この作品は現代の教育制度や家族関係についても重要な問題提起をしている。画一的な学校教育システムに適応できない子どもたちや、大人の理解不足に苦しむ子どもたちの存在は、現代社会が抱える深刻な課題である。フリースクールという選択肢の存在や、多様な生き方を認める社会の必要性についても考えさせられた。
私は高校生として、この作品から多くの教訓を得ることができた。困難に直面した時に一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することの大切さ、そして自分と同じような悩みを持つ人が必ず存在するということを理解した。また、過去の辛い経験も決して無駄ではなく、将来誰かを助けるための力になり得ることも学んだ。
『かがみの孤城』は、現代社会の闇を直視しながらも、最終的には希望の光を見出す物語である。この作品が多くの読者に愛され、本屋大賞を受賞したのも、現代人が求める救済の物語がそこにあるからだろう。私たちの社会がより優しく、理解し合える場所になることを願いながら、この感想文を結びたい。
振り返り
『かがみの孤城』の読書感想文について、小学生から高校生まで各年代に応じた書き方や例文を紹介してきました。
この記事では、感想文を書く際に押さえておきたい3つの重要な要点と、それぞれの年代に適した文体や内容の例文を提供しましたね。
辻村深月さんが描く現代の子どもたちの心の動きは、どの年代の読者にも深い共感を呼び起こします。
あなたも自分の体験や感情と重ね合わせながら、オリジナルな感想文を書くことができるはずです。
大切なのは、作品のあらすじを書くことではなく、あなた自身がどう感じ、どう考えたかを正直に表現することです。
この記事を参考にして、ぜひ心のこもった素晴らしい読書感想文を完成させてください。
きっと、あなただけの感動的な作品が書けるはずですよ。
※『かがみの孤城』の読書感想文の作成に役立つ記事がこちら。

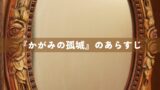


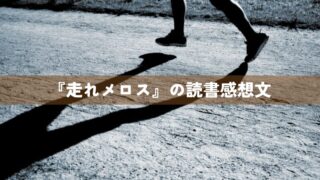

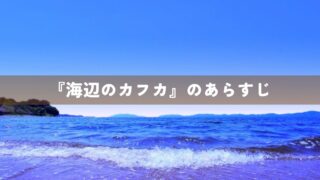



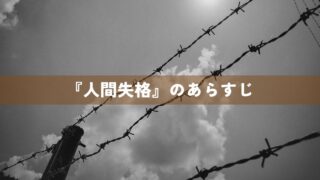



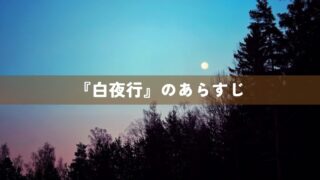




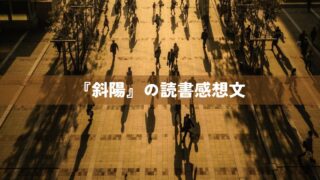

コメント