『ヘレンケラー』読書感想文を書く予定の学生のみなさん、お疲れさまです。
『ヘレンケラー』は、幼い頃に視力と聴力を失った彼女が、家庭教師のアン・サリバン先生との出会いを通じて言葉を覚え、ついにはハーバード大学を卒業するまでの感動的な自伝ですね。
1903年に出版されたこの作品は、三重苦を克服した偉人の物語として世界中で愛され続け、日本でも多くの出版社から様々な邦訳タイトルで刊行されています。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生・高校生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
| 出版社名 | 刊行タイトル | 特徴・備考 |
|---|---|---|
| 新潮社 | 奇跡の人 ヘレン・ケラー自伝 | 2004年刊。大人向け新訳版。 巻末にエッセイを収録。 |
| 講談社 | ヘレン・ケラー自伝(新装版) | 2025年刊。ふりがな付き。 教育者サリバン先生の解説付き。 |
| 角川書店 | わたしの生涯(角川文庫) | 児童向け文庫版の代表的な訳。 |
| 千代田書房 | ヘレン・ケラー自叙伝 | 1948年刊。岩橋武夫訳。 |
| 内外出版協会 | わが生涯 | 1907年刊の邦訳初期版。 |
| 東京崇文館書店 | 我身の物語 ヘレン・ケラー嬢自叙伝 | 1912年刊。三上正毅訳。 |
『ヘレンケラー』の読書感想文で触れたい3つの要点
『ヘレンケラー』の読書感想文を書くときに絶対に外せない重要なポイントが3つあります。
- 困難な状況から希望を見出す「奇跡の瞬間」
- サリバン先生との深い信頼関係と絆
- 自分自身の成長や学びにつながる気づき
これらの要点を読みながらメモを取って、自分がどう感じたかをしっかりと記録しておきましょう。
感想文で大切なのは、あらすじの説明ではなく「あなたがどう感じたか」という個人的な体験なんです。
この3つのポイントについて、本を読みながら付箋を貼ったり、ノートに「どう思ったか」「なぜそう感じたか」を書き留めておくことをおすすめします。
具体的には「この場面で胸が熱くなった」「ヘレンの気持ちがよく分かる」「自分も頑張ろうと思った」といった素直な感情をメモしておくと、後で感想文を書くときにとても役立ちますよ。
困難な状況から希望を見出す「奇跡の瞬間」
ヘレン・ケラーの人生における最も重要な転換点は、井戸端でのあの有名な「Water」の場面ですね。
三重苦という想像を絶する困難の中で暮らしていたヘレンが、サリバン先生の指導によって初めて「言葉」というものの存在を理解した瞬間です。
この場面を読んだとき、あなたはどんな気持ちになりましたか?
「奇跡が起こった!」と感動したか、「諦めなければ道は開ける」と希望を感じたか、それとも「言葉って大切なものなんだな」と改めて実感したか。
ここで大切なのは、この「奇跡」が偶然起こったものではなく、ヘレン自身の強い意志とサリバン先生の諦めない努力の結果だということです。
感想文では、この場面がなぜ印象的だったのか、自分の言葉で説明してみましょう。
「普段当たり前に使っている言葉の大切さに気づいた」「困ったときも諦めてはいけないと思った」など、あなたの心に響いた部分を具体的に書くことで、読み手にも伝わりやすい感想文になります。
サリバン先生との深い信頼関係と絆
ヘレン・ケラーの成長を語る上で、アン・サリバン先生の存在は欠かせませんね。
サリバン先生は単なる家庭教師ではなく、ヘレンにとって人生の導き手であり、最も信頼できる理解者でした。
二人の関係を読んでいて、どんなことを感じましたか?
時には厳しく、時には優しく、決して諦めることなくヘレンと向き合い続けたサリバン先生の姿勢から学べることはたくさんあります。
また、最初は反発していたヘレンが、だんだんとサリバン先生を信頼するようになっていく過程も感動的ですよね。
感想文では、この師弟関係から何を学んだかを書いてみましょう。
「信頼できる人がいることの大切さ」「お互いを理解し合うことの難しさと素晴らしさ」「愛情を持って接してくれる人への感謝」など、人間関係について考えさせられた部分を具体的に表現してください。
あなたの身の回りにも、サリバン先生のような存在がいるかもしれませんね。
自分自身の成長や学びにつながる気づき
読書感想文で最も重要なのは、この本を読んで「あなた自身がどう変わったか」「何を学んだか」を語ることです。
ヘレン・ケラーの人生から得た教訓を、自分の体験や将来の目標と結びつけて考えてみてください。
例えば、「小さなことで諦めそうになったとき、ヘレンの頑張りを思い出そう」と思ったかもしれません。
または「当たり前だと思っていることに感謝する気持ちを忘れずにいたい」と感じたかもしれませんね。
普段何気なく使っている「見る」「聞く」「話す」という能力の素晴らしさに改めて気づいた人も多いでしょう。
感想文では、このような「気づき」や「学び」を具体的なエピソードと一緒に書くと説得力が増します。
「友達とケンカしたとき、ヘレンのことを思い出して素直に謝ることができた」「勉強が嫌になったとき、ヘレンの努力を思い出してもう一度頑張った」など、実際の体験と結びつけて書いてみてください。
※『ヘレンケラー』の本のあらすじはこちらで簡単にご紹介しています。

『ヘレンケラー』の読書感想文のテンプレート
『ヘレン・ケラー』の読書感想文を楽に書くためのテンプレートをご用意しました。
以下の各ステップに「読んで感じたこと」をメモ書きを参考に入れ込んでいくと理想的な感想文が完成しますよ。
ステップ1:序論 – 本との出会いと第一印象
まず、読書感想文の導入部分を書きます。
なぜこの本を読もうと思ったのか、あるいは読み始める前にヘレン・ケラーについてどんなイメージを持っていたかを正直に書き出しましょう。
「ヘレン・ケラー」という名前は昔から知っていましたが、今回改めて本を読んでみて、想像していた以上の深い物語だと感じました。
* 私は、目や耳が聞こえないということがどういうことなのか、あまり深く考えたことがありませんでした。この本は、そんな私に、当たり前だと思っていたことの尊さを教えてくれました。
ステップ2:本論1 – 困難から希望を見出す「奇跡」
次に、物語の中心であるヘレン・ケラーの困難と、そこから希望を見出す「奇跡の瞬間」について具体的に書きます。
ここは読書体験の中で最も感動した場面を、自分の言葉で表現する部分です。
1. ヘレンが三重苦という状況で、どれほど孤独で怒りに満ちていたかを書く。
2. サリバン先生との出会いがいかに重要だったかを述べる。
3. **井戸のポンプの場面**など、ヘレンが「言葉」の意味を理解した瞬間を具体的に描写する。
4. その「奇跡」が、単なる偶然ではなく、ヘレンと先生の努力によってもたらされたものであることを考察する。
ステップ3:本論2 – サリバン先生との「深い信頼関係と絆」
ヘレンの物語は、サリバン先生との関係なしには語れません。この部分では、二人の間の深い信頼関係に焦点を当てて書きます。
1. サリバン先生がヘレンに対して、時に厳しく、しかし決して諦めずに接した様子を述べる。
2. 衝突を繰り返しながらも、お互いを理解し、深い絆を築いていった過程を考察する。
3. ヘレンの成長は、先生の献身的な支えがあったからこそ可能だったことを強調する。
4. 二人の関係から、「人を信じること」「誰かのために尽くすこと」の重要性について考える。
ステップ4:結論 – 自分自身の成長や学びにつながる気づき
最後に、本を読んで得た学びや、自分の人生にどう生かしていきたいかをまとめます。
これが、読書感想文の最も重要な部分であり、自分自身の言葉で語ることで、オリジナリティが生まれます。
1. ヘレン・ケラーの物語から学んだ、最も大切な教訓(例:諦めない心、感謝の気持ち、コミュニケーションの価値など)を一つか二つ挙げる。
2. その学びを、自分の普段の生活や将来の目標と結びつける。
3. 例えば、「小さな困難にぶつかったとき、ヘレンの諦めない姿を思い出すようにしたい」「当たり前だと思っていた言葉や周りの人たちとのつながりを、もっと大切にしたい」といった具体的な行動目標を書く。
4. 本全体を通しての感想を改めて述べ、読書感想文を締めくくる。
このテンプレートを使って、ご自身の言葉で一つずつ文章を組み立ててみてください。
これにより、型にはまった文章ではなく、あなた自身の感動が伝わる読書感想文が完成します。
『ヘレンケラー』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】あきらめない心の大切さ
私は『ヘレンケラー』を読んで、とても心が動かされた。
ヘレン・ケラーは赤ちゃんのときに病気になって、目が見えなくなり、耳も聞こえなくなってしまった。話すこともできず、家族とも気持ちを伝え合えなかった。
そんな状況の中で、ヘレンはいつも怒っていて、物を投げたりわがままを言ったりしていた。けれど私は、その気持ちが分かる気がした。心の中に伝えたいことがあるのに、それを外に出す方法がない。そのもどかしさが、ヘレンを怒らせていたのだと思う。
そんなヘレンの人生を変えたのが、サリバン先生だった。先生はヘレンの荒れた心を我慢強く、優しく支えてくれた。初めて言葉を教えようとしたとき、ヘレンは分からなかったが、先生は諦めずに繰り返した。
一番心に残ったのは、井戸のそばで先生がヘレンの手に「W-A-T-E-R」と書いた場面だ。そのとき井戸の水がヘレンの手に触れ、「水」という言葉と冷たい感覚がつながった。ヘレンが「ああ!」と叫んで意味を理解したとき、私も感動して涙が出そうになった。その瞬間から、ヘレンの世界に言葉が増え、明るく開けていった。この「奇跡」は、ヘレンの諦めない心と、先生の深い愛情がなければ起こらなかったと思う。
この本から二つの大切なことを学んだ。一つは、当たり前に思っている「言葉」がどれほど大切かということ。ヘレンは言葉を手で確かめながら世界を理解していった。私ももっと言葉を大切に使いたい。
もう一つは、どんな困難にも諦めなければ道は開けるということ。ヘレンは見えない、聞こえないという大きな壁を乗り越えて大学を卒業し、多くの人に希望を与えた。
私にも将来、夢や壁が出てくるだろう。そのときにはヘレンのように負けずに努力しようと決めた。『ヘレンケラー』は、読むたびに勇気をくれる特別な一冊になった。
『ヘレンケラー』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】言葉の力と人とのつながり
私は『ヘレンケラー』を読んで、普段何気なく使っている「言葉」の大切さと、人と人とのつながりの重要さを深く考えさせられた。
ヘレン・ケラーの人生は、生後19か月で視力と聴力を失うという、想像を絶する困難から始まった。彼女は外の世界とのつながりを完全に断たれ、自分の気持ちを表現することすらできなかった。その結果、怒りを爆発させ、家族にも手がつけられない状態になってしまう。私はこの部分を読んで、ヘレンをただのわがままな子とは思えなかった。彼女の怒りは、外の世界とつながりたいという強い欲求が満たされないことへの、魂の叫びだったからだ。
そんな彼女の人生に現れたのが、アン・サリバン先生だった。サリバン先生は自分も目が不自由でありながら、ヘレンの先生となった。彼女はまずヘレンの心を開くことから始め、激しい反発にも決して諦めず、その奥にある苦しみを理解しようと努めた。二人の間で繰り広げられた、まるで戦いのような日々は、深い信頼関係を築くために必要な過程だったのだろう。
私が最も心を揺さぶられたのは、井戸のポンプの場面だった。サリバン先生がヘレンの手に冷たい水を注ぎながら「W-A-T-E-R」と指で書いた瞬間、それまでバラバラだった感覚が一つの「言葉」として結びついた。この場面は物語のクライマックスであり、「奇跡」の瞬間として描かれている。しかしそれは魔法のように突然起こったのではなく、サリバン先生の献身と、ヘレン自身の強い意志が何度も積み重なった結果として訪れた必然だった。
言葉を習得したヘレンが、周りの物一つ一つに名前があることを知り、目を輝かせながら触れていく姿は、私たちが普段当たり前に使っている言葉の価値を改めて教えてくれた。
この本から私は二つの大切なことを学んだ。一つは「言葉」の力についてだ。ヘレンにとって言葉は単なる記号ではなく、世界と自分をつなぐ唯一の手段だった。彼女が言葉を得て世界を広げていったように、私たちももっと丁寧に言葉を使い、心を込めて人と関わるべきだと感じた。もう一つは「困難を乗り越える力」である。ヘレン・ケラーは三重苦という大きなハンディを背負いながらも、多くの人々に希望を与え続けた。その原動力となったのは、彼女自身の探究心と、サリバン先生をはじめとする周囲の支えだった。
私たちは日々さまざまな困難に直面し、ときに諦めそうになる。しかしヘレンの人生を思い出すたびに、どんな壁も、誰かの助けを得ながら、そして自分の強い意志で乗り越えられるのではないかという勇気が湧いてくる。
『ヘレンケラー』は、読むたびに新しい発見と感動を与えてくれる名作だ。この物語には、障害を持つ人々だけでなく、すべての人間に向けられた「生きるヒント」が詰まっている。私もヘレンのように、どんな困難にも負けず、自分の可能性を信じ、周りの人とのつながりを大切にしながら生きていきたいと思う。
『ヘレンケラー』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】言葉を得ることで開かれる世界
幼い頃から、ヘレン・ケラーは「奇跡の人」として、その成功物語を断片的に聞かされてきた。
しかし今回、『ヘレン・ケラー自伝』を手に取り、じっくりと読み解くと、私のそれまでの認識は大きく覆された。
この物語は、単に困難を克服した偉人の伝記ではない。
それは、人間が「言葉」を獲得することでいかにして「自分」を確立し、世界と結びついていくかという根本的な問いを突きつける、深く考えさせられる作品であった。
物語は、ヘレンが病気によって視力と聴力を失い、外界とのつながりを絶たれていく様子から始まる。
ヘレンの表現によれば、その世界は「何も存在しない、思考なき世界」であった。
この描写は、視覚や聴覚が失われることの物理的な不便さ以上に、精神的な空白と孤独を表している。
彼女は、自分の内側から湧き上がる衝動を表現する術を持たず、ただ癇しゃくを爆発させることでしか外界に働きかけることができなかった。
この状態は、私たちが普段当たり前に享受している「言葉」が、単なるコミュニケーションツールではなく、自分を形成し、内面を整理するための不可欠な要素であることを痛烈に示している。
言葉を持たないヘレンは、世界と自分を区別することができず、自分という明確な輪郭を持てなかったのではないだろうか。
そんな「無」の世界に光をもたらしたのが、アン・サリバン先生である。
彼女はヘレンに「人形」という物が持つ「概念」と「言葉」を関連付ける方法を、根気強く教え続けた。
この教育の過程は、単なる知識の伝達ではない。
それは、ヘレンの内面に秩序と意味をもたらす創造的な行為であった。
二人の間に繰り広げられた激しい「意志の戦い」は、単なる先生と生徒の衝突ではなく、ヘレンが自分を確立するための避けて通れない過程であったと私は考える。
サリバン先生は、安易な同情や甘やかしを拒否し、ヘレンを一人の人間として尊重した。
その厳しい姿勢があったからこそ、ヘレンは初めて「言葉」という武器を手に入れる準備ができたのだ。
そして、物語のクライマックスは、誰もが知る井戸のポンプの場面である。
サリバン先生がヘレンの手に水を流しながら「W-A-T-E-R」と書いた瞬間、ヘレンの内に「言葉」と「概念」が結びつき、世界が意味を持った。
ヘレンは、その時の感動を「魂が目覚めた」と表現している。
この「目覚め」は、単に文字を覚えたという以上の意味を持つ。
それは、彼女が初めて「自分」を認識し、世界との間に明確な境界線を引くことができた瞬間ではなかったか。
それまで漠然とした存在だったヘレンの内面に、「私」という確固たる自我が誕生したのだ。
この瞬間から、彼女は積極的に世界と関わり、言葉というツールを駆使して、自らの意志を表現し、知識を吸収していく。
ヘレンの人生は、この「言葉の獲得」によって、絶望から希望へと転換した。
しかし、彼女の旅はそれで終わらない。
その後の人生において、ヘレンは盲聾というハンディキャップを背負いながらも、大学に進学し、社会活動家として多くの人々に影響を与え続けた。
これは、彼女が「言葉」によって得た自分を、社会という大きな舞台でさらに発展させていった証拠である。
彼女は自らの経験を書くことで、同じ境遇にある人々に勇気を与え、社会の偏見に立ち向かった。
この行為は、言葉が単なる個人の思考ツールに留まらず、他者と共感し、社会を変革する力を持つことを証明している。
この本を読み終えて、私は「言葉」について改めて深く考えさせられた。
私たちはあまりにも当たり前に言葉を使い、その本質的な力を忘れがちだ。
しかし、ヘレン・ケラーの物語は、言葉がなければ私たちは世界を認識することも、他者とつながることも、そして何より「自分」という存在を確立することもできないのだと教えてくれる。
現代社会は、SNSやデジタルツールによって言葉が溢れかえっている。
しかし、その多くは表面的なコミュニケーションに終始し、深く意味のある言葉が失われつつあるようにも感じる。
ヘレン・ケラーの人生は、そんな現代を生きる私たちに、「言葉」をもう一度見つめ直し、その重みと力を再認識することの重要性を訴えかけている。
私たちは、ヘレンがそうであったように、言葉をただ消費するのではなく、自分を確立し、世界と深く関わるための創造的なツールとして、大切に使い続けるべきなのだ。
この物語は、私にとって人生における言葉の役割を深く問い直す貴重な機会となった。
そして同時に、これからの日常の中で言葉をどう使うか、自分自身のあり方をどのように形作っていくかを考えさせられる、かけがえのない読書体験となった。
振り返り
今回は『ヘレンケラー』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この作品が持つ普遍的なテーマ「困難を乗り越える力」「言葉の大切さ」「人とのつながり」は、どの世代にも響く深いメッセージを含んでいましたね。
小学生向けの800字から高校生向けの2000字まで、それぞれの年齢に応じた書き方や表現方法も紹介しました。
大切なのは、テンプレートをそのまま使うのではなく、あなた自身が本を読んで感じたことを素直に表現することです。
ヘレン・ケラーの物語から学んだことを自分の体験と結びつけて、オリジナルの感想文を書いてみてください。
きっと、読み手の心に響く素晴らしい感想文が完成するはずです。頑張ってくださいね!
■参照サイト:ヘレン・ケラー – Wikipedia

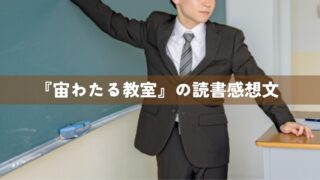


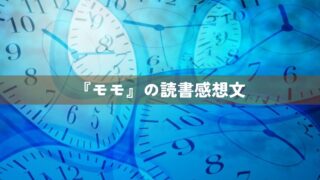

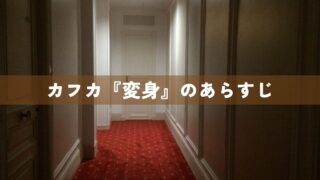
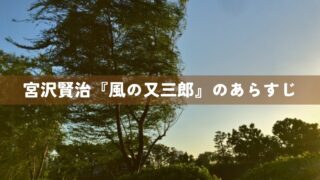
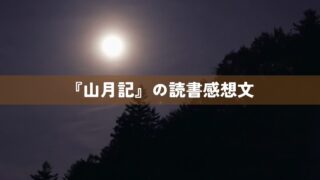
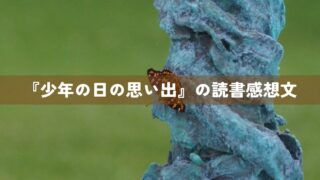

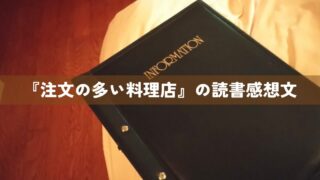




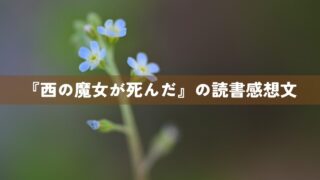


コメント