『不思議の国のアリス』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
ルイス・キャロルが1865年に発表した『不思議の国のアリス』は、アリスという少女が白ウサギを追いかけて不思議な世界に迷い込む冒険物語ですね。
この作品は聖書やシェイクスピアに次ぐといわれるほど多様な言語に翻訳され、世界中で愛され続けている名作です。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『不思議の国のアリス』の読書感想文で書くべき3つのポイント
『不思議の国のアリス』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要なポイントが3つあります。
これらのポイントについて「自分がどう感じたか」をメモしながら読み進めることで、感想文の土台がしっかりと作れるでしょう。
メモの取り方は簡単です。
読書中に「面白いな」「不思議だな」「共感できるな」と思った場面で本にふせんを貼り、そのときの気持ちを一言でもいいので書き留めておきましょう。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、感想文は単なるあらすじ紹介ではなく、あなた自身の心の動きを表現する文章だからです。
以下の3つのポイントを意識して読み進めてください。
- ナンセンス文学としての面白さと魅力
- アリスの成長と変化
- 夢落ちという結末の意味と余韻
それでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
ナンセンス文学としての面白さと魅力
『不思議の国のアリス』は「ナンセンス文学」の代表作として知られています。
ナンセンス文学とは、常識や論理が通用しない世界を描いた作品のことですね。
物語の中では、チェシャ猫が笑顔だけ残して消えてしまったり、マッドハッター(帽子屋)が永遠に終わらないお茶会を開いていたり、現実ではありえないことが次々と起こります。
これらの不思議な出来事は、一見すると意味がないように見えますが、実は当時のイギリス社会や教育制度に対する風刺が込められているとも言われています。
たとえば、ハートの女王が理不尽に「首をはねよ!」と叫ぶ場面は、権力者の横暴さを表現しているのかもしれません。
読書感想文では、このナンセンスな世界のどこが面白かったか、どんな場面で笑ったり驚いたりしたかを具体的に書いてみましょう。
また、現実の世界でも理不尽なことや理解できないことがあるとき、アリスの体験と重ね合わせて考えてみるのも良いでしょう。
言葉遊びやパロディも『不思議の国のアリス』の大きな魅力です。
作中に登場する詩や歌の多くは、当時よく知られていた教訓詩や童謡のパロディになっています。
現代の私たちにとっては元ネタがわからないものも多いですが、その音の響きやリズムの面白さは今でも十分に楽しめますね。
代用ウミガメの話で出てくる「読み方(Reading)ではなく這い方(Reeling)」といった言葉遊びは、日本語訳でも工夫されていて、翻訳者の苦労がうかがえます。
こうした言葉の面白さについても、感想文で触れてみると良いでしょう。
さらに、ナンセンス文学の特徴として、子どもを大人の価値観や常識から解放する役割があります。
『不思議の国のアリス』が発表された当時のイギリスでは、児童書といえば道徳的な教訓を教えるものが主流でした。
しかし、この作品は教訓めいたことは一切言わず、ただ純粋に想像力の世界を楽しませてくれます。
あなたは読んでいて、どんなときに自由な気持ちになったでしょうか。
現実の常識から離れて、思い切り想像の翼を広げられた場面があれば、それを感想文に書いてみてください。
アリスの成長と変化
『不思議の国のアリス』は、主人公アリスの成長物語としても読むことができます。
物語の始めでは、白ウサギを追いかけて穴に落ちたアリスは、自分の体が大きくなったり小さくなったりすることに困惑し、涙を流して途方に暮れていました。
しかし、物語が進むにつれて、アリスは様々な困難に立ち向かう勇気を身につけていきます。
特に注目したいのは、アリスが自分の意見をはっきりと言えるようになっていく過程です。
最初のうちは、イモムシや公爵夫人、マッドハッターたちの理不尽な言動に振り回されがちでした。
でも物語の終盤、裁判の場面では「あんたたちなんか、ただのトランプのくせに!」と堂々と反論するまでに成長しています。
この変化について、あなたはどう感じましたか。
アリスのどんな行動や言葉に共感したり、応援したくなったりしたでしょうか。
また、もし自分がアリスと同じ状況に置かれたら、どう行動するかを考えてみるのも良いでしょう。
アリスの体が大きくなったり小さくなったりする現象は、単なる不思議な出来事ではありません。
これは、思春期の子どもが経験する心身の変化や、アイデンティティの混乱を象徴しているとも解釈できます。
「私は一体誰なのか」とアリスが自問する場面がありますが、これは多くの若者が抱く悩みでもありますね。
体の変化に戸惑いながらも、最終的に自分らしさを見つけていくアリスの姿は、現代を生きる皆さんにとっても示唆に富んでいるのではないでしょうか。
感想文では、アリスの成長のどの部分が印象的だったか、自分の経験と重ね合わせられる部分があったかを書いてみましょう。
さらに、アリスは困難な状況でも好奇心を失わない少女です。
危険な場面に遭遇しても、「これはどういうことだろう」「なぜこんなことが起こるのだろう」と疑問を持ち続けます。
この知的好奇心こそが、アリスを成長させる原動力になっているのかもしれません。
あなたは普段、わからないことに出会ったとき、どのように対処していますか。
アリスのように積極的に探求する姿勢を持てているでしょうか。
こうした自己分析も含めて、感想文に書いてみると深みのある内容になるでしょう。
夢落ちという結末の意味と余韻
『不思議の国のアリス』は、最終的にアリスが姉の膝を枕にして眠っていた夢だったという結末を迎えます。
この「夢落ち」という結末について、読者の反応は様々です。
「せっかく面白い冒険だったのに、夢だったなんてがっかり」と感じる人もいれば、「夢だからこそ意味がある」と考える人もいます。
あなたはこの結末をどう受け止めたでしょうか。
夢落ちという結末の意味を考えてみましょう。
まず、夢だったからこそ、現実では不可能な体験ができたということが挙げられます。
体が大きくなったり小さくなったり、動物たちと会話したり、トランプが生きていたりと、これらはすべて夢の世界だから可能だったのです。
しかし、夢の中での体験が無意味かというと、そうではありません。
夢から覚めたアリスは、きっと以前とは少し違う自分になっているはずです。
夢の中で学んだこと、感じたことは、現実の生活にも影響を与えるでしょう。
また、夢という設定は、想像力の大切さを表現しているとも解釈できます。
現実の世界では制約があることでも、想像力の世界では自由に体験できます。
子どもにとって想像力は、創造性や感性を育む大切な要素ですね。
『不思議の国のアリス』は、そんな想像力の素晴らしさを教えてくれる作品とも言えるでしょう。
感想文では、夢落ちという結末をどう感じたか、なぜそう感じたのかを率直に書いてみてください。
夢と現実の関係についても、あなたなりの考えを述べてみると良いでしょう。
さらに、物語の最後で、アリスの姉が妹の将来に思いを馳せる場面があります。
姉は、アリスが大人になっても子どものような心を失わずにいてほしいと願っています。
この場面は、大人の読者にとっても印象深いものです。
成長することは大切ですが、同時に子どもらしい純粋さや想像力も大切にしたいものです。
あなたは大人になっても、どんな子どもらしさを持ち続けていたいですか。
『不思議の国のアリス』を読んで、そんなことも考えてみてください。
最後に、この作品が150年以上も愛され続けている理由について考えてみましょう。
それは、時代や文化を超えて、人々の心に響く普遍的なテーマが込められているからかもしれません。
成長への憧れと不安、現実と想像の狭間、権威への疑問など、現代を生きる私たちにも通じるテーマがたくさん含まれています。
感想文では、この作品がなぜ長く愛され続けているのか、あなたなりの答えも書いてみると良いでしょう。
※『不思議の国のアリス』で作者が伝えたいことや面白い点はこちらにまとめています。


『不思議の国のアリス』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】アリスと一緒に冒険した不思議な世界
私は『不思議の国のアリス』を読んで、とてもわくわくした気持ちになった。
この本は、アリスという女の子が白ウサギを追いかけて、穴に落ちて不思議な世界に迷い込む話だ。
そこにはしゃべる動物や、生きているトランプなど、現実では絶対にありえないものがたくさん出てきて楽しかった。
一番面白かったのは、チェシャ猫が体を消して、笑顔だけが残るところだった。猫なのに笑顔だけふわふわ浮いているなんて、本当にびっくりした。
マッドハッターのお茶会も変だった。時間が止まっているから永遠にお茶の時間で、みんなで意味のわからない話をしているのが、おかしくて笑ってしまった。
アリスはとても勇気がある女の子だと思った。体が大きくなったり小さくなったりしても、だんだん慣れて自分で考えて行動するようになった。
特にすごいと思ったのは、最後の裁判の場面で「あんたたちなんか、ただのトランプじゃない!」と叫んだところだ。ハートの女王はとても怖いのに、アリスは負けずに言い返した。
この話が最後に夢だったとわかったとき、少しさびしい気持ちになった。でも、夢だからこそこんなに楽しい冒険ができたのかもしれない。私も夜寝るときに、アリスみたいな不思議な夢を見てみたいなと思った。
この本を読んで、想像することの楽しさを改めて感じた。普段考えられないような出来事が次々と起こって、読んでいる私も一緒に冒険している気分になれた。
アリスが出会ったキャラクターたちは、みんな個性的で面白かった。代用ウミガメの話は、言葉遊びがたくさんあって、日本語でも工夫されているのがすごいと思った。
これからも想像力を大切にして、いろいろな本を読んでみたいと思う。現実では体験できないことでも、本の中では何でも体験できるから、読書って素晴らしいと思った。アリスのように好奇心を持って、新しいことにチャレンジしていきたい。
『不思議の国のアリス』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】想像力が切り開く新しい世界
私は『不思議の国のアリス』を読んで、文学における想像力の力を改めて実感した。
この作品は、アリスという少女が白ウサギを追いかけて不思議な世界に迷い込む物語だが、単純な冒険談以上の深い意味を持っていると思う。
まず私が最も印象深く感じたのは、この作品の「ナンセンス文学」としての面白さだった。
チェシャ猫が体を消して笑顔だけを残したり、マッドハッターが永遠に続くお茶会を開いていたりと、論理的には説明のつかない出来事が次々と起こる。
現実世界では、私たちは常に「論理的であること」を求められるが、アリスの世界ではそうしたルールから完全に解放されている。
代用ウミガメの「読み方(Reading)ではなく這い方(Reeling)」という言葉遊びにも、言葉の持つ可能性や創造性が表現されているのではないだろうか。
次に、アリスという主人公の成長に強く心を打たれた。
物語の冒頭では体の変化に混乱し涙を流していたアリスが、終盤では堂々と権威に立ち向かうまでに変化している。
特に印象的だったのは、最後の裁判で「あんたたちなんか、ただのトランプのくせに!」と叫ぶ場面だ。
この瞬間、アリスは理不尽な権力に屈することなく、自分の意見をはっきりと主張している。
私も中学生になって、大人の言うことが必ずしも正しいわけではないと感じることがある。
そんなとき、アリスのように勇気を持って自分の考えを表現することの大切さを学んだ。
また、アリスの体の変化は、思春期の私たちが経験する心身の変化を象徴しているようにも思える。
そして最も考えさせられたのは、物語が「夢落ち」で終わることの意味だった。
最初は「夢だったのか」と少し拍子抜けしたが、夢だからこそ意味があるのではないかと思う。
現実では制約があることでも、夢や想像の世界では自由に体験できる。
アリスが夢の中で学んだことは、決して無駄ではない。
この作品を読んで、私は三つの重要なことを学んだ。
一つ目は、常識にとらわれない自由な発想の大切さ。
二つ目は、困難な状況でも自分の意見を持ち続ける勇気の重要性。
三つ目は、想像力の持つ無限の可能性。
『不思議の国のアリス』は、150年以上も世界中で愛され続けているが、その理由がよくわかった。
この作品には、成長への憧れと不安、権威への疑問、想像力の大切さなど、時代を超えて人々の心に響く普遍的なテーマが込められている。
私もアリスのように、好奇心を持って新しい世界を探求し続けたい。
そして、困難に直面したときは、彼女のように勇気を持って立ち向かっていきたい。
想像力という翼を広げて、これからもたくさんの本を読み、自分の世界を広げていこうと思う。
振り返り
今回は『不思議の国のアリス』の読書感想文の書き方について、具体的なポイントと例文を交えて詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つのポイント(ナンセンス文学の魅力、アリスの成長、夢落ちの意味)を参考にしながら、あなた自身の感じたことを素直に書いていけば、きっと素晴らしい感想文が完成するでしょう。
大切なのは、他の誰かの意見をコピペするのではなく、あなた自身の心に響いた部分を大切にすることです。
同じ作品を読んでも、感じ方は人それぞれ違います。
その違いこそが、あなただけの個性的な感想文を作り上げる源になるのです。
小学生の皆さんも中学生の皆さんも、アリスのように好奇心を持って、この名作と向き合ってみてください。
きっと新しい発見や気づきがあるはずです。
あなたにも必ず、心に残る読書感想文が書けますよ。
※『不思議の国のアリス』のあらすじはこちらで簡単に短くまとめています。

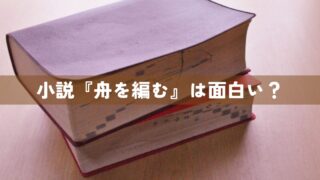
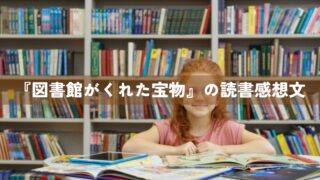



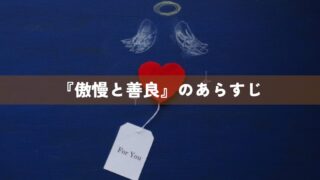






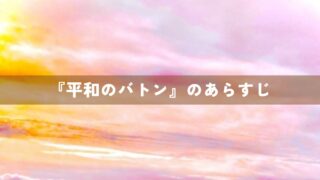
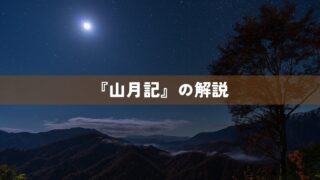





コメント