『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
2021年本屋大賞を受賞した町田そのこさんの代表作『52ヘルツのクジラたち』は、孤独を抱えた人々が新しいつながりを見つけていく感動の物語です。
児童虐待や家庭内暴力といった重いテーマを扱いながらも、人間の回復力と希望を描いた作品として多くの読者の心を打ちました。
年間100冊以上の本を読む私が『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文の書き方を、中学生・高校生の皆さんに分かりやすく解説していきますよ。
例文やコピペしたくなるような完成度の高い感想文も用意しましたので、題名の付け方から構成まで、しっかりとサポートしていきます。
『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文で触れたい3つの要点
『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文を書く際に必ず触れておきたい重要な要点を3つご紹介します。
- 孤独と共鳴、そして新たなつながりの形成
- 回復への道のりと人間の内なる強さ
- 社会問題への気づきと希望のメッセージ
これらのポイントについて、あなた自身がどう感じたかをメモしておくことが感想文執筆の第一歩です。
読書中や読了後に、心に残った場面や共感した部分を箇条書きでメモしておきましょう。
「なぜそう感じたのか」「自分の体験と重なる部分はあるか」といった視点で記録することで、オリジナリティあふれる感想文が書けますよ。
感想文で最も重要なのは「あなた自身の気持ち」を表現することです。
それぞれの要点について、具体的に解説していきましょう。
孤独と共鳴、そして新たなつながりの形成
『52ヘルツのクジラたち』のタイトルは、他のクジラに声が届かない「世界で最も孤独なクジラ」から取られています。
主人公の貴瑚も、虐待を受ける少年も、まさにこの52ヘルツのクジラのような存在です。
誰にも届かない声で必死に助けを求めているのに、周囲の人には気づいてもらえない。
そんな深い孤独感が物語の根底に流れています。
しかし注目すべきは、同じような傷を持つ者同士が出会い、少しずつ心を通わせていく過程です。
血のつながりにとらわれない新しい「家族」の形が描かれており、読者に温かな希望を与えてくれます。
あなたも日常生活で孤独を感じた経験があるでしょう。
そんな時にこの作品を読むと、きっと心に響くものがあるはずです。
回復への道のりと人間の内なる強さ
『52ヘルツのクジラたち』の登場人物たちは皆、壮絶な過去を背負っています。
しかし彼らの回復は決して一直線ではありません。
立ち止まったり、時には後戻りしたりしながらも、それでも前を向こうとする姿が丁寧に描かれているのです。
完璧ではないけれど、一歩ずつでも歩み続ける人間の回復力。
他者との関わりの中で少しずつ癒されていく心の動き。
これらのリアルな描写が、読者に深い感動を与えてくれます。
あなたも今まで困難な状況を乗り越えた経験があるでしょう。
その時の気持ちと登場人物の心境を重ね合わせることで、より深い感想が書けますよ。
社会問題への気づきと希望のメッセージ
『52ヘルツのクジラたち』には、児童虐待や毒親、ヤングケアラーなど現代社会が抱える様々な問題が描かれています。
これらは決して他人事ではありません。
私たちの身近にも、声なきSOSを発している人がいるかもしれないのです。
作品は直接的な解決策を示すわけではありませんが、当事者の苦しみや葛藤を読者に深く考えさせます。
同時に、児童相談所や里親制度といった社会的支援の存在にも触れており、絶望の中にも光を見出すことができます。
あなたも普段のニュースや身の回りの出来事から、社会問題について考えることがあるでしょう。
この作品を通じて感じた社会への思いを、感想文に込めてみてください。
※『52ヘルツのクジラたち』で作者が伝えたいことはこちらで考察しています。
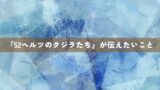
『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】52ヘルツの声に耳を傾けて
私は普段あまり読書をしないが、『52ヘルツのクジラたち』は最後まで一気に読んでしまった。
この本のタイトルにもなっている「52ヘルツのクジラ」は、他のクジラには聞こえない高い声で鳴く、世界で一番孤独なクジラのことだ。
主人公の貴瑚さんも、言葉を話せなくなった少年も、まさにこのクジラのような存在だった。
必死に声を上げているのに、誰にも届かない。
そんな深い孤独感が胸に刺さった。
貴瑚さんは毒親と呼ばれる母親から愛情をもらえず、一人で義父の介護まで押し付けられていた。
読んでいて本当につらくなったが、同時に「こんな経験をしている人が実際にいるのだ」と現実の重さを感じた。
私も家族と上手くいかない時があるが、貴瑚さんの状況と比べると、自分はまだ恵まれているのかもしれない。
でも、家族の問題で悩んでいる気持ちは同じだと思う。
この物語で最も印象的だったのは、貴瑚さんと少年が出会い、少しずつ心を開いていく場面だった。
血のつながりはないけれど、お互いの痛みを分かち合い、支え合う関係を築いていく。
本当の「家族」とは何なのかを考えさせられた。
私は今まで家族とは血がつながった人たちのことだと思っていた。
しかし『52ヘルツのクジラたち』を読んで、大切なのは血のつながりではなく、お互いを思いやる気持ちなのだと気づいた。
自分を理解してくれる人、一緒にいると安心できる人がいることの大切さを実感した。
また、この作品には児童虐待という重いテーマも含まれている。
ニュースでよく耳にする問題だが、実際にどんな苦しみがあるのかを深く考えたことはなかった。
少年が言葉を話せなくなるほどの傷を負っていたことを知り、虐待の深刻さを痛感した。
もしかすると、私の周りにも声なき助けを求めている人がいるかもしれない。
今度からは、友達の小さな変化にも気を配ろうと思う。
物語の終盤で、貴瑚さんが少年のために行動を起こす場面がある。
自分も同じような経験をしているからこそ、今度は誰かを救いたいという強い気持ちが伝わってきた。
人は一人では生きていけないが、誰かのために何かをすることで、自分も救われるのだと学んだ。
『52ヘルツのクジラたち』を読んで、私は「つながり」の大切さを深く感じた。
孤独で苦しんでいる時こそ、誰かに手を差し伸べることの意味がある。
そして、自分が困っている時は素直に助けを求めることも大切だ。
52ヘルツの声は他のクジラには届かないかもしれないが、同じ周波数で鳴く仲間がいれば、きっと通じ合えるはずだ。
私も今後は、周りの人の「52ヘルツの声」を聞き逃さないよう、もっと注意深く人と関わっていきたい。
そして自分が孤独を感じた時は、諦めずに声を上げ続けようと思う。
この本は、人と人とのつながりがいかに大切かを教えてくれる素晴らしい作品だった。
『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】孤独から生まれる新たな絆
『52ヘルツのクジラたち』というタイトルを初めて見た時、なぜクジラなのだろうと疑問に思った。
しかし読み進めるうちに、このタイトルが物語の核心を見事に表現していることが分かった。
52ヘルツで鳴くクジラは、他のクジラには聞こえない周波数のため「世界で最も孤独なクジラ」と呼ばれている。
主人公の貴瑚も、虐待を受ける少年も、まさにこのクジラのような存在だった。
必死に声を上げているのに、誰にも届かない深い孤独感が物語全体を貫いている。
町田そのこさんが描く登場人物たちの心の動きは、読者の胸に深く刺さる。
貴瑚は毒親と呼ばれる母親からネグレクトを受け、21歳という若さで義父の介護を一人で背負わされていた。
現代社会におけるヤングケアラーの問題が、リアルに描写されている。
私自身、祖父母の介護を手伝った経験があるが、それでも家族全員で分担していた。
貴瑚のように一人ですべてを背負う状況を想像すると、その絶望感は計り知れない。
彼女が死を考えるほど追い詰められていたことに、現代社会の闇を感じずにはいられなかった。
しかし、この物語の真価は絶望で終わらないところにある。
貴瑚が新天地で出会った言葉を話せない少年との関係性が、読者に希望を与えてくれる。
二人は血のつながりこそないものの、同じような傷を持つからこそ分かり合える部分がある。
お互いの痛みを理解し、支え合う関係を築いていく過程が丁寧に描かれている。
従来の家族像にとらわれない、新しい「つながり」の形がここにある。
私は今まで家族とは血縁関係で結ばれた人たちだと思っていた。
しかし『52ヘルツのクジラたち』を読んで、本当の家族とは互いを思いやり、支え合える関係なのだと気づかされた。
現代社会では核家族化が進み、家族の形も多様化している。
この作品が示す新しい家族像は、時代の変化に対応した価値観を提示していると感じた。
また、登場人物たちの回復過程も印象深い。
彼らの心の傷は一朝一夕には癒えない。
立ち止まったり、時には後戻りしたりしながら、それでも少しずつ前に進んでいく。
この「完璧ではない回復」の描写が、物語にリアリティを与えている。
私たちの人生においても、挫折や困難は避けられない。
しかし重要なのは、完璧に立ち直ることではなく、諦めずに歩み続けることなのだと学んだ。
他者との関わりの中で徐々に癒されていく心の動きは、人間の回復力の素晴らしさを教えてくれる。
『52ヘルツのクジラたち』には、現代社会が抱える様々な問題が描かれている。
児童虐待、毒親、ヤングケアラー、トランスジェンダーへの理解不足など、どれも身近にある可能性のある問題だ。
これらの問題に対する直接的な解決策は示されていないが、当事者の苦しみや葛藤を読者に深く考えさせる。
私も普段ニュースでこれらの問題を目にするが、実際の当事者の気持ちまで想像することは少なかった。
この作品を通して、社会問題を「自分事」として捉える重要性を感じた。
特に印象的だったのは、「声なきSOS」に気づくことの大切さだ。
貴瑚が少年の助けを求める声に気づき、行動を起こしたことで物語が動き出す。
現実の世界でも、私たちの周りには助けを必要としている人がいるかもしれない。
その人たちの「52ヘルツの声」を聞き逃さないよう、もっと注意深く周囲を見渡す必要があると感じた。
SNSが普及した現代では、表面的なつながりは増えたが、本当の意味での理解や共感は減っているかもしれない。
『52ヘルツのクジラたち』が描く深いつながりは、現代人が忘れかけている大切なものを思い出させてくれる。
同時に、この作品は希望も与えてくれる。
絶望的な状況にあっても、誰かとのつながりがあれば立ち直ることができる。
児童相談所や里親制度といった社会的支援の存在も描かれており、社会全体で困っている人を支える仕組みがあることも示されている。
個人の努力だけでなく、社会全体で問題に取り組む必要性も感じた。
読了後、私は自分の周りの人間関係を見直してみた。
家族や友人との関係において、相手の気持ちを理解しようとしているだろうか。
表面的な会話だけでなく、本当の意味でのコミュニケーションを取れているだろうか。
『52ヘルツのクジラたち』を読んで、人とのつながりをもっと大切にしたいと強く思った。
この作品は、孤独や絶望といった重いテーマを扱いながらも、最終的に読者に希望を与えてくれる。
現代社会を生きる私たちにとって、必読の一冊だと感じた。
52ヘルツの声は他のクジラには届かないかもしれないが、同じ周波数で鳴く仲間がいれば必ず通じ合える。
私たちもまた、誰かの「52ヘルツの声」に耳を傾け、自分自身の声も上げ続けることで、新たなつながりを築いていけるのではないだろうか。
振り返り
今回は『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この作品は孤独や社会問題といった重いテーマを扱いながらも、人間の回復力や新たなつながりの可能性を描いた素晴らしい小説です。
感想文を書く際は、あなた自身がどの場面に心を動かされたか、どんな気づきを得たかを大切にしてください。
中学生の皆さんも高校生の皆さんも、例文を参考にしながら自分らしい表現で感想を綴ってみましょう。
コピペではなく、あなた独自の視点と感性で書かれた感想文こそが、読み手の心に響く作品となります。
きっと素晴らしい読書感想文が完成しますよ。
※『52ヘルツのクジラたち』のあらすじはこちらでご紹介しています。







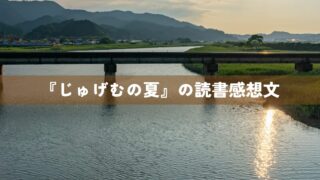
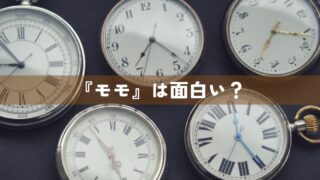

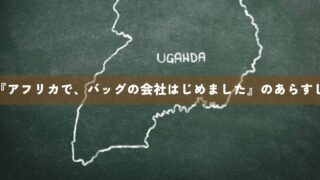
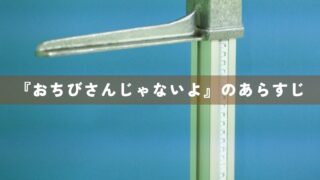
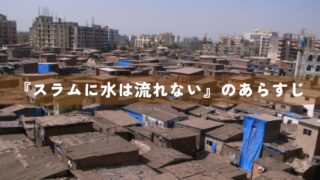
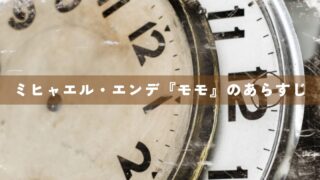
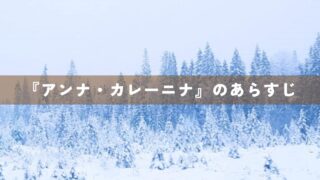





コメント