今日は『アルジャーノンに花束を』という心に深く残る本のあらすじと、あらましを解説していきますね。
この小説はアメリカの作家ダニエル・キイスが書いた感動作で、知的障害を持つ青年チャーリイが脳手術を受けて天才になり、その後の変化を日記形式で綴った物語。
読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、短くて簡単なあらすじから、結末も含めた詳しいあらすじまで、丁寧に解説していきます。
読書感想文で何を書けばいいのか迷っている方も、この記事を読めばきっと書くべきポイントがつかめるはずですよ。それではさっそく進めていきましょう。
本の虫で年間100冊以上の小説を読みふける本好きな私におまかせください。
『アルジャーノンに花束を』の簡単で短いあらすじ
『アルジャーノンに花束を』の簡潔なあらすじ
『アルジャーノンに花束を』の結末までの詳しいあらすじ
32歳でIQ68の知的障害者チャーリイ・ゴードンは、パン屋で働きながら障害者のための学習クラスに通っていた。ある日、教師のアリスから脳手術を勧められる。その手術は実験ネズミのアルジャーノンに驚くべき知能向上効果をもたらしていた。チャーリイは「かしこくなりたい」という一心で手術を受けることを決意する。
手術は成功し、チャーリイのIQは急上昇、ついには185という天才レベルに達する。彼は大学で研究し、複雑な問題を解けるようになる。しかし知能が高まるにつれ、これまで友達だと思っていた同僚たちが実は自分をからかっていたことや、母親に拒絶された過去など、つらい現実も理解するようになる。
感情の発達が知能に追いつかないチャーリイは人間関係で苦労し、孤独を感じるようになる。そんな中、アルジャーノンに異変が現れる。調査の結果、この手術には致命的な欠陥があり、知能はピークに達した後、急速に低下することを発見する。そして彼もまたアルジャーノンと同じ運命をたどることになるのだった。
『アルジャーノンに花束を』のあらすじを理解するための用語解説
| 用語 | 解説・意味 |
|---|---|
| 知能向上手術 | 脳の外科的手術や実験的な医学的手法によって、 被験者(チャーリイやマウスのアルジャーノン)の 知能指数(IQ)を劇的に上昇させる架空の治療法。 本作の大きな物語の核。 |
| IQ(知能指数) | Intelligence Quotientの略。 知能レベルを示す標準的指標で、 手術前後で急激に数値が変動することがストーリー上の注目点。 |
| 信頼できない語り手 | 主人公自身の手記という形式上、 知能や認知の変化によって 物語の内容や真偽にバイアスがかかる「文学的効果」。 |
『アルジャーノンに花束を』の概要
| 作者 | ダニエル・キイス(Daniel Keyes) |
|---|---|
| 出版年 | ・1959年(短編) ・1966年(長編) |
| 受賞歴 | ・1960年ヒューゴー賞短編小説部門 ・1967年ネビュラ賞 |
| 主な舞台 | アメリカの都市部 |
| 時代背景 | 1950年代〜1960年代のアメリカ |
| 出版社 | 早川書房 |
| 青空文庫 | 未収録 |
『アルジャーノンに花束を』の主要な登場人物
『アルジャーノンに花束を』には魅力的な登場人物がたくさん登場します。
以下、チャーリイを中心に物語を形作る重要人物をご紹介しますね。
| チャーリイ・ゴードン | 主人公。32歳の知的障害者で、パン屋で働いている。 IQは68から手術後は185に。 純粋で優しい性格だが、知能向上後に苦悩する。 |
|---|---|
| アルジャーノン | 実験用のハツカネズミ。 チャーリイと同じ脳手術を受けて高い知能を得る。 チャーリイの運命を先取りする存在。 |
| アリス・キニアン | チャーリイの担任教師。 彼に脳手術を勧め、後に恋愛感情を抱く。 最後まで一人の人間として接し続けた。 |
| ハロルド・ニーマー教授 | プロジェクトの研究主任。 プライドが高く神経質な性格で、 チャーリイを一人の人間としてではなく 研究対象としか見ていない。 |
| ジェイ・ストラウス博士 | 脳神経外科医。 チャーリイの手術を執刀した。 気さくな性格でチャーリイに親しく接する。 |
| バート・セルドン | プロジェクトの助手を務める大学院生。 アルジャーノンの世話をしており、親切な性格。 |
| フェイ・リルマン | 女流画家。 自由奔放な性格で、 天才となったチャーリイと一時期交際していた。 |
| ローズ・ゴードン | チャーリイの母親。 息子の障害を受け入れられず、 健常者と同等にすることに固執していた。 |
| マット・ゴードン | チャーリイの父親。 息子の障害を受け入れており、 妻と対立することもあった。 |
| ノーマ・ゴードン | チャーリイの妹。 母の影響で兄を嫌っていたが、 後に思いやりのある優しい性格に成長している。 |
これらの登場人物たちがそれぞれの立場からチャーリイとかかわり、物語を深く豊かなものにしています。
『アルジャーノンに花束を』の文字数と読了時間
『アルジャーノンに花束を』はどのくらいの長さなのか、どれくらいの時間があれば読めるのか気になりますよね。
以下に文字数と読了時間の目安をまとめました。
| 推定文字数 | 約278,400文字 (464ページ×600文字) |
|---|---|
| 平均的な読了時間 | 約9時間20分(500字/分の読書速度で計算) |
| 速読の場合 | 約5時間30分(800字/分の読書速度で計算) |
| じっくり読む場合 | 約13時間50分(350字/分の読書速度で計算) |
小説を読む際の目安としてください。
この作品は内容が深いので、じっくり味わいながら読むことをおすすめします。
※『アルジャーノンに花束を』を通して作者が伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『アルジャーノンに花束を』はどんな人向けの小説か
『アルジャーノンに花束を』は多くの人の心を動かす作品ですが、特に以下のような方々にぴったりの小説と言えるでしょう。
- 人間の心理や感情の変化に興味がある人
- 知性と幸福の関係について考えたい人
- 感動的な物語が好きな人
- 社会的な問題について深く考えたい人
- SF要素を含んだヒューマンドラマが好きな人
この作品は「知能」という一見単純な概念を通して、人間の本質や社会のあり方について深く掘り下げています。
また、日記形式の独特の語りが臨場感を生み出し、チャーリイの成長と苦悩を自分のことのように感じられる構成になっています。
知的な刺激を求める方にも、感動的なストーリーを楽しみたい方にも、どちらにも満足していただける珠玉の一冊です。
特に、自分自身や他者との関係について見つめ直したいと思っている方には、新たな視点を提供してくれるでしょう。
※『アルジャーノンに花束を』の面白いところは、以下の記事で力説しています。

『アルジャーノンに花束を』と類似した内容の小説3選
『アルジャーノンに花束を』のテーマや雰囲気に近い作品をいくつか紹介します。
この小説を気に入った方は、ぜひ以下の作品にも触れてみてください。
『怪笑小説』by 東野圭吾
東野圭吾のこの短編集には「あるジーサンに線香を」という作品が収録されており、『アルジャーノンに花束を』へのオマージュとなっています。
若返りをテーマにした物語で、能力の向上と低下という点で共通点があります。
東野圭吾らしい独特のユーモアとミステリー要素を交えながら、人間の根源的な願望や葛藤を描いています。
『フラニーとズーイ』by J.D.サリンジャー
サリンジャーのこの連作小説は、精神的な成長や人間関係の複雑さをテーマにしており、『アルジャーノンに花束を』と共通する部分があります。
特に、理想と現実のギャップに苦しむ主人公の内面描写は類似点が多く、知性や才能を持つことの喜びと苦悩を描いた作品として興味深いものになっています。
『あなたの人生の物語』by テッド・チャン
SF短編集である本作には、言語習得によって世界の見方が変わっていく「バビロンの塔」など、知能や認識の変化をテーマにした物語が収録されています。
『アルジャーノンに花束を』同様、知性の変化が人間の存在や人生にどのような影響を与えるかを探る内容で、深い思索を促してくれる作品です。
振り返り
今回は『アルジャーノンに花束を』について、あらすじから読書感想文のポイント、そして類似作品まで幅広く紹介しました。
この小説が多くの人々に愛され続けているのは、単なるSF的な設定を超えて、人間の本質や尊厳、幸福とは何かといった普遍的なテーマを深く掘り下げているからでしょう。
チャーリイの成長と苦悩の物語は、私たちに「知能」や「障害」についての固定観念を見直すきっかけを与え、一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを教えてくれます。
読書感想文を書く際には、ただあらすじを書くだけでなく、この記事で紹介した「知能と人間関係」「自己受容」「知性と幸福」といったテーマを踏まえ、自分なりの考えを述べることが大切。
この作品との出会いが、皆さんにとって新たな視点や思考のきっかけとなれば幸いです。
※『アルジャーノンに花束を』の読書感想文を書く際はこちらの記事をおすすめします。



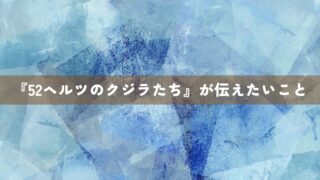







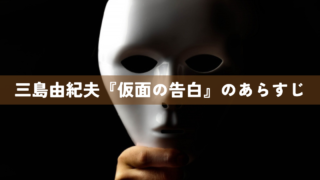

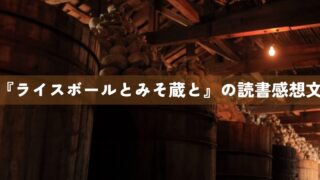



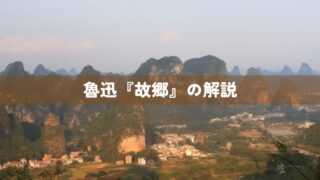
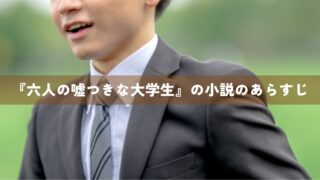

コメント