『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
いとうみく作の『かあちゃん取扱説明書』は、小学4年生の男の子・哲哉が毎日ガミガミうるさい母親に不満を感じ、「かあちゃん取扱説明書」を作ることで母親の本当の気持ちに気づいていく心温まる家族の物語ですね。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文で書くべき3つのポイント
『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要なポイントを3つ紹介します。
これらのポイントについて「どう感じたか」をしっかりとメモしておくことが、魅力的な感想文を書くための第一歩になりますよ。
- 主人公・哲哉の心の変化と成長の過程
- 「取扱説明書」という設定から見えてくる家族関係の本質
- 母親の愛情と日常の大変さへの理解
これらのポイントを読んでいる間に感じたことをメモするときは、「なぜそう思ったのか」「自分の経験と重ね合わせるとどうだろう」という視点で書き留めておくといいでしょう。
感想文では、あらすじを説明するよりも「自分がどう感じたか」が最も大切な要素になります。
だからこそ、読書中に感じた素直な気持ちや疑問を大切にして、それを文章にしていくことが重要なんですね。
主人公・哲哉の心の変化と成長の過程
物語の始まりで哲哉は、毎日ガミガミうるさい「かあちゃん」に対して不満でいっぱいです。
「自分の思い通りに動かそう」という気持ちから「かあちゃん取扱説明書」を作り始めますが、観察を続けるうちに母親への見方が大きく変わっていきます。
最初は母親を攻略したいと考えていた哲哉が、最終的には母親への愛情や家族のつながりの大切さに気づく過程は、この物語の最も重要なテーマですね。
哲哉がどんなきっかけで心境の変化を迎えたのか、どの場面で特に成長を感じられたのかを具体的に挙げながら、自分自身の経験と照らし合わせて感想を書いてみてください。
「私も哲哉と同じように家族に対して不満を感じることがある」「でもこの物語を読んで、家族を見る目が変わった」といった個人的な体験を交えることで、より説得力のある感想文になりますよ。
「取扱説明書」という設定から見えてくる家族関係の本質
この物語の最もユニークな点は、主人公が母親を家電製品のように扱い、その「取扱説明書」を作ろうとする設定です。
家電の取扱説明書を真似て作り始めた「かあちゃん取扱説明書」ですが、人間は機械とは違って複雑で、簡単に「攻略」できる存在ではないことが物語を通して明らかになります。
哲哉が取扱説明書を作る過程で発見する「かあちゃんの意外な一面」や「知らなかった過去」は、家族といえども互いをすべて知っているわけではないという事実を教えてくれますね。
この設定について皆さんはどう感じましたか。
「もし自分が家族の取扱説明書を作るとしたら」という視点で考えてみると、家族関係の複雑さや温かさについて新しい発見があるかもしれません。
母親の愛情と日常の大変さへの理解
物語の中で哲哉は、母親の行動を観察し、昔の話を聞く中で、母親の本当の気持ちや日々の大変さを理解していきます。
スーパーで働きながら家事をこなし、時には厳しく、時には優しく接する母親の姿は、多くの読者にとって身近な存在として映るでしょう。
哲哉が発見する「かあちゃんの秘密」や「愛情の表現方法」は、普段当たり前だと思っている家族の存在の大切さを改めて教えてくれます。
物語の中で特に印象的だった母親の行動や言葉があれば、それについてどう感じたかを具体的に書いてみてください。
「私のお母さんも同じようなことをしている」「家族の愛情にはいろいろな形がある」といった気づきを、自分の言葉で表現することが大切ですよ。
※『かあちゃん取扱説明書』のあらすじはこちらで簡単にご紹介しています。

『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文のテンプレート
読書感想文を書くのが苦手な皆さんでも、このテンプレートに沿って書けば、きっと素敵な感想文が完成しますよ。
1~6の各ステップの空欄を埋めながら、自分だけの感想文を作り上げていきましょう。
- 書き出し(作品との出会い)
私は『かあちゃん取扱説明書』を読んで、( )と感じた。なぜなら( )だからだ。 - 主人公への共感ポイント
主人公の哲哉が( )する場面では、私も( )と思った。特に印象的だったのは( )のシーンで、( )と感じた。 - 「取扱説明書」という設定について
哲哉が「かあちゃん取扱説明書」を作ろうとする発想は( )だと思う。もし私が家族の取扱説明書を作るとしたら、( )について書きたい。 - 母親への理解の変化
物語の中で哲哉の母親に対する見方が変わったように、私も( )について考えが変わった。特に( )の場面では、( )ことに気づかされた。 - 自分自身への応用・まとめ
この物語を読んで、私は家族との関係について( )と思うようになった。これからは( )していきたい。
このテンプレートを使えば、先ほど紹介した3つのポイントがすべて含まれた感想文が書けるようになっています。
無理にすべての空欄を埋める必要はありませんが、自分が一番強く感じたポイントを中心に、具体的なエピソードを交えながら書いてみてくださいね。
『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】かあちゃんの本当の気持ち
私は『かあちゃん取扱説明書』を読んで、家族の大切さについて考えた。
主人公の哲哉がかあちゃんに対して感じている不満は、私も日頃からお母さんに対して感じていることとよく似ていた。哲哉のかあちゃんは「早く早く」と口うるさく言うのに、自分は朝の準備が遅かったりする。
私のお母さんも「宿題やったの?」「片付けなさい」と毎日のように言ってくる。だから哲哉が「かあちゃん取扱説明書」を作ろうと思った気持ちがよくわかった。
哲哉が家電の取扱説明書を参考にして「正しい扱い方」を研究し始めたのは面白いアイデアだと思った。でも読み進めると、最初は「かあちゃんを思い通りにする方法」だったのが、だんだん「かあちゃんの気持ちを知ること」に変わっていくのに気がついた。
特に印象的だったのは、昔の写真を見てかあちゃんの過去を知る場面だった。かあちゃんにも子ども時代があり、哲哉を産んだときの不安や、心から愛している思いを知った哲哉の驚きが伝わってきた。私もこの場面を読んで、お母さんにも私の知らない人生があるのだと気づいた。
また、哲哉が観察して見つけた「かあちゃんの頑張り」も心に残った。スーパーで働き、家事もこなし、疲れていても哲哉のために時間を作ってくれる。私のお母さんも同じように毎日働きながら家のことをしてくれているのに、私は「怒ってばかり」と不満に思っていた。でもこの本を読んで、怒るのは心配しているからだとわかった。
哲哉が最後に「やっぱりかあちゃんにはかなわない」と書いた気持ちはよくわかる。どんなに説明書を作っても、かあちゃんは機械じゃないから完全に理解はできない。でもそれが人間らしく温かいところなのだと思う。
この物語を読んで、私もお母さんのことをもっと知りたいと思った。今度子どもの頃の話を聞いてみたいし、文句を言う前に理由を考えてみようと思う。家族は当たり前にそばにいるからこそ特別で大切なのだと教えてくれた物語だった。
『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】家族を理解するということ
私は『かあちゃん取扱説明書』を読んで、家族関係の複雑さと温かさについて深く考えさせられた。
主人公の哲哉が母親に対して抱く不満や疑問は、思春期を迎えた私自身が日々感じているものと重なり、物語の世界に自然と引き込まれていった。哲哉が「かあちゃん取扱説明書」を作ろうと思い立った発想には、最初は子どもらしい面白さを感じた。
家電製品の説明書のように、母親の「正しい扱い方」や「機嫌を良くする方法」をマニュアル化しようとする試みは合理的で効率的に思える。私も時々、家族の行動を分析して、どうすれば怒られずに済むかを考えることがある。
しかし、物語が進むにつれて哲哉の取り組みは単なる「攻略法」から「理解」へと変化していく。母親を観察し、過去の話を聞き、行動の理由を探る中で、母親が単純に攻略できる相手ではなく、複雑な感情や背景を持つ一人の人間だとわかっていく。この変化は、親を一面的に見がちな私たちに大切な気づきを与えてくれる。
特に印象的だったのは、哲哉が母親の昔の作文を読む場面だ。そこには妊娠した当時の不安や、生まれてくる子どもへの深い愛情が綴られていた。哲哉にとって母親は常に「お母さん」だったが、一人の女性としての人生や積み重ねた経験があると知る瞬間は、物語の大きな転機に思えた。
私もこの場面を読んで、自分の母にも学生時代や夢を抱いた時期があったことに改めて気づいた。一人の人間が子どもを育てるために悩みや犠牲を抱えながら「お母さん」になったのだと思うと、これまでの反抗的な態度を少し反省した。
また、母親の日常の忙しさや大変さを目にする場面も心に残った。スーパーでの仕事、帰宅後の家事や子育て。それらをこなしながら、疲れていても家族のために時間を作る姿は多くの家庭に共通する現実だろう。子どもは親の苦労を当たり前と受け取りがちだが、その背後に努力や我慢があることを、この物語は気づかせてくれる。
哲哉が最終的に出した「やっぱりかあちゃんにはかなわない」という結論は、家族関係の本質を表している。完璧ではないが、だからこそかけがえのない存在。この言葉には、理想化ではなく現実の親を受け入れる成熟した視点が感じられた。私もこの物語を読んで、親の欠点や理不尽さだけでなく、その背後の愛情や努力に目を向けるべきだと思った。
完璧な「取扱説明書」は存在しないが、相手を理解しようとする姿勢こそが、家族関係を築く第一歩だろう。この作品は、最も身近でありながら最も複雑な人間関係について、ユーモアを交えつつ深い洞察を与えてくれる物語だった。私も哲哉のように家族の「取扱説明書」を作ってみたい。それは攻略法ではなく、理解を深めるための手段として。
振り返り
『かあちゃん取扱説明書』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
この作品は家族関係の複雑さと温かさを描いた名作で、読書感想文のテーマとしても非常に書きやすい作品ですね。
今回紹介した3つのポイントを意識しながら、テンプレートを活用すれば、皆さんも必ず心に響く感想文が書けるはずです。
大切なのは、コピペに頼らず自分の言葉で素直な気持ちを表現することです。
哲哉と同じように、家族のことを改めて見つめ直すきっかけとして、この読書感想文を書いてみてください。
きっと皆さんなりの素敵な発見があるはずですよ。
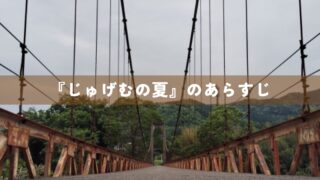
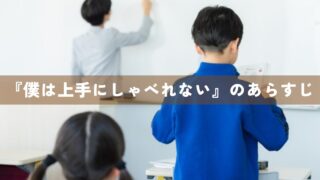

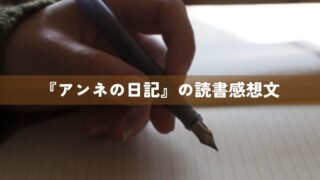





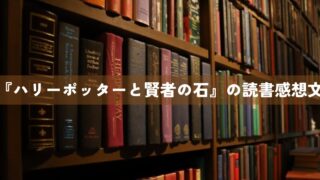
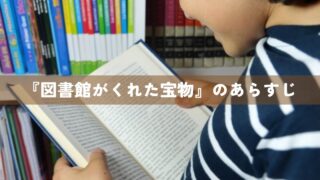
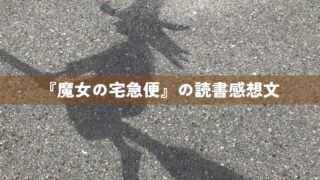



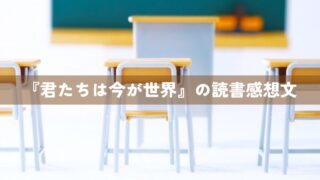
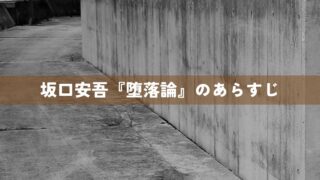


コメント