『いつかの約束1945』のあらすじを簡単に短く、そして詳しくご紹介していきますね。
この作品は山本悦子さんによる感動的な児童文学で、2024年の青少年読書感想文全国コンクールの課題図書にも選ばれた話題作です。
戦争と平和をテーマに、認知症のおばあちゃんと現代の子どもたちの心温まる交流を描いた物語をネタバレなしでお伝えしますので安心してくださいね。
年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんのお役に立てるよう、短くて簡単なあらすじから詳しい内容まで丁寧に解説していきます。
この記事を読めば『いつかの約束1945』の魅力が十分に理解でき、きっと読みたくなるはずですよ。
山本悦子『いつかの約束1945』のあらすじを短く簡単に
夏の日、小学生のゆきなとみくは道端で不思議なおばあちゃんに出会う。
おばあちゃんは「私は9歳の関根すずよ」と言い、自分の心が子どもと入れ替わったのだと話した。
2人の女の子はすずと一緒に町を歩きながら、戦争の記憶と現代の暮らしが交じり合う不思議な一日を過ごしていく。
山本悦子『いつかの約束1945』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
夏の陽射しが照りつける道端で、小学生のゆきなとみくはしゃがみ込んでいるおばあちゃんを見つけた。「私はおばあちゃんじゃない、9歳の関根すずよ」と名乗るその女性の言葉に二人は驚きながらも、不思議な出会いに心惹かれ、すずの”元の心”を探す旅に連れ立った。
町を歩くすずは現代の風景に目を輝かせた。自動販売機から飲み物が出てくる光景に驚き、頭上を飛ぶ飛行機を指さして声を上げる。だが戦争の話題になると表情が曇り、胸を押さえて苦しそうにするのだった。ゆきなとみくは次第に、これが単なる心の入れ替わりではなく、すずの心の奥底に眠る記憶が呼び覚まされているのではと感じるようになる。
市の戦争展で三人の足が止まったのは、「いつかの約束」と題された一枚の絵の前だった。幼いすずが描いたというその絵には、明るい空の下で手を取り合う人々の姿が力強く表現されていた。未来への希望を映し出すその絵に、ゆきなとみくの胸は静かに熱くなっていくのだった。
『いつかの約束1945』のあらすじを理解するための用語解説
物語に登場する重要な用語をまとめましたので、参考にしてくださいね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 心の入れ替わり | 物語のミステリー要素。 実際は認知症による記憶の混乱が原因だが 主人公たちは心が入れ替わったと考える。 |
| 1945年 | 太平洋戦争終戦の年。 物語の重要な背景であり すずの過去に深く関わる年。 |
| いつかの約束 | タイトルが示す平和への願い。 戦争の悲しみを繰り返さず 未来に向けて平和を守る約束を象徴している。 |
これらの用語を理解しておくと、『いつかの約束1945』の物語がより深く味わえますよ。
『いつかの約束1945』の感想
正直に言うと、『いつかの約束1945』を読み始めた時は「児童書だから軽く読めるだろう」と思っていました。
でも、これが大間違いでしたね。
ページをめくるごとに、じわじわと胸に迫るものがあって、気がついたら涙がこぼれていたんです。
特に印象深かったのが、すずおばあちゃんが現代の自動販売機を見て驚くシーンです。
「こんなに便利な機械があるのね」という純粋な驚きの声に、戦時中を生きた人の気持ちがリアルに伝わってきました。
私たちが当たり前だと思っている日常が、実はどれほど恵まれているのかを改めて実感させられましたよ。
ゆきなとみくの2人が、すずと一緒に町を歩きながら少しずつ真実を理解していく過程も本当に巧妙に描かれています。
子どもたちの素直な疑問や優しさが、読んでいる私の心もほっこりさせてくれるんです。
「なんでおばあちゃんは痛がるんだろう」「戦争って何だったんだろう」という純粋な問いかけが、戦争の重みを自然に伝えてくれました。
山本悦子さんの文章力には本当に脱帽です。
重いテーマを扱いながらも、決して説教臭くならず、子どもの視点から戦争と平和を考えさせてくれる構成が見事でした。
認知症という現代的な問題と戦争体験を組み合わせたアイデアも秀逸で、「こんな切り口があったのか」と唸らされましたね。
特に感動したのは、物語の終盤で市の戦争展に登場する「いつかの約束」という絵の場面です。
すずが子ども時代に描いた平和への願いが現代につながっているという設定に、思わずぐっときてしまいました。
戦争を知らない世代の私でも、平和の尊さが心に染み入るような感覚を覚えたんです。
ただ、正直に言うと理解に時間がかかった部分もありました。
認知症の複雑な症状や、過去と現在が交錯する心理状態の描写は、大人の私でも「ちょっと難しいな」と感じる箇所がありましたからね。
でも、それも含めて現実的で、安易に美化しない作者の姿勢を感じました。
読み終わった後は、しばらく本を閉じることができませんでした。
「平和って当たり前じゃないんだ」「今の暮らしがどれだけありがたいことか」という思いが胸いっぱいに広がって、家族や友人の顔が頭に浮かんだんです。
『いつかの約束1945』は確実に私の中に残り続ける一冊になりました。
読書感想文を書く学生さんたちには、ぜひ自分なりの感じ方で向き合ってほしい作品ですね。
『いつかの約束1945』の作品情報
こちらが『いつかの約束1945』の基本的な作品情報になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 山本悦子(作) 平澤朋子(絵) |
| 出版年 | 2023年6月14日 |
| 出版社 | 岩崎書店 |
| 受賞歴 | 2024年『第70回青少年読書感想文全国コンクール』 小学校中学年の部課題図書 |
| ジャンル | 児童文学 |
| 主な舞台 | 現代の町と1945年の戦争終結期 |
| 時代背景 | 現代と太平洋戦争終戦期 |
| 主なテーマ | 戦争と平和、世代を超えたつながり、認知症 |
| 物語の特徴 | ファンタジー要素を交えた平和教育作品 |
| 対象年齢 | 小学校中学年向け(およそ9歳以上) |
| 青空文庫の収録 | 2025年8月時点で未収録 |
感想文コンクールの課題図書に選ばれるほど教育的価値の高い作品として認められています。
『いつかの約束1945』の主要な登場人物とその簡単な説明
物語の中心となる人物たちをご紹介しますね。
| 人物名 | 説明 |
|---|---|
| 関根すず | 認知症により 自分は9歳の少女だと信じているおばあさん。 戦争体験を持ち 過去と現在が交錯する心の中でゆきな・みくと出会う。 |
| ゆきな | 物語の語り手の一人で現代の小学生。 明るく好奇心旺盛で、 すずとの交流を通して戦争や平和について考える。 |
| みく | もう一人の小学生主人公。 ゆきなとともにすずと行動し、 戦争の記憶と現在のつながりに気づいていく。 |
| すずのひ孫 | 物語後半で登場する重要人物。 すずとの関係を通して 戦争の過去と現在の世代をつなぐ役割を持つ。 |
子どもたち(ゆきな・みく)が中心となって進む『いつかの約束1945』の物語構造がよくわかりますね。
『いつかの約束1945』の読了時間の目安
読書計画を立てる参考にしてくださいね。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ページ数 | 152ページ |
| 文字数 | 不明 |
| 読了時間の目安 | 1~2時間 |
『いつかの約束1945』は児童書なので比較的読みやすく、集中すれば一日で読み終えることも可能です。
ただし、内容が深いので じっくりと味わいながら読むことをおすすめしますよ。
『いつかの約束1945』はどんな人向けの小説か?
この作品がぴったり合う読者のタイプをまとめてみました。
『いつかの約束1945』をおすすめしたい人は以下の通りです。
- 戦争と平和について考えたい小学生~中学生
- 親子で一緒に読書を楽しみたいファミリー
- 感動的な児童文学を探している大人の読者
特に読書感想文の課題図書に選ばれているため、夏休みの宿題で取り組む学生さんには最適の一冊でしょう。
逆に、重いテーマが苦手な方や、ファンタジー要素に抵抗がある方にはあまり向かないかもしれませんね。
でも、多くの読者に愛され続けている『いつかの約束1945』なので、一度手に取ってみる価値は十分にありますよ。
『いつかの約束1945』と似たテーマの小説2選
『いつかの約束1945』と同じようなテーマや雰囲気を持つ作品をご紹介しますね。
戦争、平和、世代を超えたつながりに興味がある方は、きっと気に入るはずです。
高木敏子『ガラスのうさぎ』
戦争で家族や日常を失った少女が、生きる強さと平和の大切さを学ぶ実話をもとにした感動作です。
戦争の悲惨さや命の重さ、家族愛がテーマとなっており、『いつかの約束1945』と同じく平和の尊さを伝える点で共通していますね。
実体験に基づいた重みのある内容で、戦争を知らない世代にも強く訴えかける力を持った一冊です。

野坂昭如『火垂るの墓』
戦争で両親を失った兄妹の悲劇的な体験を描いた代表的な反戦文学です。
『いつかの約束1945』と同様に戦争の悲しみと子どもの純粋さを対比させながら、平和への願いを込めた作品となっています。
より直接的に戦争の現実を描いているため、重厚な読み応えを求める方におすすめですよ。
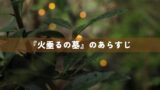
振り返り
『いつかの約束1945』は戦争と平和をテーマにした珠玉の児童文学作品でした。
認知症のおばあちゃんと現代の子どもたちの交流を通して、重いテーマを優しく、そして深く描いた山本悦子さんの手腕には本当に感動させられましたね。
読書感想文を書く予定の皆さんにとって、きっと心に残る一冊になるはずです。
この記事が皆さんの読書の助けになれば幸いです。

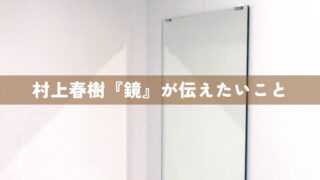



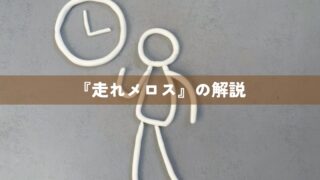



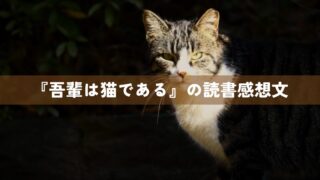
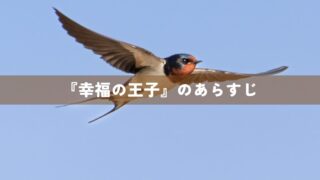

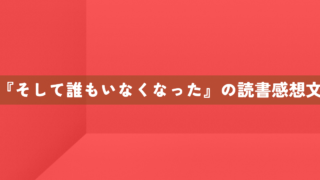


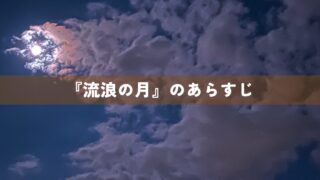

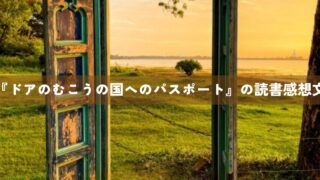

コメント