『くちびるに歌を』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
中田永一による青春小説『くちびるに歌を』は、長崎県五島列島の中学校合唱部を舞台に、思春期の生徒たちが音楽を通して心の成長を遂げていく感動的な物語ですね。
NHKのドキュメンタリー番組をもとに小説化されたもので、2015年には映画化もされた人気作品。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が小学生・中学生・高校生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『くちびるに歌を』の読書感想文で触れたい3つの要点
『くちびるに歌を』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要なポイントがあります。
これらの要点について、読みながら「どう感じたか」をメモしておくことが大切ですよ。
感想文で最も重要なのは、あなた自身がその場面でどんな気持ちになったか、どんなことを考えたかという「個人的な感想」だからです。
まずは、感想文で触れるべき3つの要点を見てみましょう。
- 五島列島という離島の舞台設定が物語に与える影響
- サトルとナズナの心の成長と変化
- 合唱と「15年後の自分への手紙」が持つ意味
これらの要点を読み進めながら、付箋やノートに「ここで私はこう感じた」「この場面は自分の経験と似ている」といったメモを取ってください。
例えば、「サトルが一人でいることを選んでいる場面で、私も似たような経験があったな」とか「合唱部のみんなが心を一つにする場面で涙が出そうになった」といった具合にです。
このような個人的な感想こそが、コピペでは書けない、あなただけのオリジナルな読書感想文の核になるんですよ。
五島列島という舞台設定と物語への影響
五島列島という離島が舞台に選ばれているのには、深い意味があります。
本土から離れた閉鎖的な環境だからこそ、登場人物たちの人間関係がより濃密になり、お互いの心の動きがはっきりと見えてくるのです。
都会とは違って、島では一度起きたことがすぐに知れ渡ってしまい、逃げ場がないという厳しさもあります。
でも、その分、本当の絆を築くことができる環境でもあるのです。
美しい海や自然の描写が、登場人物たちの心の状態を象徴している場面も多くあります。
この舞台設定について、あなたはどう感じましたか?
自分の住んでいる環境と比較して、どんなことを思ったでしょうか?
島という限られた空間で生活することの良さや大変さについて、あなたなりの考えをまとめてみてください。
主人公たちの心の成長
物語の中心となるサトルとナズナは、それぞれ深い悩みを抱えています。
サトルは自閉症の兄を持つことで家族に負い目を感じ、「ぼっち上級者」として周りと距離を置いています。
ナズナは父親の失踪という辛い過去から、男性に対して心を閉ざしてしまっています。
でも、合唱という活動を通じて、二人は少しずつ変わっていきます。
最初はバラバラだった合唱部のメンバーたちが、お互いの気持ちを理解し合い、支え合うようになっていく過程は本当に感動的です。
特に、サトルが長谷川コトミを守って怪我をする場面や、ナズナが自分の過去について話すようになる場面など、彼らの勇気ある行動に心を動かされた人も多いでしょう。
あなたは、サトルやナズナの気持ちに共感できましたか?
自分にも似たような悩みや経験はありませんでしたか?
彼らの成長ぶりを見て、どんなことを学んだか、ぜひ感想文に書いてみてください。
音楽と手紙の力
この物語で最も重要なテーマの一つが、音楽の持つ不思議な力です。
合唱は、一人一人の声が重なって美しいハーモニーを作り出します。
それは、バラバラだった心が一つになることの象徴でもあります。
課題曲「手紙~拝啓 十五の君へ~」にちなんで、生徒たちが「15年後の自分への手紙」を書くという設定も素晴らしいですね。
この手紙を書くことで、生徒たちは自分自身と向き合い、今の気持ちや将来への思いを整理することができました。
物語の終盤で、サトルの兄アキオのために合唱部全員がホールの外で歌う場面は、多くの読者が涙を流す名場面です。
音楽が言葉では表現できない気持ちを伝える力を持っていることを、この場面は教えてくれます。
あなたも、音楽に救われたり、励まされたりした経験はありませんか?
「15年後の自分への手紙」を書くとしたら、どんなことを書きたいでしょうか?
これらの体験と重ね合わせて、感想文を書いてみてください。
『くちびるに歌を』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】歌が繋ぐ心のきずな
私は『くちびるに歌を』を読んで、音楽ってすごいなと心から思った。
この本は、長崎県の五島列島の中学校を舞台にした合唱部の話だ。
主人公の一人サトル君は、自閉症のお兄さんがいて、いつも一人でいることが多い。学校では「ぼっち上級者」と自称しているが、本当はさびしかったのだと思う。私も転校したばかりの頃、友達を作るのが苦手で、一人で過ごすことが多かったので、その気持ちがよく分かる。
もう一人の主人公ナズナさんは、お父さんが家を出て行き、お母さんも亡くなってしまい、深い悲しみを抱えている。そんな二人が合唱部で歌うようになり、少しずつ心を開き、仲間とつながっていく姿がとても感動的だった。
特に印象に残ったのは、柏木先生が「15年後の自分に手紙を書きなさい」と宿題を出したことだ。私もやってみたいと思った。15年後の私は何歳になっていて、どんな大人になっているのだろう。今の私が一生懸命頑張っていることや、夢を諦めずにいる気持ちを未来の自分に伝えたい。
合唱の場面も心に残った。最初は男子と女子が仲良くなく、歌もバラバラだったのに、何度も一緒に歌ううちに心が一つになっていく。歌声が重なり、きれいなハーモニーになる様子を読むと、私もその輪の中で歌っているような気持ちになった。
一番感動したのは、最後にサトル君のお兄さんのために、みんなで心を込めて歌う場面だ。そこには優しさや思いやりがあふれていて、涙が出そうになった。歌には、言葉だけでは届かない気持ちを伝える力があるのだと分かった。
この本を読んで、友達の大切さを改めて感じた。一人でいる時間も悪くないけれど、みんなで力を合わせて何かを成し遂げた時の喜びはとても大きい。
サトル君やナズナさんのように、人は音楽や仲間との出会いで変わることができる。私も、困っている友達がいたら迷わず声をかけて協力したいと思う。
『くちびるに歌を』は、友情や家族の愛、そして音楽の力を教えてくれる本だった。
『くちびるに歌を』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】合唱が教えてくれた本当の絆
『くちびるに歌を』を読み終えたとき、胸の奥から温かいものがこみ上げてきた。
長崎県の五島列島を舞台にしたこの青春小説は、音楽を通じて成長していく中学生たちの姿を、とてもリアルに描いている。
物語の主人公であるサトルとナズナの二人は、それぞれ重い悩みを抱えている。
サトルは自閉症の兄アキオがいることで、家族に負担をかけているという罪悪感に苦しみ、「ぼっち上級者」として一人で過ごすことを選んでいる。
私も中学に入学したばかりの頃、新しい環境に馴染めず、一人でいることが多かった。だから、サトルの気持ちがとても良く分かる。
一方、ナズナは父親の失踪という辛い過去を背負っている。母親も亡くなり、男性に対して不信感を抱いている彼女の心の傷は深い。
そんな二人が合唱部という場所で出会い、音楽を通じて少しずつ心を開いていく過程が、この物語の魅力だと思う。
五島列島という離島が舞台に選ばれているのも意味深い。島という閉鎖的な空間では、逃げ場がない分、人間関係がより濃密になる。美しい自然に囲まれた環境が、登場人物たちの心の動きをより鮮やかに映し出している。
物語の中で特に印象的だったのは、「15年後の自分への手紙」という宿題だ。この課題を通じて、生徒たちは自分自身と向き合うことになる。
私も、もし今「15年後の自分への手紙」を書くとしたら、中学生として抱えている不安や悩み、将来への希望を素直に書くと思う。
合唱の場面では、音楽の持つ力を強く感じた。最初はバラバラだった部員たちが、歌声を重ねるうちに心も一つになっていく。合唱は一人では作り出せない美しいハーモニーを生み出す。それは人と人との関係も同じで、一人一人の個性が重なることで、より素晴らしいものができるのだと思った。
物語の終盤で、サトルの兄アキオのために合唱部員全員がホールの外で歌うシーンは、本当に感動的だった。ここを読んでいるとき、涙が止まらなくなった。
音楽には、言葉では表現しきれない隠れた気持ちを伝える力がある。大切な人への愛情や感謝の気持ちを、歌声に込めて届けることができるのだと物語を通して教えられた気がする。
この物語から学んだのは、一人で抱え込まずに、周りの人を信じて心を開くことの大切さだ。サトルもナズナも、最初は自分の殻に閉じこもっていたが、仲間との出会いと音楽によって変わることができた。
私たち中学生は、思春期という複雑な時期を過ごしている。時には一人になりたいと思うこともあるが、この小説が教えてくれるように、音楽や友達との絆があれば、きっと乗り越えられるはずだ。
『くちびるに歌を』は、青春時代の悩みや葛藤を、温かい希望の光で照らしてくれる作品だった。
『くちびるに歌を』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】五島の風に響く歌声が教えてくれたもの
『くちびるに歌を』を読み終えた瞬間、五島列島の潮風と共に、美しい合唱の歌声が心に響いているような感覚に包まれた。
中田永一によるこの青春小説は、ただの学園ものを超えて、思春期という複雑な時期を生きる私たちに、深い共感と希望を与えてくれる作品だった。
離島という特別な環境で繰り広げられる中学生たちの物語は、都会で生活する私にとっても、決して遠い世界の話ではなかった。
物語の舞台である五島列島という設定に、まず強く惹かれた。
本土から離れた島という閉鎖的な環境は、登場人物たちの人間関係をより濃密にし、彼らの心の動きを鮮明に浮き彫りにしている。
都会のように逃げ場のない環境だからこそ、お互いと真正面から向き合わざるを得ない状況が生まれる。
それは時として息苦しさを感じさせるが、同時に、表面的な関係では得られない深い絆を築く可能性も秘めている。
主人公の一人であるサトルの心境に、私は深く共感した。
自閉症の兄アキオを持つことで、家族に負担をかけているという罪悪感と責任感に苛まれている彼の姿は、私たち高校生が抱える「自分の存在意義」への疑問と重なる部分が多い。
「ぼっち上級者」として周囲と距離を置く彼の選択は、一見消極的に見えるかもしれないが、実は自分なりに家族や周りの人を思いやった結果なのだと理解できた。
私自身も、時として一人でいることを選ぶ時がある。
それは必ずしも孤独を好むからではなく、周りに迷惑をかけたくない、自分のペースで物事を考えたいという気持ちからだ。
もう一人の主人公ナズナの抱える傷の深さにも、胸が痛くなった。
父親の失踪と母親の死という二重の喪失感は、想像を絶する辛さだっただろう。
男性に対する不信感を抱くのも当然で、彼女が心を閉ざしてしまうのも理解できる。
でも、そんな彼女が合唱部での活動を通じて、少しずつ他人を信じることを学んでいく過程は、本当に感動的だった。
人は誰でも、心に傷を抱えて生きている。
それは大小様々だが、誰もが何らかの痛みや悲しみを経験している。
ナズナの姿を見て、傷ついた心が癒されるためには、時間と共に、信頼できる人との出会いが必要なのだと学んだ。
柏木先生が課した「15年後の自分への手紙」という宿題は、物語の中でも特に重要な意味を持つ設定だろう。
この課題は、生徒たちに自分自身と向き合う機会を与え、現在の自分の気持ちを整理し、未来への希望を見つける手助けとなった。
もし私が今、15年後の自分に手紙を書くとしたら、進路への不安、将来への漠然とした期待、そして今大切に思っている友人や家族への感謝の気持ちを、きっと素直に綴るだろう。
この小説を読んで、自分自身への手紙を書くことの意味深さを実感した。
合唱が持つ力についても、深く考えさせられた。
一人一人の声が重なってハーモニーを作り出す合唱は、人間関係の理想的な形を表している。
個々の特性や個性を活かしながら、全体として美しい調和を生み出す。
これは、多様性を認め合いながら、共通の目標に向かって協力することの大切さを教えてくれる。
最初はバラバラだった合唱部のメンバーたちが、練習を重ねるうちに互いを理解し、信頼し合うようになっていく過程は、私たち高校生が友人関係を築いていく過程と似ている。
物語の終盤で描かれる、サトルの兄アキオのために合唱部員全員がホールの外で歌うシーンは、涙なしには読めなかった。
歌声に込められた純粋な思いが、アキオの心に直接届く様子は、音楽の持つ不思議で力強い影響力を証明していた。
私も音楽に救われたり、励まされたりした経験がある。
辛い時に聞いた歌が心の支えになったり、友人と一緒に歌った歌が絆を深めるきっかけになったりした。
音楽には、人の心を動かし、人と人を繋ぐ特別な力があるのだと改めて感じた。
この物語を通して、思春期を生きる私たちにとって最も重要なのは、自分一人で悩みを抱え込まず、周りの人との繋がりを大切にすることだと学んだ。
サトルもナズナも、最初は孤独を選んでいたが、合唱部という居場所と信頼できる仲間を得ることで、自分らしさを取り戻すことができた。
私たち高校生も、進路や将来について様々な不安を抱えている。
時には一人で考え込んでしまうこともあるが、家族や友人、先生といった周りの人たちとの関わりの中で、解決の糸口を見つけることができる。
『くちびるに歌を』は、青春時代の複雑な感情や葛藤を、音楽という美しい表現を通して描いた傑作だった。
五島列島の自然の中で響く合唱の歌声が、登場人物たちの心を癒し、成長させていく様子は、読んでいる私の心にも深い感動を与えてくれた。
この作品が教えてくれた「繋がることの大切さ」と「音楽の力」を、これからの人生でも大切にしていきたいと思う。
振り返り
『くちびるに歌を』の読書感想文について、詳しく解説してきました。
この記事では、五島列島という舞台設定の意味、主人公たちの心の成長、そして音楽と手紙が持つ力という3つの重要なポイントを中心に、小学生・中学生・高校生それぞれの例文を紹介しましたね。
感想文を書く際に大切なのは、物語の内容を説明するだけでなく、あなた自身がどう感じたか、どんなことを考えたかという「個人的な体験」を書くことです。
サトルやナズナの気持ちに共感した部分、音楽の力を感じた場面、15年後の自分への手紙について考えたことなど、あなたの心に残った部分を中心に書いてみてください。
コピペに頼らず、あなた自身の言葉で書いた感想文は、きっと読む人の心に響く素晴らしい作品になるはずです。
この記事を参考にしながら、ぜひ自分だけのオリジナルな感想文を書き上げてくださいね。
※小説『くちびるに歌を』のあらすじはこちらで簡単にご紹介しています。


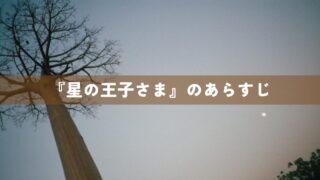



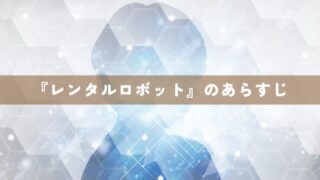
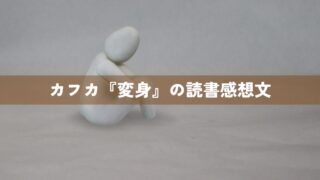

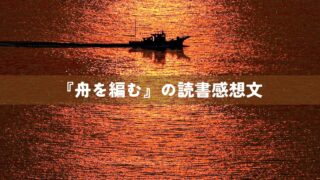



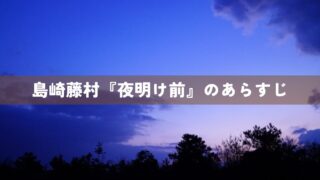


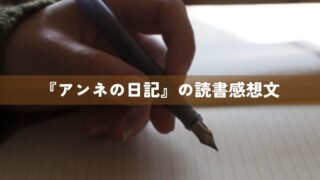



コメント