世界中で愛され続ける児童文学の名作『不思議の国のアリス』のあらすじを、簡単に短く、そして詳しくネタバレありでご紹介していきますね。
この作品はルイス・キャロルが1865年に発表した本で、少女アリスが白ウサギを追いかけて不思議な世界に迷い込む冒険物語です。
原作の魅力を余すところなくお伝えするため、年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう丁寧に解説していきますよ。
この記事は簡潔なあらすじから詳しいストーリー展開、登場人物の魅力、そして実際に読んだ私の率直な感想まで、『不思議の国のアリス』の全てが分かる内容になっています。
ルイス・キャロル原作『不思議の国のアリス』の本のあらすじを簡単に短く
ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』のあらすじを一言で表現すると?
ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』のあらすじを詳しく(ネタバレ)
『不思議の国のアリス』の本のあらすじを理解するための用語解説
『不思議の国のアリス』の原作本に登場する独特な用語や概念について、簡単に説明しておきますね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ウサギ穴 | アリスが落ちていく穴で 現実世界と不思議の国の境界となる象徴的な場所。 |
| コーカス・レース | 円を描いてぐるぐる回る無意味な競走。 英国の政治的な風刺を込めたレース。 |
| チェシャ猫の笑い | 猫は消えても笑いだけが残る現象。 物語の不可解さと不確かさを表すメタファー。 |
| マッドハッターのお茶会 | 帽子屋、三月ウサギ、ネムリネズミが開く 永遠に終わらないお茶会。 時間が止まった世界を象徴。 |
| クロッケー | 芝生の上で槌でボールを打ち 門を通して進めるイギリス発祥の球技。 |
| ナンセンス | 論理的でない言葉や行動のこと。 意味や常識を覆す奇妙な現象を指す。 |
| 夢落ち | 物語の出来事がすべて夢だったという結末。 |
これらの用語を知っておくと、物語の奇妙な展開がより深く理解できるはずです。
原作本『不思議の国のアリス』を読んだ感想
正直言って、この作品を読み終えた時の感想は「なんじゃこりゃ!」でした。
最初に手に取った時は「有名な児童文学だし、さくっと読めるだろう」なんて軽く考えていたんですが、いやいや、これがとんでもない代物でしたね。
まず驚いたのが、この作品の「意味不明さ」です。
普通の物語なら起承転結があって、主人公が何かを学んで成長するじゃないですか。
ところが『不思議の国のアリス』は違います。
アリスが不思議な世界に迷い込んで、訳の分からない連中と出会って、訳の分からない出来事に巻き込まれて、最後は夢でした、おしまい。
「え?それだけ?」って思いましたよ、最初は。
でも何度か読み返すうちに、この「意味不明さ」こそがこの作品の真骨頂なんだと気づいたんです。
特にマッドハッターのお茶会のシーンは圧巻でした。
「なぜカラスは書き物机に似ているのか?」なんて答えのない謎かけをふっかけてくる帽子屋。
時間が止まってしまったから永遠にお茶会を続けているって設定も、考えれば考えるほど不気味で面白い。
現実では絶対にありえない状況なのに、なぜか妙にリアルに感じられるんですよね。
チェシャ猫の「猫のない笑い」も忘れられません。
猫は消えたのに笑いだけが宙に浮いているなんて、普通に考えたら恐ろしい光景です。
でもアリスは意外と冷静に受け入れているんですよね。
子どもの柔軟性というか、大人になると失ってしまう想像力の豊かさを感じました。
それから、ハートの女王の「首をはねよ!」の連発も印象的でした。
最初は怖いと思ったんですが、よく読むと実際に首をはねられた人は一人もいないんですよね。
つまり女王の権力なんて見かけだけの張り子の虎。
これって現実の権力者への皮肉なのかな、なんて深読みしてしまいました。
言葉遊びの部分は正直言って理解しきれませんでした。
原文が英語だから、日本語の翻訳では伝わりにくい部分があるのは仕方ないですが、それでも独特のリズム感や音の面白さは感じられます。
「誰がタルトを盗んだ?」の裁判シーンは、大人になってから読むとまた違った味わいがありますね。
証拠もないのに有罪にしようとする不条理な裁判制度への批判が込められているように感じました。
アリスが最後に「あんたたちなんか、ただのトランプのくせに!」と叫ぶシーンは痛快でした。
理不尽な大人の世界に対する子どもからの反撃って感じがして、胸がすっとしましたね。
ただ、全てが夢オチで終わるのはちょっと拍子抜けだったかな……。
「夢でした」って結末は今の時代だとベタすぎる気もしますが、1865年の作品だと考えると斬新だったのかもしれません。
読み終えて思うのは、この作品は子ども向けの顔をした大人向けの本だということです。
表面的には楽しい冒険物語ですが、裏には大人社会への風刺や哲学的な問いかけが隠されている。
だから年齢によって全く違う読み方ができるんでしょうね。
私は40代になってから読みましたが、10代の時に読んでいたらまた違った感想を持ったと思います。
最後に言えるのは、この作品は「理解しよう」とするより「感じる」ものだということです。
論理的に考えようとすると頭が痛くなりますが、子ども心に戻って読むと不思議と楽しめる。
そんな魔法のような本でした。
※『不思議の国のアリス』の読書感想文の書き方と例文(小学生と中学生向け)はこちらです。

小説『不思議の国のアリス』(本)の作品情報
『不思議の国のアリス』の基本情報を整理しておきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | チャールズ・ラトウィッジ・ドドソン (筆名:ルイス・キャロル) |
| 出版年 | 1865年 |
| 出版社 | マクミラン社(初版) |
| 受賞歴 | 特定の文学賞受賞はないが、世界的な古典として評価 |
| ジャンル | 児童文学・ファンタジー・ナンセンス文学 |
| 主な舞台 | 不思議の国(ワンダーランド) |
| 時代背景 | ヴィクトリア朝時代のイギリス |
| 主なテーマ | 夢と現実、成長、大人社会への風刺 |
| 物語の特徴 | 言葉遊び、ナンセンス、パロディが豊富 |
| 対象年齢 | 5歳以上(大人も楽しめる) |
| 青空文庫の収録 | 著作権切れのため収録あり |
『不思議の国のアリス』の主要な登場人物とその簡単な説明
原作『不思議の国のアリス』の本に登場する魅力的なキャラクターたちを重要度順にご紹介します。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| アリス | 主人公の好奇心旺盛な少女。 不思議の国で様々な冒険を体験する。 |
| 白ウサギ | チョッキを着て懐中時計を持つウサギ。 アリスを不思議の国へ導く重要な存在。 |
| チェシャ猫 | ニヤリと笑いながら現れたり消えたりする不思議な猫。 「猫のない笑い」を残すことで有名。 |
| ハートの女王 | 短気で権力的な女王。 「首をはねよ!」が口癖だが実際は張り子の虎。 |
| マッドハッター | 狂ったお茶会を開く帽子屋。 時間が止まってしまったと言っている。 |
| 三月ウサギ | マッドハッターと共にお茶会に参加する騒がしいウサギ。 3月だから狂っているという設定。 |
| イモムシ | キノコの上で水たばこを吸っている毛虫。 アリスにサイズを変えるキノコの秘密を教える。 |
| 公爵夫人 | 赤ん坊を抱いた気難しい夫人。 何でも教訓に結びつけたがる性格。 |
| ネムリネズミ | お茶会でいつも居眠りしている小さなネズミ。 時々面白い話をする。 |
| ハートの王 | 女王の夫だが影が薄い存在。 裁判では判事役を務める。 |
どのキャラクターも個性的で、物語に独特の色彩を添えています。
『不思議の国のアリス』の読了時間の目安
原作本『不思議の国のアリス』を読み終えるのにどれくらい時間がかかるか、目安をまとめました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ページ数 | 約192ページ(新潮文庫版) |
| 推定文字数 | 約115,200文字 |
| 読了時間 | 約3時間50分 |
| 1日の読書時間 | 1時間なら4日、30分なら8日 |
比較的薄い本なので、集中すれば1日で読み切ることも可能です。
ただし言葉遊びやナンセンスな表現が多いため、じっくり味わいながら読むことをおすすめしますよ。
『不思議の国のアリス』はどんな人向けの小説か?
『不思議の国のアリス』の本は以下のような方に特におすすめできます。
- 想像力豊かで不思議な世界観を楽しめる人
- 言葉遊びやナンセンスなユーモアが好きな人
- 古典文学に興味があり、文学史上の名作を読みたい人
一方で、論理的で筋道立った物語を好む方や、現実的な話を求める方には少し合わないかもしれません。
この作品の魅力は「意味不明さ」にあるので、それを受け入れられるかどうかが楽しめるかの分かれ目ですね。
子どもから大人まで幅広い年齢層が読めますが、年齢によって全く違った楽しみ方ができるのも特徴です。
あの本が好きなら『不思議の国のアリス』も好きかも?似ている小説3選
『不思議の国のアリス』の世界観が気に入った方におすすめの作品をご紹介しますね。
『星の王子さま』サン=テグジュペリ
大人になって失った純粋な心や想像力をテーマにした名作です。
主人公が不思議な星々を旅する設定や、一見子ども向けだが大人が読むと深い哲学的メッセージが込められている点が『不思議の国のアリス』と似ています。
どちらも表面的には簡単だが、実は深い意味が隠された作品ですね。

『ナルニア国ものがたり』C.S.ルイス
子どもたちが異世界に迷い込んで冒険する王道ファンタジーです。
衣装だんすの奥からナルニア国に入るという設定は、ウサギ穴から不思議の国に入るアリスの物語と共通点があります。
現実世界とファンタジー世界の境界を越える体験や、子どもが主人公として活躍する点も似ていますよ。
『モモ』ミヒャエル・エンデ
時間泥棒と少女モモの戦いを描いたドイツの児童文学です。
時間という抽象的な概念を扱った点や、大人社会の問題を子どもの視点で描いている点が『不思議の国のアリス』と重なります。
どちらも一見不可解だが、よく読むと現代社会への鋭い批評が込められている作品です。
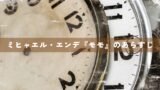
振り返り
『不思議の国のアリス』は単なる児童文学の枠を超えた、時代を越えて愛される名作でした。
簡単に読めそうに見えて実は奥が深く、ナンセンスな世界の中に現実社会への鋭い洞察が隠されている点が魅力的でしたね。
アリスの冒険を通じて、私たち読者も日常の常識から解放される体験ができます。
読書感想文を書く際は、表面的なストーリーだけでなく、作品に込められた深いメッセージにも注目してみてください。
※『不思議の国のアリス』で作者が伝えたいことや面白い点はこちらにまとめています。



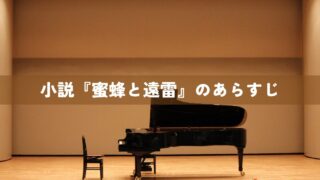


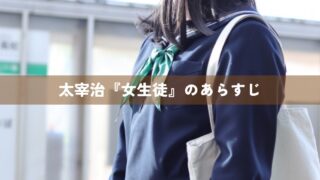
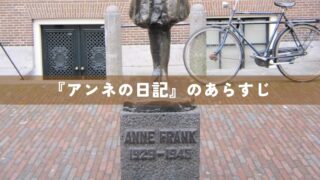






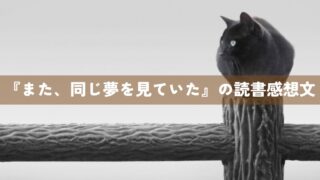






コメント