『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文を書こうと思っている皆さん、こんにちは。
朝井リョウさんの『桐島、部活やめるってよ』は2010年に発表された青春小説で、2012年には映画化もされた話題作です。
この物語は、男子バレーボール部のキャプテンだった桐島が部活をやめることから始まる群像劇。
桐島本人は一度も登場しないのに、彼の決断が学校の生徒たちに大きな波紋を広げていく構成が印象的ですね。
中学生や高校生の皆さんが読書感想文を書く際の例文も用意しましたので、題名の付け方から具体的な書き方まで、コピペに頼らずオリジナルの感想文が書けるようサポートしていきますよ。
読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私にお任せください。
『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文で触れたい3つの要点
『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要な要点があります。
これらのポイントを押さえることで、深みのある感想文を書くことができるでしょう。
- 桐島の不在が生み出す影響と群像劇の構造
- スクールカーストや高校内の社会構造の描写
- 自己のアイデンティティと他者との関係性の葛藤
これらの要点について読みながら「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切です。
感想文を書く際は、小説の内容紹介だけでなく、あなた自身の気持ちや体験と結びつけて書くことが重要なんですよ。
メモを取る時は、「この場面で自分だったらどう思うか」「自分の学校生活と似ている部分はあるか」「登場人物の気持ちが理解できるか」といった視点で書き留めてみてください。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は単なるあらすじ紹介ではなく、あなた自身の心の動きや成長を表現するものだからです。
桐島の不在が生み出す影響と群像劇の構造
『桐島、部活やめるってよ』の最大の特徴は、タイトルロールである桐島が一度も直接登場しないことです。
物語は5人の高校生の視点から語られる群像劇の形式で構成されており、それぞれが桐島の部活やめるという出来事にどう影響されるかが描かれています。
野球部の菊池宏樹、男子バレーボール部の小泉風助、ブラスバンド部の沢島亜矢、映画部の前田涼也、ソフトボール部の宮部実果。
彼らはそれぞれ異なる立場にいながら、桐島という存在の大きさを感じているのです。
この構造の巧妙さは、桐島を直接描かないことで、読者が想像する余地を残している点にあります。
各登場人物の目線から見た桐島像は少しずつ違っており、それが桐島という人物の多面性を表現しているのですね。
読書感想文では、この群像劇という手法があなたにどんな印象を与えたか、また自分の学校生活でも似たような「中心人物」がいるかどうかを考えてみるといいでしょう。
スクールカーストや高校内の社会構造の描写
『桐島、部活やめるってよ』では、学校内の見えない階層構造、いわゆるスクールカーストが丁寧に描かれています。
桐島を中心とした人気者グループ、運動部の生徒たち、文化部の生徒たち、それぞれが異なる立ち位置にいて、同じ出来事でも受け取り方が全く違うのです。
例えば、バレー部のリベロである小泉風助は、桐島がやめることで自分が試合に出られるようになることに複雑な感情を抱きます。
一方、映画部の前田涼也にとって桐島の存在は遠い世界の話であり、直接的な影響は少ないように見えます。
しかし、実際には学校全体の空気が変わることで、彼らの日常にも微細な変化が生まれているのです。
この描写の巧みさは、読者自身の学校生活を振り返らせる効果があります。
あなたも自分の学校でのポジションや、周りの人たちとの関係性について考えたことがあるでしょう。
読書感想文では、登場人物たちの立場と自分の体験を重ね合わせて、どんな共感や発見があったかを書いてみてください。
自己のアイデンティティと他者との関係性の葛藤
物語の根底にあるのは、高校生特有の「自分らしさとは何か」「他者の期待にどう応えるか」という葛藤です。
桐島は周囲から「いいやつ」と評価される一方で、その期待に応え続けることに疲れを感じ、最終的に部活をやめるという選択をします。
他の登場人物たちも、それぞれが自分の役割と本当の気持ちの間で揺れ動いています。
宮部実果は義姉として振る舞うことを求められる複雑な家庭環境に置かれており、前田涼也は映画への情熱と周囲からの期待の狭間で悩んでいます。
このようなアイデンティティの模索は、まさに思春期の普遍的なテーマといえるでしょう。
読者である皆さんも、家族や友人、先生からの期待と自分の本当の気持ちが一致しない経験をしたことがあるはずです。
また、周りの人に合わせすぎて疲れてしまったり、逆に自分らしさを貫こうとして孤立感を味わったりしたこともあるでしょう。
読書感想文では、登場人物たちの葛藤に共感した部分や、自分だったらどうするかという視点で書くことで、深みのある内容になります。
さらに、この物語を読んで自分の人間関係や将来について新たに考えたことがあれば、それも大切な感想として盛り込んでみてください。
※『桐島、部活やめるってよ』で作者が伝えたいことはこちらで考察しています。

『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】見えない「桐島」という存在
『桐島、部活やめるってよ』には、タイトルにある桐島は一度も出てこない。
でも、桐島が部活をやめたせいで、学校にいる友人たちの気持ちが大きく変わっていく。
桐島がいないのに桐島の存在がものすごく大きくて、読んでいてとても不思議な感じがした。
物語は五人の高校生の目線で書かれているが、それぞれが桐島のことを違う風に見ているのが面白かった。
バレー部の小泉風助は、桐島がやめて自分が試合に出られるようになって嬉しいが、そんな自分が嫌になってしまう。
映画部の前田涼也にとって桐島は遠い存在だけど、学校の雰囲気が変わることで間接的に影響を受けている。
野球部の菊池宏樹は桐島の友達だから直接的にショックを受けているし、ブラスバンド部の沢島亜矢も桐島に憧れを持っていた。
ソフトボール部の宮部実果は桐島の彼女の友達で、この出来事が自分たちのグループにも影響すると感じている。
同じ「桐島が部活をやめる」という出来事なのに、立場によってこんなに受け取り方が違うのかと驚いた。
私の学校にも、桐島みたいに人気があって中心的な存在の人がいる。
その人がもし突然何かをやめたり、学校を転校したりしたら、きっと同じようなことが起こるだろう。
人気者のグループ、運動部の人たち、文化部の人たち、それぞれが違う反応をするに違いない。
私は文化部だから、前田涼也の気持ちがよく分かった。
運動部の人気者の世界は確かに遠く感じるし、直接関係ないと思いがちだ。
でも実際は、学校全体の空気が変わると、自分たちにも何かしら影響があるものだと思う。
一番考えさせられたのは、みんな内心では悩みを抱えていることだった。
人気者だった桐島も、周りからの期待に応えるのに疲れて部活をやめてしまった。
他の登場人物たちも、家族のことや友達のこと、将来のことで悩んでいる。
人気者でも普通の生徒でも、何かしら困ったり迷ったりしながら毎日を過ごしているのだと分かった。
私も最近、友達との関係で悩むことがある。
みんなに合わせようとしすぎて疲れることもあるし、自分の意見を言えないでもやもやすることもある。
桐島みたいに「やめる」と言える勇気があればいいのにと思うこともあるが、実際にはなかなか難しい。
でも、この小説を読んで、悩んでいるのは自分だけではないと分かって少し安心した。
また、五人の高校生それぞれの視点で物語が進んでいくのも面白かった。
一つの出来事をいろいろな角度から見ることで、物事には様々な側面があることが分かる。
普段、自分の視点でしか物事を見ていないけれど、相手の立場に立って考えることの大切さを教えてもらった気がする。
この小説では特別な事件が起こるわけではないけれど、高校生の心の動きがとてもリアルに描かれていた。
桐島という存在を通して、友情や恋愛、部活動、家族関係など、高校生活の様々な面が浮き彫りになっている。
読み終わった後、自分の学校生活や人間関係について改めて考えるきっかけになった。
これから高校生になる私にとって、とても参考になる小説だったと思う。
『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】見えない存在が教えてくれたもの
朝井リョウさんの『桐島、部活やめるってよ』を読み終え、私はこの物語について深く考え続けた。タイトルにある桐島は登場しないが、彼の存在が物語全体を支配し、強い印象を受けた。男子バレー部キャプテンの桐島が突然部活をやめることから始まる群像劇で、五人の高校生の視点から彼の決断がどう影響するかが描かれている。読み進めるうち、自分の高校生活と重ね合わせずにはいられなかった。
最も印象深かったのは、桐島の不在が物語に与える効果だ。彼が直接登場しないからこそ、読者が想像力を働かせ、各登場人物の視点を通して彼の多面的な人物像を構築することになる。この巧妙な手法は、読者が能動的に物語に参加している感覚を味わわせた。例えば、彼の部活仲間や友人、あるいは彼に憧れる生徒など、それぞれの目に映る桐島像が重なり合うことで、その存在の大きさと影響力を改めて実感した。
次に強く感じたのは、学校内のヒエラルキーだ。明確に「スクールカースト」の言葉はないが、登場人物たちの関係性から、目に見えない階層構造が浮き彫りになる。人気者グループ、運動部、文化部など、それぞれ異なる立場で、桐島が部活をやめるという同じ出来事でも全く違う受け取り方をしているのが印象的だった。私は地味な文化部にいるが、学校全体の空気が人気者の動向に左右されることを日々感じている。彼らの言動一つで、教室の雰囲気が変わるのを肌で感じるほどだ。
三つ目に深く考えさせられたのは、アイデンティティの問題だ。桐島は周囲の期待に応え続けることに疲れ、部活をやめる決断をした。これは現代の高校生が抱える典型的な悩みだろう。友達や先生、家族からの「こうあるべき」という期待と、本当の自分がやりたいことや感じていることの間にギャップがある時、どう選択すべきか。その葛藤は、多くの人が経験することだろう。他の登場人物たちも、家族や友人関係、将来のことで悩みを抱え、人気者でも普通でも皆、心の中で何かしらの迷いを抱えながら日々を過ごしている。
群像劇の力についても考えさせられた。複数の視点から描くことで、立体的で複雑な人間関係が浮かび上がる。現実では自分の視点からしか物事を見られないが、この小説で他者の視点に立つ練習ができた。読み終え、私は周囲の人々を以前とは違う目で見るようになった。皆それぞれ悩みや葛藤を抱えながら過ごしていることを、この小説が教えてくれた。
『桐島、部活やめるってよ』は、高校生活の表面的な出来事を通して、人間関係の本質を描いた作品だ。桐島を媒介に登場人物の内面が丁寧に掘り下げられている。特別な事件や劇的な展開はないが、日常の些細な変化を通して、高校生の心の動きがリアルに表現されていた。この小説を読んで、私は自分の高校生活を深く見つめ直すきっかけを得た。友人関係、部活動、将来への不安など、様々な問題について考える機会となり、これからの高校生活で得た気づきを大切にしたい。
振り返り
今回は『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この作品は桐島の不在という独特な構造、スクールカーストの描写、アイデンティティの葛藤という三つの要素を軸に読書感想文を組み立てることができます。
中学生向けと高校生向けの例文では、それぞれの年齢に応じた語彙や表現を用いながら、自分の体験と重ね合わせて書くことの重要性を示しました。
読書感想文で大切なのは、単なるあらすじの紹介ではなく、あなた自身がどう感じ、何を考えたかを素直に表現することです。
コピペに頼らず、自分の言葉で書いた感想文こそが、読み手の心に響く文章になります。
この記事を参考にして、ぜひあなたらしい感想文を書いてくださいね。
きっと素晴らしい作品が完成するはずです。
※『桐島、部活やめるってよ』の読書感想文を書く際に参考になる記事がコチラ。

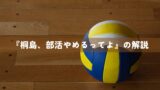
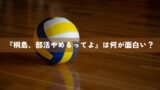





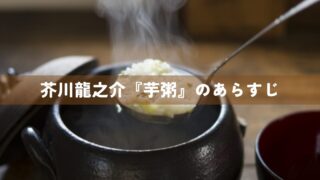



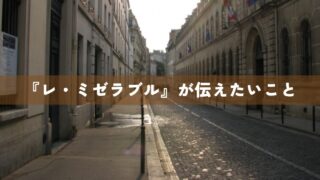


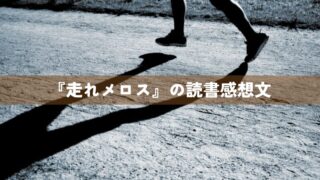
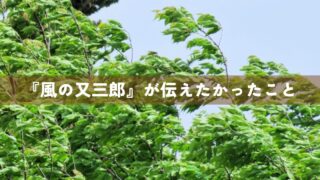



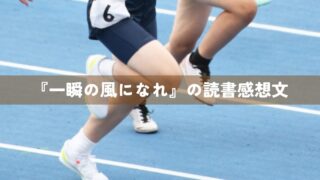
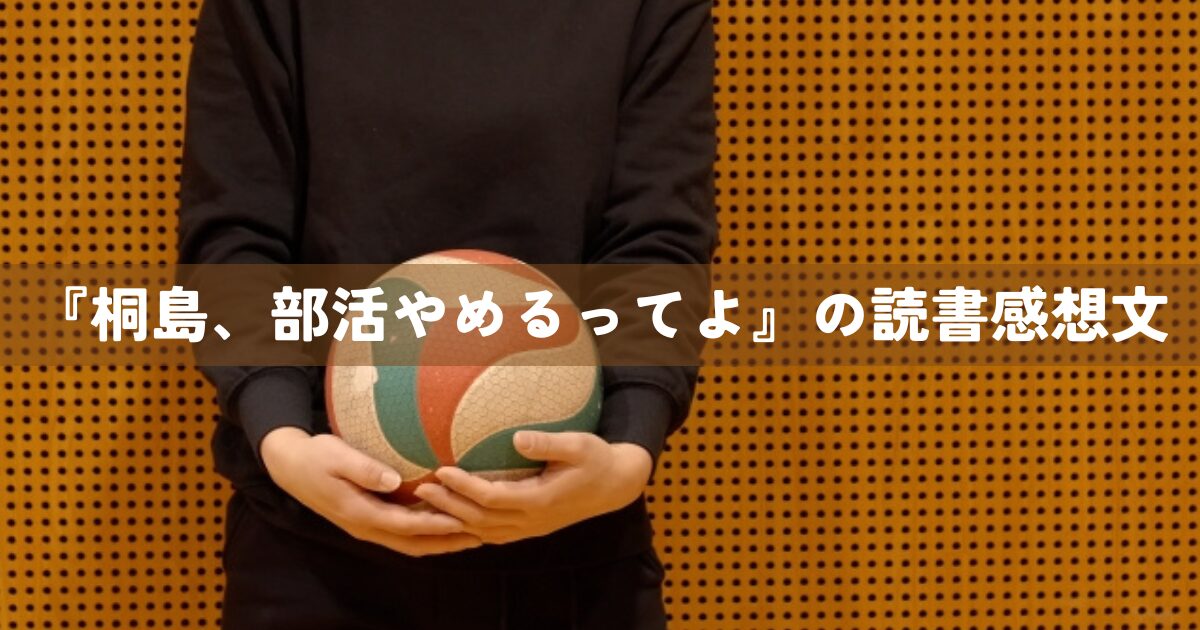
コメント