『推し、燃ゆ』の読書感想文を書く予定の皆さんに向けて、書き方のコツをお伝えしていきます。
『推し、燃ゆ』は宇佐見りんさんが21歳で芥川龍之介賞を受賞した話題作。
アイドルを”推す”女子高生あかりが主人公で、推しが炎上事件を起こしたことから物語が動き出します。
現代のSNS文化や推し活をリアルに描いた作品として大きな注目を集めました。
私は年間100冊以上の本を読む読書好きで、特に現代小説の分析を得意としています。
この記事では『推し、燃ゆ』の読書感想文の書き方から題名の付け方、中学生・高校生向けの例文まで詳しく解説していきます。
コピペではなく、あなた自身の言葉で書ける感想文作りをサポートしますよ。
『推し、燃ゆ』の読書感想文で触れたい3つの要点
『推し、燃ゆ』の読書感想文を書く際に押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
これらの要点について「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切ですよ。
メモの取り方としては、該当する場面を読みながら「共感した」「驚いた」「考えさせられた」といった感情を素直に書き留めてください。
なぜこのメモが重要かというと、読書感想文は「あなた自身がどう思ったか」を書くものだからです。
まずは3つの要点を箇条書きで確認しましょう。
- 「推し」という存在が主人公のアイデンティティに与える影響
- 現代社会におけるSNSの功罪とコミュニケーションの変化
- 「普通」であることへの葛藤と自己受容のテーマ
これらの要点を軸にして、あなたなりの視点を加えていけば説得力のある感想文が完成します。
それでは各要点について詳しく見ていきましょう。
「推し」という存在が主人公のアイデンティティに与える影響
主人公あかりにとって、アイドル上野真幸は単なる好きな芸能人ではありません。
彼女の生きる意味そのものになっているのです。
学校でも家庭でもうまくいかないあかりが、推し活だけは一生懸命に取り組める理由がここにあります。
推しが炎上したとき、あかりの世界が崩れそうになる描写は特にリアルですね。
現代の若者にとって「推し」がどれほど重要な存在なのか、この作品を通じて深く考えることができます。
あなたも好きなアーティストやキャラクターがいるなら、その存在が自分にとってどんな意味を持つのか振り返ってみてください。
依存と応援の境界線はどこにあるのか、健全な「推し活」とは何なのか、といった現代的な問題についても触れられそうです。
現代社会におけるSNSの功罪とコミュニケーションの変化
『推し、燃ゆ』はSNS時代特有の現象を巧みに描いています。
推しの情報収集、ファン同士の交流、そして炎上の拡散まで、すべてがSNSを通じて行われます。
匿名性ゆえの誹謗中傷や、情報の真偽が曖昧なまま拡散される怖さも描かれていますね。
一方で、SNSは同じ推しを応援する仲間と繋がれる貴重なツールでもあります。
この二面性こそが現代のコミュニケーションの特徴といえるでしょう。
あなた自身のSNS体験と照らし合わせて考えてみることをおすすめします。
良い面と悪い面の両方を経験したことがあるはずですよ。
リアルな人間関係が希薄になりがちな現代において、SNSがもたらす影響について深く考察できそうです。
「普通」であることへの葛藤と自己受容のテーマ
あかりは学校生活やアルバイトで「普通」に馴染めない自分に悩んでいます。
この「普通」って一体何なのでしょうか。
社会が求める理想像に合わせることが本当に幸せなのか、作品を通じて問いかけられます。
あかりが推し活に没頭するのは、現実逃避の側面もありますが、同時に自分らしくいられる唯一の場所でもあるのです。
物語が進むにつれて、あかりが少しずつ自分自身と向き合おうとする姿が描かれています。
完璧でなくても、周りと違っていても、自分は自分として価値があるのだという気づきが重要なポイントですね。
中学生や高校生の皆さんも、きっと同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。
自己受容の難しさと大切さについて、あなたなりの体験を交えて書けるとよいでしょう。
※『推し、燃ゆ』で作者が伝えたいことはこちらで考察しています。

『推し、燃ゆ』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】推しと共に生きること
『推し、燃ゆ』を読んで、私は主人公あかりの気持ちにとても共感した。
あかりは学校でも家でもうまくいかず、自分の居場所を見つけられずにいる。
そんな彼女にとって、アイドルの上野真幸を応援することだけが生きがいになっている。
私にも好きなアイドルグループがいるので、あかりの気持ちがよく分かった。
推しのことを考えているときだけは、嫌なことを忘れて幸せな気分になれるのだ。
あかりが推し活に全力で取り組む姿を見て、何かに夢中になることの素晴らしさを改めて感じた。
しかし、推しが炎上事件を起こしたとき、あかりの世界は一変してしまう。
彼女の動揺ぶりを読んでいて、私も胸が苦しくなった。
もし自分の推しが同じような状況になったら、きっと私も同じようにショックを受けるだろう。
推しという存在が、あかりのアイデンティティそのものになっていることがよく分かった。
これは現代の若者にとって、とても身近な問題だと思う。
この作品で特に印象的だったのは、SNSの描写だった。
推しの情報を得るのも、ファン同士で交流するのも、すべてSNSを通じて行われる。
でも同時に、心ない言葉や間違った情報もあっという間に広がってしまう。
私たちが普段何気なく使っているSNSが、人を簡単に傷つける道具にもなり得ることを思い知らされた。
匿名だからといって何を書いてもいいわけではないし、相手も同じ人間なのだということを忘れてはいけない。
SNSの便利さと怖さの両面を描いた宇佐見りんさんの視点は、とても鋭いと思った。
私も普段からSNSを使うときは、もっと慎重になろうと反省した。
あかりは学校でも家庭でも「普通」に馴染めない自分に悩んでいる。
クラスメイトとうまく話せなかったり、アルバイトが続かなかったりする彼女の姿に、私は自分を重ねて見ていた。
みんなと同じでなければいけない、普通でなければいけないという思い込みに苦しんでいるのだ。
でも「普通」って一体何なのだろうか。
この作品を読んで、周りと違っていても、不器用でも、それが自分らしさなのだと思えるようになった。
あかりが少しずつ自分自身を受け入れようとする姿は、とても勇気を与えてくれる。
完璧な人間なんてどこにもいないし、みんなそれぞれ違った個性を持っている。
その違いこそが、その人の魅力なのではないだろうか。
『推し、燃ゆ』は、現代を生きる私たちが抱える様々な問題を鋭く描いた作品だった。
推し活の楽しさと苦しさ、SNSの光と影、自分らしさを見つけることの難しさ。
どれも私たち中学生にとって身近で切実な問題ばかりだ。
この作品を読んで、自分の推しへの気持ちや、SNSとの付き合い方、そして自分自身について深く考えることができた。
あかりのように悩みながらも、自分らしく生きていく勇気をもらった気がする。
推しがいることの幸せを大切にしながら、現実からも逃げずに向き合っていきたいと思う。
『推し、燃ゆ』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】現代を生きる私たちへのメッセージ
『推し、燃ゆ』を読み終えたとき、私は言葉にできない複雑な感情に包まれていた。
21歳で芥川賞を受賞した宇佐見りんさんが描く現代社会の断面は、あまりにもリアルで生々しく、読んでいて息苦しくなるほどだった。
主人公あかりの生き方は、現代を生きる私たち若者の姿を鏡に映したようで、目を逸らすことができなかった。
この作品が提示する問題は、決して他人事ではない。
私たちの日常に深く根ざした現実なのだ。
まず私が強く印象を受けたのは、「推し」という存在があかりのアイデンティティに与える絶大な影響力についてだった。
あかりにとって、アイドル上野真幸を応援することは単なる趣味ではない。
それは彼女の存在理由そのものであり、生きる意味なのだ。
学校でも家庭でもうまくいかない彼女が、推し活だけは全力で取り組める理由がここにある。
推しが炎上したとき、あかりの精神状態が激しく動揺する描写は、読んでいて胸が締め付けられるようだった。
彼女の世界が崩れ落ちていく様子は、まるで自分のことのように感じられた。
私にも好きなアーティストがいるが、もしその人が同じような状況になったら、きっと私もあかりと同じような反応をするだろう。
現代の若者にとって「推し」がどれほど重要な存在なのか、この作品を通じて改めて実感した。
しかし同時に、推しに依存することの危険性についても考えさせられた。
応援と依存の境界線はどこにあるのか。
健全な「推し活」とは何なのか。
自分自身の体験を振り返りながら、これらの問題について深く考える機会を得た。
次に、この作品が描くSNS社会の光と影についても言及したい。
『推し、燃ゆ』は現代のコミュニケーションの変化を見事に捉えている。
推しの情報収集、ファン同士の交流、そして炎上の拡散まで、すべてがSNSを通じて行われる。
匿名性ゆえの誹謗中傷や、真偽不明の情報があっという間に広がる怖さは、私たちが日常的に目にしている現象だ。
特に印象的だったのは、推しが炎上したときのSNS上の反応だった。
事実確認もせずに感情的な言葉が飛び交い、当事者を追い詰めていく様子は、まさに現代社会の病理を表している。
私も普段からSNSを利用しているが、この作品を読んで自分の発言に対してより慎重になろうと思った。
画面の向こうにいるのも同じ人間であり、軽はずみな言葉が誰かを深く傷つける可能性があることを忘れてはいけない。
一方で、SNSが同じ推しを応援する仲間と繋がれる貴重なツールであることも事実だ。
物理的に離れていても共通の話題で盛り上がったり、お互いを励まし合ったりできる。
この二面性こそが現代のコミュニケーションの特徴といえるだろう。
リアルな人間関係が希薄になりがちな現代において、SNSがもたらす影響について私たちはもっと真剣に考える必要がある。
そして、この作品で最も深く考えさせられたのは、「普通」であることへの葛藤と自己受容のテーマだった。
あかりは学校生活やアルバイトで「普通」に馴染めない自分に常に悩んでいる。
クラスメイトとうまく話せない、アルバイトが続かない、家族ともぎくしゃくしている。
そんな自分を恥じて、推し活にのめり込むことで現実逃避を図ろうとする。
この「普通」への呪縛は、私たち高校生にとっても非常に身近な問題だ。
みんなと同じでなければいけない、周りから浮いてはいけないという強迫観念に苛まれることは珍しくない。
しかし、この作品を読んで気づいたのは、「普通」という基準自体が曖昧で不確実なものだということだ。
誰が決めた「普通」なのか、なぜそれに合わせなければいけないのか。
あかりが物語を通じて少しずつ自分自身と向き合おうとする姿は、私に大きな勇気を与えてくれた。
完璧でなくても、周りと違っていても、自分は自分として価値がある。
この当たり前のことを受け入れることが、どれほど難しく、そして重要なことなのかを教えられた。
私自身も、他人と比較して落ち込んだり、自分の個性を否定したりすることがある。
でもあかりの姿を見て、そんな自分も含めて受け入れていこうと思えるようになった。
『推し、燃ゆ』は、現代を生きる私たちが直面している様々な問題を鋭く抉り出した作品だった。
推し活の意味と限界、SNS社会の功罪、自己受容の困難さ。
どれも私たち若者にとって切実で避けて通れない問題ばかりだ。
宇佐見りんさんは21歳という若さで、同世代の心の内を見事に言語化してくれた。
この作品を読むことで、自分自身や周りの世界について深く考える機会を得ることができた。
あかりのように悩み苦しみながらも、自分らしく生きていく道を探していきたいと思う。
推しがいることの幸せを大切にしながら、現実からも逃げずに向き合っていく。
そんな生き方を模索していこうと、この作品は私に教えてくれた。
振り返り
ここまで『推し、燃ゆ』の読書感想文の書き方について詳しく解説してきました。
3つの要点を軸にして、あなた自身の体験や感情を織り交ぜることで、オリジナリティのある感想文が完成するはずです。
中学生向けと高校生向けの例文も参考にしながら、自分の学年に合った語彙や表現を選んでくださいね。
大切なのは、コピペではなくあなた自身の言葉で書くことです。
この作品を読んで何を感じたのか、どんなことを考えたのか、素直な気持ちを文章にしてみてください。
きっと先生にも伝わる、心のこもった読書感想文が書けるはずですよ。
※『推し、燃ゆ』のあらすじはこちらでご紹介しています。


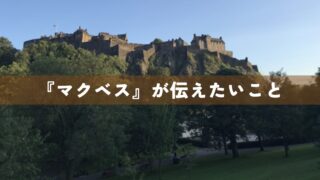


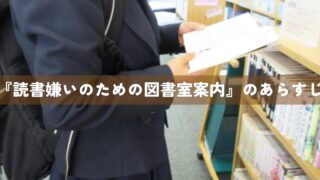
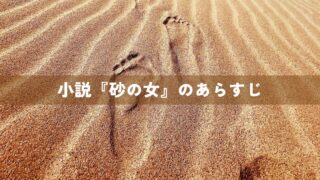

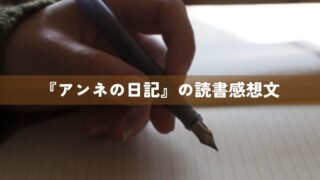
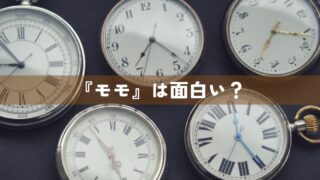

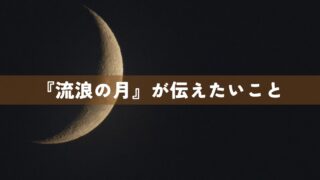
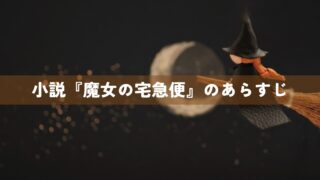
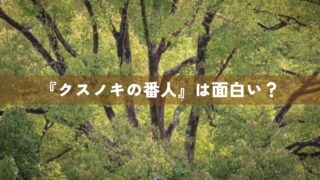



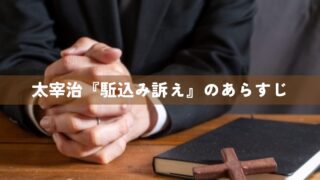

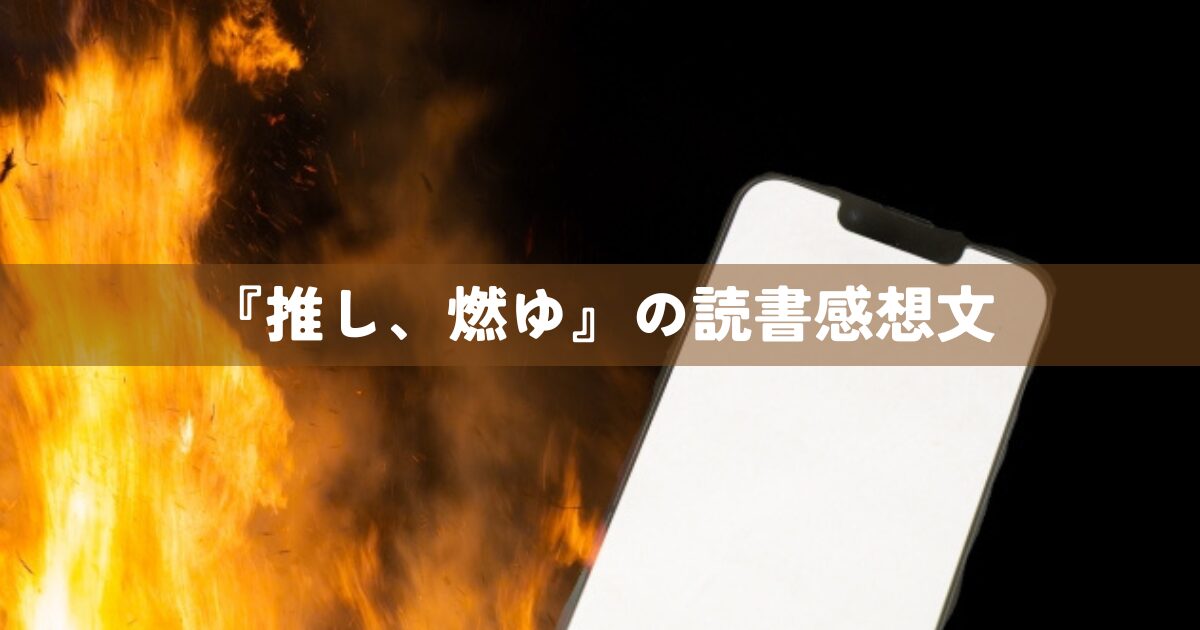
コメント