『スラムに水は流れない』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
2025年度第71回青少年読書感想文全国コンクールの中学生の部課題図書に選ばれた、ヴァルシャ・バジャージさんの『スラムに水は流れない』について、読書感想文の書き方を詳しく解説していきますよ。
この作品は、インド・ムンバイのスラムで暮らす12歳の少女ミンニの物語。
水不足に苦しむスラムで、家族の絆や友情を大切にしながら、希望を失わずに生きる子どもたちの姿が描かれています。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読みますが、この作品は読みごたえがあって心にズシーンとくる一冊でしたね。
今回の記事では、読書感想文を書く中学生の皆さんに向けて、この作品の重要なポイントや感想文の書き方、そして実際の例文まで、丁寧にお伝えしていきます。
『スラムに水は流れない』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『スラムに水は流れない』の読書感想文を書く際に、必ず押さえておきたい重要なポイントが3つあります。
これらのポイントを理解しておくことで、深みのある素晴らしい読書感想文が書けるはずです。
- 水不足が象徴する生きる厳しさと日常の尊さ
- 主人公ミンニの強さと希望に満ちた生き方
- 社会格差と構造的な問題への気づき
これらの3つのポイントを軸に、感想文を組み立てていくことをおすすめします。
それでは、各ポイントについて詳しく解説していきますね。
水不足が象徴する生きる厳しさと日常の尊さ
『スラムに水は流れない』で最も重要なテーマの一つが、「水不足」という現実が登場人物たちの生活に与える深刻な影響です。
主人公のミンニたちが暮らすムンバイのスラムには、人口の40%が住んでいるにも関わらず、水は全体のわずか5%しか供給されていません。
この事実だけでも、どれほど不公平な状況かがわかりますよね。
物語の中で、ミンニたちは毎朝早くから共同栓に並んで水を手に入れなければなりません。
運べる水の量は限られており、飲み水は煮沸消毒が必要です。
これらの描写から、私たちが当たり前だと思っている「蛇口をひねれば水が出る」という日常が、実はとても貴重で恵まれたことなのだと気づかされます。
読書感想文では、この水不足という現実を通して、自分の日常生活を見つめ直した感想を書くことが重要です。
「水がある当たり前」の有難さや、水不足や貧困問題がどれほど深刻かを、自分の生活と比較しながら考えてみてください。
また、水くみのために勉強や遊ぶ時間が削られてしまうスラムの子どもたちの現実についても触れると良いでしょう。
主人公ミンニの強さと希望に満ちた生き方
過酷な環境の中でも、主人公のミンニは決して希望を失いません。
詩が好きで、慈善団体運営の私立学校に通い、「どんな環境でも学びたい」という強い意志を持っています。
兄のサンジャイが水マフィアに関わる危険な事件に巻き込まれて家を離れることになったり、母が汚染された水が原因で重い病気にかかったりと、家族が引き裂かれる危機に直面します。
それでも、ミンニは学校に通いながら、家事や水くみ、母の務めていた家での労働も背負うことになります。
こうした困難な状況でも、ミンニは自分の夢や詩を書くことを諦めません。
読書感想文では、このミンニの強さや希望を失わない生き方について、自分が感じた感動や共感を具体的に書くことが大切です。
「どんな状況でも諦めない強さ」や「夢や希望を持ち続ける意義」について、自分自身の経験と重ねて考えてみてください。
また、家族や友人との絆がミンニの支えになっている場面についても注目すると良いでしょう。
社会格差と構造的な問題への気づき
『スラムに水は流れない』は、単なる貧困の物語ではありません。
スラムにおける「貧困」「水マフィア」「格差」「カースト制度」といった社会的な問題がリアルに描かれています。
富裕層の住む高層ビルの屋上にはプールがある一方で、スラムには基本的な飲み水すらない。
この残酷な対比は、社会の不公平さを象徴しています。
また、水マフィアの存在は、水問題が単なる自然現象ではなく、人為的な構造によって引き起こされていることを示しています。
読書感想文では、こうした社会問題や格差について、自分がどのような気づきを得たかを書くことが重要です。
ただし、単に「かわいそう」と同情するだけでは浅い感想文になってしまいます。
「自分にできること」や「この本を読んだあと世界の見え方がどう変わったか」をまとめると、感想文に深みが生まれます。
自分の学びや感じたことを、社会全体や未来への希望につなげる視点を持つことが、心に響く読書感想文のコツです。
より良い読書感想文を書くために『スラムに水は流れない』を読んだらメモしたい3項目~貧困と格差に対してあなたが感じたこと~
『スラムに水は流れない』を読んで、より良い読書感想文を書くためには、読書中に自分がどう感じたかをメモしておくことが非常に重要です。
感想文は、あなた自身の心の動きや気づきを文章にするものだからです。
以下の3つの項目について、読書中に感じたことをメモしておきましょう。
- 水不足の現実を知ったときの驚きや衝撃
- ミンニの強さや希望に対する感動や共感
- 社会格差の現実に対する怒りや疑問
これらの感情や思考をメモしておくことで、読書感想文を書く際に、より具体的で説得力のある内容にすることができます。
では、各項目について詳しく説明していきますね。
水不足の現実を知ったときの驚きや衝撃
『スラムに水は流れない』を読んで、まず多くの人が驚くのは、水不足の現実の深刻さです。
毎朝長い列に並んで水を手に入れること、運べる水の量が限られていること、不衛生な水による健康被害。
これらの描写を読んだとき、あなたはどのような気持ちになりましたか?
「信じられない」「こんなことが現実にあるなんて」といった驚きや衝撃を感じたかもしれません。
また、自分の日常生活と比較して、「私たちは何て恵まれているんだろう」と思ったかもしれません。
こうした最初の感情や気づきは、読書感想文の冒頭部分で非常に効果的に使えます。
読者の心をつかむ導入として、あなたが感じた驚きや衝撃を素直に表現してみてください。
ただし、感情だけでなく、なぜそう感じたのかという理由も併せて書くことが大切です。
ミンニの強さや希望に対する感動や共感
主人公のミンニの生き方に対して、あなたはどのような感情を抱きましたか?
困難な状況でも諦めない強さ、詩を書き続ける情熱、家族を思う気持ち。
これらのミンニの姿に、感動や共感を覚えた人が多いはずです。
「私だったらこんなに強くいられないかもしれない」「ミンニのような希望を持ち続けたい」といった思いを感じたかもしれません。
また、ミンニの年齢が12歳という自分たちと近い世代だからこそ、より深く共感できた部分もあるでしょう。
読書感想文では、このような感動や共感の気持ちを具体的に書くことが重要です。
ミンニのどの行動や言葉に心を動かされたのか、なぜそう感じたのかを明確にしてください。
そして、ミンニの生き方から学んだことや、自分の生活に活かしたいことがあれば、それも併せて書くと良いでしょう。
社会格差の現実に対する怒りや疑問
『スラムに水は流れない』を読んで、社会格差の現実に対してどのような感情を抱きましたか?
富裕層の住む高層ビルには豊富な水があるのに、スラムには基本的な飲み水すらない。
この不公平な現実に対して、怒りや疑問を感じた人が多いはずです。
「なぜこんなことが許されるのか」「何か改善する方法はないのか」といった疑問や、「不公平すぎる」「何とかしたい」といった怒りの感情。
これらの感情も、読書感想文において非常に重要な要素です。
ただし、感情だけでなく、その先の建設的な思考も大切です。
「では、私たちに何ができるのか」「この現実を知った今、どう行動すべきか」といった前向きな視点を持つことが重要です。
読書感想文では、社会問題に対する自分の考えや、今後の行動への決意を書くことで、深みのある内容にすることができます。
『スラムに水は流れない』の読書感想文の例文(1200字の中学生向けバージョン)
【題名】水が教えてくれた大切なこと
私は今まで、水道の蛇口をひねれば当たり前のように水が出ることを、特別なことだと思ったことがなかった。
しかし、『スラムに水は流れない』を読んで、この「当たり前」がどれほど貴重で恵まれたことなのかを初めて知った。
主人公のミンニが暮らすインド・ムンバイのスラムでは、人口の40%が住んでいるにも関わらず、水は全体のわずか5%しか供給されていない。
この数字を知ったとき、私は大きな衝撃を受けた。
なぜこんなに不公平なことが起こるのだろうか。
ミンニたちは毎朝早くから長い列に並んで、少しの水を手に入れなければならない。
運べる水の量は限られており、飲み水は煮沸消毒が必要だ。
水くみのために勉強や遊ぶ時間が削られてしまうことも珍しくない。
私が毎日何気なく使っている水が、ミンニたちにとっては命そのものなのだと感じた。
お風呂に入るときも、歯を磨くときも、料理をするときも、私は水を無駄にしていないだろうか。
この本を読んで、自分の生活を見つめ直すきっかけになった。
しかし、この物語で最も印象的だったのは、過酷な環境の中でも希望を失わないミンニの強さだった。
兄のサンジャイが水マフィアに関わる危険な事件に巻き込まれて家を離れることになったり、母が病気になったりと、家族が引き裂かれる危機に直面する。
それでも、ミンニは学校に通いながら、家事や水くみ、母の務めていた家での労働も背負うことになる。
私がミンニの立場だったら、こんなに強くいられるだろうか。
きっと絶望してしまうかもしれない。
でも、ミンニは詩を書き続け、夢を諦めない。
「どんな環境でも学びたい」という強い意志を持ち続ける。
この姿に、私は深い感動を覚えた。
また、『スラムに水は流れない』を読んで、社会格差の現実についても考えさせられた。
富裕層の住む高層ビルの屋上にはプールがあるのに、スラムには基本的な飲み水すらない。
この残酷な対比は、社会の不公平さを象徴している。
水マフィアの存在も、水問題が単なる自然現象ではなく、人為的な構造によって引き起こされていることを示している。
なぜこんなことが許されるのか、最初は怒りを感じた。
でも、ただ怒るだけでは何も変わらない。
この現実を知った今、私に何ができるのかを考える必要がある。
まずは、水を大切に使うことから始めたい。
そして、世界の水問題について学び、できる範囲で支援活動に参加することも考えている。
『スラムに水は流れない』は、私に多くのことを教えてくれた。
当たり前だと思っていた日常の尊さ、どんな困難な状況でも希望を持ち続ける大切さ、そして社会問題に対する自分なりの考えを持つことの重要性。
これらの学びを胸に、私はこれからの生活を送っていきたいと思う。
『スラムに水は流れない』の読書感想文の例文(1900字の高校生向けバージョン)
【題名】水が映し出す世界の現実と希望
私たちが毎日何気なく使っている水。
蛇口をひねれば当たり前のように出てくる水が、世界のどこかでは命をかけて手に入れなければならない貴重な資源だということを、『スラムに水は流れない』を読んで初めて深く理解した。
この作品は、インド・ムンバイのスラムで暮らす12歳の少女ミンニの物語だが、単なる貧困の描写にとどまらず、社会の構造的な問題や人間の尊厳、そして希望について深く考えさせられる内容だった。
物語の舞台となるムンバイのスラムには、1200万人の人口のうち約40%が暮らしているにも関わらず、水道インフラは極めて不十分で、スラム地区に供給される水の量は全体のわずか5%だという。
この数字を知ったとき、私は大きな衝撃を受けた。
なぜこれほどまでに不公平な状況が存在するのだろうか。
ミンニたちの日常は、私たちが想像する以上に厳しいものだった。
毎朝早くから共同栓に並んで水を手に入れること、運べる水の量が限られていること、飲み水は煮沸消毒が必要なこと。
水くみのために勉強や遊ぶ時間が削られてしまうことも珍しくない。
私が毎日何気なく使っている水が、ミンニたちにとっては命そのものなのだと感じた。
お風呂に入るときも、歯を磨くときも、料理をするときも、私は水を無駄にしていないだろうか。
この本を読んで、自分の生活を見つめ直すきっかけになった。
しかし、この物語で最も印象的だったのは、過酷な環境の中でも希望を失わないミンニの強さだった。
兄のサンジャイが水マフィアに関わる危険な事件に巻き込まれて家を離れることになったり、母が汚染された水が原因で重い病気にかかったりと、家族が引き裂かれる危機に直面する。
それでも、ミンニは学校に通いながら、家事や水くみ、母の務めていた家での労働も背負うことになる。
私がミンニの立場だったら、こんなに強くいられるだろうか。
きっと絶望してしまうかもしれない。
でも、ミンニは詩を書き続け、夢を諦めない。
「どんな環境でも学びたい」という強い意志を持ち続ける。
この姿に、私は深い感動を覚えた。
また、家族や友人との絆がミンニの支えになっている場面も印象的だった。
困難な状況でも、お互いを思いやり、支え合う姿は、人間の温かさを感じさせてくれた。
ミンニが「人は水なしでは生きていけない。でも、ほんとうに必要なのはそれだけじゃない」と感じる場面があるが、この言葉には深い意味があると思う。
水という物質的な必要性だけでなく、愛情や希望、夢といった精神的な支えもまた、人間が生きていくために不可欠なのだということを表しているのではないだろうか。
さらに、『スラムに水は流れない』を読んで、社会格差の現実についても深く考えさせられた。
富裕層の住む高層ビルの屋上にはプールがあるのに、スラムには基本的な飲み水すらない。
この残酷な対比は、社会の不公平さを象徴している。
水マフィアの存在も、水問題が単なる自然現象ではなく、人為的な構造によって引き起こされていることを示している。
カースト制度や社会的偏見の問題も描かれており、スラムの外から訪れる人々への視線など、複雑な社会問題が絡み合っていることがわかる。
なぜこんなことが許されるのか、最初は怒りを感じた。
でも、ただ怒るだけでは何も変わらない。
この現実を知った今、私に何ができるのかを考える必要がある。
まずは、水を大切に使うことから始めたい。
そして、世界の水問題について学び、できる範囲で支援活動に参加することも考えている。
また、この本を読んで、自分の価値観や世界観が大きく変わったことを実感している。
今まで当たり前だと思っていたことが、実はとても恵まれたことなのだと気づいた。
そして、遠い国の出来事だと思っていた貧困や格差の問題が、実は私たちの生活とも深く関わっていることを理解した。
グローバル化が進む現代社会において、世界のどこかで起こっている問題は、私たち一人ひとりに関係があるのだと感じる。
『スラムに水は流れない』は、私に多くのことを教えてくれた。
当たり前だと思っていた日常の尊さ、どんな困難な状況でも希望を持ち続ける大切さ、そして社会問題に対する自分なりの考えを持つことの重要性。
これらの学びを胸に、私はこれからの生活を送っていきたいと思う。
そして、ミンニのように、どんな状況でも前向きに生きる強さを身につけたいと思う。
振り返り
『スラムに水は流れない』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この作品は、水不足という現実を通して、社会格差や人間の尊厳、希望について深く考えさせてくれる素晴らしい物語です。
読書感想文を書く際は、自分が感じた驚きや感動、疑問を大切にしてください。
ミンニの強さに共感した気持ちや、社会格差の現実に対する怒りなど、あなた自身の素直な感情を文章にすることが重要です。
また、この本を読んで学んだことを、自分の生活にどう活かしていくかを考えることも大切です。
きっと皆さんも、この記事を参考にして、心に響く素晴らしい読書感想文を書くことができるはずです。
頑張ってくださいね。
※『スラムに水は流れない』のあらすじはこちらでご覧ください。


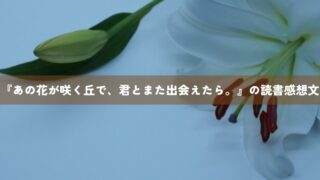
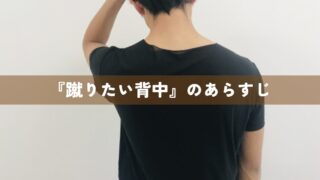
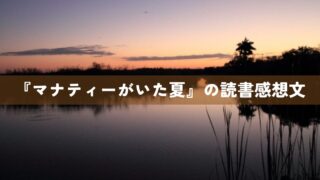






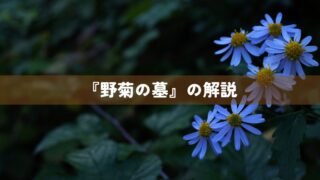

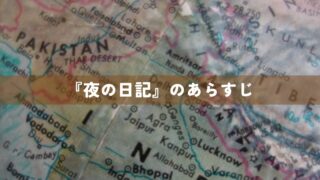


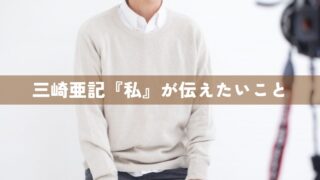
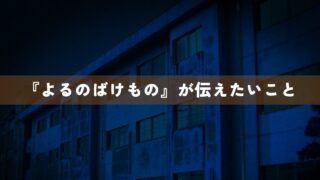
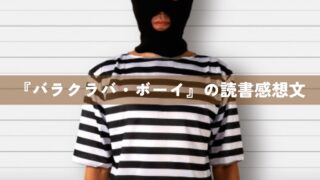
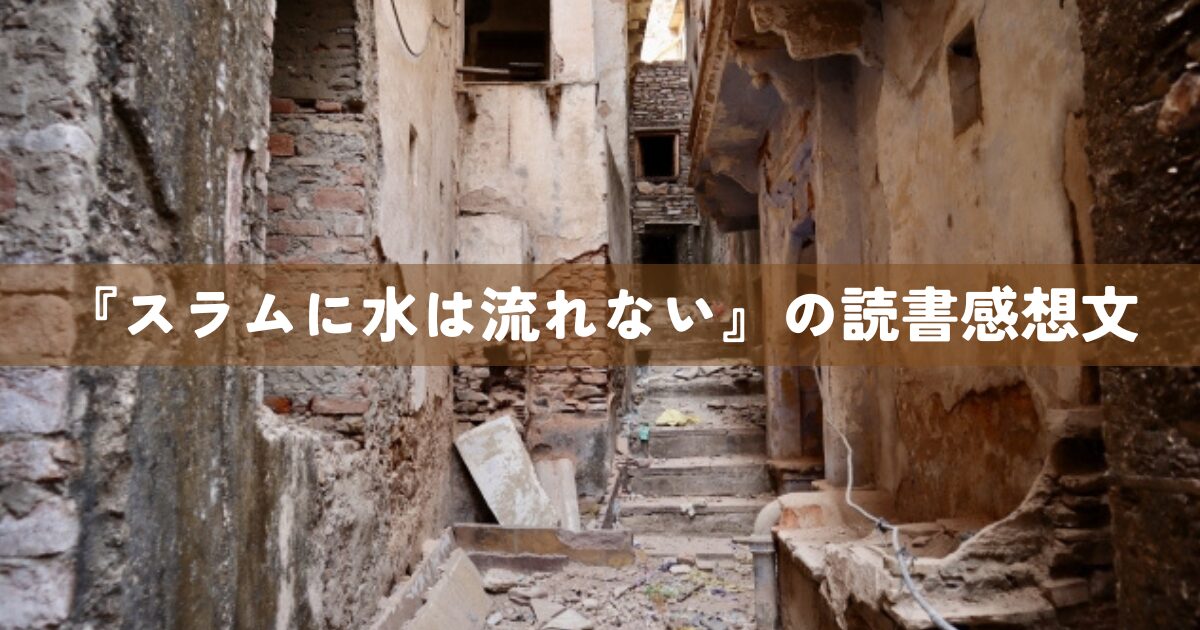
コメント