『モチモチの木』は怖い!トラウマになった!、そう感じる人、実はとても多いんです。
私も子供の頃、この絵本を読んだときの衝撃は今でも鮮明に覚えています。
斎藤隆介作、滝平二郎絵の『モチモチの木』は、1971年に岩崎書店から発行された名作絵本。
小学校の教科書に長年掲載され続けており、2020年度にはすべての小学校3年生の教科書に採用されているほど評価の高い作品です。
作者の斎藤隆介さんは、東北地方の民話をモチーフにした作品を多く手がけた児童文学作家として知られています。
読書家として年間100冊以上の本を読む私から見ても、『モチモチの木』は子供の成長と勇気を描いた傑作といえるでしょう。
まず結論から申し上げると
- 『モチモチの木』が怖いのは滝平二郎の切り絵の迫力と豆太の恐怖心が読者に伝わるから
- おじいさんの死亡説や仮病説は深読みに過ぎず、物語の本筋とは異なる
- 両親不在の設定は豆太とじいさまの絆を際立たせる演出効果がある
この記事では、多くの人が感じる疑問や恐怖の正体について、読書経験豊富な視点から詳しく解説していきます。
『モチモチの木』の奥深い魅力と、隠された意味について一緒に考えてみましょう。
『モチモチの木』が怖い!トラウマになった!と言われているのはなぜ?4つの理由
『モチモチの木』を読んで「怖い」「トラウマになった」と感じる読者は驚くほど多いんです。
実際、インターネット上でも「モチモチの木 怖い」という検索が頻繁に行われています。
この名作絵本がなぜ恐怖を与えるのか、主な理由を4つに分けて解説しましょう。
- 滝平二郎の独特な切り絵表現による視覚的インパクト
- 豆太の恐怖心がリアルに描かれている心理描写
- 東北方言と民話調の語り口による重厚な雰囲気
- 幼少期の受け取り方と大人になってからの印象の違い
それぞれの理由について、詳しく見ていきますね。
滝平二郎の独特な切り絵表現による視覚的インパクト
『モチモチの木』の恐怖感を決定づけているのは、何といっても滝平二郎さんの切り絵です。
黒を基調とした影絵のような表現は、昼間の場面でも薄暗い雰囲気を醸し出しています。
特にモチモチの木の巨大で威圧的な存在感は、多くの子供たちに強烈な印象を残します。
表紙の強烈な黒のインパクトも、手に取った瞬間から読者を圧倒するんです。
夜の暗闇の中でうごめく木の枝が、まるで怪物の手のように見えることも恐怖を増幅させる要因。
この切り絵の技法は芸術的に非常に優れているのですが、その分だけ子供の心に深く刻まれてしまうわけですね。
豆太の恐怖心がリアルに描かれている心理描写
主人公の豆太が感じる「暗闇への恐怖」が、読み手の子供たちにダイレクトに伝わってしまいます。
夜中にひとりでトイレに行けない豆太の心境は、多くの子供が共感できる体験。
大きな木が襲いかかってくるような視覚的表現と、暗闇の中での孤独感が組み合わさることで、読者も豆太と同じ恐怖を味わうことになります。
この心理描写のリアルさこそが、『モチモチの木』が長年愛され続ける理由でもあるんです。
東北方言と民話調の語り口による重厚な雰囲気
斎藤隆介さんの文章は東北の方言を使った民話調で書かれており、これが独特の重厚感を生み出しています。
「なんか怖い」「暗くて悲しそう」という印象を与える語り口は、都市部の子供たちには馴染みのない響き。
この文体が物語全体に神秘的で不気味な雰囲気を与えているんですね。
民話特有の教訓的な要素も、子供にとっては重く感じられることがあります。
幼少期の受け取り方と大人になってからの印象の違い
多くの人が証言しているのは、「子供の頃は怖かったけど、大人になって読み直すと感動する」ということです。
幼い頃は絵の迫力に圧倒されて内容に集中できなかった読者も、成長してから読み返すと物語の深いメッセージを理解できるようになります。
豆太の恐怖心をそのまま受け取ってしまう子供時代から、物語の本質を理解できる大人へと読み方が変化するわけです。
この変化こそが、『モチモチの木』が優れた文学作品である証拠といえるでしょう。
※大人になってからの読み直しのきっかけとしてこちらの『モチモチの木』のあらすじ紹介記事をおすすめします。

『モチモチの木』の「おじいさん死亡説」と「仮病説」を検証
『モチモチの木』には長年にわたって語り継がれている都市伝説的な解釈があります。
それが「おじいさん死亡説」と「仮病説」です。
これらの説について、物語の本文と照らし合わせながら詳しく検証してみましょう。
- おじいさん死亡説の根拠と反証
- 仮病説が生まれた背景と問題点
- 物語の本来の意図と教育的価値
読書家として多くの作品を分析してきた経験から、これらの説の真偽について解説していきます。
おじいさん死亡説の根拠と反証
「おじいさん死亡説」は、じいさまが豆太が医者を呼びに行く前に、あるいは医者が到着する前に既に息を引き取っていたのではないかという説です。
この説の根拠として挙げられるのは、じいさまの容態の急変と重篤さ。
夜中に突然うめき声をあげ、布団を蹴飛ばすほどの尋常でない苦しみ方をしていました。
豆太がいくら呼びかけても返事がないという描写も、意識を失っていた、あるいは既に亡くなっていた可能性を示唆するものとして解釈されることがあります。
しかし、物語の本文を注意深く読めば、この説は成立しないことが分かります。
豆太が医者を連れて戻った際、「じいさまの顔がなんだか、色がよくなっているように見える」という描写があるんです。
この表現は、じいさまが回復に向かっていることを示しており、死亡説とは矛盾します。
また、医者が実際に治療を行い、その結果としてじいさまが立ち直ったという明確な記述もあります。
仮病説が生まれた背景と問題点
「仮病説」は、じいさまが豆太を成長させるために意図的に病気のふりをしたのではないかという説です。
この説が生まれた背景には、じいさまの教育者的な側面があります。
じいさまは豆太の臆病な性格をよく理解しており、「本当の勇気」について日頃から話していました。
病気の発症が唐突で、回復も比較的早いように見えることから、演技だったのではないかと推測する読者もいるんです。
しかし、この説には重大な問題があります。
まず、じいさまの苦しみの描写があまりにもリアルで、演技とは考えにくいこと。
子供への教育のためとはいえ、命の危険を伴うような重篤な状態を演じるのは、じいさまの豆太への深い愛情と矛盾します。
また、仮病なら医者を呼ぶ必要がなく、医者が来れば嘘が露呈してしまうリスクもあります。
物語の本来の意図と教育的価値
これらの説は興味深い深読みではありますが、物語の本来の意図からは外れています。
『モチモチの木』は、豆太がじいさまのために勇気を振り絞って行動し、それを通して成長する「通過儀礼」の物語として読むのが適切です。
斎藤隆介さんが伝えたかったのは、「人間、優しさがあれば、やらなければならないことは必ずやるものだ」というメッセージです。
このメッセージの純粋性や感動を損なわないためにも、死亡説や仮病説のような解釈は避けるべきでしょう。
物語が小学校の教科書に長年採用され続けているのも、この普遍的な教育的価値が認められているからなんです。
『モチモチの木』の疑問点を解説(おじいさんの名前・お母さんやお父さんが不在の理由)
『モチモチの木』を読んだ多くの読者が抱く疑問があります。
それは登場人物の設定に関する疑問です。
読書家として数多くの作品を分析してきた経験から、これらの疑問に答えていきましょう。
- おじいさんの名前が明かされない理由
- 豆太の両親が不在である背景
- 家族構成が物語に与える効果
これらの疑問点について、作品の構造と作者の意図を踏まえて詳しく解説します。
おじいさんの名前が明かされない理由
『モチモチの木』の中で、おじいさんは一貫して「じいさま」と呼ばれており、固有名詞は一切登場しません。
これは斎藤隆介さんが意図的に行った演出と考えられます。
特定の名前を与えないことで、どこの家庭にもいるような「おじいさん」としての普遍性を強調しているんです。
読者が自分のおじいさんや、理想のおじいさんの姿を重ね合わせやすくする効果があります。
「じいさま」という呼び方自体が、豆太にとって彼がどのような存在であるかを端的に示しています。
頼れる、優しい、身近な大人という役割を、名前よりも関係性で表現しているわけですね。
絵本という特性上、登場人物の名前をあえて多くしないことで、物語の焦点を絞り、シンプルに感情移入しやすいように工夫されています。
豆太の両親が不在である背景
豆太の両親は物語に登場せず、その不在の理由も明確には語られていません。
ただし、父親については「生前は熊と取っ組み合うほど肝が座っていた」という記述があり、すでに亡くなっていることが示されています。
母親については直接的な説明はありませんが、豆太が「たった一人の孫」と表現されていることから、何らかの理由で不在であることが推察できます。
この設定は、当時の山村部では珍しいことではありませんでした。
病気や事故による早逝、出稼ぎによる長期離別など、様々な理由で祖父母が孫を育てる状況は一般的だったんです。
作者はこうした現実的な背景を踏まえながら、物語に必要な設定を選択したと考えられます。
家族構成が物語に与える効果
豆太とじいさまの二人だけという家族構成は、物語に重要な効果をもたらしています。
まず、二人の絆がより際立つこと。
他に頼れる大人がいない状況だからこそ、豆太がじいさまのために勇気を振り絞る必然性が生まれます。
また、豆太の成長がより印象的に描かれること。
両親がいれば、緊急時には両親が対応するのが自然ですが、豆太一人しかいない状況だからこそ、彼の勇気ある行動が際立つんです。
さらに、物語のテーマがシンプルに伝わること。
「真の勇気とは何か」「人間の優しさと強さ」といった普遍的なテーマに集中できるのは、家族関係を複雑にしていないからです。
この家族構成の選択は、物語の教育的効果を最大化するための巧妙な演出といえるでしょう。
振り返り
『モチモチの木』について、多くの読者が抱く疑問や恐怖の正体を詳しく解説してきました。
この記事の要点をまとめると
- 恐怖感の正体は滝平二郎の切り絵の表現力と豆太の心理描写のリアルさ
- 死亡説や仮病説は深読みに過ぎず、物語の本筋とは異なる解釈
- 登場人物の設定は物語のテーマを際立たせる巧妙な演出
- 大人になってから読み直すと違った感動を味わえる名作
『モチモチの木』は確かに「怖い」と感じる要素を持った作品ですが、それは作者と画家の表現力の高さの証明でもあります。
子供の頃に怖い印象を持った方も、大人になってから再読すると、きっと新たな発見と感動を得られるはずです。
真の勇気とは何か、人間の優しさと強さとは何かを問いかけるこの物語は、時代を超えて読み継がれる価値のある名作なんですね。



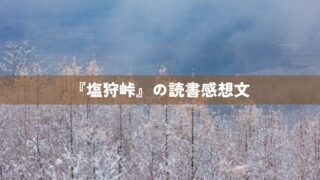

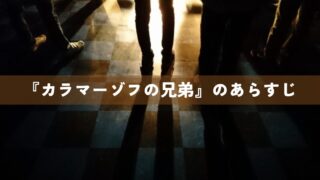
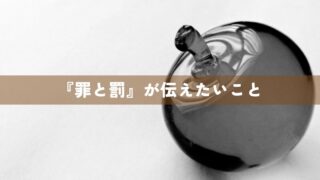

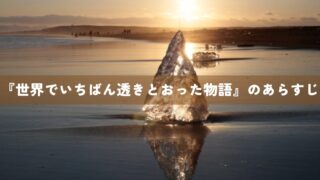
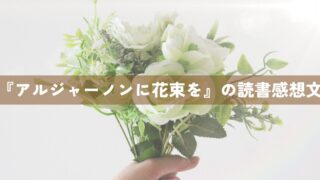
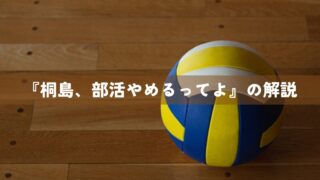


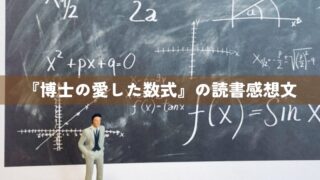

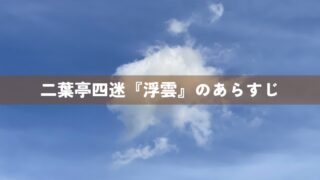
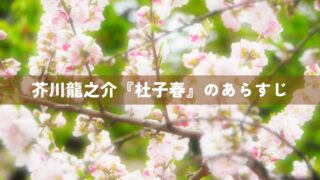
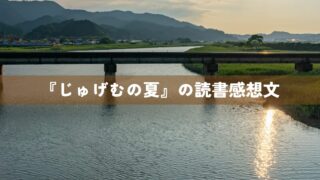
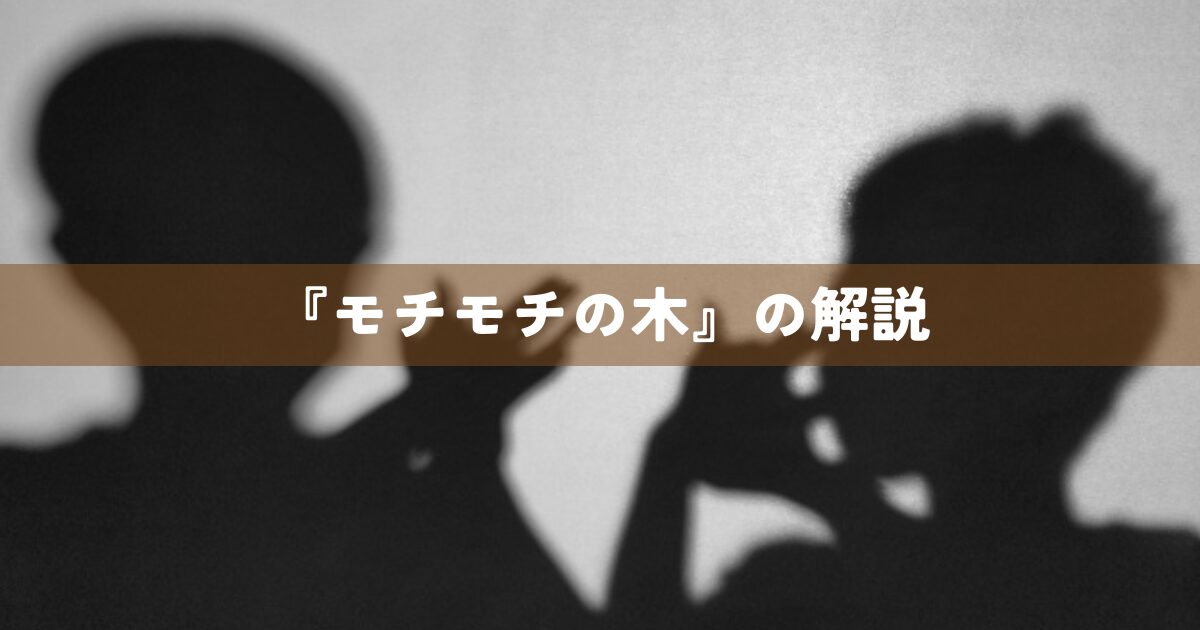
コメント