『「コーダ」のぼくが見る世界』のあらすじを読書感想文を書く予定の皆さんに分かりやすく紹介していきますね。
『「コーダ」のぼくが見る世界』は五十嵐大さんによる、聴こえない両親のもとで育った「コーダ」としての体験を綴ったエッセイ。
第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書にも選ばれたこの作品は、映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の原作者でもある五十嵐さんが、自身の幼少期から現在までの複雑な心情を率直に語った一冊となっています。
コーダという存在を通じて、家族やアイデンティティ、社会の偏見について深く考えさせられる内容になっているんですね。
読書感想文を書く際にも、多様性や家族の絆、社会との関わり方など、たくさんのテーマが見つかる作品ですよ。
それでは、さっそく進めていきましょう。
五十嵐大『「コーダ」のぼくが見る世界』のあらすじを短く簡単に
五十嵐大『「コーダ」のぼくが見る世界』の詳しいあらすじ(内容の要約)
『「コーダ」のぼくが見る世界』のあらすじを理解するための用語解説
『「コーダ」のぼくが見る世界』を読む上で知っておきたい専門用語を、分かりやすく説明しますね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| コーダ(CODA) | Children of Deaf Adultsの略語で、
聴覚障害のある親のもとで育った聴こえる子どもを指す。 |
| ろう者 | 生まれつき、または後天的に聴覚を失った人のこと。 独自の文化や手話言語を持つコミュニティを形成している。 |
| 中途失聴者 | 生まれた後に何らかの原因で聴力を失った人のこと。 著者の父親がこれに該当する。 |
| 手話 | 手や指、表情を使って意思疎通を図る視覚言語。 各国に固有の手話言語が存在する。 |
| ヤングケアラー | 家族の世話や支援を日常的に行う子どもや若者のこと。 コーダは通訳役として重責を担うことが多い。 |
これらの用語を理解しておくと、作品の内容がより深く理解できるでしょう。
『「コーダ」のぼくが見る世界』の感想
この作品を読んで、私は本当に深い感動を覚えました。
五十嵐さんの文章は、決して感情的に訴えかけるものではなく、淡々と事実を述べているように見えるのですが、その中に込められた複雑な思いがひしひしと伝わってくるんです。
特に印象的だったのは、コーダという存在の曖昧さについて語られた部分でした。
聴者でもろう者でもない、どちらの世界にも属しているようで属していない、その揺れ動く心境が痛いほど伝わってきます。
私自身、健常者として生きてきて、コーダという存在について全く知りませんでした。
五十嵐さんが幼い頃から家族の通訳役を担い、時には大人顔負けの責任を背負わされてきたという話には、本当に胸が詰まる思いがしました。
でも、同時に五十嵐さんの文章からは、家族への深い愛情も感じられるんです。
聴こえない両親との間に生まれた温かな思い出や、手話という美しい言語への愛着、そして何より家族の絆の強さが、静かに、しかし確実に伝わってきます。
読んでいて特に考えさせられたのは、「善意による差別」についての部分でした。
健常者が良かれと思って行う行為が、実は当事者にとって迷惑だったり、傷つけたりすることがあるという指摘は、本当に目から鱗でした。
手話歌の問題や、障害者を描いた作品における「感動モノ」の話など、私たちが無意識に行っている行為の問題点を、五十嵐さんは優しく、しかし鋭く指摘しています。
これは障害者の問題だけでなく、すべてのマイノリティに対する私たちの向き合い方を問い直すきっかけになると思います。
また、テクノロジーの発達がコーダの家族に与える影響についても、非常に興味深く読みました。
スマートフォンの普及により、筆談が簡単になったり、通訳アプリが登場したりすることで、コーダの役割や負担がどう変わっていくのか。
そこには希望もあり、同時に新たな課題もあることが分かります。
五十嵐さんの文章は決して重苦しくなく、むしろ軽やかで読みやすいのですが、そこに込められたメッセージは非常に深いものがあります。
私たちが「当たり前」だと思っている日常が、実は多くの人にとって「当たり前」ではないこと。
そして、その「違い」を理解し、受け入れることの大切さを、静かに、しかし確実に教えてくれる作品でした。
読後、私は自分の周りにいる人たちへの接し方を改めて考え直すきっかけを得ました。
これは本当に素晴らしい作品だと思います。
※『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文の書き方はこちらで解説しています。

『「コーダ」のぼくが見る世界』の作品情報
『「コーダ」のぼくが見る世界』の基本情報を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 五十嵐大 |
| 出版年 | 2024年 |
| 出版社 | 紀伊國屋書店 |
| 受賞歴 | 第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高等学校の部) |
| ジャンル | エッセイ |
| 主な舞台 | 日本(宮城県を中心とした著者の生活圏) |
| 時代背景 | 1983年生まれの著者の幼少期から現在まで |
| 主なテーマ | 家族、アイデンティティ、多様性、マイノリティ、コミュニケーション |
| 物語の特徴 | コーダとしての実体験を基にした自伝的エッセイ |
| 対象年齢 | 高校生以上 |
課題図書にも選ばれている通り、教育的価値の高い作品として評価されています。
『「コーダ」のぼくが見る世界』の主要な登場人物とその簡単な説明
『「コーダ」のぼくが見る世界』に登場する主要な人物たちを紹介しますね。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| 五十嵐大(著者) | 1983年宮城県生まれのコーダ。 エッセイスト、小説家として活動している。 |
| 著者の母親 | 生まれつきのろう者。 補聴器をしても音をほとんど認識できない。 |
| 著者の父親 | 4歳で聴力を失った中途失聴者。 手話でコミュニケーションを取る。 |
基本的に著者の家族を中心とした構成になっており、登場人物は多くありません。
『「コーダ」のぼくが見る世界』の読了時間の目安
『「コーダ」のぼくが見る世界』の読了時間について、具体的な数字とともに説明しますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総ページ数 | 約170ページ |
| 推定文字数 | 約102,000文字 |
| 読了時間(目安) | 約3時間24分 |
| 1日30分読書の場合 | 約7日で読了可能 |
| 1日1時間読書の場合 | 約3〜4日で読了可能 |
エッセイということもあり、小説に比べて読みやすく、集中して読めば数時間で読み終えることができます。
文章も分かりやすく、高校生でも無理なく読める内容になっています。
『「コーダ」のぼくが見る世界』はどんな人向けの作品か?
『「コーダ」のぼくが見る世界』は以下のような人に特におすすめです。
- 家族の絆や多様性について深く考えたい人
- マイノリティの体験や心情を理解したい人
- 社会の偏見や差別について学びたい人
特に、自分とは異なる立場の人の体験を知ることで、視野を広げたいと考えている人にはぴったりの作品です。
また、読書感想文の課題図書として選ばれていることからも分かるように、多様性や人権について考える機会を求めている学生にも最適でしょう。
逆に、重いテーマを扱っているため、軽い読み物を求めている人には向かないかもしれません。
しかし、著者の温かい文章により、決して読みにくい作品ではありませんよ。
あの本が好きなら『「コーダ」のぼくが見る世界』も好きかも?似ている作品3選
『「コーダ」のぼくが見る世界』と似たテーマを扱った作品を3つ紹介しますね。
家族の絆や多様性、マイノリティの体験といった共通点を持つ作品を選びました。
『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』(丸山正樹)
聴覚障害者の両親を持つコーダが主人公の社会派ミステリー小説です。
主人公の荒井尚人は法廷手話通訳士として活躍していますが、コーダとしての複雑なアイデンティティや家族との関係に悩んでいます。
『「コーダ」のぼくが見る世界』と同様に、コーダの心情や社会との関わり方がリアルに描かれており、手話やろう文化についても詳しく学べます。
『レインツリーの国』(有川浩)
聴覚障害を持つヒロインとの恋愛を描いた小説です。
インターネットを通じて知り合った男女の物語で、障害をめぐる葛藤や周囲との関わり方が優しいタッチで描かれています。
『「コーダ」のぼくが見る世界』と同じく、「違い」を持つ人の心情や、コミュニケーションの難しさと大切さが丁寧に表現されています。
『聲の形』(大今良時)
聴覚障害の少女とかつて彼女をいじめた少年の再生を描いた青春作品です。
いじめや障害の問題、「違い」を持つ者の孤独感、社会の無理解などが等身大で描かれています。
『「コーダ」のぼくが見る世界』と同様に、障害と社会との関わり、当事者の複雑な心情、そして理解し合うことの大切さがテーマとなっています。
振り返り
『「コーダ」のぼくが見る世界』は、聴覚障害のある両親を持つコーダとしての体験を通じて、家族の絆や多様性、社会の偏見について深く考えさせてくれる素晴らしい作品でした。
五十嵐大さんの率直で温かい文章により、コーダという存在の複雑さや、マイノリティとして生きることの意味を知ることができます。
読書感想文の課題図書としても選ばれているように、現代社会を生きる私たちにとって非常に重要なテーマを扱った一冊です。
この記事が、皆さんの読書や感想文作成のお役に立てれば幸いです。

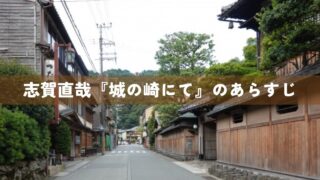

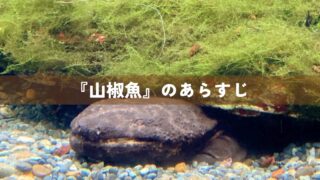

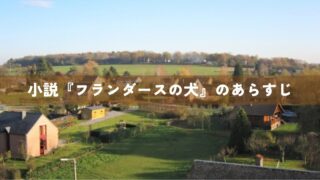


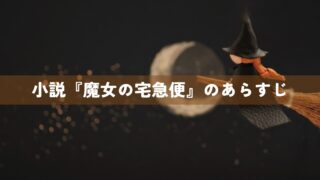
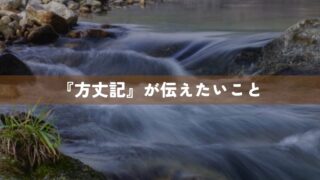
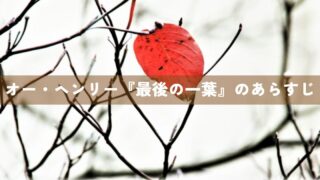



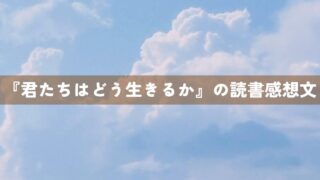

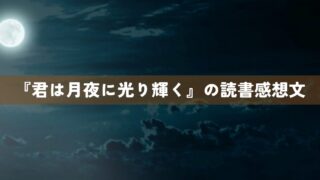


コメント