2025年度青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれた『ねえねえ、なに見てる?』のあらすじや私の感想をご紹介していきますね。
『ねえねえ、なに見てる?』はビクター・ベルモントさんによる色覚に特徴のある少年を主人公とした心温まる絵本です。
2021年にスペインでもっとも歴史のあるラサリーリョ賞を受賞した作品で、小学校中学年向けの課題図書として多くの子どもたちに読まれています。
年間100冊以上の本を読む私が読書感想文を書く予定のみなさんの力になれるよう、登場人物の紹介や作品のテーマまでしっかりとお伝えしますね。
それでは、さっそく進めていきましょう。
ビクター・ベルモント『ねえねえ、なに見てる?』のあらすじを短く簡単に(ネタバレなし)
主人公のトーマスは他の人と色の見え方がちがう男の子。自分ではちっとも変だと思わないが、家族みんながまわりの世界をどんなふうに見ているのかとても気になっている。科学者のママ、ゲーム好きのパパ、画家のマルタおばさんなど、それぞれが違った「メガネ」をかけて世界を見ていることにトーマスは気づいていく。
ビクター・ベルモント『ねえねえ、なに見てる?』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
主人公のトーマスは、他の人と色の見え方がちがうと言われる少年。
でも自分では全然変だとは思わないし、それよりも家族みんながまわりの世界をどう見ているのかがとても気になっている。
ある日、家族で食事をしているときにトーマスは想像を始めた。
生き物好きのねえさんのイレネには、お肉を食べる家族が石器時代の野蛮な人に見えているのかもしれない。
まだ小さいおとうとには、食べ物や家族がすごく大きく見えているだろう。
科学者のママは食べ物やお皿を科学的な目で見ているし、ゲーム好きのパパには家族がゲームのキャラクターのように見えているかもしれない。
画家のマルタおばさんは世界をキュービズム風に見ているし、恐竜好きのいとこのルーカスは何でも恐竜に見立てて考えている。
愛犬のオレオにも犬なりの見え方があるに違いない。
こうしてトーマスは、同じテーブルを囲んでいるのに家族みんながちがうふうに世界を見ていることを理解していくのだった。
『ねえねえ、なに見てる?』のあらすじを理解するための用語解説
『ねえねえ、なに見てる?』の中に出てくる専門的な用語をわかりやすく説明しますね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 色覚特性 | 一般的な色の見え方と異なる個性のこと。 「異常」ではなく、その人らしい特徴として考えられている。 |
| キュービズム | 20世紀初頭に生まれた美術のスタイル。 対象物をいろいろな角度から見て分解し再構成する技法のこと。 |
| 多様性 | 人それぞれが異なる見方や感じ方を持っていること。 違いがあることの素晴らしさを表す言葉。 |
| 認知バイアス | 人が無意識に持ってしまう偏った見方のこと。 職業や趣味によって世界の見え方が変わることを指す。 |
これらの言葉を知っておくと、物語の深い意味がよく理解できますよ。
『ねえねえ、なに見てる?』の感想
『ねえねえ、なに見てる?』を読み終えたとき、私はすっかり心を打たれてしまいました。
この絵本は表面的には色覚特性を持つ少年の話ですが、実際にはもっと普遍的で深いメッセージが込められていますね。
まず何より素晴らしかったのは、トーマスの視点の豊かさです。
他の人と色の見え方が違うことを「問題」として捉えるのではなく、「みんなはどう見えているんだろう?」という好奇心に変えてしまう発想力に感動しました。
これって実は私たち大人も学ぶべき姿勢だなと思うんです。
家族の食卓を描いた場面では、それぞれのキャラクターが本当に生き生きと描かれていて思わず笑ってしまいました。
科学者のママが食べ物を科学的に見ているという設定も面白いし、ゲーム好きのパパが家族をゲームキャラクターのように見ているという想像も楽しいですよね。
特に印象的だったのは、画家のマルタおばさんがキュービズム風に世界を見ているという描写でした。
私も美術館でピカソの絵を見たことがありますが、確かに同じ対象でも角度を変えて見ると全然違って見えるものです。
この絵本はそんな「見え方の違い」を視覚的にも美しく表現していて、大人が読んでも十分に楽しめる作品だと感じました。
イラストも本当に素晴らしくて、ページをめくるたびに新しい発見がありました。
同じ食卓の場面でも、それぞれの人の「メガネ」を通して見ると色合いや雰囲気がガラリと変わるんですよね。
これは絵本というメディアだからこそ表現できた技法だと思います。
ただ、私が一番感動したのは物語に込められたメッセージです。
私たちは普段、自分の見ている世界が「当たり前」だと思いがち。
でも実際には、年齢も職業も興味も違う人たちが、それぞれ全く異なる世界を見ているんですよね。
この絵本を読んで、私は改めて「他者理解」の大切さを実感しました。
相手の立場に立って考えるというのは言葉では簡単ですが、実際にはとても難しいことです。
でもトーマスのように「みんなはどう見えているんだろう?」と想像してみることから始められるのかもしれません。
読書感想文を書く小学生のみなさんにも、ぜひこの「想像する力」について考えてほしいと思います。
きっと友達との関係も、家族との関係も、今までとは違って見えてくるはずですよ。
※『ねえねえ、なに見てる?』の読書感想文の書き方はこちらでご覧ください。

『ねえねえ、なに見てる?』の作品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | ビクター・ベルモント |
| 翻訳者 | 金原瑞人 |
| 出版年 | 2024年 |
| 出版社 | 河出書房新社 |
| 受賞歴 | 2021年ラサリーリョ賞受賞 全国学校図書館協議会選定図書 |
| ジャンル | 児童文学・絵本 |
| 主な舞台 | トーマスの家庭 |
| 時代背景 | 現代 |
| 主なテーマ | 多様性、他者理解、個性の尊重 |
| 物語の特徴 | 色覚特性を題材とした心温まる家族の物語 |
| 対象年齢 | 小学校中学年(3~4年生) |
『ねえねえ、なに見てる?』の主要な登場人物とその簡単な説明
『ねえねえ、なに見てる?』に登場する主要な人物たちをご紹介しますね。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| トーマス | 物語の主人公。 他の人と色の見え方が違う男の子だが、 自分では特別だとは思っていない。 |
| ママ | トーマスの母親で科学者。 日常のものごとを科学的な視点で見ている。 |
| パパ | トーマスの父親でゲーム好き。 世界がゲームのように見えている様子が描かれる。 |
| イレネ(ねえさん) | トーマスの姉で生き物好き。 お肉や魚を食べない菜食主義者。 |
| マルタおばさん | 画家をしている親戚。 物事をキュービズム的に捉えて見ている。 |
| 音楽家のおじさん | 音楽を職業とする親戚。 音楽やリズムで世界を感じ取っている。 |
| いとこのルーカス | 恐竜が大好きな親戚の子ども。 何でも恐竜に見立てて考える。 |
| オレオ | トーマスの飼い犬。 犬なりの世界の見え方をしている。 |
それぞれが異なる「メガネ」をかけて世界を見ている様子が丁寧に描かれています。
『ねえねえ、なに見てる?』の読了時間の目安
『ねえねえ、なに見てる?』の読書にかかる時間をまとめてみました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ページ数 | 40ページ |
| 文字数 | 不明 |
| 読了時間 | 約15分程度 |
| 読み終える期間 | 1日で完読可能 |
絵本なので文字数はそれほど多くなく、小学生でも短時間で読み終えることができます。
イラストも豊富で読みやすく、読書感想文の題材としても取り組みやすい作品ですね。
『ねえねえ、なに見てる?』はどんな人向けの絵本か?
『ねえねえ、なに見てる?』は特に以下のような人におすすめしたいと思います。
- 他人の気持ちや考え方に興味がある好奇心旺盛な子ども
- 「なぜみんな違うことを考えるの?」と疑問に思ったことがある子ども
- 絵や色、デザインなどの視覚的な表現が好きな子ども
読書感想文を書く小学校中学年のみなさんには特にぴったりの作品だと思いますよ。
逆に、すぐに結論が知りたくてじっくり考えるのが苦手な子には少し物足りないかもしれませんね。
でも多様性や他者理解について考えるきっかけとして、多くの子どもたちに読んでほしい一冊です。
振り返り
『ねえねえ、なに見てる?』は色覚特性を持つ少年トーマスを主人公とした、多様性と他者理解をテーマにした素晴らしい絵本でした。
2025年度の課題図書として選ばれているだけあって、小学校中学年のみなさんが読書感想文を書くのにぴったりの作品だと思います。
家族それぞれが異なる「メガネ」をかけて世界を見ているという設定は、読者に深い気づきを与えてくれますね。
簡単なあらすじから詳しい内容、登場人物の紹介まで、この記事がみなさんの読書感想文作成のお役に立てれば嬉しいです。
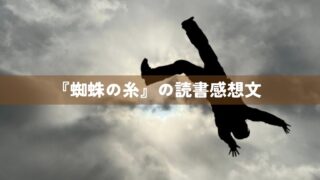



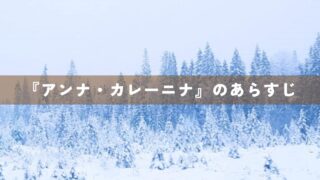
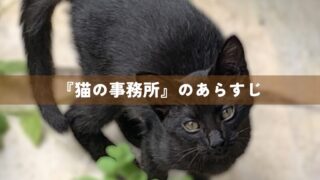
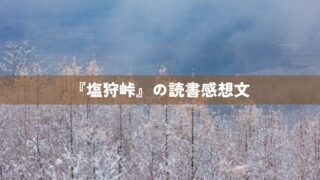


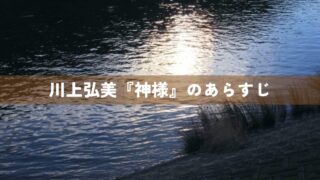

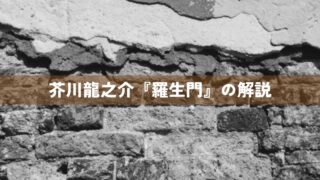
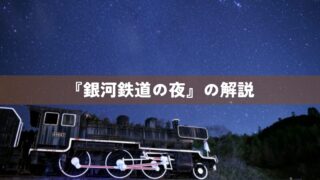

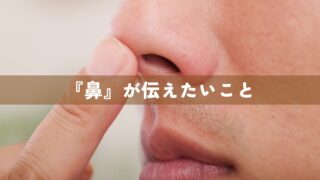

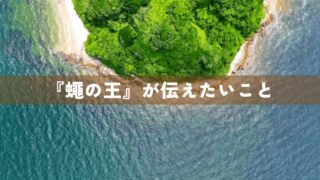


コメント