今日は住野よるさんの『よるのばけもの』について、あらすじをご紹介していきますね。
この物語は、夜になると化け物に変身してしまう中学生の男の子と、クラスでいじめられている女の子の交流を描いた青春小説です。
読書感想文を書く皆さんの力になれるよう、短くて簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、丁寧に解説していきますね。
読書が大好きで年間100冊以上の本を読む私におまかせください。
それではさっそく進めていきましょう!
住野よる 『よるのばけもの』のあらすじを簡単に短く
住野よる『よるのばけもの』の中間の長さのあらすじ
夜になると怪物に変身する高校生・安達は、ある晩、学校でクラスメイトの矢野さつきと出会う。彼女はクラスでは孤立し、いじめの対象となっているにもかかわらず、いつも不気味なほど笑顔を絶やさない不思議な少女だった。安達は、誰にも知られていない彼女の秘密の「夜休み」に付き合うようになる。
矢野の独特な言動や振る舞いを理解できない安達だったが、ある出来事をきっかけに、彼女の笑顔が恐怖や不安を隠すためのものだと知る。クラスから疎外される矢野と、怪物に変身するという秘密を抱える自分。二人はそれぞれの孤独を分かち合う中で、安達は矢野に対して単なる好奇心ではない感情を抱き始める。しかし、昼の学校での立場と夜の交流の間で揺れ動く安達は、彼女に対してどう向き合うべきか葛藤するのだった。
住野よる『よるのばけもの』の詳しいあらすじ(ネタバレなし)
高校生の安達は、夜になると八つ目、六つ足、四つの尾を持つ怪物に変身するという秘密を抱えていた。怪物に変身している間は夜も眠る必要がなく、誰もいない夜の街を自由に過ごしていた。ある夜、学校に忍び込んだ安達は、同じように夜の学校にいたクラスメイトの矢野さつきと出会う。彼女はクラスでいじめの対象となり、孤立しているにもかかわらず、いつもニタニタと笑っている不思議な少女だった。
矢野は、いじめの標的となっていたクラスメイトを助けるために、あえて自分がさらにいじめられるような行動をとる。その姿を見て、安達は彼女の笑顔の裏に隠された、決して愉快ではない本当の感情があるのではないかと考えるようになる。安達は、夜の学校で矢野と過ごす「夜休み」を通して、次第に彼女の孤独や優しさに触れていく。しかし、安達自身もまた、昼の学校ではクラスの人間関係を気にする「俺」であり、夜の怪物として矢野と心を通わせる「僕」であるという二つの自分に葛藤する。
そんな中、安達は矢野の笑顔が、実は恐怖や不安を隠すためのものであったことを知る。そして、矢野の抱える孤独と、自分が抱える怪物の秘密が重なり合うように感じ始める。クラスの一員として振る舞いたいという昼の自分と、矢野の孤独を放っておけない夜の自分。安達は、どちらかを選ぶのではなく、自分なりの方法で矢野に寄り添うことを決意するのだった。
『よるのばけもの』のあらすじを理解するための用語解説
『よるのばけもの』のあらすじやストーリーに出てくる用語を解説します。
| 用語 | 意味・解説 |
|---|---|
| 夜 | 主人公・安達が 本音や本当の自分と向き合う時間を象徴。 昼間の「正しい」行動と対比され 自分の弱さと直面する特別な時間。 |
| 化け物(ばけもの) | 安達の心の中の「本当の自分」や、 人に見せたくない異質な面の象徴。 社会に合わせて自分を偽る葛藤や恐怖を具現化した存在。 |
| 夜休み | クラスメイトの矢野さつきが持つ 自分だけの安心できる時間。 外の世界と自分の狭間で心を解放する秘密のひととき。 |
| 表の顔・裏の顔 | 社会で見せる自分(表の顔)と 本当は隠している感情や弱さ(裏の顔)という二面性。 化け物になる夜の姿が象徴。 |
『よるのばけもの』の作品情報
| 作者 | 住野よる |
|---|---|
| 出版年 | 2016年 |
| 出版社 | 双葉社 |
| 受賞歴 | – |
| 主な舞台 | 中学校と夜の街 |
| 時代背景 | 現代日本 |
『よるのばけもの』の主要な登場人物
『よるのばけもの』の主人公や重要なサブキャラクターたちをご紹介しますね。
それぞれが物語に深みを与える大切な役割を持っています。
| 人物名 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| 安達(あだち) | 主人公。 気弱で他人の目を気にする中学3年生の男子。 夜になると8つ目、6本足、4本尾の化け物に変身する。 昼は「俺」、夜は「僕」と自分を呼び分ける。 |
| 矢野さつき | クラス全員からいじめを受けている女子生徒。 いじめられてもにんまり笑っていることから 頭がおかしいと思われているが 実は恐怖を感じると笑ってしまう癖がある。 |
| 緑川双葉 | いつも図書館で過ごし 挨拶をしても「うん」としか返さない女子生徒。 矢野の元友達で矢野とは対照的な扱いを受けている。 |
| 笠井 | クラスの中心人物の優秀な男子生徒。 周囲を自分の思い通りに動かすことができる。 |
| 工藤 | 安達と隣の席の女子生徒。 元気で後輩の面倒見も良いが、 矢野の頭にジュースのパックを 躊躇なく投げつける一面も持つ。 |
| 中川ゆりこ | 顔も性格も派手でクラスの男子から 人気がある女子生徒。 率先して矢野のいじめに加担する。 |
| 井口 | 誰にも笑顔を振りまく優しい性格の女子生徒。 矢野の消しゴムを拾ったことでいじめの対象になる。 |
| 元田 | 野球部員。 率先して矢野のいじめに加担し 夜の学校に怪獣を捕まえに侵入する。 |
| 能登先生(のんちゃん) | 保健室の33歳の先生。 面倒見が良いが 矢野へのいじめに介入しない姿勢を見せる。 |
『よるのばけもの』の文字数と読了時間
『よるのばけもの』の文字数と読むのにかかる時間の目安をご紹介します。
読書感想文を書く前の計画づくりに役立ててくださいね。
| 推定文字数/ページ数 | 約172,800文字 (288ページ/双葉文庫) |
|---|---|
| 読了時間の目安 | 約5時間45分 |
| 読破難易度 | 中~易 (中高生向けに書かれている) |
ページ数から見ると比較的短くて読みやすい長さですが、内容は深いので、じっくり味わって読むことをおすすめします。
※『よるのばけもの』を通して作者が伝えたいことは、こちらの記事で考察しています。
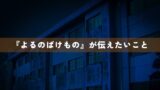
『よるのばけもの』を読んだ私の感想
正直、タイトルに惹かれて軽い気持ちで読み始めたのですが、いやはや、これは参りました。読み終えてからもしばらく、あの夜の静けさや、矢野さんの笑顔が頭から離れませんでした。
物語は、夜に怪物に変身する主人公・安達と、昼間にいじめられながらもニタニタ笑っている不思議な少女・矢野さつきの出会いから始まります。
この二人の「昼と夜」の顔が、とにかくリアルで胸に刺さるんです。大人になった今でも、会社の顔と家族の顔、本音と建前を使い分けることってあるじゃないですか。
若かった頃の、学校という閉鎖された世界で必死に「空気を読む」ことに疲れて、もう一人の自分をどこかに探していた感覚を、まざまざと思い出させられました。
特に心を揺さぶられたのは、矢野さんのあの笑顔の真実です。「良い子が傷つくのは嫌だね」と言いながら、いじめの矛先を自分に向けさせる彼女の行動。
あれは、僕たちの想像をはるかに超えた優しさであり、同時に、心の底からのSOSだったのかもしれません。安達がその真意に気づいたときの衝撃は、まさに読んでいる私自身の衝撃でもありました。
この物語は、いじめや孤独という重いテーマを扱っていながら、決して説教じみていません。むしろ、二人が夜の闇の中で見つける、ささやかな安寧の時間や、最後に安達が下す、ほんの少しの勇気ある決断が、じんわりと心に響きます。
誰かを救う大それた力ではなく、ただ「誰かの言葉を受け止める」という小さな一歩。それこそが、一番難しいことだと知っているからこそ、深く感動しました。
若い人に限らず、生きづらさを感じているすべての大人の「僕たち」に、ぜひ読んでほしい一冊ですね。
※『よるのばけもの』の読書感想文の書き方と例文はこちらにまとめています。

『よるのばけもの』はどんな人向けの小説?
『よるのばけもの』はどんな人に読んでほしい本なのか、考えてみました。
- 自分の居場所や本当の自分について悩んでいる中高生
- いじめや学校での人間関係に苦しんでいる人
- ファンタジー要素と現実の問題が融合した物語が好きな人
- 繊細な心理描写を味わいたい人
- 青春小説ファンで、少し異色の学園物語を求めている人
特に思春期の複雑な感情や学校での人間関係に悩む中高生には、強く響く作品だと思います。
自分自身の内面と向き合うきっかけになるかもしれませんね。
また、大人になってからでも、自分の中学・高校時代を振り返りながら読むと、新たな発見があるかもしれません。
シンプルながらも深いテーマを持つ作品なので、年齢を問わず楽しめる小説です。
『よるのばけもの』に似た小説3選
『よるのばけもの』を読んで感動した人におすすめの、似たテーマや雰囲気を持つ小説を紹介します。読書の幅を広げるきっかけになれば嬉しいです。
『君の膵臓をたべたい』(住野よる)
住野よるさんのデビュー作で、余命宣告を受けた女子高生と彼女の秘密を知ってしまった男子高生の物語です。
『よるのばけもの』と同様に、人との距離感や本当の自分を見せることの難しさ、そして勇気を持って一歩踏み出す姿が描かれています。
主人公たちの繊細な心理描写や、シンプルながらも心に響く文体など、住野よるさんの特徴がよく表れた作品です。
『よるのばけもの』を読んで感動した人なら、きっとこの作品にも心を揺さぶられるでしょう。
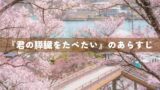
『青くて痛くて脆い』(住野よる)
こちらも住野よるさんの作品で、高校の文芸部を舞台にした青春小説です。
自分の本音と向き合うことの難しさや、人間関係の複雑さが描かれており、『よるのばけもの』と共通するテーマを持っています。
特に、主人公たちが自分の弱さや本心と向き合いながら成長していく過程は、『よるのばけもの』の安達の成長と重なる部分があります。
青春の痛みや葛藤を繊細に描いた作品として、ぜひ読んでみてください。
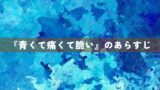
『か「」く「」し「」ご「」と「』(住野よる)
住野よるさんのもう一つの代表作で、秘密を抱えた人々の物語です。
『よるのばけもの』の「化け物」という外には見せられない部分を持つというテーマと通じるものがあります。
人それぞれが抱える「隠しごと」と、それを抱えながら生きていくことの苦しさや強さが描かれています。
人間関係の複雑さや自己受容というテーマを探求したい方におすすめです。

振り返り
今回は住野よるさんの『よるのばけもの』について、あらすじをご紹介しました。
この作品は、化け物に変身する少年と、いじめられている少女の交流を通して、「本当の自分とは何か」「他者との関係性」「社会の中での居場所」といった普遍的なテーマを描いています。
短くて簡単なあらすじから詳しいあらすじまで段階的に紹介したので、皆さんの読書感想文作成の参考になれば嬉しいです。
※よりくわしい『よるのばけもの』の考察は以下の記事で解説しています。



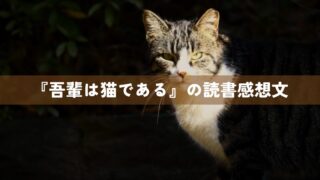
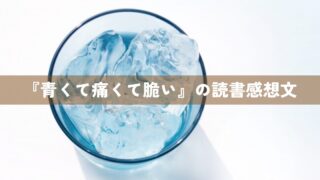


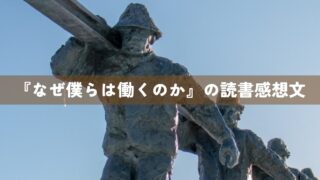



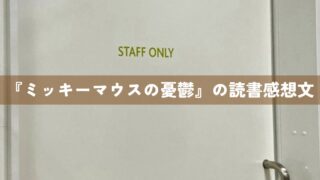
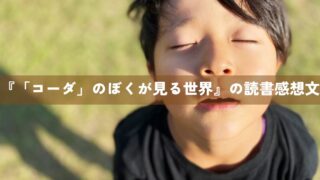


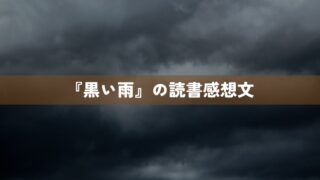


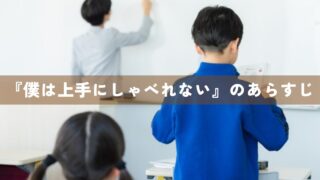

コメント