『図書館がくれた宝物』のあらすじを簡単に短く、そして詳しく解説していきますね。
この小説は、第二次世界大戦中のイギリスを舞台に、疎開先で生きる三人きょうだいの図書館を舞台にした心温まる児童文学です。
ケイト・アルバスさんによる本作は、第71回産経児童出版文化賞翻訳作品賞を受賞し、第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書にも選定された話題の作品なんです。
私は年間100冊以上の本を読む読書家として、この『図書館がくれた宝物』を実際に読んでみました。
戦時下という厳しい環境の中でも、本と図書館が子どもたちにとってどれほど大切な存在なのか、そしてきょうだいの絆がいかに美しいものかを感じられる素晴らしい作品でしたね
ではネタバレなしで、このストーリーの魅力をお伝えしていきますよ。
ケイト・アルバス『図書館がくれた宝物』のあらすじを簡単に短く
ケイト・アルバス『図書館がくれた宝物』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
『図書館がくれた宝物』のあらすじを理解するための用語解説
ここでは『図書館がくれた宝物』のストーリーを理解するために重要な用語をまとめました。
戦時下の背景や制度について知っておくと、物語がより深く理解できますよ。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 第二次世界大戦 (1940年のイギリス) |
物語の時代背景。 ドイツ空軍による空襲が激しさを増していた時期で ロンドン市民は日々不安な生活を送っていた。 |
| 学童疎開 | 都市部に住む子どもたちを空襲の危険から守るため、 田舎や地方の家庭に一時的に避難・移住させる政策。 本書のきょうだいもこの学童疎開によって ロンドンから地方へ移動する。 |
| 後見人 | 未成年の子どもが遺産を管理したり 合法的に暮らしたりするために 必要な保護者や代理人。 本作では両親と祖母を亡くしたきょうだいが、 疎開先で信頼できる後見人を探すことがテーマの一つ。 |
| 図書館 | 村にある公共施設で 本作における「心の拠りどころ」。 戦時下で孤立しがちな子どもたちにとって、 現実逃避や自分らしさを保つための場所として描かれる。 |
| 本・読書 | ただの娯楽や学びというだけでなく、 ・「心を癒やすもの」 ・「現実の苦しさから一瞬でも逃れさせてくれる存在」 として重要なモチーフとなっている。 |
これらの背景知識があると、きょうだいが置かれた状況や心情がより理解しやすくなりますね。
『図書館がくれた宝物』の感想
『図書館がくれた宝物』を読み終え、心が温かい気持ちでいっぱいになっちゃいました。
正直、児童文学だからと軽く考えていたのに、読み進めるうちにグッと引き込まれた感じですね。
戦争という厳しい時代に、子どもたちが感じるつらさがリアルに描かれていて、胸が締めつけられる場面も多かったです。特に、親を亡くした子どもたちが、さらに居場所まで奪われていく様子は本当に心が痛みます。
それでも、三兄弟が互いに支え合い、希望を捨てずに生きる姿には、私たちも力をもらえます。
そして、この物語で描かれる図書館の役割、本当に素敵でしたね。
本が好きな人にとって、図書館はただ本を借りる場所ではなく、心の拠り所みたいな特別な場所。物語の中でも、図書館はまさにそんな「心の避難所」として描かれていて、感動しました。
兄弟が図書館で本を開き、物語の世界に逃げ込むことで現実のつらさを乗り越える。そんな美しい描写を読むと、子どもの頃に感じた読書のワクワク感を思い出しますよね。
三兄弟のキャラクターも魅力的でした。長男のウィリアムは12歳で弟妹を守ろうとする姿が本当に立派。ちょっと出来すぎた子に思えるけど、純粋な兄弟愛が伝わってきて胸を打たれます。
お調子者だけど優しいエドマンド、そして純粋なアンナも可愛くて、三人の個性が光っていましたね。みんなが違う個性を持っているのに、互いを思いやる姿は本当に美しいです。
物語の展開は予想できる部分もあったけど、それがかえって読みやすさにつながっているように感じます。安心して読み進められるからこそ、登場人物の気持ちに深く寄り添うことができる。児童文学としては、とても大事なことかもしれません。
改めて、本や図書館が持つ力ってすごいなと感じさせてくれる物語でしたね。
つらい現実があっても、本を開けばそこには別の世界が広がる。登場人物たちと一緒に冒険したり、悩んだり、成長したりすることで、現実を生きる元気をもらえる。
この本を読んだ後、久しぶりに図書館に行きたくなった人も多いのでは?本を読む喜びや、図書館の価値を再確認させてくれる、そんな一冊でしたね。
※『図書館がくれた宝物』の読書感想文の書き方と例文はこちらにまとめています。

『図書館がくれた宝物』の作品情報
『図書館がくれた宝物』の基本的な作品情報をまとめました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作者 | ケイト・アルバス |
| 翻訳 | 櫛田理絵 |
| 出版年 | 2023年7月12日 |
| 出版社 | 徳間書店 |
| 受賞歴 | 第71回産経児童出版文化賞 翻訳作品賞 第70回青少年読書感想文全国コンクール 「課題図書」(小学校高学年の部) |
| ジャンル | 児童文学(翻訳児童文学) |
| 主な舞台 | 1940年ドイツとの戦争が始まったばかりの イギリス・ロンドン(主に疎開先の村) |
| 時代背景 | 第二次世界大戦初期 |
| 主なテーマ | 家族の絆、本と図書館の力、戦時下での成長 |
| 物語の特徴 | 戦時下イギリスの疎開先で生きる 3人兄弟と図書館との心温まる交流を描く |
| 対象年齢 | 小学校5~6年生向け |
| 青空文庫収録 | 未収録 |
『図書館がくれた宝物』の登場人物と簡単な説明
『図書館がくれた宝物』に登場する主要な人物たちをご紹介します。
三兄弟を中心とした心温まる人間関係が、この物語の大きな魅力の一つですね。
| 登場人物 | 紹介 |
|---|---|
| ウィリアム(12歳・長男) | 三きょうだいのリーダー的存在で、しっかり者。 家族を守りたいという責任感が強い。 |
| エドマンド(11歳・次男) | 感受性豊かでややお調子者。 本や冒険が大好きな性格。 |
| アンナ(9歳・末っ子) | やさしく素直な少女で、本を読むことが大好き。 きょうだいたちの癒し的存在。 |
| エンガーソル氏 | 三人を支える弁護士。 きょうだいの疎開を提案し 面倒を見てくれる大人。 |
物語の中心となるのは、やはりこの三兄弟ですね。
それぞれが違った個性を持ちながらも、互いを思いやる気持ちが物語全体を温かく包んでいます。
『図書館がくれた宝物』の読了時間の目安
『図書館がくれた宝物』の読了時間について詳しく解説しますね。
この作品のページ数や文字数から、どのくらいの時間で読み終えられるかを計算してみました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 総ページ数 | 384ページ |
| 推定文字数 | 約228,600文字 |
| 読了時間(連続読書) | 約7時間37分 |
| 1日1時間読書の場合 | 約8日 |
| 1日30分読書の場合 | 約15日 |
児童文学として書かれているため、文章も読みやすく、大人なら思ったより早く読み終えることができるでしょう。
小学生でも無理なく読み進められる難易度になっています。
『図書館がくれた宝物』はどんな人向けの小説か?
『図書館がくれた宝物』は、特に以下のような人におすすめしたい作品です。
- 小学校高学年の子ども – 読書感想文の課題図書として選ばれており、子どもたちが戦時中の困難を乗り越える姿から家族の絆や読書の大切さを学べます
- 本や図書館が好きな読者 – 作中に多くの児童文学の名作が登場し、読書愛好者にとって楽しめる工夫が満載です
- 心温まる家族の物語を求める人 – 戦時下でも兄弟が助け合いながら成長する姿や、図書館が心の支えとなる描写に感動できます
ただし、物語の展開が予想しやすい部分や、キャラクターがやや理想的すぎる面もあるため、複雑で予想のつかない展開を求める読者には物足りなく感じるかもしれません。
それでも、読後に温かい気持ちになりたい人や、読書や図書館の価値を再認識したい人には強くおすすめしたい作品ですね。
あの本が好きなら『図書館がくれた宝物』も好きかも?似ている小説3選
『図書館がくれた宝物』と同じような感動や魅力を味わえる、似た傾向の児童文学作品をご紹介します。
どの作品も「困難の中で助け合う」「本や物語が心の支えになる」「成長と希望」という共通のメッセージを持っていますよ。
エーリッヒ・ケストナー『エーミールと探偵たち』
ドイツを舞台に、少年エーミールが仲間たちと協力して泥棒を追いかける冒険物語。
親や大人と離れた場所で、子どもたちだけで問題を解決していくストーリー構造が『図書館がくれた宝物』と共通しています。
友情や信頼の大切さが丁寧に描かれており、困難に立ち向かう子どもたちの姿に勇気をもらえる作品です。
ミヒャエル・エンデ『モモ』
時間泥棒と戦う少女モモの物語で、社会や大人の不条理さの中で子どもが持つ純粋さや勇気が希望となる構造が魅力。
心の支えや大切な居場所を守ることの価値、時間や生き方の意味について深く考えさせられます。
『図書館がくれた宝物』と同様に、子どもの視点から大人の世界の問題に立ち向かう姿が描かれています。
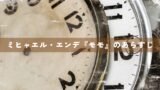
ルーシー・モード・モンゴメリ『赤毛のアン』
孤児のアンが新しい家族のもとで成長していく物語で、困難な環境からスタートする主人公の設定が似ています。
本や想像力が心の支えとなる点、家族の絆の大切さを描く点で『図書館がくれた宝物』と共通のテーマを持っています。
読書好きな主人公の成長物語として、多くの人に愛され続けている名作です。

振り返り
『図書館がくれた宝物』のあらすじから感想まで、詳しく解説してきました。
この作品は戦時下という厳しい環境を舞台にしながらも、家族の絆と読書の力によって希望を失わない子どもたちの姿を美しく描いた感動作です。
ケイト・アルバスさんが紡ぎ出した温かな物語を、ぜひ実際に手に取って味わってみてくださいね。

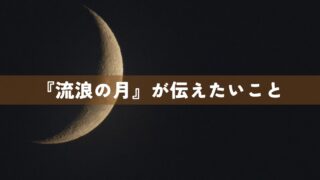










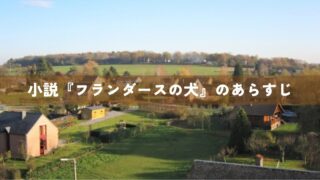





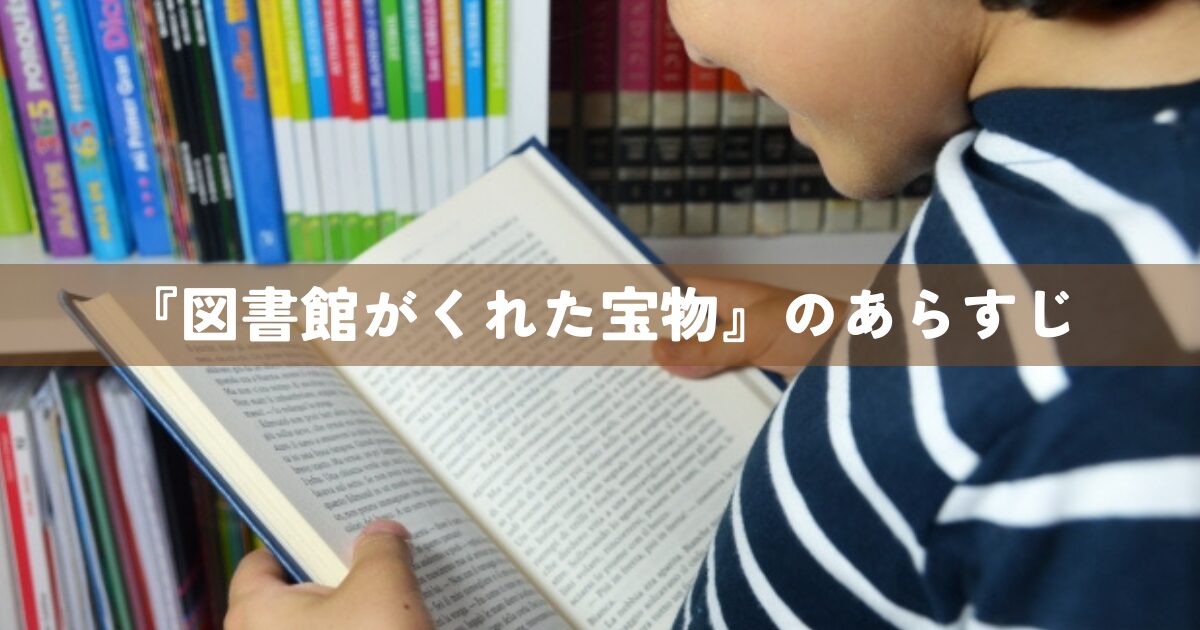
コメント