ヘルマン・ヘッセの名作『車輪の下』のあらすじをご紹介していきますね。
私は年間100冊以上の本を読む読書好きであり、20年以上前の学生時代にこの作品を読みました。
この物語の短くて簡単なあらすじから、結末までネタバレを含んだ詳しいあらすじまで用意したので、必要な長さを選んで読んでいただければと思います。
今回、再読したのでフレッシュな情報をもとにまとめていますよ。
ヘルマンヘッセ『車輪の下』のあらすじを短く
ヘルマンヘッセ『車輪の下』のあらすじを簡単に
ヘルマンヘッセ『車輪の下』のあらすじを結末まで詳しく
南ドイツのシュヴァルツヴァルトの町で暮らす少年ハンス・ギーベンラートは、母を早くに亡くし父親に育てられていた。生まれつき聡明な頭脳を持つハンスは、周囲から将来を期待され、猛勉強の末に難関の神学校に合格する。
寄宿生活では、詩を愛する自由奔放な性格のハイルナーと親しくなるが、彼の影響で次第に勉学への情熱を失っていく。ハイルナーが退学処分を受けた後、ハンスも神経衰弱となり故郷へ戻ることになる。
帰郷後、ハンスは靴屋の姪エンマに恋をするが、彼女は町を去ってしまう。その後、機械工として働き始め、ものづくりの楽しさを見出すが、ある夜、仲間との飲み会の帰り道で川に落ちて命を落としてしまうのだった。
『車輪の下』のあらすじを理解するための用語解説
『車輪の下』のあらすじやストーリーに出てくる馴染みのない用語を解説します。
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| マウルブロン | ドイツ・ヴュルテンベルク州にある 神学校(ラテン語学校)のこと。 主人公ハンスが、厳しい規律の中で学ぶことになる。 |
| 神学校(ラテン語学校) | 作中での正式名称は「Landesexamen」。 優秀な少年たちが官僚や聖職者になるための エリート教育を受けるための全寮制の学校。 |
| シュヴァルツヴァルト | 「黒い森」を意味する ドイツ南西部の広大な森林地帯。 ハンスの故郷である小さな村がこの地域にある。 |
| ギムナジウム | ドイツの教育制度における、 大学進学を目的とする高等中学校。 ハンスの友人のヘルマンが通っている学校。 |
『車輪の下』の作品情報
『車輪の下』の基本情報を、以下の表にまとめてみました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | ヘルマン・ヘッセ |
| 出版年 | 1906年 |
| 出版社 | 新潮社・岩波書店・光文社など |
| 舞台 | 南ドイツ・シュヴァルツヴァルトの町 |
| 時代背景 | 20世紀初頭のドイツ |
| 何歳向け? | 中学生以上 |
| 青空文庫 | 未収録 |
※『車輪の下』の面白い点や魅力は以下の記事にて紹介しています。

『車輪の下』の登場人物とその説明
『車輪の下』の主な登場人物たちをご紹介します。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| ハンス・ギーベンラート | 主人公。母を亡くした聡明な少年。 周囲の期待に応えようと努力する |
| ヨーゼフ・ギーベンラート | ハンスの父親。 厳格な性格で一人息子に大きな期待を寄せる |
| ヘルマン・ハイルナー | 神学校でハンスと出会う友人。 自由な精神の持ち主で詩を愛する |
| エンマ | 靴屋の姪。 ハンスが恋心を抱くが、 すぐに町を去ってしまう |
※これらの登場人物の解説を含めた考察は以下の記事にまとめています。

『車輪の下』の文字数と読了時間
『車輪の下』の文字数と読むのにかかる時間の目安です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 総ページ数(新潮文庫) | 246ページ |
| 推定総文字数 | 約147,600文字 |
| 読了時間の目安 | 約5時間 |
『車輪の下』を読んだ私の感想
学生時代に授業で読まされたヘッセの『車輪の下』、正直、あの頃は「眠い…」としか思わなかったんですよね。
それが40代になった今、なんとなく手に取って読み返してみたら、これがもう、とんでもない傑作だったと気づいて、ぶっ飛びました。
まず、主人公のハンス。もう、かつての自分と重なりすぎて、読んでて胸がギューッとなりましたよ。
彼は周りの期待に応えようと、ひたすらガリ勉する。その真面目さ、努力家なところはすごいんだけど、心の奥底で「もっと自由に生きたい!」っていう気持ちを、社会っていう大きな「車輪」に踏み潰されていく。
若かった自分も、いい学校、いい会社、いい人生っていう、誰が決めたかわからないレールの上を、ただひたすら走ってた気がするんですよね。
そのために、本当はやりたかったこととか、もっと大切にしたかった何かを、知らず知らずのうちに諦めていたのかもしれない。
そんなハンスの前に現れるのが、自由人のハイルナー。規則なんて関係ねえ!って感じで、自分の感性だけで生きてる。学生の頃なら、「やべーやつだ」って距離を置いてたと思うんです。
でも、今の自分には、彼の生き方がめちゃくちゃ輝いて見える。ハイルナーは、ヘッセが描きたかったもう一つの生き方、つまり「自分らしく生きる」ってことを体現してたんだな、と。
ハイルナーとの出会いが、ハンスの心の奥底に眠ってた「本当の自分」を揺さぶる。その葛藤が、もう切なくて切なくて。
結局、ハンスはレールから外れて、心も体も壊れてしまう。そして、若くして死んでしまうという悲しい結末。このラストは、レールの上を走り続けることのヤバさと、そこから外れることの難しさ、両方を示しているように感じました。
40代になって、少しは人生のレールから降りて、自分の足で歩けてるかな、なんて思ってたけど、本当にそうか?と問いかけられているような気がします。
この小説は、ただの青春物語じゃない。人生の途中で一度立ち止まって、「俺って、これでいいのかな?」って考えるきっかけをくれる、深~い一冊でした。
若い頃には全然見えなかった、この本の本当のすごさに、今ようやく気づけた気がします。
※『車輪の下』の読書感想文の例文と書き方はこちらで解説しています。

『車輪の下』はどんな人向けの小説?
『車輪の下』は、特に以下のような方におすすめです。
- 周囲の期待に応えようと頑張っている人
- 教育のあり方について考えたい人
- 青春期の繊細な心の動きを味わいたい人
- 人生の岐路に立っている人
『車輪の下』に似た小説3選
『車輪の下』と同じような主題を扱った作品を3つご紹介します。
『こころ』(夏目漱石)
主人公の青年が、厳しい受験勉強や人間関係に悩む姿が描かれています。
教育や社会の圧力という点で『車輪の下』と共通するテーマを持ちます。

『若きウェルテルの悩み』(ゲーテ)
繊細な青年の心の動きを丹念に描いた作品です。
社会との軋轢や恋愛など、青春期特有の悩みが『車輪の下』と通じるものがあります。

『三四郎』(夏目漱石)
地方から都会に出てきた青年の成長を描いた作品です。
新しい環境での戸惑いや、人間関係の機微が『車輪の下』と重なります。

振り返り
『車輪の下』は、100年以上の時を超えて、現代の私たちの心に深く響く作品です。
特に受験や進路に悩む学生の皆さんには、ぜひ読んでいただきたい一冊ですね。
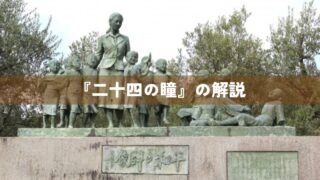

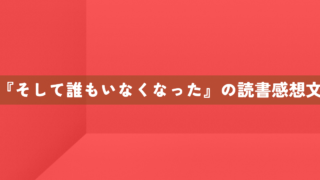

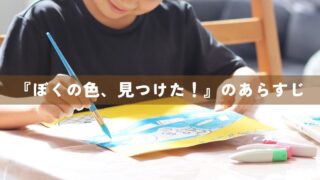

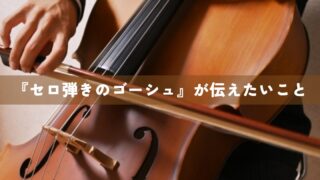
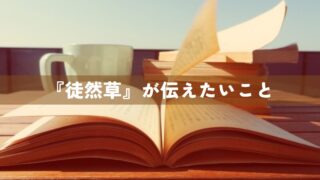
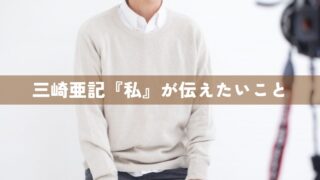

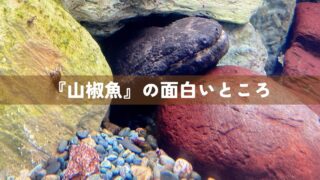

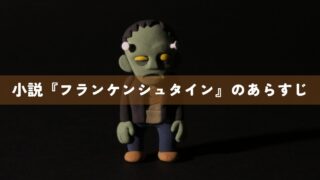
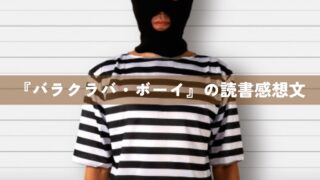


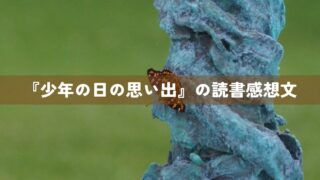


コメント