今回は『藪の中』を考察していきます。
教科書で読んだけれど何だかよくわからなかった…そんな人は多いはず。
実は私も高校時代に初めて読んだときは、「結局誰が犯人なの?」って混乱したんです。
でも年間100冊以上の本を読むようになった今では、芥川龍之介の『藪の中』がどれほど巧妙に作られた作品なのかがよくわかります。
この作品は1922年に発表された短編小説で、芥川龍之介の代表作のひとつとして知られています。
平安時代を舞台に、ある武士の殺人事件について複数の人物が証言するという構成になっているんですね。
まず要点だけをまとめると…
- 『藪の中』には木こり説・真砂説・多襄丸説という3つの犯人説がある
- 物理的証拠と心理的動機から真砂(妻)が最も有力な犯人候補
- 芥川龍之介は意図的に犯人を特定せず「真実の相対性」を描いた
「でも、結局答えがないなんて釈然としない…」って思う気持ち、すごくよくわかります。
でもご安心を。
この記事では、各説の根拠を詳しく分析し、なぜ芥川がこのような構造にしたのかまで踏み込んで解説していきますよ。
『藪の中』の犯人は誰か?3つの説を理由を含めて考察
『藪の中』を読んだ多くの読者が抱く疑問、それは「結局誰が犯人なの?」ということでしょう。
実は研究者や評論家の間でも、この問題について長年議論が続いています。
主要な犯人説は以下の3つに分類されます。
- 木こり説(第一発見者である木こりが真犯人)
- 真砂説(被害者の妻である真砂が真犯人)
- 多襄丸説(盗人の多襄丸が真犯人)
それぞれの説には説得力のある根拠があり、だからこそ読者は迷ってしまうわけです。
各説の詳細な分析を通して、『藪の中』の巧妙な構造を理解していきましょう。
木こり説
木こり説は、死体を発見した木こりが実は真犯人だったという説です。
この説の最大の根拠は、木こりの証言に不自然な点があることです。
木こりは第一発見者として事件の様子を詳しく語っていますが、実際には事件の当事者だった可能性があります。
被害者の霊が「誰かが小刀を抜いた」と証言している点も、木こりの関与を示唆しているかもしれません。
具体的な推理としては、木こりが現場で小刀を盗もうとして死体に近づき、まだ息のあった被害者にとどめを刺したという説が有力です。
ただし、この説には弱点もあります。
木こりが殺人を犯す明確な動機が示されていないことです。
また、他の証言者たちがなぜ嘘をつくのかという疑問も残ります。
真砂説
真砂説は、被害者の妻である真砂が夫を殺害したという説で、最も支持者が多い説でもあります。
この説の根拠は、真砂の心理的動機の明確さと物理的証拠の両方にあります。
平安時代の貞操観念を考えると、多襄丸に暴行された真砂にとって、それは死に等しい屈辱でした。
さらに、夫が自分を軽蔑するような目で見たことが、真砂の絶望と怒りを決定的なものにしたわけです。
物理的証拠としては、殺害に使用された小刀が真砂の所持品であることが挙げられます。
また、真砂が事件後に清水寺で懺悔していることも、実際に罪を犯した者の行動として解釈できるでしょう。
「気を失った」という証言も、殺害行為の記憶を曖昧にするための心理的防衛かもしれません。
多襄丸説
多襄丸説は、盗人の多襄丸が被害者を殺害したという説です。
多襄丸自身が「自分が武士を殺した」と自白しており、23合目で胸を貫いたという具体的な描写もあります。
犯罪者としての性格や過去の殺人歴を考えると、多襄丸が犯人でも不思議ではありません。
また、捕縛時に被害者の太刀や弓矢を所持していたことも状況証拠として挙げられます。
しかし、この説にも疑問点があります。
なぜ縄を解いて危険な一対一の勝負をしたのか、その理由が不自然だからです。
また、多襄丸の証言には自己美化や虚飾が含まれている可能性も指摘されています。
私が考察した『藪の中』の真犯人は真砂
長年の読書経験と文学的分析を通じて、私は真砂(妻)が真犯人である可能性が最も高いと考えています。
この結論に至った理由は、物理的証拠、心理的動機、行動パターンの三つの観点から総合的に判断した結果です。
以下の分析表を見ていただくと、各説の特徴がより明確になります。
| 説 | 主な根拠 | 弱点 | 信憑性 |
|---|---|---|---|
| 木こり説 | 証言の矛盾、小刀を抜いた可能性 | 明確な動機が不明 | 低 |
| 真砂説 | 小刀の所有、心理的動機、懺悔行動 | 激情的犯行の証明困難 | 高 |
| 多襄丸説 | 自白、武具の所持、犯罪歴 | 一騎打ちの理由が不自然 | 中 |
真砂説が最も説得力がある理由を詳しく説明していきますね。
まず物理的証拠から見ると、殺害に使用された小刀は真砂の所持品でした。
夫の縄を解いたのも真砂であることが、複数の証言で一致しています。
つまり、真砂だけが小刀を自由に使える立場にあったわけです。
心理的動機についても、平安時代の女性の価値観を考慮すると非常に明確です。
貞操観念の強い時代において、夫以外の男性との関係を持つことは死に等しい屈辱でした。
さらに、夫が自分を守れなかったこと、そして軽蔑するような目で見たことが、真砂の絶望を決定的なものにしたでしょう。
行動パターンの分析でも、真砂説を支持する証拠があります。
事件後の清水寺での懺悔、自殺未遂、そして「気を失った」という証言は、すべて実際に罪を犯した者の行動として解釈できます。
一方で、他の説には決定的な弱点があります。
多襄丸の証言には虚飾が多く、なぜ危険な一騎打ちをしたのかという疑問が残ります。
木こり説に至っては、明確な動機が全く示されていません。
『藪の中』で芥川龍之介は「犯人を特定していない説」を解説
しかし、ここで重要な観点を見落としてはいけません。
実は芥川龍之介自身が、意図的に犯人を特定しなかった可能性が高いのです。
この「犯人不特定説」こそが、『藪の中』の真の価値を理解する鍵となります。
芥川が描きたかったのは、単純な推理小説的な謎解きではなく、もっと深い哲学的なテーマだったわけです。
作品の構造を詳しく分析すると、以下のような特徴が見えてきます。
- 7人の証言がすべて食い違い、誰の供述も決定的な証拠にならない
- 多襄丸、真砂、武弘の三者がそれぞれ異なる「自分が殺した」という証言をしている
- 目撃者たちの証言も細部で矛盾している
このような構成は、明らかに意図的なものです。
芥川は読者に「犯人探し」をさせながら、同時にその不可能性を示しているのです。
作品のテーマは「真実の相対性」にあります。
人はそれぞれの立場や主観、利己心によって事実を歪めて語る、という人間の本質を描いているわけです。
つまり、「絶対的な真実は存在しないのではないか」という現代的な相対主義を、芥川は文学的に表現したのです。
実際に文学研究においても、「どんな読者も、そして芥川自身でさえも、犯人探しは不可能」と解説されています。
作者自身が犯人を決めていない、というのが定説となっているのです。
この解釈の根拠として、以下の点が挙げられます。
当事者たちが皆「自分が殺した」と言い、皆「自分が縄を解いた」と言っている異常さ。
登場人物同士の証言に矛盾が見られ、真相が分からないまま終わってしまう構造。
推理小説のようでいて、実は犯人探し自体が成立しない仕組み。
芥川の真の意図は、読者を「犯人探し」という迷宮に誘い込みながら、最終的に「真実とは何か」という哲学的な問いを投げかけることだったのです。
現代のSNS時代における情報の真偽、裁判における証言の信憑性といった問題とも通じる、時代を超えた普遍的なテーマを提示した名作といえるでしょう。
※『藪の中』を通じて芥川龍之介が伝えたいことはこちらで解説しています。

振り返り
『藪の中』の考察を通じて、この作品の奥深さを理解していただけたでしょうか。
芥川龍之介が仕掛けた巧妙な文学的トリックは、読者を推理の迷宮に誘い込みながら、最終的により深い人間理解へと導いてくれます。
この記事の要点をまとめると以下のようになります。
- 『藪の中』には木こり説・真砂説・多襄丸説の3つの犯人説がある
- 物理的証拠と心理的動機から真砂説が最も有力である
- しかし芥川龍之介は意図的に犯人を特定せず、真実の相対性を描いた
- 作品の真の価値は犯人探しではなく、人間認識の限界を示すことにある
教科書で読んだときは難しく感じた『藪の中』も、このような観点から読み直すと、きっと新しい発見があるはずです。
文学作品は答えを求めるものではなく、考えを深めるためのものなのかもしれませんね。
読書を通じて、人間の複雑さや世界の多様性について学ぶことができたら最高だと思います。
※『藪の中』で読書感想文を書く際はこちらの記事のあらすじをご覧ください。


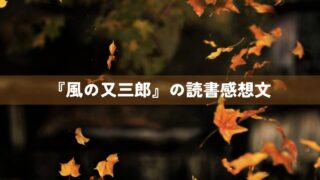


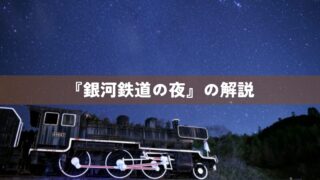
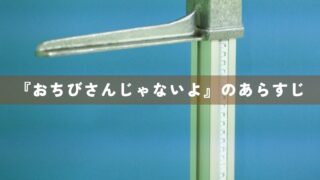






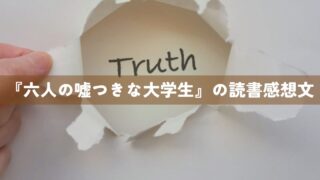

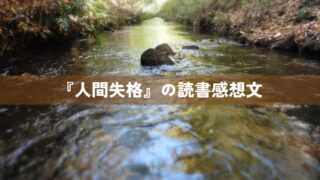




コメント