『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文を書く予定の皆さん、お待たせしました。
この作品は、五十嵐大さんによる感動的なエッセイ集で、聴こえない両親のもとで育った「コーダ」としての体験が綴られています。
2024年9月に公開された映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の原作者でもある五十嵐大さんが、自身の幼少期の葛藤やアイデンティティの揺らぎを丁寧に描いた話題作。
この記事では、『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文を書く際に押さえておきたい重要なポイントや、高校生の課題図書としても取り上げられることが多いこの作品の感想文の例文を1200~2000字バージョンで紹介していきます。
中学生向けの書き方から高校生レベルの例文まで、皆さんの感想文作成をしっかりサポートしていきますよ。
『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『「コーダ」のぼくが見る世界』で読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要なポイントを3つご紹介します。
- コーダとしてのアイデンティティの複雑さと葛藤
- 家族との深い絆と手話による独特なコミュニケーション
- 社会の中での「違い」に対する理解と共生への問いかけ
これらのポイントを押さえることで、深みのある感想文が書けるはずです。
それでは、それぞれのポイントを詳しく解説していきましょう。
コーダとしてのアイデンティティの複雑さと葛藤
『「コーダ」のぼくが見る世界』の最も重要なテーマは、著者がコーダ(聴こえない両親を持つ聴こえる子ども)として経験してきたアイデンティティの揺らぎです。
聴こえる世界と聴こえない世界、どちらにも属しているようで完全には属せない複雑な立場が丁寧に描かれています。
著者は手話を母語としながらも、時にはヤングケアラーとして家族の通訳役を担い、聴者の社会では「特別な存在」として見られることもあります。
このような「はざま」に立つ体験は、多くの読者にとって新鮮な驚きと深い共感を呼び起こすでしょう。
感想文では、著者の心の動きに注目し、自分だったらどう感じるかを想像して書くことが大切です。
また、「普通」とは何か、アイデンティティとは何かについて、自分なりの考えを述べることも重要なポイントになります。
家族との深い絆と手話による独特なコミュニケーション
『「コーダ」のぼくが見る世界』では、聴こえない両親との温かい家族関係が印象的に描かれています。
手話という視覚的な言語を通じて交わされる家族のやりとりは、音声言語とは違った豊かさを持っています。
著者の五十嵐大さんは
聴こえない親を持ったことで、たしかに必要以上の苦労をする可能性は否めない。けれど、過去を振り返ったとき、そこにネガティブな想い出しかないのかというと、そんなことはない
■引用:『「コーダ」のぼくが見る世界』
といった趣旨のことを述べています。
この言葉が示すように、困難な面もありながら、家族との間には確かな愛情と絆が存在していることが伝わってきます。
感想文では、家族の形は様々であること、コミュニケーションの方法も多様であることについて、自分の体験と重ね合わせながら書いてみましょう。
また、著者の家族への愛情や感謝の気持ちがどのように表現されているかに注目することも大切です。
社会の中での「違い」に対する理解と共生への問いかけ
『「コーダ」のぼくが見る世界』は、単なる家族の物語に留まらず、社会における多様性への理解について深く考えさせる作品です。
著者は「善意」や「配慮」が時に当事者を傷つけてしまう現実や、「お涙頂戴」と呼ばれる一方的な美談化への違和感についても率直に語っています。
また、テクノロジーの発達によってコミュニケーションの方法が変化していることや、社会のバリアフリー化の進展についても触れられています。
読書感想文では、「知る」ことの重要性や、異なる立場の人々への理解を深めることの大切さについて、自分の言葉で表現してみましょう。
また、日常生活の中で出会う様々な「違い」に対して、どのような姿勢で向き合うべきかについても考えを述べることが重要です。
より良い読書感想文を書くために『「コーダ」のぼくが見る世界』を読んだらメモしておきたい3項目
『「コーダ」のぼくが見る世界』を読んだ後、感想文を書く前にメモしておきたい重要な項目を3つご紹介します。
- 著者の葛藤や心の動きに共感した場面
- 自分の家族や日常生活と比較して感じたこと
- 社会の「当たり前」について考え直したこと
これらの項目についてメモを取ることで、より深みのある感想文が書けるようになります。
「どう感じたか」という主観的な体験こそが、読書感想文の核心部分だからです。
著者の葛藤や心の動きに共感した場面
『「コーダ」のぼくが見る世界』を読みながら、著者の心の動きに共感した場面をメモしておきましょう。
例えば、通訳として大人の責任を背負わされる重圧感や、友人関係での微妙な違和感など、著者が体験した様々な葛藤があります。
これらの場面で「自分だったらどう感じるか」「似たような経験はないか」と考えることが大切です。
また、著者が前向きに成長していく過程で印象に残った言葉や出来事もメモしておくと良いでしょう。
感想文では、これらの共感ポイントを具体的に書くことで、読み手に自分の感動を伝えることができます。
自分の家族や日常生活と比較して感じたこと
『「コーダ」のぼくが見る世界』を読んで、自分の家族や日常生活と比較して新たに気づいたことをメモしておきましょう。
著者の家族の特殊な状況と自分の「普通」の生活を比べることで、当たり前だと思っていたことの意味を再発見できるはずです。
例えば、家族間でのコミュニケーションの取り方や、社会との関わり方について、違いを感じた部分があったでしょう。
これらの気づきは、読書感想文において最も重要な要素の一つです。
自分の体験と結びつけて書くことで、より説得力のある感想文になります。
社会の「当たり前」について考え直したこと
『「コーダ」のぼくが見る世界』は、社会の「当たり前」について深く考えさせる作品です。
読書中に「これまで気づかなかった」「考えたことがなかった」と感じた社会の仕組みや人々の意識についてメモしておきましょう。
例えば、聴覚障害者への配慮や理解について、バリアフリーの現状について、多様性を受け入れる社会のあり方について、新たな視点を得たはずです。
これらの気づきを感想文に盛り込むことで、単なる感想を超えた深い洞察を示すことができます。
また、これからの社会に必要なことについて、自分なりの考えを述べることも重要です。
※『「コーダ」のぼくが見る世界』のあらすじはこちらでご案内しています。

『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文の例文(1200字の中学生向けバージョン)
【題名】コーダとして生きる意味
私は『「コーダ」のぼくが見る世界』を読んで、「普通」とは何かということを深く考えさせられた。この本の著者である五十嵐大さんは、聴こえない両親を持つ「コーダ」として生きてきた体験を綴っている。コーダとは「Children of Deaf Adults」の略で、聴こえない両親のもとで育つ聴こえる子どものことだ。
私はこの本を読むまで、コーダという言葉すら知らなかった。著者の体験を読んでいると、私が当たり前だと思っていた家族の形や社会との関わり方が、実は「普通」ではないのかもしれないと感じた。
著者は手話を母語として育ち、家族とのコミュニケーションは主に手話で行われていた。しかし、学校や社会では音声言語が中心で、時には家族の通訳を務めることもあった。このような「はざま」に立つ体験は、私には想像もつかないものだった。
特に印象に残ったのは、著者が友人から親のことを聞かれたときの複雑な気持ちだった。善意で聞いているのは分かるが、どこか「特別な存在」として見られることへの違和感があったと書かれている。私も友人の家族について無邪気に質問することがあるが、相手がどう感じているかまで考えたことはなかった。
また、著者の家族への愛情がとても温かく描かれていることも心に残った。「聴こえない親を持ったことで、たしかに必要以上の苦労をする可能性は否めない。けれど、過去を振り返ったとき、そこにネガティブな想い出しかないのかというと、そんなことはない」といったメッセージからは、困難な面もありながら、家族との間には確かな絆があることが伝わってきた。
手話という視覚的な言語を通じて交わされる家族のやりとりは、音声言語とは違った豊かさを持っているのだと感じた。コミュニケーションの方法は一つではなく、様々な形があることを知った。
この本を読んで、私は「違い」について考えるようになった。社会には様々な立場の人がいて、それぞれ異なる体験をしている。私が「普通」だと思っていることが、他の人にとっては「普通」ではないかもしれない。
著者は「善意」や「配慮」が時に当事者を傷つけてしまう現実についても書いている。良かれと思ってした行動が、相手にとっては迷惑だったり、複雑な気持ちにさせたりすることがあるのだ。これは私にとって新しい発見だった。
これからは、異なる立場の人々に対して、決めつけや思い込みをせず、相手の気持ちを考えて行動したいと思う。また、「知る」ことの大切さも学んだ。知らないことは怖いことではなく、学ぶチャンスなのだと思う。
『「コーダ」のぼくが見る世界』は、私に多様性について考えるきっかけを与えてくれた。著者の体験を通して、社会にはいろいろな人がいて、それぞれが大切な存在であることを改めて感じた。これからも、身の回りの「違い」に気づき、理解しようと努力していきたい。
『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文の例文(2000字の高校生向けバージョン)
【題名】聴こえる世界と聴こえない世界の間で
私は『「コーダ」のぼくが見る世界』を読み、これまで考えたことのなかった「アイデンティティ」や「多様性」について深く考えさせられた。この作品は、五十嵐大さんが聴こえない両親のもとで育った「コーダ」としての体験を綴ったエッセイ集である。コーダ(CODA:Children of Deaf Adults)とは、聴こえない両親を持つ聴こえる子どものことで、著者は自身の複雑な立場と心の動きを率直に語っている。
この作品を読んで最も印象的だったのは、著者が「聴こえる世界」と「聴こえない世界」の境界線上に立つことで経験した、アイデンティティの揺らぎである。手話を母語として育ちながら、音声言語中心の社会で生活する困難さ、家族の通訳役として大人の責任を背負わされる重圧感、そして「普通」とは何かという根本的な問いかけ。これらの体験は、私にとって全く新しい世界であった。
特に心に残ったのは、著者が友人から親のことを質問されたときの複雑な気持ちである。善意で聞いているのは分かるが、「特別な存在」として見られることへの違和感、そして自分の家族を説明することの難しさ。これらの描写を読んで、私は自分が無意識のうちに他者を「普通」と「特別」に分類していることに気づかされた。
また、著者の家族への深い愛情と感謝の気持ちが温かく描かれていることも印象的だった。「聴こえない親を持ったことで、たしかに必要以上の苦労をする可能性は否めない。けれど、過去を振り返ったとき、そこにネガティブな想い出しかないのかというと、そんなことはない」という言葉からは、困難な面もありながら、家族との間には確かな絆があることが伝わってきた。
手話という視覚的な言語を通じて交わされる家族のコミュニケーションは、音声言語とは異なる豊かさを持っている。表情、身振り、空間の使い方など、多様な要素が組み合わさって意味を作り出す手話の世界は、私にとって新鮮な驚きだった。コミュニケーションの形は一つではなく、様々な方法があることを改めて認識した。
この作品のもう一つの重要なテーマは、社会における「善意」や「配慮」の複雑さである。著者は「善意」が時に当事者を傷つけてしまう現実や、「感動系コンテンツ」と呼ばれる一方的な美談化への違和感について率直に語っている。これらの指摘は、私にとって衝撃的だった。良かれと思ってした行動が、相手にとっては迷惑だったり、複雑な気持ちにさせたりすることがあるということを、具体的な例を通して理解することができた。
例えば、「手話ができてすごいね」という言葉が、著者にとっては「これは自分にとって普通なんだけど」という複雑な思いを抱かせるというエピソードは、私の価値観を大きく揺さぶった。私たちが「褒め言葉」だと思っている言葉が、相手にとっては「特別扱い」として受け取られる可能性があることを知った。
また、著者がヤングケアラーとして捉えられることへの複雑な気持ちについても考えさせられた。家族の一員として当然のことをしているのに、外部から「大変だね」「頑張っているね」と言われることの居心地の悪さ。これは、支援する側と支援される側の立場の違いや、当事者の気持ちを理解することの難しさを示している。
私はこの作品を読んで、「知る」ことの重要性について深く考えるようになった。知らないことは決して恥ずかしいことではなく、学ぶチャンスである。しかし、知識を得るだけでは不十分で、その知識をどう活かすかが重要だということも学んだ。著者が「『知る』だけで終わらせない」と述べているように、理解を深めた後の行動が大切なのだ。
現代社会では、多様性や包摂性が重要視されているが、この作品を読んで、それらの概念を表面的に理解するだけでは不十分だと感じた。実際に異なる立場の人々がどのような体験をしているかを知り、その人たちの気持ちに寄り添うことが必要である。
また、テクノロジーの発達によってコミュニケーションの方法が変化していることについても興味深く読んだ。聴覚障害者向けの技術革新や、遠隔での手話通訳サービスなど、社会の変化に合わせて支援の形も変わっていく。これらの変化を通して、より良い共生社会を築くことが可能になるのだと感じた。
私は『「コーダ」のぼくが見る世界』を読んで、自分の価値観や社会に対する見方が大きく変わった。これまで「普通」だと思っていたことが、実は一つの視点でしかないことを知った。また、異なる立場の人々への理解を深めることの重要性と、その理解に基づいて行動することの大切さを学んだ。
これからは、身の回りの「違い」に気づき、決めつけや思い込みをせず、相手の気持ちを考えて行動したいと思う。また、多様性を受け入れる社会を築くために、自分にできることは何かを考え続けていきたい。『「コーダ」のぼくが見る世界』は、私にとって単なる読書体験を超えた、人生の指針となる作品である。
振り返り
『「コーダ」のぼくが見る世界』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
この作品は、コーダとしてのアイデンティティの複雑さ、家族との深い絆、そして社会の多様性について深く考えさせる素晴らしい作品です。
読書感想文を書く際は、著者の体験に共感しながら、自分の日常生活や価値観と照らし合わせて考えることが大切です。
また、「知る」ことの大切さや、異なる立場の人々への理解を深めることの重要性についても、自分なりの考えを述べることで、より深みのある感想文になるでしょう。
皆さんも、この記事を参考にして、心に響く読書感想文を書いてみてください。
きっと素晴らしい作品に仕上がるはずです。
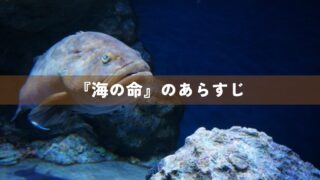



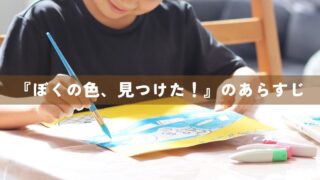


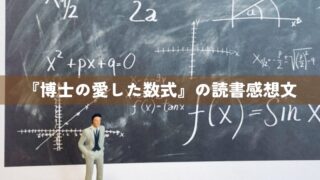



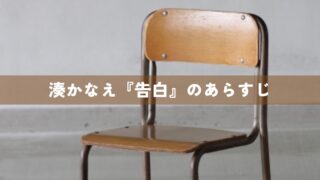





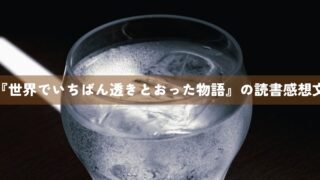
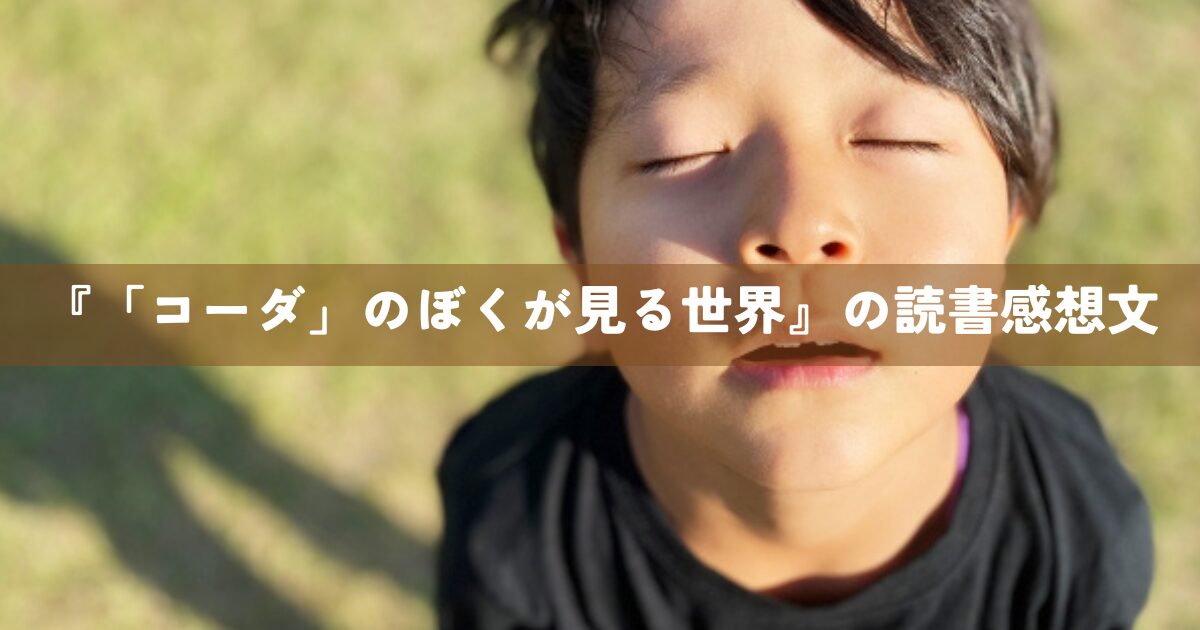
コメント