『流浪の月』の読書感想文を書く予定のみなさん、こんにちは。
凪良ゆうさんの『流浪の月』は、第17回本屋大賞を受賞した話題の小説ですね。
世間から「誘拐犯」と「被害者」のレッテルを貼られた二人の主人公が、15年後に再会するというストーリー。
表面的には理解しがたい関係性の裏に隠された、深い絆と真実が描かれています。
この記事では、年間100冊以上の本を読む私が『流浪の月』の読書感想文の書き方から例文まで、みなさんの力になるよう丁寧に解説していきます。
中学生向けと高校生向けの例文も用意しましたので、題名や書き出しの参考にしてくださいね。
コピペはいけませんが、構成や表現の仕方は大いに参考になるはずですよ。
『流浪の月』の読書感想文で触れたい3つの要点
『流浪の月』の読書感想文を書く際に、ぜひ盛り込みたい要点を3つご紹介します。
これらのポイントについて「どう感じたか」をメモしながら読み進めることが大切ですよ。
感想文の核となる部分ですから、しっかりと自分の心の動きを記録しておきましょう。
- 世間の偏見と当事者の真実との乖離
- 孤独な魂が求める「居場所」の意味
- 愛のかたちの多様性と社会の理解
メモの取り方のコツは、各場面で「なぜそう思ったのか」「自分ならどうするか」「現実社会との共通点は何か」を具体的に書き残すこと。
これらの要点について深く考察することで、単なるあらすじの紹介ではない、質の高い感想文が書けるはずです。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は本の内容を説明するレポートではなく、あなた自身の心の変化や気づきを表現する文章だからですね。
世間の偏見と当事者の真実との乖離
『流浪の月』の最も核心的なテーマが、この「世間の見方」と「当事者の真実」のギャップです。
更紗と文の関係は、メディアや周囲の人々によって「誘拐事件」として単純化されてしまいます。
しかし、実際の二人の関係は、そんな一言では表現できない複雑で深いものでした。
ここで考えてほしいのは、私たちがいかに表面的な情報だけで物事を判断しがちかということ。
SNSやニュースで流れる情報を鵜呑みにして、知らず知らずのうちに誰かを傷つけていないでしょうか。
『流浪の月』を読みながら、「もし自分が更紗や文の立場だったら」「もし自分が周囲の人間だったら」と想像してみてください。
そのとき感じた複雑な気持ちや葛藤こそが、感想文の材料となります。
現代社会における情報の扱い方や、多様性への理解についても考察を深められるでしょう。
孤独な魂が求める「居場所」の意味
更紗も文も、それぞれに深い孤独を抱えて生きています。
更紗は家庭内での居場所のなさに苦しみ、文は社会からの視線に怯えながら生活していました。
そんな二人にとって、互いの存在がどれほど大切な「居場所」だったことか。
ここで重要なのは、「居場所」とは物理的な場所ではなく、心が安らげる関係性のことだということです。
あなたにとっての「居場所」はどこでしょうか。
家族、友人、学校、部活動、趣味の場など、人それぞれ違うはずです。
『流浪の月』を読みながら、自分の「居場所」について考えてみてください。
そして、もし自分にそんな場所がなかったら、または失ってしまったらどう感じるかも想像してみましょう。
孤独の痛みや、誰かに理解されることの喜びについて、きっと深い気づきが得られるはずです。
現代社会では、多くの人が「居場所」を見つけられずに悩んでいます。
この作品を通じて、そうした社会問題についても考察できるでしょう。
愛のかたちの多様性と社会の理解
『流浪の月』が描く更紗と文の関係は、恋愛でも友情でもない、独特のものです。
世間一般が想像する「普通」の関係性の枠には当てはまりません。
しかし、だからといってその関係性が間違っているわけではないのです。
愛にはさまざまなかたちがあります。
家族愛、恋愛、友愛、そして名前のつけられない愛もあるでしょう。
『流浪の月』を読みながら、「愛とは何か」について考えてみてください。
社会が認める愛と認めない愛があるとしたら、その境界線はどこにあるのでしょうか。
そして、その境界線は正しいものなのでしょうか。
こうした問いかけは、読書感想文を書く上で非常に重要な視点となります。
LGBTQ+の権利や多様性について学ぶきっかけにもなるでしょう。
自分自身の価値観を見つめ直し、より寛容で理解ある人間になるためのヒントが、この作品には込められています。
※『流浪の月』が伝えたいことや面白い点はこちらでご紹介しています。

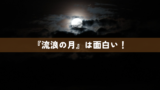
『流浪の月』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】心の「居場所」を見つけるということ
凪良ゆうさんの『流浪の月』を読んで、私はこれまで味わったこともなかった複雑な気持ちになった。
この物語は、世間から「誘拐犯」と「被害者」というレッテルを貼られた二人の関係を描いている。
でも、読み進めていくうちに、そんな簡単な言葉では表現できない深い絆があることがわかってきた。
主人公の更紗は、親戚の家で居場所がなくて、いつも公園で時間を過ごしていた。
孤独で心を閉ざしていた彼女が出会ったのが、静かな雰囲気をまとった大学生の文だった。
更紗にとって文の家は、初めて心が安らげる場所だったのだと思う。
誰にも否定されず、ただそこにいるだけで受け入れてもらえる空間が、彼女にとってどれだけ大切だったか、想像すると胸が痛くなる。
でも、二人の関係が世間に知られると、文は「悪い人」、更紗は「かわいそうな子」として扱われてしまう。
私が一番驚いたのは、ニュースや周りの人が言うことと、実際の二人の気持ちがまったく違っていたことだ。
世間の人たちは、表面的な情報だけで二人を判断していた。
でも、物語を読んでいると、二人の間には誰にも邪魔されたくない特別な絆があったことがよくわかる。
本当は、どちらも「守られるべき存在」であり、「傷ついた心を持った人」だったのではないかと思う。
私たちも普段、見た目や噂だけで人を決めつけてしまうことがあるのではないだろうか。
話したこともない同級生を周りの人の意見や印象だけで遠ざけていないだろうか。
ニュースから得た表面的な情報だけで、「悪いこと」・「良いこと」と単純に判断していないだろうか。
この本を読んで、そんな自分の態度を反省させられた。
また、更紗と文がそれぞれに「居場所」を求めていることも印象的だった。
更紗は家族の中で息苦しさを感じ、文も社会の中で孤独を抱えて生きていた。
二人にとって、お互いが唯一の「居場所」だったのかもしれない。
私にも、家族や友達と一緒にいても、なんとなく居心地が悪いときがある。
誰にも見せられない気持ちを、そっと抱えたまま過ごすことがある。
そんなとき、本当に自分らしくいられる場所があったらどんなにいいだろうと思う。
『流浪の月』を読んで、「居場所」というのは物理的な場所ではなく、心が安らげる関係性のことなんだと気づいた。
更紗と文の関係は、恋愛でも友情でもない独特なものだった。
でも、だからといって間違っているわけではないと思う。
愛にはいろいろな形があるし、世間の常識に当てはまらないからって否定されるべきではない。
この物語が教えてくれたのは、人を簡単に判断してはいけないということだ。
表面的な情報だけでなく、その人の本当の気持ちや事情を理解しようと努力することが大切だと学んだ。
そして、みんなが自分らしく生きられる社会になってほしいと強く思った。
『流浪の月』は、複雑だけれども大切なことを教えてくれる、とても心に残る一冊になった。
『流浪の月』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】真実と偏見の狭間で見つけた希望
凪良ゆうさんの『流浪の月』を読み終えて、私の心には今まで感じたことのない複雑な感情が渦巻いている。
この作品は、世間が「女児誘拐事件」として片付けてしまった出来事の裏側に隠された、深く純粋な人間関係を描いている。
読み進めるうちに、自分がいかに表面的な情報だけで物事を判断していたかを痛烈に思い知らされた。
物語の中心にいるのは、小学生の更紗と大学生の文という二人の主人公だ。更紗は親戚の家で居場所を見つけられず、文は社会からの偏見に怯えながら生きていた。
そんな二人が公園で出会い、お互いにとって唯一の「居場所」となっていく過程が丁寧に描かれている。
しかし、二人の関係が世間に知られると、メディアや周囲の人々によって「誘拐犯」と「被害者」というレッテルを貼られてしまう。
私がこの作品で最も考えさせられたのは、世間の常識と当事者の真実との間にある深い溝についてだ。
ニュースやSNSで流れる情報を見て、私たちはすぐに善悪を判断してしまいがちだ。でも、『流浪の月』を読んでいると、そんな単純な二分法では捉えきれない複雑な人間関係があることがわかる。
更紗と文の間にあったのは、世間が想像するような関係ではなく、互いの心の傷を癒し合う純粋な絆だった。
特に印象に残っているのは、更紗が文のもとを離れたくないと泣き叫ぶ場面だ。その映像が拡散されることで、更に二人への偏見が強まっていく。
この場面を読んで、現代のSNS社会の怖さを実感した。一つの映像が切り取られて拡散され、真実とは異なる物語が作り上げられてしまう。
この作品を通じて、私は自分自身の価値観を見つめ直すことになった。
普段から、見た目や第一印象だけで人を判断していないだろうか。マスメディアが作り出すイメージに踊らされて、本質を見失っていないだろうか。
『流浪の月』は、そんな私の浅はかさを鋭く指摘してくる。
実際、私も過去に噂だけで同級生を避けてしまったことがある。その子の本当の性格を知ろうともせずに、周りの評判だけで判断していた。今思えば、その子も更紗や文のように、誤解によって孤立していたのかもしれない。
また、この物語は「居場所」の意味についても深く考えさせてくれた。
更紗も文も、それぞれに深い孤独を抱えて生きている。家族がいても、学校や職場があっても、心から安らげる場所を見つけられずにいた。
そんな二人にとって、お互いの存在がどれほど大切だったことか。
私自身も、高校生活の中で「本当の居場所」について考えることがある。友達といても、家族といても、どこか息苦しさを感じるときがある。クラスメイトとの会話に合わせるために、本当の自分を隠してしまうこともある。
そんなときを思い出すと、『流浪の月』の主人公たちの気持ちが痛いほどわかった。
居場所というのは、物理的な場所ではなく、ありのままの自分を受け入れてもらえる関係性のことなのだと気づいた。
文にとって更紗は、自分の弱さを隠す必要のない相手だった。更紗にとって文は、大人からの期待を感じることなく、子どもらしくいられる相手だった。
15年後に再会した二人の姿を見ていると、時間が経っても変わらない絆の強さを感じる。周囲の視線や社会の常識に屈することなく、自分たちの真実を守り続けた強さに胸を打たれた。
さらに、この作品は愛の多様性についても問いかけてくる。
更紗と文の関係は、恋愛でも友情でもない、名前のつけられない独特なものだ。
世間一般の「普通」の枠には当てはまらない。でも、だからといってその関係性が間違っているわけではない。愛にはさまざまな形があり、それぞれに価値があるのだと思う。
現代社会では、LGBTQ+の権利や多様性について議論されることが多い。『流浪の月』を読んで、そうした議論の根底にある問題を実感できた。
社会が認める愛と認めない愛の境界線は、果たして正しいものなのだろうか。この物語は、そんな根本的な疑問を投げかけてくる。
物語の中で描かれる周囲の人々の反応も考えさせられる。
善意から行動している人でも、結果的に更紗や文を傷つけてしまうことがある。「普通」を押し付けることが、いかに暴力的になりうるかを学んだ。
読み終えた今、私は以前よりも寛容で理解ある人間になりたいと強く思っている。
表面的な情報だけで判断するのではなく、その人の本当の気持ちや事情を理解しようと努力したい。そして、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に、少しでも貢献できればと願っている。
具体的には、クラスで孤立している人がいたら声をかけてみる。噂話に惑わされることなく、自分の目で相手を見極める。そんな小さなことから始めていきたい。
『流浪の月』は、私にとって人生観を変える一冊となった。
この作品が教えてくれた「真実を見極める大切さ」「居場所の意味」「愛の多様性」について、これからもずっと考え続けていきたい。
複雑で重いテーマを扱いながらも、最後には希望を感じさせてくれるこの物語に、心から感謝している。
そして、いつか私も誰かにとっての「居場所」になれるような、そんな人間に成長したいと強く決意している。
振り返り
『流浪の月』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つの要点を意識しながら読み返せば、きっと深い感想が書けるはずです。
中学生向けと高校生向けの例文も、あなたの感想文作りの参考になったでしょうか。
大切なのは、コピペではなく自分自身の言葉で感じたことを表現すること。
『流浪の月』という素晴らしい作品と向き合えば、必ずあなただけの感想が生まれます。
題名や書き出しに悩んだときは、今回の例文を参考にしてみてくださいね。
あなたにも必ず、心に響く読書感想文が書けますよ。
※『流浪の月』の短くて簡単なあらすじはこちらでご紹介しています。
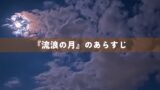

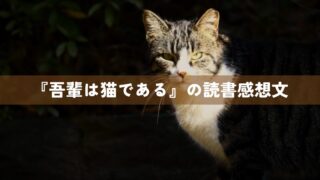
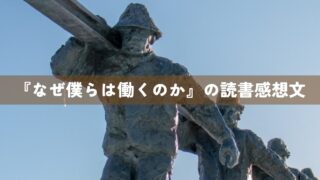




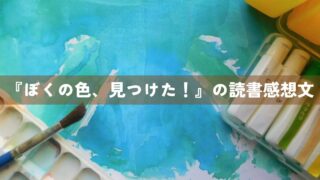


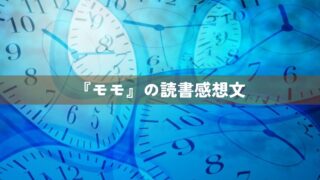


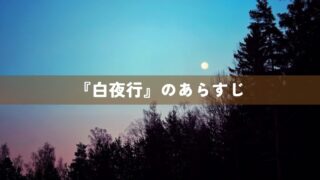
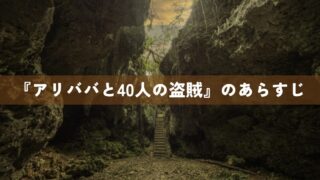




コメント