『少年と犬』の読書感想文を書く予定のみなさん、お疲れさまです。
第163回直木三十五賞を受賞した馳星周さんの『少年と犬』は、東日本大震災で飼い主を失った犬・多聞が様々な人々と出会いながら旅を続ける連作短編小説。
震災から熊本地震まで約5年間の物語を通して、人と動物の絆や困難に立ち向かう勇気が描かれた感動作品です。
私は読書が趣味で年間100冊以上の本を読んでいますが、この作品は特に読書感想文の題材として非常に優れていると太鼓判を押したいですね。
今回は中学生・高校生のみなさんが書き方に迷わないよう、コピペせずに済む書き出しのコツから例文まで、丁寧に解説していきますよ。
『少年と犬』の読書感想文で触れたい3つの要点
『少年と犬』の読書感想文を書く際に必ず押さえておきたい要点を3つご紹介します。
以下の要点について読書中に「どう感じたか」をメモしておくと、感想文を書く時にとても役立ちますよ。
メモの取り方としては、印象的な場面や心に残った台詞の横に付箋を貼って、そこに短い感想を書き込んでおくのがおすすめです。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は物語の要約ではなく、あなた自身の心の動きや気づきを表現する文章だからですね。
この3つの要点を意識して読み進めてみてください。
- 災害や困難に直面した人々と犬の絆
- 勇気と希望を持ち続けることの大切さ
- 自分らしさや生きる意味を見つけて成長していく過程
それでは、それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
災害や困難に直面した人々と犬の絆
『少年と犬』の最も重要なテーマの一つが、災害に見舞われた人々と犬・多聞との心のつながりです。
東日本大震災で飼い主を失った多聞は、窃盗団の運転手・和正、泥棒のミゲル、富山の夫婦、娼婦の美羽、猟師の弥一、そして熊本の内村家と、様々な境遇の人々と出会います。
それぞれの人物が抱える心の傷や孤独感、生活の困難さと、多聞がもたらす癒しや希望の対比に注目してみてください。
特に印象的なのは、多聞が単なるペットとしてではなく、人々の心の支えとなり、時には人生を変えるきっかけを与える存在として描かれている点です。
あなたも動物と接した経験があるなら、その時の気持ちを思い出しながら読むと、より深く物語を理解できるでしょう。
災害という現実的な背景があることで、人と動物の絆がより際立って感じられるはずです。
この要点について感想文を書く際は、多聞と登場人物たちの関係性から何を学んだか、自分の体験と重ね合わせて考えてみることが大切ですね。
勇気と希望を持ち続けることの大切さ
物語を通して一貫して描かれているのが、困難な状況でも希望を失わずに前進しようとする人々の姿です。
多聞自体が、飼い主を失った悲しみを乗り越えて長い旅を続ける勇気の象徴として描かれています。
登場人物たちも、それぞれが抱える問題や過去のトラウマと向き合いながら、少しずつ前向きな気持ちを取り戻していく過程が丁寧に描写されています。
特に注目してほしいのは、希望や勇気が突然現れるものではなく、日々の小さな積み重ねや他者との関わりの中で育まれていく様子です。
あなた自身が困難に直面した時のことを思い出しながら読むと、登場人物たちの気持ちがより理解できるでしょう。
また、勇気とは大きな行動を起こすことだけでなく、毎日を生き抜くことや誰かを思いやることも含まれるという視点も大切です。
この要点について書く時は、物語の中の具体的なエピソードと、あなた自身が「勇気」や「希望」について考えたことを関連付けて表現してみてください。
自分らしさや生きる意味を見つけて成長していく過程
『少年と犬』では、多聞と出会う人々がそれぞれ自分自身と向き合い、新たな生きる意味を見出していく成長の物語が描かれています。
犯罪に手を染めざるを得なかった和正、家族との関係に悩む登場人物たち、過去の失敗に苦しむ人々が、多聞との交流を通して自分の在り方を見つめ直していきます。
特に重要なのは、成長が一方向的なものではなく、挫折や迷いを含んだ複雑なプロセスとして描かれている点です。
多聞自身も、ただの理想的な存在ではなく、時に迷いながらも自分の道を歩み続ける姿が印象的ですね。
この要点を読書感想文に取り入れる際は、登場人物の成長過程と、あなた自身の成長体験や悩みを重ね合わせて考えてみてください。
中学生や高校生のみなさんにとって、「自分らしさとは何か」「どう生きていけばいいのか」という問いは身近なテーマでしょう。
物語の中の人物たちがどのように答えを見つけていったか、そしてそれを見てあなたが何を感じたかを具体的に書くことで、説得力のある感想文になります。
また、完璧な答えが見つからなくても、探し続けること自体に意味があるという視点も大切にしてください。
『少年と犬』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】多聞が教えてくれた絆の大切さ
『少年と犬』を読んで、私は人と動物の間にある特別な絆について深く考えさせられた。
この物語は東日本大震災で飼い主を失った犬・多聞が、様々な人と出会いながら旅を続ける話だ。
最初は悲しい設定だと思ったが、読み進めていくうちに、多聞が出会う人々にとってかけがえのない存在になっていく様子に心を打たれた。
特に印象に残ったのは、多聞が窃盗団の運転手をしている和正と出会う場面だ。
和正は認知症の母親のために仕方なく犯罪に手を染めているが、多聞と一緒にいると不思議と仕事がうまくいく。
多聞は和正にとって守り神のような存在になるのだが、私はここで動物が人間に与える力の大きさを実感した。
我が家でも犬を飼っているが、確かに辛い時や疲れた時に犬がそばにいてくれると、なんとなく心が軽くなる。
多聞と和正の関係を読んでいて、それは気のせいではないのだと確信した。
また、多聞が常に南の方角を気にしている描写も心に残っている。
多聞には何か大切な目的があって、それに向かって一歩ずつ進んでいるのだということが伝わってきた。
人間だって、目標があるから頑張れるし、困難に立ち向かえるのだと思う。
多聞の姿を見ていると、私も自分の目標をもっとはっきりさせて、諦めずに努力し続けたいと思った。
物語の中で多聞は色々な人の家で暮らすが、どの人も最初は心に傷を負っていたり、孤独を感じていたりする。
でも多聞と過ごすうちに、少しずつ前向きな気持ちを取り戻していく。
富山の夫婦のエピソードでは、多聞を「トンバ」や「クリント」と呼んで大切にする様子が描かれていた。
名前を付けるということは、その存在を受け入れて愛するということだと思う。
多聞もきっと、自分のことを大切に思ってくれる人がいることで、旅を続ける力をもらっていたのだろう。
私は部活で挫折を味わった時、家族や友達に支えられて立ち直ることができた。
一人では乗り越えられなかった困難も、誰かが側にいてくれることで頑張れるのだと実感している。
多聞と登場人物たちの関係は、まさにそういう支え合いの大切さを教えてくれる。
この小説を読んで、私は改めて周りの人や動物との絆を大切にしたいと思った。
困っている人がいたら手を差し伸べること、辛い時は素直に助けを求めること、そして感謝の気持ちを忘れないこと。
多聞が様々な人に愛され、同時に多くの人を癒やしていたように、私も誰かの心の支えになれるような人間になりたい。
災害という大きな悲しみから始まった物語だったが、最後は希望に満ちた気持ちになった。
どんなに辛いことがあっても、必ず誰かが支えてくれるし、自分も誰かを支えることができる。
そんな当たり前だけど忘れがちな大切なことを、多聞が思い出させてくれた気がする。
『少年と犬』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】多聞が照らし出した人生の意味
『少年と犬』を読み終えた時、私は久しぶりに本を読んで涙を流していた。
東日本大震災で飼い主を失った犬・多聞の物語は、表面的には一匹の犬の冒険譚に見えるが、実際は現代社会を生きる人々の孤独や絶望、そしてそこから立ち上がろうとする意志を描いた深い作品だった。
多聞が辿る岩手から熊本までの長い旅路は、単なる地理的な移動ではない。
それは人間社会の様々な層を横断し、それぞれの場所で苦悩を抱える人々と出会い、彼らの人生に小さな光をもたらす精神的な旅なのだと感じた。
窃盗団の運転手・和正との出会いから始まる物語の冒頭で、私は現代社会の厳しい現実を突きつけられた。
認知症の母親を抱え、正当な仕事では生活できずに犯罪に手を染めざるを得ない和正の状況は、けっして他人事ではない。
高齢化社会が進む中で、若い世代が背負わされる責任の重さや、社会のセーフティネットから漏れ落ちる人々の存在を、和正の姿を通して実感した。
しかし、そんな絶望的な状況の中で多聞が和正にもたらしたのは、単なる癒やしではなく生きる意味の再発見だった。
多聞と共にいることで和正の運が向上するという設定は、一見すると非現実的に思える。
だが実際は、多聞という存在が和正に責任感と愛情を思い出させ、それが彼の行動を変化させた結果なのではないかと考えた。
誰かを守りたいという気持ちが人を強くする。
私自身も部活動で後輩の指導を任された時、自分のためだけでなく後輩のために頑張ろうという気持ちが、今まで以上の力を発揮させてくれた経験がある。
多聞が各地で出会う人々の多様性も印象深かった。
外国人の泥棒、富山の夫婦、滋賀の娼婦、島根の猟師、そして熊本の家族。
年齢も職業も境遇も全く異なる人々が、それぞれに深い傷や悩みを抱えている。
この多様性は現代日本社会の縮図でもあり、誰もが何かしらの困難を抱えて生きているという現実を浮き彫りにする。
特に心に残ったのは、島根の猟師・弥一のエピソードだ。
末期がんを患い、長年連れ添った猟犬を失った弥一にとって、多聞は最後の慰めとなる存在だった。
弥一が多聞を「ノリツネ」と名付け、疎遠になった娘の代わりに自分を看取るために来てくれたと信じる場面では、人間の孤独の深さと、それを癒やそうとする心の働きに胸を打たれた。
現代社会では核家族化が進み、地域のつながりも希薄になっている。
そんな中で、多くの人が弥一のような孤独を抱えているのではないだろうか。
私の祖父母も一人暮らしをしており、時々電話で話すと寂しそうな声を聞くことがある。
弥一の物語を読んで、家族や身近な人とのつながりをもっと大切にしなければと反省させられた。
一方で、多聞自身の成長も見逃せない要素だった。
最初は飼い主を失った悲しみに暮れていた多聞が、様々な人との出会いを通して、自分の使命を見つけていく過程は感動的だった。
多聞は決して完璧な存在ではない。
時には迷い、時には間違いを犯す。
しかし、そうした不完全さがあるからこそ、多聞の存在に説得力があるのだと思う。
私たちも完璧である必要はない。
重要なのは、困難に直面した時に諦めずに前進し続けることなのだと、多聞の姿が教えてくれた。
物語の構成も秀逸だった。
各章で異なる人物の視点から語られることで、多聞という存在の多面性が浮かび上がる。
ある人にとっては守り神であり、別の人にとっては家族の一員であり、また別の人にとっては人生最後の友人である。
一つの存在が持つ無限の可能性と、人それぞれの受け取り方の違いを実感した。
これは人間関係においても同じことが言えるだろう。
同じ人物でも、関わる人によって全く違う側面を見せる。
私自身も、家族の前での自分、友達の前での自分、先生の前での自分は微妙に異なる。
それは決して偽りではなく、人間の自然な在り方なのだと理解できた。
最後に、この物語が震災という現実的な背景を持っていることの意味について考えたい。
東日本大震災から10年以上が経過した今でも、その傷跡は完全には癒えていない。
しかし『少年と犬』は、災害がもたらした悲しみや絶望だけでなく、そこから立ち上がろうとする人々の強さや、支え合うことの大切さを描いている。
多聞の旅路は、被災地から始まって全国各地を巡り、最終的に熊本で新たな家族と出会う。
これは災害の記憶を全国で共有し、支え合うことの象徴でもあるのではないだろうか。
私たちは個人として生きているが、同時に社会の一員でもある。
一人ひとりが他者を思いやり、支え合うことで、より良い社会を築いていけるのだと、この物語は訴えかけている。
『少年と犬』を読んで、私は改めて人とのつながりの大切さ、困難に立ち向かう勇気、そして生きることの意味について深く考えさせられた。
多聞のように、周りの人々に希望や癒やしを与えられる存在になりたいと心から思う。
完璧である必要はない。
ただ、誠実に生き、困っている人がいたら手を差し伸べ、自分が困った時は素直に助けを求める。
そんな当たり前のことを大切にしながら、これからの人生を歩んでいきたい。
振り返り
今回は『少年と犬』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説しました。
3つの要点を押さえて、あなた自身の体験や気持ちと重ね合わせながら書くことで、説得力のある感想文が完成するはずです。
大切なのは、物語の要約ではなく「あなたがどう感じたか」を素直に表現することですね。
コピペに頼らず、自分の言葉で書いた感想文は必ず読み手の心に響きます。
今回の例文を参考にしながら、ぜひあなただけの素晴らしい読書感想文を書いてみてください。
きっと素敵な作品が完成しますよ。
※『少年と犬』のあらすじはこちらに掲載しています。


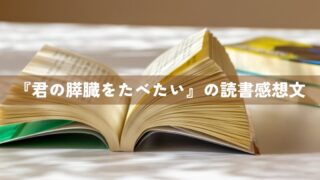
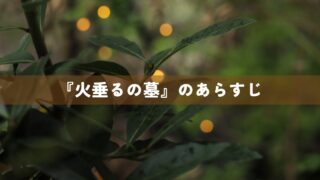

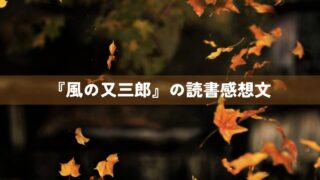



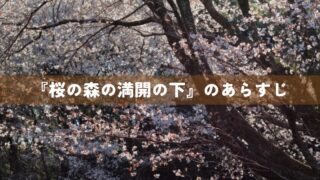
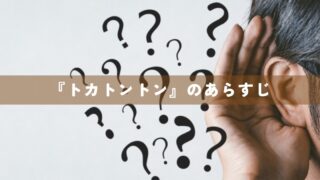

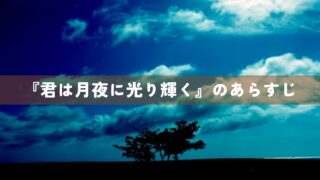

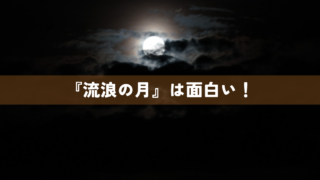

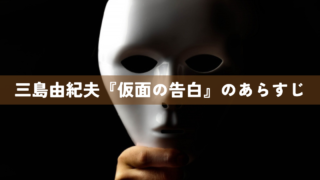



コメント