『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文を書く予定のみなさん、お疲れさまです。
浅倉秋成さんによる話題のミステリー小説『六人の嘘つきな大学生』は、就職活動を舞台にした心理戦が魅力的な作品ですよね。
年間100冊以上の本を読む読書好きの私が、この作品の読書感想文の書き方を丁寧に解説していきます。
書き出しから題名の付け方まで、中学生・高校生のみなさんが参考にできる例文もご用意しました。
コピペは絶対にダメですが、構成や表現方法は大いに参考にしてくださいね。
この記事を読めば、きっと素晴らしい読書感想文が書けるはずですよ。
『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文で触れたい3つの要点
『六人の嘘つきな大学生』で読書感想文を書くなら、以下の3つの要点を押さえておきましょう。
- 嘘と真実が織りなす緊迫した心理戦
- 友情から競争へと変化する人間関係
- 現代社会の就職活動への鋭い風刺
これらの要点について、読みながら「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切です。
感想文で最も重要なのは、あなた自身の感情や考えを素直に表現することですからね。
メモの取り方は簡単です。
読んでいて心が動いた場面では、そのページに付箋を貼って、余白に「怖かった」「悲しかった」「驚いた」などの感情を書き込んでおきましょう。
なぜこの方法が効果的かというと、感想文を書くときに具体的な場面と自分の感情を結び付けて表現できるからです。
それでは、3つの要点をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
嘘と真実が織りなす緊迫した心理戦
『六人の嘘つきな大学生』の最大の魅力は、登場人物たちの心理戦にあります。
就職活動という設定の中で、6人の大学生それぞれが抱える「嘘」や「秘密」が少しずつ明かされていく過程は、読者をハラハラドキドキさせてくれますね。
物語が進むにつれて、最初は好印象だったキャラクターの裏の顔が見えてきたり、逆に印象の悪かった人物の意外な一面が明らかになったりします。
この展開を読んでいて、あなたはどんな気持ちになりましたか?
人間の複雑さや、表面だけでは分からない人の本性について、何か感じることはありませんでしたか?
また、主人公たちが互いを疑い合う場面では、緊張感が伝わってきて息が詰まるような思いをした読者も多いでしょう。
この心理戦の描写について、あなたなりの感想をメモしておくと、感想文を書くときにきっと役立ちますよ。
特に「なぜこのキャラクターは嘘をついたのだろう?」「もし自分がこの状況だったら?」という視点で考えてみると、深い感想が書けるはずです。
友情から競争へと変化する人間関係
物語の冒頭では、6人の大学生たちが協力し合って就職活動に取り組んでいます。
しかし、「内定は1名のみ」というルール変更によって、彼らの関係性は一変してしまいますね。
最初は仲間だったはずの相手が、いつの間にか競争相手になっている。
この変化を読んでいて、あなたはどんなことを感じましたか?
友情と利害関係の狭間で揺れ動く人間の心理は、とてもリアルで考えさせられるものがあります。
現実の世界でも、友達同士が同じ高校や大学を受験したり、同じ部活でレギュラーを争ったりする場面では、似たような心の動きを経験することがありますよね。
登場人物たちの心の変化を追いながら、「友情とは何か?」「競争と友情は両立できるのか?」といった疑問について、あなたなりの答えを見つけてみてください。
また、物語の中で印象に残ったキャラクターの行動や発言があれば、それについてどう思ったかもメモしておきましょう。
「この人の気持ち、分かるなあ」とか「これはひどいと思う」といった素直な感情が、感想文を書くときの貴重な材料になります。
現代社会の就職活動への鋭い風刺
『六人の嘘つきな大学生』は、現代の就職活動が抱える問題を鋭く描いた作品でもあります。
企業側の理不尽なルール変更や、学生たちが「良い顔」をするために嘘をつかざるを得ない状況など、現実の就活でも起こりそうな出来事が描かれています。
この作品を読んで、あなたは将来の就職活動について何か考えることはありませんでしたか?
「こんな選考は不公平だ」と感じたり、「でも実際の就活でも似たようなことがありそう」と不安になったりした人もいるでしょう。
また、登場人物たちが就活のために自分を偽らなければならない状況について、どんな感想を持ちましたか?
「仕方がないことだ」と思うか、「本当の自分を見てもらいたい」と感じるか、人それぞれ異なる意見があるはずです。
この作品を通して見えてくる現代社会の問題について、あなたなりの考えをまとめておくと、深みのある感想文が書けますよ。
さらに、物語の中で描かれる大学生たちの価値観や行動について、「自分だったらどうするか?」という視点で考えてみることも大切です。
正解のない問題だからこそ、あなた自身の価値観や人生観を表現する良い機会になるでしょう。
『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】嘘の向こう側にある真実
『六人の嘘つきな大学生』を読んで、私は「嘘」というものについて深く考えさせられた。
この物語は、IT企業の就職試験を受ける6人の大学生が主人公だ。
最初は協力し合っていた彼らが、「内定は1名のみ」という突然のルール変更で競争相手になってしまう。そして、それぞれが抱える秘密や嘘が次々と暴かれていく展開には、最後までハラハラしながら読んだ。
物語の中で最も印象に残ったのは、登場人物たちの心の変化だった。仲間だと思っていた相手を疑うようになったり、自分の秘密がばれることを恐れて嘘を重ねたりする姿は、とても人間らしくリアルだった。
特に、明るく人気者だった袴田が、実は高校時代の辛い過去を抱えていたことには驚いた。人は見た目や普段の様子だけでは分からないものだと実感した。
また、波多野の行動にも考えさせられることが多かった。彼は「封筒は開けるべきではない」と言い、周りからは真面目すぎると思われていたが、実際は一番深い秘密を抱えていた。この展開を読んで、人を表面的に判断してはいけないと強く思った。
物語に描かれる友情と競争の関係も印象的だった。
6人は最初、お互いを応援し合っていた。ファミレスで対策を練ったり、励まし合ったりする場面には温かさがあった。しかし、「1名のみ」と告げられてからは、その関係が一変する。
友達だった相手を蹴落とさなければならない状況で、彼らの心は大きく揺れ動いた。私はこの部分を読みながら、自分が同じ立場ならどうするかを考えた。友情よりも夢を選ぶのか、それとも競争を避けるのか。
答えは簡単に出せないが、人間関係の難しさや複雑さを学ぶことができた。
また、この作品は現代の就職活動の厳しさも描いている。企業側が急にルールを変えたり、学生が本当の自分を隠して「良い人」を演じたりする場面は、実際にも起こりそうで怖かった。
私はまだ中学生だけど、将来の就職活動について少し不安になった。でも、どんなに厳しい状況でも、自分らしさを失わずにいたいとも思った。
この物語の登場人物たちは皆、何かしらの嘘や秘密を抱えていた。しかしその嘘の奥には、それぞれの事情や思いがあった。
完璧な人間などいないし、誰でも隠したいことの一つや二つはある。大切なのは、相手を一方的に批判せず、その人なりの背景を理解しようとする気持ちなのかもしれない。
『六人の嘘つきな大学生』はミステリーとしても楽しめるが、それ以上に人の心の奥深さを教えてくれる作品だった。この本を通して、私は人との関わり方や、自分自身との向き合い方について考えるきっかけを得た。
これから先、様々な人と出会い、時には競争しなければならない場面もあるだろう。そんなとき、この物語で学んだことを思い出し、相手を理解しようとする心を忘れずにいたい。
『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】人間の多面性と現代社会への警鐘
『六人の嘘つきな大学生』を読み終えて、私の心に最も強く残ったのは、人間という存在の複雑さと多面性についての深い洞察だった。
浅倉秋成氏が描く6人の大学生たちは、それぞれが表の顔と裏の顔を持ち、読み進めるうちに私の印象は何度も覆された。
この作品は単なるミステリー小説ではなく、現代社会を生きる若者たちの心の葛藤と、競争社会の歪みを鋭く描いた社会派作品としても読むことができる。
物語の舞台となる就職活動の最終選考は、まさに現代社会の縮図だった。
最初は協力し合っていた6人が、企業側の一方的なルール変更によって競争相手となり、互いを疑い合うようになる過程には、読んでいて息が詰まるような緊張感があった。
特に印象的だったのは、それぞれのキャラクターが持つ秘密が明かされていく場面だった。
明るくムードメーカー的存在だった袴田の過去、真面目で常識的に見えた波多野の隠された一面、そして他の登場人物たちの意外な秘密。
これらの展開を通して、私は人を外見や第一印象だけで判断することの危うさを痛感した。
私たちは日常生活の中で、つい相手を単純化して捉えがちだ。
「あの人は明るい性格だから悩みなんてなさそう」とか、「真面目そうだから嘘なんてつかない」といった具合に。
しかし、この物語の登場人物たちを見ていると、そうした決めつけがいかに浅はかなものであるかがよく分かる。
袴田の過去を知ったとき、私は彼の普段の明るさが、実は辛い過去を隠すためのものだったのではないかと考えた。
人は時として、本当の自分を守るために仮面を被ることがある。
それを「嘘つき」と断罪するのは簡単だが、その嘘の背景にある事情や心境を理解しようとする姿勢こそが大切なのだと思った。
また、この作品で描かれる友情と競争の関係についても深く考えさせられた。
6人は当初、同じ目標を持つ仲間として結束していた。
ファミレスで集まり、情報交換をしたり、互いの就職活動を応援し合ったりする姿は、理想的な友人関係に見えた。
しかし、「内定は1名のみ」という現実を突きつけられた瞬間、その関係性は一変する。
友達を応援することが、自分の夢を諦めることを意味する状況で、彼らの心は激しく揺れ動いた。
この展開を読みながら、私は自分自身の経験と重ね合わせて考えた。
部活動でのレギュラー争い、定期試験での順位競争、そして将来の大学受験。
友達でありながら同時にライバルでもあるという関係は、高校生の私にとっても身近なテーマだった。
友情と競争は本当に両立できるのだろうか。
この問いに対する明確な答えは見つからないが、少なくとも相手を蹴落としてまで自分が上がろうとするのは健全とは思えない。
真の友情とは、競争の中でも相手の成功を心から祝福できる関係なのかもしれない。
さらに、この作品は現代社会の就職活動が抱える問題を鋭く風刺している点でも注目に値する。
企業側の一方的なルール変更、学生たちが「優秀な人材」を演じるために本当の自分を偽らなければならない現実。
これらの描写は、まさに今の就活生が直面している問題そのものだった。
私も数年後には就職活動を迎えることになる。
そのとき、自分らしさを保ちながら活動できるのかと不安に感じたのも事実だ。
しかし同時に、どんなに厳しい状況でも、自分の価値観や信念を曲げてはいけないという思いも強くなった。
企業が求める「理想の学生像」に無理に自分を当てはめるのではなく、ありのままの自分を受け入れてくれる場所を見つけたい。
それが簡単ではないと分かっていても、嘘や偽りに基づいた成功は本当の幸せをもたらさないと、この物語は教えてくれた。
物語の終盤で明かされる真実には驚かされたが、それ以上に心に残ったのは、登場人物たちがそれぞれ自分なりの答えを見つけていく姿だった。
完璧な解決があるわけではないが、自分の行動に責任を持ち、前に進もうとする彼らの姿勢には感動すら覚えた。
『六人の嘘つきな大学生』は、表面的には就職活動を題材にしたミステリーだが、その本質は人間の心の複雑さと現代社会の矛盾を描いた深い作品だった。
この物語を通して、私は人を見る目の大切さ、友情と競争の関係、そして自分らしく生きることの意味について考えるきっかけを得た。
これから社会に出るまでの間に、さまざまな人と出会い、時には競争し、時には協力していくことになるだろう。
そのとき、この作品で学んだ教訓を忘れずに、相手を理解しようとする心と、自分らしさを大切にする姿勢を持ち続けたい。
人は誰でも完璧ではないし、時に嘘をついてしまうこともある。
でも、その背景にある事情や気持ちに目を向けることで、より深い人間関係を築けるはずだ。
この物語が教えてくれた人間の多面性への理解と、現代社会への批判的視点を胸に、私はこれからの人生を歩んでいきたい。
振り返り
今回は『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文の書き方について詳しく解説してきました。
3つの要点を押さえて、中学生・高校生それぞれのレベルに応じた例文もご紹介しましたね。
大切なのは、物語を読みながら自分がどう感じたかをしっかりとメモしておくことです。
そして、その感情や考えを素直に表現することで、あなただけのオリジナルな感想文が完成します。
例文を参考にしながらも、コピペはせずに、必ずあなた自身の言葉で書いてくださいね。
きっと素晴らしい読書感想文が書けるはずです。
頑張ってください!
※『六人の嘘つきな大学生』の読書感想文を書くのに役立つあらすじや読みどころの解説はこちら。












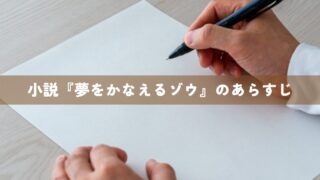
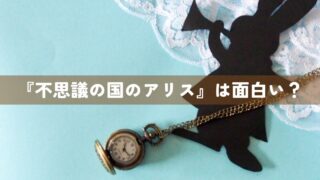




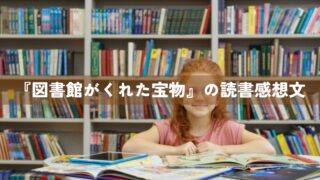

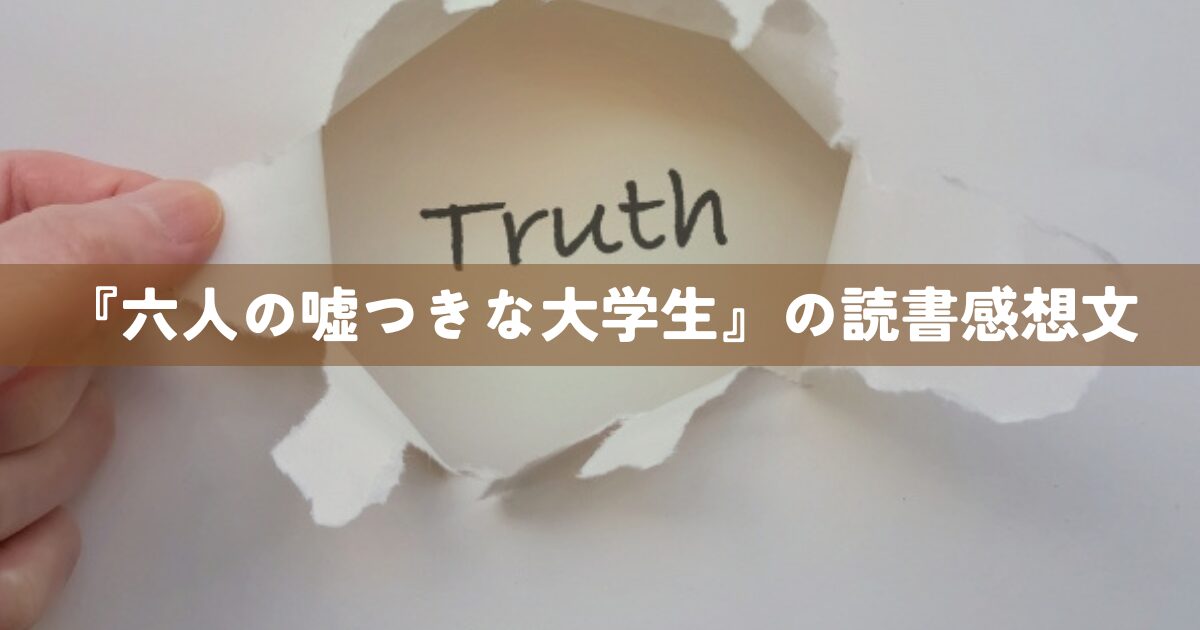
コメント