『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文を書く予定の小学生のみなさん(と親御さん)!
この絵本は髙津修さんと遠藤義人さんが文を担当し、長崎訓子さんが絵を描いた2023年発行の科学絵本ですね。
2024年青少年読書感想文全国コンクール小学校中学年の部の課題図書に選ばれた注目の一冊。
この記事では、読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文の書き方を例文やテンプレートを使って丁寧に説明していきます。
書き出しのコツから題名の付け方まで、小学生でもコピペして使えるような実用的な内容をお届けしますよ。
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文に書くべき3つのポイント
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』で読書感想文を書く場合、以下の3つのポイントを必ず含めるようにしましょう。
- 「音」の正体と身の回りにある音の不思議について
- 耳の構造と音が聞こえる仕組みについて
- 本を読んで気づいたことや今後の生活への活かし方について
これらのポイントを意識して感想文を書くことで、ただの感想に終わらない深みのある読書感想文になりますよ。
読みながら「どんなことを感じたか」「どこが一番印象に残ったか」をメモしておくと、感想文を書くときに役立ちます。
「音」の正体と身の回りにある音の不思議
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』では、音の正体が「空気のふるえ」つまり振動であることを教えてくれます。
大きな音は大きくうねり、高い音は細かく震えているという科学的な仕組みを、イラストを使って分かりやすく説明していますね。
読書感想文では、この「音の正体」について学んだことを自分なりの言葉で説明してみましょう。
たとえば太鼓を叩いたときの「ドーン!」という音や、鳥の「チーチー」という鳴き声など、日常生活で聞こえる様々な音について考えてみてください。
電気自動車のモーター音、電車の通過音、雨の音など、普段は意識しないけれど実は音に囲まれて生活していることに気づいたエピソードを書くと良いでしょう。
音の大きさや高低の違いがどのようにして生まれるのか、波の仕組みについて学んだことも感想文に盛り込んでみてくださいね。
耳の構造と音が聞こえる仕組み
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』で最も驚くのは、耳の複雑で精巧な仕組みかもしれません。
耳介、鼓膜、耳小骨、蝸牛など、音をキャッチして脳に伝えるまでの一連の流れは本当に不思議で興味深いものです。
特に左右の耳に届く音のわずかなズレを脳が感知し、音の方向や場所を判断できる「ステレオ効果」については詳しく書いてみましょう。
読書感想文では、この本を読む前と読んだ後で、音が聞こえることへの見方がどう変わったかを述べると良いですね。
「ただ聞こえているだけだと思っていたけれど、こんなに複雑な仕組みで音が届いていることに感動した」といった気持ちの変化を表現してみてください。
鼓膜や耳小骨、カタツムリのような形をした蝸牛など、耳の不思議な構造に驚いた具体的な点も書いてみましょう。
本を読んで気づいたことや今後の生活への活かし方
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』を読んで、あなたがどんなことに気づいたかを具体的に書いてみましょう。
大きな音を聞きすぎると耳に悪影響があることを知って、「これからはイヤホンを使うときに気をつけたい」といった今後への決意を書くのも良いですね。
動物たちが人間では聞き取れない高い音や低い音を使ってコミュニケーションを取っていることについて、どう感じたかも書いてみてください。
ネズミと猫の関係や、イルカやコウモリの超音波、クジラやゾウの低周波など、動物の音の世界も興味深いトピックです。
学んだ知識を今後の生活でどう活かしていきたいか、具体的な行動や心がけを書くと感想文に深みが出ますよ。
普段当たり前だと思っていた「聞く」という行為が、どれほど貴重で素晴らしいことなのかを再認識した感想で締めくくると、より深い読書感想文になるでしょう。
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文のテンプレート
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文を楽に書けるよう、以下のテンプレートを用意しました。
ステップ1~6の空欄を埋めるだけで、しっかりとした読書感想文が完成しますよ。
- 【書き出し】この本を読んだきっかけや最初の印象を書く
- 【音の正体について】空気の振動という音の仕組みについて学んだことを書く
- 【耳の仕組みについて】耳の構造や音が聞こえるメカニズムで驚いたことを書く
- 【気づきと変化】この本を読んで気づいたことや考えが変わったことを書く
- 【今後への活かし方】学んだことを今後の生活でどう活かすかを書く
- 【まとめ】全体を通して感じたことや読書の価値について書く
ステップ1:書き出し
私は( )という理由で『聞いて聞いて!音と耳のはなし』を読みました。
最初は( )と思っていましたが、読み始めると( )でした。
ステップ2:音の正体について
この本で一番驚いたのは、音の正体が( )だということです。
普段聞いている( )という音も、実は( )なんだと知りました。
ステップ3:耳の仕組みについて
耳の仕組みで特に興味深かったのは( )です。
( )という部分が( )する仕組みに驚きました。
ステップ4:気づきと変化
この本を読んで、( )ということに気づきました。
今まで( )と思っていたことが、実は( )だったのです。
ステップ5:今後への活かし方
学んだことを活かして、これからは( )したいと思います。
特に( )については( )していこうと決めました。
ステップ6:まとめ
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』を読んで、( )ということを学びました。
この本は私に( )を教えてくれた大切な一冊です。
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】音の世界への気づき
私は『聞いて聞いて!音と耳のはなし』を読んで、毎日当たり前のように聞こえてくる音が、実はとても不思議なものだと気づいた。
読む前は、音はただ空気中を飛んでくるものだと思っていた。でも、音の正体は「空気のふるえ」、つまり振動だと知り、とても驚いた。
太鼓を叩くと「ドーン!」と鳴るのは、太鼓の皮がふるえ、周りの空気も一緒にふるえ、その波が広がるからだ。車のブーンという低い音はゆっくり大きなふるえで、鳥のチーチーという高い鳴き声は細かく速いふるえなのだと分かった。
身の回りを意識して聞いてみると、冷蔵庫のモーター音や時計のチクタクなど、普段気にしていなかった音に囲まれていることも分かった。
耳の仕組みについても、この本は詳しく教えてくれた。音をキャッチする耳介から鼓膜、耳小骨、蝸牛までが連携して音を脳に伝える仕組みは、まるで魔法のようだった。特に驚いたのは、カタツムリのような形をした蝸牛の中に多くのセンサーがあり、ふるえの大きさや速さによって違う場所が刺激されることだった。左右の耳に届く音のわずかなズレを脳が感知して方向や距離を判断するステレオ効果についても興味深かった。
また、大きな音を聞きすぎると耳の細胞が傷つき、一度壊れると元に戻らないことも学んだ。これからはイヤホンで音楽を聞くときに音量を小さくしたり、時間を短くしたりして耳を大切にしたいと思った。
動物たちが人間には聞こえない高音や低音でコミュニケーションしていることも面白かった。ネズミが高い声で仲間に合図を送るが、その声が猫によく聞こえてしまうという話には驚いた。
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』を読んで、普段当たり前だと思っていた「聞く」という行為が、複雑で素晴らしい仕組みで成り立っていると知ることができた。これからは身の回りの音に耳をすませ、音の世界をもっと楽しんでいきたいと思う。
『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文の例文(1200字の小学生向け)
【題名】聞こえる奇跡への感謝
私は『聞いて聞いて!音と耳のはなし』という本を読んで、毎日当たり前のように聞こえてくる「音」が、実はとても不思議で貴重なものだと気づいた。
この本は、身近な「音」と、その音を聞き取る「耳」の仕組みを、とても分かりやすく教えてくれる科学絵本だった。読む前は、音や耳の仕組みは難しい話ばかりだろうと思っていたが、カラフルな絵や問いかけに引き込まれ、まるで音の世界をめぐる冒険をしているような気分になった。
まず一番驚いたのは「音」の正体についてだった。今まで私は、音は空気の塊が飛んでくるものだと思っていた。でも実際には「空気のふるえ」、つまり「振動」なのだ。太鼓を叩くと「ドーン!」と鳴るのは、太鼓の皮がふるえ、その振動が波のように広がるからだと知ったとき、本当に驚いた。
考えてみると、車のブーンという低い音はゆっくり大きなふるえで、鳥のチーチーという高い鳴き声は細かく速いふるえだ。風のヒューという音や木のガサガサという音も、全部ちがうふるえの波なのだと思うと、身の回りの音が一気に新鮮に感じられた。
そして、耳の仕組みもとても面白かった。耳はただの穴ではなく、音を集めて脳に伝える複雑な装置だ。耳介が音を集め、鼓膜がふるえ、さらに小さな三つの耳小骨がそのふるえを大きくして蝸牛に伝える。カタツムリの形をした蝸牛の中には多くのセンサーがあり、振動の種類によって違う場所が反応する。その刺激が脳に届いて初めて私たちは「音」として感じるのだ。この仕組みを知って、一つの音の裏にこれほど多くの働きがあるのかと感動した。
左右の耳に届く音のわずかなズレから方向や距離を判断するステレオ効果についても、とても興味深かった。日常の「聞く」という行為の裏で、こんな高度な働きがあるのだと気づかされた。
さらに、大きな音を聞きすぎると耳の細胞が傷つき、二度と元に戻らないことも学んだ。お父さんとお母さんに「イヤホンの音を大きくしすぎないように」と言われていたが、その理由がよく分かった。これからは音量を小さくしたり、聞く時間を短くしたりして、自分の耳を守ろうと思った。
また、動物たちが人間には聞こえない音を使って生活していることも面白かった。ネズミが高い声で仲間に合図を送るが、それは猫には聞こえてしまうという話は驚きだった。イルカやコウモリが高い周波数の音でやり取りし、クジラやゾウが低い声を遠くまで届けるという話も、自然の神秘を感じさせてくれた。
この本を読んでから、風のそよぎや時計のチクタク、遠くのクラクションなど、普段の音がすべて新しい意味を持って聞こえるようになった。『聞いて聞いて!音と耳のはなし』は、私に「ものの見方」と「学ぶ楽しさ」を教えてくれた宝物の一冊だ。当たり前だと思っていたことが、実はとても尊いものだと知り、これからも「どうして?」と問いかけながら多くのことを学んでいきたい。
振り返り
今回は『聞いて聞いて!音と耳のはなし』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
音と耳という科学的なテーマでも、3つのポイントを意識すれば素晴らしい読書感想文が書けることがお分かりいただけたでしょう。
テンプレートや例文を参考にしながら、あなた自身の感じたことや気づいたことを大切にして感想文を書いてみてくださいね。
きっと、読む人の心に響く素敵な読書感想文が完成するはずです。
がんばって書いてみてください!
※『聞いて聞いて!音と耳のはなし』のあらすじはこちらでご紹介しています。





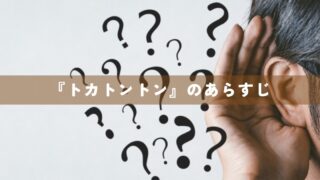

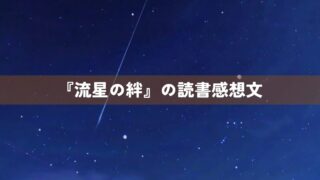
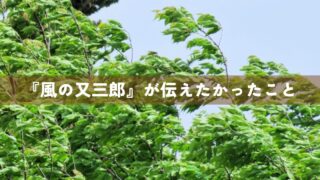
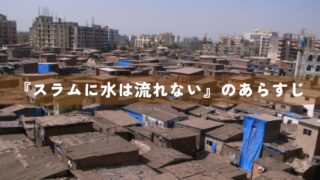

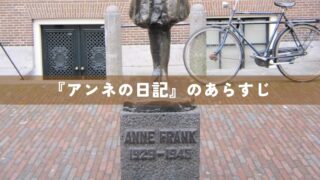



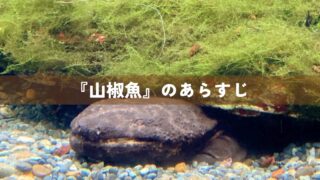


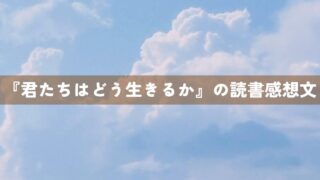

コメント