『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文を書こうと思っている中高生のみなさん、こんにちは。
青谷真未さんによる『読書嫌いのための図書室案内』は、2020年に早川書房から発刊された青春ビブリオミステリー小説です。
読書嫌いの高校2年生・荒坂浩二が図書委員になり、廃刊されていた図書新聞の再刊を任されることから始まる物語で、読書への苦手意識を持つ人にこそ読んでほしい作品として話題になりました。
今回は年間100冊以上の本を読む私が『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文の書き方を、例文や題名、書き出しのコツも含めて詳しく解説していきますよ。
中学生・高校生の皆さんがコピペに頼らず、自分らしい感想文を書けるようサポートしていきます。
『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文で触れたい3つの要点
『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要な要点が3つあります。
読書感想文では、ただあらすじを書くのではなく、物語の核心部分について「自分はどう感じたか」を書くことが大切です。
以下の3つのポイントについて、読みながらメモを取っておきましょう。
- 読書嫌いの主人公・荒坂浩二の心境の変化
- 図書室や本を通じた人間関係の描かれ方
- 読書の意味や価値についての新しい気づき
メモを取るときは「なぜそう感じたのか」「自分の体験と似ている部分はあるか」「今まで考えたことがなかった視点はどこか」といった観点で書いてみてください。
感想文で最も重要なのは「どう感じたか」の部分だからです。
それでは、3つの要点を詳しく見ていきましょう。
読書嫌いの主人公・荒坂浩二の心境の変化
物語の主人公である荒坂浩二は、最初から最後まで完全に「読書好き」になるわけではありません。
しかし、図書委員として図書新聞の再刊に取り組む中で、読書や本に対する見方が少しずつ変わっていきます。
「本なんて面倒くさい」と思っていた荒坂が、なぜ変化していったのでしょうか。
読書好きの同級生・藤生蛍との出会い、図書新聞のための感想文集めを通じた様々な人との交流、そして隠された学校の秘密を探る過程で、荒坂は読書の新たな面を発見していきます。
この変化の過程で、あなた自身が共感した部分や驚いた部分はありましたか。
読書に対する苦手意識を持つ人なら、荒坂の気持ちに重ねて感じる場面が多いはずです。
逆に、読書が好きな人でも、荒坂の視点から読書の別の側面を発見できるかもしれません。
荒坂の変化について書く際は、自分の読書体験と比較しながら考えてみましょう。
図書室や本を通じた人間関係の描かれ方
『読書嫌いのための図書室案内』では、図書室という空間が単なる本を読む場所ではなく、人と人をつなぐ重要な舞台として描かれています。
荒坂と藤生蛍のコンビ、感想文を依頼される生徒や先生たち、そして司書の河合先生など、登場人物たちはみな本や読書を通じてつながっていきます。
特に注目したいのは、読書感想文を書いてもらう際に出される不可解な条件です。
緑川彰人が本のタイトルを隠して「当ててみて」と言ったり、樋崎先生が特別な要求をしたりする場面は、単なる課題のやり取りを超えた深い人間関係を表しています。
これらの条件の背景には、それぞれのキャラクターが抱える秘密や過去の出来事が隠されているのです。
あなたは学校生活の中で、本や読書をきっかけに誰かと深い話をしたことはありますか。
図書室という場所に対して、この物語を読む前と後で印象が変わったでしょうか。
本が人と人をつなぐ架け橋になるという描写について、自分なりの感想を書いてみましょう。
読書の意味や価値についての新しい気づき
作中で藤生蛍が語る「裏読み(深読み)」という考え方は、読書の新しい楽しみ方を示しています。
藤生蛍は
いろんな考え方ができるように。他人の言葉をひとつの意味にしか解釈できないと苦しくなってしまうから、逃げ道をたくさん作っておけるように。
■引用:『読書嫌いのための図書室案内』
と、このように説明します。
これは読書の技術的な話にとどまらず、現実世界での人間関係や困難な状況を乗り越える知恵としても描かれています。
また、司書の河合先生が荒坂に図書新聞の復刊を頼む際の「本に興味がない人の気持ちがわからない」といったニュアンスの発言も印象的。
読書好きと読書嫌いの人が互いの視点を理解し合うことの大切さが表現されていますよね。
あなたにとって読書とは何でしょうか。
この物語を読んで、読書に対する考え方や感じ方に変化はありましたか。
読書感想文を書くという行為自体についても、新たな発見があったかもしれません。
自分なりの読書観や、この作品から得られた気づきについて整理してみましょう。
『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】本との新しい向き合い方
『読書嫌いのための図書室案内』を読んで、今まで読書に対して持っていた固定観念が大きく揺らいだ。主人公の荒坂浩二と同じように、私も読書が好きではなく、本を読むことに少し苦手意識を持っていたからである。
荒坂が図書委員になり、しぶしぶ図書新聞の再刊に取り組む姿は、まるで自分のことのように感じられた。「好きな本は特にない」と正直に答える場面では、私も同じことを言ってしまいそうだと思った。読書好きに囲まれると、何となく居心地が悪くなる気持ちがよく分かる。
しかし物語が進むにつれて、荒坂の考え方が少しずつ変わっていく過程に引き込まれた。特に印象的だったのは、読書好きの藤生蛍との出会いである。蛍は本の話になると目をキラキラ輝かせて語る少女で、最初は荒坂との間に大きな溝があるように見えた。しかし、図書新聞を一緒に作る中で、お互いの違いを認め合いながら協力していく姿が素敵だった。
私が最も心を動かされたのは、蛍が語る「裏読み(深読み)」という考え方である。「現実に嫌な人が現れても、たくさん裏読みをすることで『何か理由があるのかも』と思える」という言葉は、読書の技術を超えて、人間関係を円滑にする知恵だと感じた。私は今まで本を読むことは単なる娯楽だと思っていたが、この物語を通じて、読書が現実を生きる力になることを知った。
図書新聞のために感想文を集める場面では、荒坂が様々な人と関わり、それぞれの秘密や悩みに触れていく。緑川彰人が本のタイトルを隠して「当ててみて」と言ったり、樋崎先生が特別な条件を出したりする背景には、深い理由があることが次第に明かされていった。私はこの展開を読みながら、普段何気なく接している人たちにも、それぞれ様々な思いや過去があることを改めて実感した。
荒坂は最後まで完全な読書好きにはならない。それでも読書や本に対する見方は確実に変わっていく。この変化が無理なく描かれているところに親近感を覚えた。急に本好きになったら嘘くさく感じるだろうが、少しずつ本との距離が縮まっていく過程はとてもリアルで説得力がある。
図書室という場所についても、この物語を読んで印象が変わった。今まで図書室は静かで少し近寄りがたい場所だと思っていたが、実は人と人がつながる温かい空間でもあるのだと気づいた。司書の河合先生が荒坂に図書新聞の復刊を頼む際の言葉も印象的だった。「本に興味がない人の気持ちがわからないから」という理由で読書嫌いの荒坂に任せるという発想は、新鮮でとても良い。
この本を読んで、読書嫌いでも恥ずかしくないし、それぞれに合った本との向き合い方があるのだと学んだ。無理に読書好きになる必要はないが、本を完全に避けるのももったいないかもしれない。荒坂のように自分なりのペースで本と付き合っていけばいいのだと思う。
次に図書室に行くときは、少し勇気を出して新しい本を手に取ってみたい。読書感想文を書く課題も、ただの宿題ではなく、自分の気持ちを整理する大切な機会として捉えられるようになった気がする。
『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】読書嫌いから見えてきた本当の読書の意味
『読書が嫌いです』と堂々と言うことは、なぜか少し後ろめたい気持ちになる。世間では読書は良いことだとされ、本を読まない人は教養がないと思われがちだからだ。私も読書に対して複雑な感情を抱いていた一人である。そんな私が『読書嫌いのための図書室案内』を手に取ったのは、タイトルに惹かれたからだ。読書嫌いのための本なら、きっと私の気持ちを理解してくれるだろうと思った。
主人公の荒坂浩二は、私と同じ高校二年生の読書嫌いだ。部活を辞め図書委員になり、廃刊されていた図書新聞の再刊を任される。「好きな本は特にありません」と正直に答える荒坂に強い共感を覚えた。読書好きに囲まれた時の居心地の悪さや、本について語れない自分への劣等感はまさに私が感じていたものと同じだった。
しかし物語は単純に読書嫌いを肯定する話ではない。荒坂が図書新聞制作を通じて様々な人と関わり、読書や本に対する見方を少しずつ変えていく過程が丁寧に描かれている。特に印象的だったのは、読書好きの同級生・藤生蛍との関係だ。蛍は本の話になると目を輝かせる少女で、最初は荒坂との間に大きな溝があるように見えた。しかし、図書新聞を一緒に作る中で、お互いの違いを認め合いながら協力していく姿が美しく描かれている。
蛍が語る「裏読み(深読み)」という考え方は私にとって新鮮な発見だった。「現実に嫌な人が現れても、たくさん裏読みすることで『何か理由があるのかも』『前向きに受け止めよう』と思える。いろんな考え方ができるように」という言葉は、読書の技術を超え、人間関係や現実を生きる知恵として響いた。私は今まで物事を一つの視点からしか見られず、それが自分を苦しめることもあった。蛍の言葉は読書が現実を生きる道具になり得ることを教えてくれた。
図書新聞のために感想文を集める過程で描かれる人間関係の複雑さも興味深い。緑川彰人が本のタイトルを隠して「当ててみて」と言ったり、樋崎先生が特別な条件を出したりする背景には、それぞれ深い理由や過去の出来事が隠されている。これらのエピソードを通じ、私は普段何気なく接している人たちにも様々な思いや秘密があることを改めて実感した。本や読書が人の内面に触れるきっかけになることもあるのだと知った。
司書の河合先生が荒坂に図書新聞の復刊を頼む際の言葉も印象的だった。「本に興味がない人の気持ちがわからないから、読書をしない荒坂くんに、本に興味がない人も手に取ってもらえる新聞を作ってもらいたい」という理由は、読書好きと読書嫌いの人が互いの視点を理解し合う大切さを示している。この発想は私にとって目から鱗だった。読書嫌いであることが逆に価値ある視点を提供できることもあると気づかされた。
物語の中で描かれる学校生活のリアリティも心に残った。蛍がクラスメイトに上履きを隠されるいじめの場面や、学校という閉鎖的な環境での息苦しさは多くの高校生が感じている現実だろう。そんな中、荒坂が蛍を助け二人の関係が深まっていく過程は、読書や本を超えた人間としての成長を描いている。
私が最も印象に残ったのは、荒坂が最後まで完全な読書好きにはならないことだ。劇的な変化ではなく、少しずつ本との距離が縮まっていく過程が丁寧に描かれている。これは非常にリアルで説得力があった。もし荒坂が急に文学オタクになったら嘘くさく感じただろう。読書嫌いから読書好きへの完全な転換ではなく、新しい向き合い方を見つける結論は、私のような読書に苦手意識を持つ人にとって希望があるメッセージだった。
図書室に対する見方も変わった。今まで図書室は静かで近寄りがたい場所だと思っていたが、実は人と人がつながる温かい空間でもあるのだと気づいた。本を通じて様々な人の思いに触れ、深い人間関係を築く場所として描かれている図書室は、とても魅力的に見えた。
この物語を読んで、私は読書に対する固定観念から解放された気がする。読書嫌いでも恥ずかしくないし、それぞれに合った本との向き合い方があると学んだ。無理して読書好きになる必要はないが、本を完全に避けるのももったいない。荒坂のように自分なりのペースで本と付き合っていけばいいと思う。
読書感想文を書くことについても新たな発見があった。今まで読書感想文は面倒な宿題と思っていたが、自分の気持ちを整理し成長を言葉にする大切なプロセスだと気づいた。この感想文を書いている今も、物語について考えることで自分の読書観が少しずつ変わっていることを感じる。
次に図書室に行く時は、少し勇気を出して新しい本を手に取ってみたい。読書嫌いの私にも、きっと心に響く一冊があるはずだ。『読書嫌いのための図書室案内』はそんな希望を与えてくれた素晴らしい作品である。読書の本質的な意味や価値を考えさせられると同時に、読書嫌いでも読書と向き合う方法があることを教えてくれた。これからは読書を義務ではなく、自分を変えたり人とつながったりするための手段として捉えていこうと思う。
振り返り
『読書嫌いのための図書室案内』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つの要点を参考に、あなた自身が物語を読んで感じたことを大切にしながら感想文を書いてみてください。
読書感想文の題名や書き出しで悩んだ時は、今回の例文を参考にしても構いません。
ただし、コピペではなく、必ず自分の言葉で表現することが重要です。
中学生・高校生の皆さんそれぞれの年齢に応じた語彙や表現を使って、等身大の感想を書くことが一番の近道です。
『読書嫌いのための図書室案内』は、読書に苦手意識を持つ人にこそ読んでほしい作品です。
きっとあなたにとっても、読書や本との新しい向き合い方を発見する良いきっかけになるでしょう。
自分らしい感想文を書いて、読書の新たな魅力を見つけてくださいね。
※『読書嫌いのための図書室案内』のあらすじはこちらでご紹介しています。


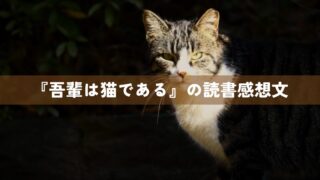
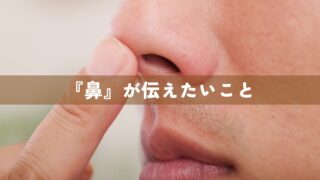
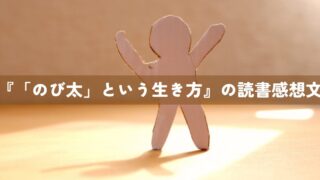






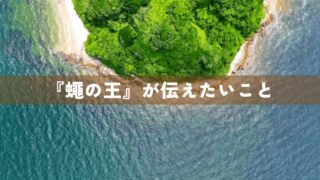

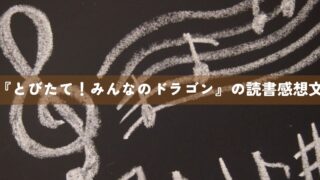


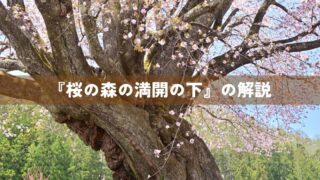
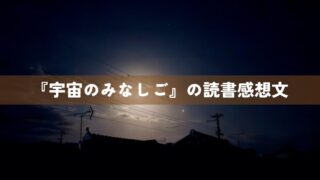

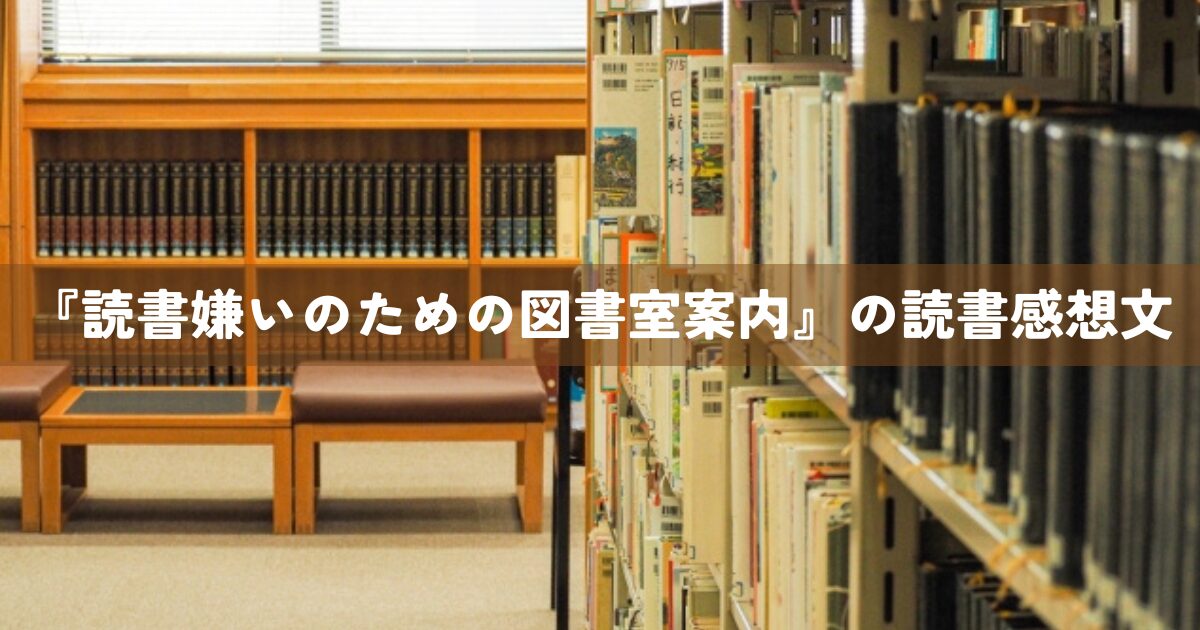
コメント