『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文を書く予定の学生さん、お疲れさまです。
椎野直弥さんの『僕は上手にしゃべれない』は、吃音に悩む中学1年生の柏崎悠太が放送部に入部し、周囲の支えによって少しずつ成長していく感動的な青春物語ですね。
この作品は、作者自身の吃音体験をもとに書かれており、同じ悩みを抱える人々に勇気を与える素晴らしい読み物として話題になりました。
読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、小学生・中学生・高校生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、ごゆっくりお付き合いください。
テンプレートを参考にしながらも、オリジナルの感想文を作れるよう丁寧に指導していきますね。
『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文で触れたい3つの要点
『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文を書く際には、以下の3つの重要な要点について「自分はどう感じたか?」をメモしておくことが大切です。
- 吃音という障害に対する理解と共感
- 言葉にできない想いを伝える方法
- 人とのつながりが与える成長の力
これらの要点について感じたことをメモする時は、付箋紙に短い言葉で書き留めるか、ノートに箇条書きで記録しておくと便利ですよ。
「自分(あなた)がどう感じたか?」という感情の記録が感想文の核になります。
読書感想文は単なる物語の要約ではなく、皆さんが読んで何を考え、何を感じたかを伝える文章だからですね。
それでは、これら3つの要点について詳しく見ていきましょう。
吃音という障害に対する理解と共感
主人公の悠太が抱える「吃音」という症状について、皆さんはどのような印象を受けましたか?
吃音は単なる話し方のクセではなく、本人にとって非常につらい症状であることが作品を通じて丁寧に描かれています。
入学式で自己紹介ができずに教室から逃げ出してしまう悠太の気持ちや、人前で話すことへの恐怖心について、皆さんはどう感じたでしょうか。
「私も人前で話すのが苦手だから、悠太の気持ちがよくわかった」と感じる人もいれば、「吃音の大変さを初めて知った」と思う人もいるでしょう。
このような皆さんの率直な気持ちこそが、読書感想文で一番大切な部分なのです。
また、吃音によって生まれる孤独感や自己嫌悪についても、作品では真摯に向き合っています。
悠太が感じる「普通じゃない」という思いや、周囲からの視線に対する恐怖について、皆さんはどのような感想を持ちましたか?
言葉にできない想いを伝える方法
『僕は上手にしゃべれない』では、「言いたいことがあるのに、言葉にできない」という悠太の葛藤が描かれています。
しかし、言葉以外にも気持ちを伝える方法があることを、作品は教えてくれますね。
悠太が放送部でアニメの台本を使った発声練習をしたり、文章で自分の想いを表現したりする場面で、皆さんはどんなことを感じましたか?
「話すこと以外にも、相手に気持ちを伝える方法があるんだ」と気づいた人もいるでしょう。
また、古部さんや立花先輩が悠太の気持ちを理解し、言葉の裏にある本当の想いを読み取ろうとする姿勢についても考えてみてください。
相手の気持ちを理解するためには、言葉だけでなく、表情や行動からもメッセージを受け取ることが大切だということを学べたのではないでしょうか。
このような「言葉を超えたコミュニケーション」について、皆さんの体験や考えを交えながら感想文に書いてみると、とても深みのある内容になりますよ。
人とのつながりが与える成長の力
悠太は最初、吃音を理由に他人との関わりを避けてきました。
しかし、放送部の仲間や家族、先生たちとの出会いによって、少しずつ心を開き、成長していく姿が描かれています。
特に古部さんとの友情や、立花先輩の優しさ、家族の温かい支えについて、皆さんはどのような印象を受けましたか?
「周りの人の支えがあれば、困難なことも乗り越えられるんだ」と感じた人が多いのではないでしょうか。
また、悠太が他の人の痛みや悩みにも気づいていく過程も重要なポイントです。
自分だけでなく、みんなそれぞれに苦しみや悩みを抱えていることを知った悠太の変化について、どう思いましたか?
人とのつながりの中で、相手を理解し、支え合うことの大切さを学んだ体験が皆さんにもあるかもしれませんね。
そのような実体験と重ね合わせながら感想を書くと、説得力のある文章になります。
悠太が最終的に弁論大会に出場する決意を固める場面では、彼が得た勇気や成長について深く考えてみてください。
※『僕は上手にしゃべれない』のあらすじや内容はこちらで簡単に短くご紹介しています。

『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文のテンプレート
『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文が楽に書けるようにテンプレートをご用意しました。
このテンプレートは、中学生や高校生向けに、上記の3つの要素を取り入れて作品のテーマを深く掘り下げられるように構成されています。
ステップ1:導入(150字〜200字)
なぜこの本を読もうと思ったのか、読む前の「吃音」や主人公に対するイメージを正直に書きます。
* この本を手に取ったのは、タイトルに強く惹かれたからです。人と話すことが得意ではない自分にとって、「上手にしゃべれない」という言葉はどこか共感できる響きがありました。
* 読む前は、吃音という症状が、単なる話し方の問題だと漠然と思っていました。しかし、この本を読んで、それがどれほど深い心の苦しみを生むかを知ることになりました。
ステップ2:本論(600字〜700字)
以下の3つのポイントについて、それぞれ自分の考えや感想を深めていきましょう。
1. 吃音という障害に対する理解と共感
主人公が吃音によってどれだけ苦しんでいるかを具体的に書きます。
* 主人公は、自分の名前を言うことさえ難しく、いつも言葉に詰まることに恐怖を感じています。この場面を読んで、言葉が出ないことの辛さだけでなく、周りの目が気になることで心がどんどん閉じていく様子が伝わってきました。
* 私も人前で発表する時に緊張してうまく話せないことがありますが、主人公の抱える苦しみは、その何倍も大きいものだと感じました。
2. 言葉にできない想いを伝える方法
言葉以外で気持ちを伝えることの大切さについて考察します。
* 主人公はうまく話せませんが、手紙を書くことや、誰かのために行動することを通して、自分の気持ちを伝えています。言葉がなくても、彼の優しさや想いが周りの人に届いている様子が、とても心に残りました。
* 「言葉だけがすべてではない」というメッセージが強く伝わってきました。相手の表情や行動、書かれた文章から気持ちを読み取る大切さを、この本は教えてくれたように思います。
3. 人とのつながりが与える成長の力
主人公が、周りの人との関わりを通してどう変わっていくかを書きます。
* 主人公は吃音を隠すために、人と関わることを避けてきました。しかし、彼のことを理解しようとしてくれる先生や、ありのままを受け入れてくれる友達との出会いが、彼の心を少しずつ開いていきます。
* 完璧に話せなくても、自分のことを受け入れてくれる人がいることの安心感や、人とのつながりが、自分を強くしてくれることを学びました。彼が最後に前を向いて歩き始める姿は、人と心を通わせることの素晴らしさを教えてくれます。
ステップ3:まとめ(150字〜200字)
この本を読んで、今後の自分の生き方や考え方がどう変わったかをまとめます。
* この本を読んで、私は「上手にしゃべること」よりも、相手の気持ちを想像しながら「心で聞くこと」が大切だと気づきました。
* これからは、自分の気持ちを伝える時も、無理に完璧な言葉を探すのではなく、ありのままの自分を表現していこうと思います。そして、困っている人がいたら、その人の言葉にならない想いを理解しようと努めたいです。
『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】悠太から教わった大切なこと
私は椎野直弥さんの『僕は上手にしゃべれない』を読んだ。
この本は、中学1年生の柏崎悠太という男の子のお話である。
悠太は吃音という病気で、言葉がうまくしゃべれない。
そのせいで学校の入学式では自己紹介ができずに、教室から逃げてしまった。
私は悠太のこの場面を読んで、とても悲しい気持ちになった。
話したいことがあるのに、うまく話せないのはとてもつらいと思う。
私も人前で話すのが苦手なので、悠太の気持ちが少しわかった。
でも私は普通に話せるから、悠太の方がもっともっと大変だと感じた。
悠太は放送部に入って、話す練習を始めた。
放送部の古部さんや立花先輩は、悠太のことを笑ったりしない。
みんな優しくて、悠太を応援してくれる。
私はこの場面を読んで、友達の大切さがよくわかった。
困っている人を助けてくれる友達がいると、頑張れるんだなと思った。
悠太の家族も素敵だった。
お母さんやお姉さんは、悠太が吃音で悩んでいることを理解して、いつも支えてくれる。
私の家族も私のことを応援してくれるから、悠太の気持ちがよくわかった。
家族に愛されていると安心できるし、勇気も出てくるのだと思う。
この本を読んで、話すことだけがコミュニケーションじゃないということも学んだ。
悠太は言葉がうまく出なくても、一生懸命気持ちを伝えようとしていた。
相手のことを思う気持ちがあれば、きっと伝わるのだと感じた。
私も今度から、友達が困っているときは優しくしてあげたいと思った。
そして、自分が苦手なことがあっても、あきらめないで頑張りたい。
悠太のように、少しずつでも成長していけたらいいなと思う。
『僕は上手にしゃべれない』は、勇気をくれる本だった。
みんなそれぞれ苦手なことがあるけれど、周りの人と支え合えば大丈夫だということがわかった。
私もこれから、自分らしく頑張っていきたい。
『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】言葉を超えた想いの力
『僕は上手にしゃべれない』には考えさせられることがたくさんあった。
この作品は、吃音という障害を持つ中学1年生の柏崎悠太が、放送部での活動を通じて少しずつ成長していく物語である。
悠太が入学式の自己紹介で言葉が出ずに教室から逃げ出してしまう場面は、読んでいてとても胸が痛くなった。
私も人前で話すことは得意ではないが、悠太の抱える困難はそれとは比べ物にならないほど深刻で、想像するだけでつらくなった。
吃音という障害について、私はこの本を読むまで詳しく知らなかった。
単に「どもる」というだけではなく、本人にとってはコミュニケーションを取ること自体が恐怖になってしまう、とても深刻な問題なのだと理解した。
悠太が感じている孤独感や、「普通じゃない」という自己嫌悪は、読んでいて本当につらかった。
しかし同時に、私たちの身の回りにも、見た目ではわからない困難を抱えている人がいるかもしれないと考えるようになった。
放送部に入った悠太を支える周囲の人々の存在が、この物語の一番素晴らしい部分だと感じた。
古部さんは無表情で近寄りがたい印象だったが、悠太の吃音を決して笑わず、一緒にアニメの台本で練習してくれた。
立花先輩も受験勉強で忙しい中、後輩である悠太のことを気にかけてくれた。
椎名先生も悠太の気持ちを理解し、温かく見守っていた。
このような人間関係を見ていると、人は一人では生きていけないし、誰かの支えがあるからこそ困難を乗り越えられるのだと強く感じた。
私の周りにも、困っているクラスメートがいたら、古部さんや立花先輩のように手を差し伸べられる人間になりたいと思った。
この作品で最も印象的だったのは、「言葉にできない想いをどう伝えるか」というテーマである。
悠太は話すことは苦手だが、心の中にはたくさんの想いを抱えている。
放送部での練習や、文章を書くことで、少しずつ自分の気持ちを表現する方法を見つけていく姿に感動した。
また、古部さんや家族が悠太の言葉にならない気持ちを理解しようと努力する姿も美しかった。
真のコミュニケーションとは、単に流暢に話すことではなく、相手の気持ちに寄り添い、理解しようとすることなのだと学んだ。
私自身も、友達との会話で相手の表情や雰囲気から気持ちを読み取ることの大切さを改めて感じた。
悠太が最終的に弁論大会への出場を決意する場面は、彼の大きな成長を表していると思う。
吃音という困難と向き合いながらも、自分の想いを人に伝えたいという気持ちが勝ったのだろう。
この場面を読んで、私も自分の苦手なことから逃げずに挑戦していきたいと強く思った。
『僕は上手にしゃべれない』は、障害や困難を抱える人への理解を深めてくれただけでなく、人とのつながりの大切さ、そして自分らしく生きることの意味を教えてくれた作品だった。
これからも悠太のように、周りの人への感謝を忘れずに、自分の道を歩んでいきたい。
『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】声なき声に耳を傾けて
『僕は上手にしゃべれない』を読み終えた時、私の胸には感動と同時に、これまで気づかなかった多くのことへの反省が込み上げてきた。
この作品は、吃音という言語障害を抱える中学1年生の柏崎悠太が、放送部での活動を通じて自分自身と向き合い、周囲の人々との関係の中で成長していく物語である。
作者自身が吃音の体験を持つということもあり、主人公の心の動きや苦悩が非常にリアルに描かれており、読み手の心に深く響く作品となっている。
物語の冒頭で悠太が入学式の自己紹介で言葉を発することができず、教室から逃げ出してしまう場面を読んだ時、私は強いショックを受けた。
私たちが何気なく行っている「話す」という行為が、悠太にとってはこれほどまでに困難で恐怖に満ちたものだったのかと思うと、胸が締め付けられるような思いだった。
吃音という障害について、恥ずかしながら私はこの本を読むまで深く考えたことがなかった。「どもる」ということを単純な話し方の特徴として捉えていた自分の浅はかさを痛感した。
悠太が感じている孤独感、周囲からの視線への恐怖、「普通」になりたいという切実な願い、そして自分を責める気持ちなど、その内面の複雑さと深刻さを知り、私は自分の無知が恥ずかしくなったほどだ。
同時に、私たちの社会がいかに「普通」であることを前提として成り立っているか、そしてその「普通」から外れた人々がどれほどの困難を感じているかについても考えさせられた。
しかし、この物語の真の価値は、悠太を取り巻く人々の存在にあると私は感じた。
古部加耶という同級生の女の子は、一見冷たそうな印象を与えるが、悠太の吃音に対して一度も笑ったり馬鹿にしたりすることなく、むしろ彼を理解し支えようとする。
アニメの台本を使った発声練習を一緒にしてくれる場面では、真の友情とは何かを深く考えさせられた。
立花先輩もまた、受験勉強という自分の課題を抱えながらも、後輩である悠太のことを気にかけ、放送部の活動を支えてくれる。このような人間関係を見ていると、人は決して一人では生きていけない存在であり、他者との関わりの中でこそ成長できるのだと強く感じた。
私自身の学校生活を振り返ると、クラスメートの中に困難を抱えている人がいても、それに気づかずに過ごしてしまうことが多いのではないかと反省した。
悠太の家族の存在も非常に印象的だった。母親や姉が悠太の吃音を理解し、決して責めることなく温かく見守り続ける姿は、家族の愛の深さを表している。家族という最も身近な関係の中で安心感を得られるからこそ、悠太は外の世界での困難に立ち向かう勇気を持てるのだと思った。私も家族に支えられて今の自分があることを改めて実感し、その存在の有り難さを感じた。
この作品で最も深く考えさせられたのは、「コミュニケーションとは何か」という問題である。悠太は流暢に話すことはできないが、彼の心には豊かな想いや感情がある。言葉として音声で表現することは困難でも、文章を書いたり、表情や行動で気持ちを伝えたりできる。
また、周囲の人々が悠太の気持ちを理解しようと努力する姿からは、真のコミュニケーションとは一方的に話すことではなく、相手の心に寄り添い、その人の想いを受け取ろうとする姿勢にあるのだと学んだ。
現代社会では、SNSやインターネットを通じたコミュニケーションが主流になりつつあるが、重要なのは技術ではなく、相手を理解しようとする心なのだと改めて感じた。私自身も、普段の友人との会話で相手の話を本当に聞いているだろうか、表面的な言葉だけでなく、その人の気持ちを理解しようと努力しているだろうかと自問した。
悠太が物語の終盤で弁論大会への出場を決意する場面は、彼の大きな成長と勇気を表している。吃音という困難があっても、自分の想いを人に伝えたいという気持ちが恐怖に勝った瞬間だったのだろう。この場面を読んで、私は深く感動すると同時に、自分自身の生き方について考えさせられた。私たちは誰しも何らかの困難や苦手なことを抱えている。それは悠太の吃音ほど深刻ではないかもしれないが、それでも自分にとっては重要な問題である。
『僕は上手にしゃべれない』は、障害や困難を抱える人々への理解を深めてくれる作品であると同時に、人間関係の本質、真のコミュニケーションの意味、そして生きることの意味について深く考えさせてくれる名作である。悠太の物語を通じて、私は多くの大切なことを学ぶことができた。これからの人生で困難に直面した時、悠太の姿を思い出して、諦めずに前進していきたい。そして、周りの人々への感謝の気持ちを忘れず、自分らしく生きていきたい。
振り返り
今回は『僕は上手にしゃべれない』の読書感想文について、小学生から高校生まで幅広い年齢層に向けて詳しく解説してきました。
この作品は吃音という障害をテーマにした深いメッセージが込められた素晴らしい物語です。
皆さんも悠太の成長や周囲の人々の温かさから、きっと多くのことを感じ取れたはずですね。
読書感想文を書く時は、物語の要約ではなく「自分がどう感じたか」を中心に書くことが一番大切です。
皆さんの率直な気持ちや体験談を交えながら、オリジナルの感想文を作ってみてください。
きっと心に響く素晴らしい作品ができあがりますよ。頑張ってくださいね。
■参照サイト:僕は上手にしゃべれない|teens’ best selections|児童読み物(国内)|本を探す|ポプラ社


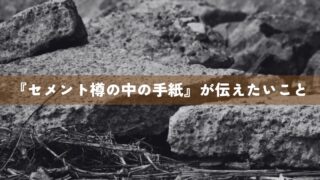




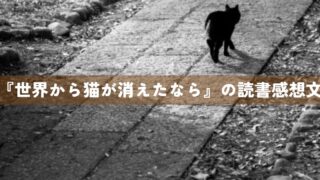

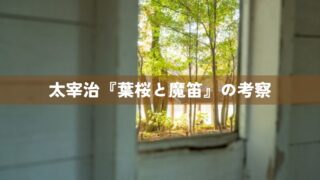







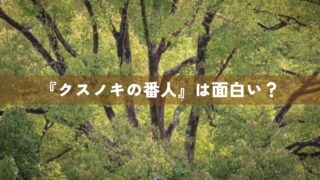

コメント