『火垂るの墓』の読書感想文を書く皆さんに、書き方から例文まで徹底的にサポートしていきますよ。
野坂昭如さんが自身の戦争体験をもとに書いた『火垂るの墓』は、1967年に発表され直木賞を受賞した名作です。
神戸大空襲で両親を失った14歳の清太と4歳の妹・節子が、戦火の中を必死に生き抜こうとする物語。
兄妹の絆と戦争の悲惨さを描いたこの作品は、読書感想文の題材として多くの学生に選ばれています。
私は読書が趣味で、これまで数多くの戦争文学を読んできました。
その経験を活かして、小学生から高校生まで、それぞれの学年に適した書き方のコツや例文を紹介していきます。
書き出しから2000字の構成まで、コピペではない自分だけの感想文が書けるよう、丁寧に解説していきますね。
『火垂るの墓』の読書感想文で触れたい3つの要点
『火垂るの墓』の読書感想文を書くなら、必ず押さえておきたい重要なポイントがあります。
これらの要点について、あなたがどう感じたかをメモしておくことが大切です。
なぜなら感想文は作品の解説ではなく、あなた自身の心の動きを表現するものだからです。
メモを取るときは、その場面を読んでいて胸が苦しくなった、涙が出た、怒りを感じたなど、素直な気持ちを書き留めておきましょう。
なぜその場面でそう感じたのか、自分の体験と重ね合わせて考えることで、深みのある感想文が書けるようになりますよ。
- 戦争の悲惨さと兄妹の絆
- 社会の冷たさと大人たちの態度
- 蛍の象徴的な意味と命の尊さ
それぞれの要点について、詳しく見ていきましょう。
戦争の悲惨さと兄妹の絆
『火垂るの墓』で最も印象的なのは、戦争が子どもたちから家族も住む場所も奪い去ってしまう残酷さです。
清太と節子は神戸大空襲で母親を失い、頼る人もいない状況に追い込まれます。
でも二人は最後まで支え合い、お互いを大切に思い続けました。
清太が節子のために必死に食べ物を探したり、節子が兄を慕って付いて行ったりする姿は、家族の愛の深さを教えてくれます。
あなたがもし清太の立場だったら、どんな気持ちになるでしょうか。
たった14歳で妹の命を預かる責任の重さ、食べ物を手に入れられない無力感、それでも妹を守りたいという気持ち。
そうした複雑な感情について、自分なりに考えてメモしておいてください。
戦争は遠い昔の出来事かもしれませんが、家族を思う気持ちは今も昔も変わりません。
あなた自身の家族との関係を振り返りながら、この兄妹の絆について感想を書いてみましょう。
社会の冷たさと大人たちの態度
『火垂るの墓』では、戦争中の社会の冷たさも描かれています。
特に叔母さんの態度は、多くの読者に強い印象を与える部分です。
最初は二人を受け入れてくれた叔母さんでしたが、だんだん冷たくなっていきます。
「働きもしないで食べ物ばかり食べる」と言われた清太の気持ちを想像してみてください。
大人たちも戦争で大変だったとはいえ、子どもたちへの扱いに疑問を感じる読者も多いでしょう。
現代でも、困っている人に冷たい態度を取る人がいるかもしれません。
あなたの周りで似たような場面を見たことはありませんか。
そのとき、どんな気持ちになったでしょうか。
清太と節子の体験を通して、人間の優しさと冷たさについて考えたことをメモしておきましょう。
また、もしあなたが叔母さんの立場だったら、どう行動したかも考えてみてください。
正解のない難しい問題ですが、自分なりの答えを見つけることが大切です。
蛍の象徴的な意味と命の尊さ
作品のタイトルにもなっている「蛍」は、とても重要な意味を持っています。
防空壕で光る蛍の美しさと、翌朝には死んでしまう儚さ。
これは清太と節子の短い命を象徴しているようにも見えます。
節子が蛍のお墓を作る場面は、特に印象的です。
幼い節子なりに「死」というものを理解しようとする姿が切ないですね。
蛍の光は暗闇の中での希望の光でもありました。
でも、その光がやがて消えてしまうように、二人の希望も打ち砕かれてしまいます。
あなたは蛍の場面を読んで、どんなことを感じましたか。
美しいと思ったのか、悲しいと思ったのか、それとも両方でしょうか。
命の尊さについて、あなた自身はどう考えているかもメモしておきましょう。
身近な人やペットとのお別れを経験したことがあれば、そのときの気持ちと重ね合わせて考えてみてください。
蛍のように短い命でも、光り続けることの意味について、あなたなりの感想を書いてみましょう。
『火垂るの墓』の読書感想文の書き方をテンプレート化
『火垂るの墓』の読書感想文の書き方をテンプレート化しました。
1~5の各ブロックに文章をはめこめば立派な読書感想文が完成しますよ。
本を選んだ理由や、どんな本か簡単に紹介します。
例:「私は戦争のことを考えたくて、『火垂るの墓』を読みました。これは戦争中の兄妹の物語です。」
物語の概要を要約します。登場人物も含めて触れますが、長くなりすぎないように注意。
例:「主人公は14歳の清太で、妹の節子と一緒に戦争の中で生きていきます。母を空襲で亡くし、親戚の家に預けられますが、生活は厳しくなっていきます。」
特に印象に残った場面や人物を具体的に書き、その理由を述べます。
例:「節子が栄養失調で倒れた場面がとても悲しかったです。清太の妹思いの優しさに心を打たれました。」
作品から得たメッセージや考えたことを書きます。戦争の悲惨さや命の尊さ、家族の絆など、自分の言葉で。
例:「この物語を読んで、戦争がいかに多くの命や家族を奪うかを強く感じました。二度と戦争が起きてほしくないと思います。」
本を読んでの感想全体のまとめや、読んだ人へのメッセージなどで締めます。
例:「『火垂るの墓』はとても悲しい話ですが、平和の大切さを教えてくれる作品です。多くの人に読んでほしいと思います。」
このテンプレートは小学生中学年~高学年向けにも使えますし、文章量に応じて内容を調整してください。
感想文のポイントとしては、あらすじは要約的にし、感想や考えを中心に書くことが大切です。
※『火垂るの墓』の本/小説のあらすじはこちらでご紹介しています。
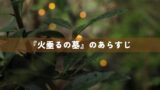
上記のテンプレートを使った具体的な例文がこちら。
これだけでは短いので、下記でご紹介する学年別の読書感想文の例を参考にして、必要な長さの感想文を書きましょう。
『火垂るの墓』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】蛍のように光った兄妹の愛
『火垂るの墓』を読んだ私は、清太と節子の兄妹がお母さんを失って一人ぼっちになってしまう場面で、胸が苦しくなって涙が出そうになった。
私にも弟がいるので、もし同じことが起こったらどうしようと考えてしまったからだ。
清太はまだ中学生なのに、4歳の節子を一人で守らなければならなくなった。
私だったら、そんな大変なことはできないと思う。
でも清太は最後まで節子を大切にして、一緒にいてあげた。
お腹がすいても、節子に先に食べさせてあげる清太を見て、本当のお兄ちゃんの愛情を感じた。
私も弟にもっと優しくしなければいけないと反省した。
叔母さんの家にいたとき、だんだん冷たくされるようになって、二人は防空壕で暮らすことになった。
叔母さんの気持ちも分からなくはないけれど、小さな子どもたちがかわいそうで仕方がなかった。
戦争中だから食べ物がなくて大変だったと思うけれど、もう少し優しくできなかったのかなと思った。
私の家族だったら、絶対に追い出したりしないと思う。
防空壕で蛍を見つけた場面は、とても美しかった。
暗い穴の中で光る蛍は、まるで希望のように見えた。
でも、翌朝には蛍が死んでしまって、節子が小さなお墓を作ってあげる場面では泣いてしまった。
この蛍は、清太と節子の命のことを表しているのだと先生に教えてもらった。
短い間だけれど、とても美しく光っていた蛍のように、二人も短い人生だったけれど、お互いを愛し合って生きていたのだと思う。
節子が栄養失調で弱っていく場面は、見ているのがつらかった。
清太が一生懸命に食べ物を探しても、もう手遅れだった。
戦争さえなければ、二人は幸せに暮らせたはずなのにと思うと、戦争が憎らしくなった。
私たちは今、平和な時代に生きている。
お腹いっぱい食べることができて、家族と一緒に暮らせることは、当たり前のことではないのだと分かった。
清太と節子のように苦しい思いをする子どもがいない世界になってほしいと思う。
私も毎日を大切に過ごして、家族を大切にしていきたい。
そして、戦争の恐ろしさを忘れずに、平和の大切さを心に刻んでおきたいと思った。
『火垂るの墓』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】戦争が奪った小さな光
『火垂るの墓』を読み終えて、しばらく本を閉じることができなかった。
清太と節子の悲しい運命を思うと、自分の幸せを改めて感じずにはいられなかった。
この物語は、戦争の残酷さを子どもの視点から描いた作品だが、単なる反戦小説以上の深いメッセージが込められていると思う。
物語の中心にあるのは、14歳の清太と4歳の節子の兄妹愛である。
神戸大空襲で母親を失った二人は、親戚の叔母さんの家に身を寄せることになる。
私と同じ年頃の清太が、幼い妹の命を預かる重責を背負う姿を見て、自分だったらどうしただろうかと何度も考えた。
私にも小さな妹がいるが、彼女を一人で守り抜く自信はない。
清太の決断力と責任感の強さに、同世代として尊敬の気持ちを持った。
叔母さんとの関係が悪化したとき、防空壕での生活を選んだ判断は、大人から見れば無謀だったかもしれない。
でも、プライドを傷つけられ、大切な妹まで邪魔者扱いされた清太の気持ちを考えると、その選択も理解できる気がする。
私だって、家族を馬鹿にされたら怒るし、意地を張ってしまうかもしれない。
清太の心情は、現代を生きる私たちにも通じるものがあるのではないだろうか。
叔母さんの態度については、複雑な思いを抱いた。
確かに戦時中の食糧不足は深刻で、自分の家族を守るのに精一杯だったのだろう。
でも、小さな子どもたちに対する冷たい言葉や態度は、どんな理由があっても正当化できないと思う。
だが私の家族が同じ状況に置かれたら、果たして他人の子どもを面倒を見ることができるだろうかという疑問も湧いた。
戦争は人間から優しさを奪い、生き延びるためには他者への思いやりさえ捨てなければならない状況を作り出すのかもしれない。
物語の象徴である蛍の場面は、最も印象に残った部分である。
防空壕の中で光る蛍の美しさと、翌朝の死という現実の対比が、二人の運命を暗示しているようで切なかった。
節子が蛍のお墓を作るシーンでは、幼いながらも死を理解し、命あるものへの優しさを示す彼女の純真さに胸を打たれた。
蛍の短い命は、清太と節子の人生そのものを表している。
闇の中でわずかな時間だけ美しく光り、そして消えていく。
二人の生命もまた、戦争という闇の中で、兄妹愛という美しい光を放ちながら、あまりにも早く消えてしまった。
この作品を読んで、私は改めて平和の尊さを実感した。
毎日学校に通い、友達と笑い合い、家族と食事を共にできることは、決して当たり前のことではない。
清太と節子が奪われたささやかな日常を、私たちは当然のように享受している。
その現実に、申し訳なさと同時に感謝の気持ちを覚えた。
私は今まで、自分に関係のない他人の苦しみに、どれだけ真剣に向き合ってきただろうか。
叔母さんのような冷たさを、知らず知らずのうちに示していたのではないだろうか。
この物語は、戦争の悲惨さを伝えるだけでなく、人間としての優しさや思いやりの大切さを教えてくれる。
清太と節子の短い人生が無駄にならないよう、私たちは彼らの物語を語り継ぎ、二度と同じ悲劇を繰り返してはならないと思う。
そして、日常の中で出会う小さな困難に直面している人々に、もっと温かい心で接していきたい。
『火垂るの墓』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】命の光が教えてくれたもの
『火垂るの墓』を読み終えた後、私は長い間、本を手に持ったまま動けずにいた。
清太と節子という幼い兄妹が辿った悲劇的な運命について、どのような言葉で表現すればよいのか分からなかったからである。
この作品は、戦争の悲惨さを描いた反戦小説として読むことができる。しかし私が感じたのは、それ以上に深い人間性への問いかけだった。
戦争という極限状況の中で、人はどこまで人間らしさを保てるのか。愛する人を守るために、どこまでの犠牲を払えるのか。
そして、社会から見捨てられた弱者に対して、私たちはどのような責任を負うべきなのか。これらの重い問いが、物語を通じて私の心に深く刻まれた。
主人公の清太は、わずか14歳の少年である。私と同じ高校生の年齢でありながら、彼が背負った責任の重さは計り知れない。
神戸大空襲で母親を失い、4歳の妹・節子の唯一の保護者となった清太。父親は海軍に従軍中で、生死も不明だった。
そんな中で彼が選んだのは、親戚の叔母の家を出て、妹と二人で生きていくことだった。多くの大人たちはこの判断を愚かと見るかもしれない。
確かに現実的には叔母の家にとどまる方が安全だったかもしれない。しかし清太が守ろうとしたのは、食べ物や住む場所ではなく、妹と自分の尊厳だったのではないか。
叔母から受けた冷たい扱いや心ない言葉は、思春期の彼にとって耐え難い屈辱だったに違いない。特に妹までもが同じように扱われることは、兄として許せなかったのだろう。
私自身も、家族の尊厳が傷つけられたとき、理性より感情が先に立ってしまうことがある。清太の行動は、そんな人間らしい感情の発露として理解できる部分がある。
一方で、叔母の態度を一方的に責めることもできない。戦時中の食糧難の中で、自分の家族を養うだけでも必死だったはずである。
血のつながりが薄い子どもを引き取ることは、大きな負担だっただろう。叔母もまた、戦争の被害者だったのかもしれない。
それでもなお、節子への冷たい態度には強い違和感を覚えた。どんな理由があっても、あのような扱いは正当化できない。
子どもに罪はないのに、なぜあのような仕打ちを受けなければならなかったのか。
この問題は現代社会にも通じる。経済的困難や社会不安の中で、私たちは弱者にどう向き合うべきなのか。
自分の利益を優先することが許される限界はどこにあるのか。明確な答えは出ないが、少なくとも無力な存在を見捨ててはならないという思いが強くなった。
物語で最も印象深かったのは蛍の場面だ。防空壕の中で光る蛍の美しさは、絶望の中の二人に束の間の希望を与えてくれた。
しかし翌朝には蛍は死に、節子が小さな墓を作る。この場面には命の儚さと美しさが凝縮されていた。
蛍の短い命は、二人の運命を象徴している。節子が蛍の死を悲しみながら墓を作る姿に深く心を打たれた。
4歳の彼女が命あるものに敬意を示す純真さは、大人たちが失った大切なものを私たちに思い出させてくれる。
戦争という残酷な現実の中でも、節子は人間としての優しさを失わなかった。どんな困難な状況でも人間性を保つことの大切さを教えてくれる。
物語後半、節子が衰弱していく様子は胸が締め付けられた。清太が懸命に助けようとしても、適切な医療や食事が得られない。
敗戦を知った清太がようやく手に入れた食べ物を与えようとする場面では、すでに手遅れだった。
もし戦争がもう少し早く終わっていれば、あるいは社会がもっと優しければ、二人は救われたかもしれない。
そうした「もしも」を考えることで、今の平和に感謝できるのではないか。学校に通い、家族と食卓を囲む日常は決して当たり前ではない。
彼らが失ったものを私たちは享受している。この現実に感謝すると同時に、ある種の責任も感じる。
彼らの犠牲を無駄にせず、平和を守り、弱者を支える社会を築く必要がある。
また、この物語は個人の選択の重さも教えてくれる。清太の決断が悲劇を招いたとしても、妹を守ろうとした気持ちは尊い。
私たちも日常で様々な選択を迫られる。そんなとき、自分の利益だけでなく、他者への思いやりを忘れずにいたい。
清太の生き方は、そうした問いを私たちに投げかけている。
『火垂るの墓』は戦争の悲惨さだけでなく、人としてどう生きるかを深く考えさせてくれる作品である。
蛍のように短くても美しく光る命の尊さ、愛する人を守る気持ちの大切さ、そして弱者を支える社会の必要性。
それらを胸に刻み、私もまた、困難な状況でも人間性を失わない強さを持ちたい。そして、二度と同じ悲劇を繰り返さない社会を目指し、できることから始めていきたい。
振り返り
ここまで『火垂るの墓』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
戦争の悲惨さ、兄妹の絆、蛍の象徴性という3つの要点を中心に、あなた自身の感情や体験と結び付けて書くことが大切です。
小学生なら素直な気持ちを、中学生なら自分との比較を、高校生なら深い考察を交えながら、それぞれの年齢に応じた表現で感想文を仕上げてください。
大切なのは、清太と節子の物語を通してあなたが何を感じ、何を学んだかを正直に書くことです。
コピペではない、あなただけの感想文を書けるよう応援しています。
きっと心に響く素晴らしい読書感想文が完成するはずですよ。
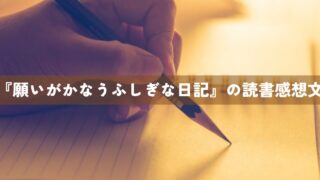
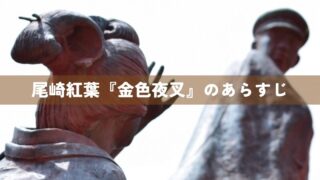






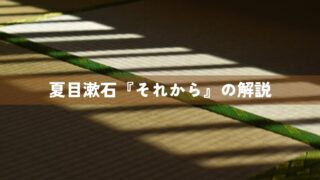
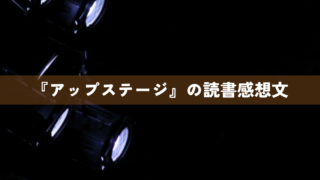
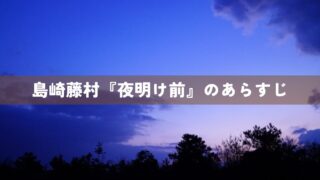

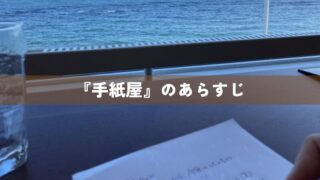
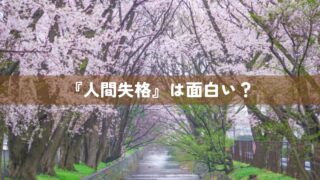
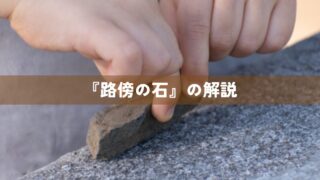

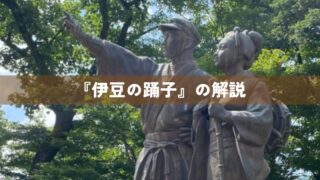

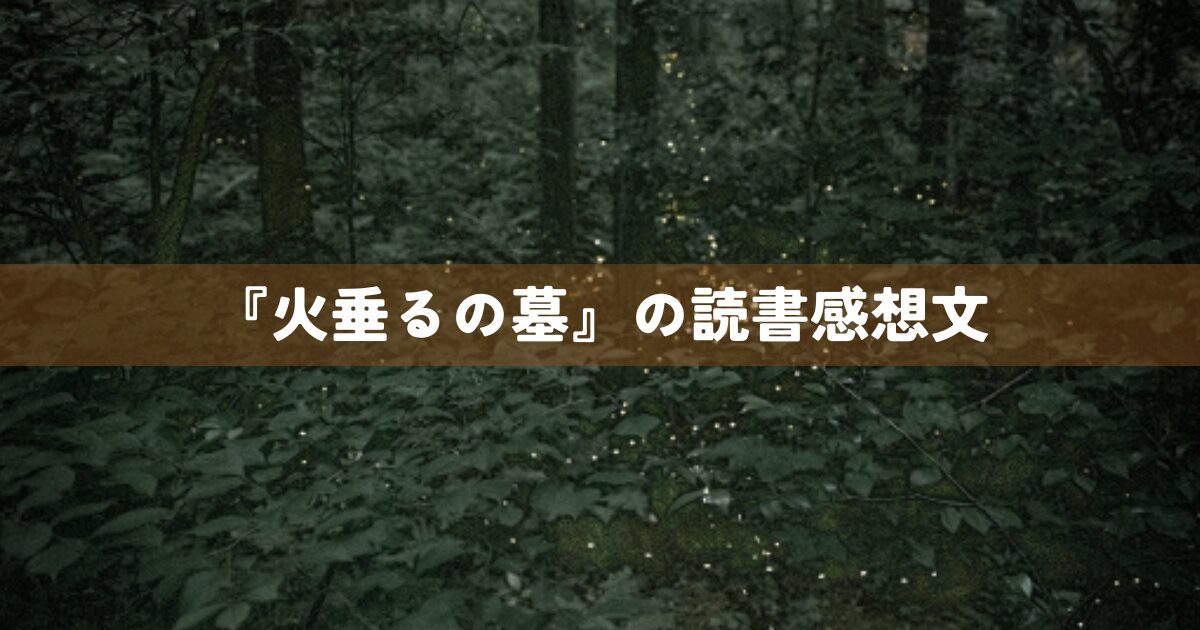
コメント