朝井リョウさんの小説『正欲』の読書感想文を書く予定の皆さん、こんにちは。
この作品は2021年に新潮社から刊行され、第34回柴田錬三郎賞を受賞した話題作。
横浜の検事や広島のショッピングモール店員、大学生など複数の人物の視点から描かれる物語で、現代社会における多様性や人間の欲望、生きづらさを鋭く描いた社会派小説となっています。
読書感想文の書き方やテンプレートを探している皆さんにとって、この記事がお役に立てるよう、年間100冊以上の本を読む私が例文や題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきます。
コピペやパクリに頼らず、自分なりの感想を書けるようサポートしますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
『正欲』の読書感想文で触れたい3つの要点
『正欲』の読書感想文を書く際に重要なのは、ただあらすじを書くのではなく、この作品が提起する深いテーマについて「自分がどう感じたか」を記録することです。
感想文で高い評価を得るためには、物語を読んで心が動いた瞬間や、考えさせられた場面について具体的にメモを取ることが大切。
メモを取る際は、「なぜそう感じたのか」「自分の経験と重なる部分はあるか」「この場面から何を学んだか」といった観点で記録しましょう。
これらの個人的な感想こそが、読み手に響く感想文の核になるからです。
『正欲』で特に注目すべき要点は以下の3つです。
- 「普通」という概念の曖昧さと多様な価値観への理解
- 現代社会における「多様性」の理想と現実のギャップ
- 人間の複雑さと善悪では割り切れない現実
それぞれの要点について、どのような場面で何を感じたかを詳しく見ていきましょう。
「普通」という概念の曖昧さと多様な価値観への理解
『正欲』の最も重要なテーマの一つが、「普通」とは何かという問いかけです。
桐生夏月や佐々木佳道が抱える特殊な性的嗜好について、作者は偏見なく丁寧に描写しています。
この部分を読んで、皆さんはどのような感情を抱いたでしょうか。
最初は戸惑いを感じた人も多いかもしれません。
しかし、彼らの内面を深く知ることで、「こんな風に感じる人もいるんだ」という新たな理解が生まれたのではないでしょうか。
感想文では、自分の中にあった「普通」の枠組みがどのように変化したかを具体的に書くことが重要です。
例えば、「最初は理解できなかったが、彼らの苦悩を知ることで、多様性の本当の意味を考えるようになった」といった気付きを記録しましょう。
また、検事の寺井啓喜が息子の不登校に悩む姿も、親が持つ「普通」への期待を描いた重要な場面。
息子がYouTuberになりたいという夢を、社会的に「まっとう」ではないと感じてしまう啓喜の葛藤から、現代社会の価値観の多様化について何を感じたかをメモしておくことが大切です。
現代社会における「多様性」の理想と現実のギャップ
神戸八重子が企画する「ダイバーシティフェス」のエピソードは、多様性というテーマを象徴的に描いた場面です。
多様性を受け入れようという理想的な取り組みの裏で、八重子自身が複雑な感情(兄への嫌悪感からくる異性恐怖症)を抱えていることが明らかになります。
この矛盾した状況から、皆さんは何を感じ取ったでしょうか。
「多様性」という言葉は美しく聞こえますが、実際にそれを実現することの難しさを痛感した人も多いはず。
感想文では、表面的な理解と真の共感の違いについて、自分なりの考えを書くことが重要です。
例えば、「多様性を口にするのは簡単だが、本当に他者を理解し受け入れることの困難さを知った」といった気付きを記録しましょう。
また、現代社会で頻繁に語られる「多様性」という言葉に対して、この作品を読む前と後でどのような認識の変化があったかも重要なポイント。
理想と現実のギャップに気付いた瞬間の心境を詳しくメモしておくことで、深みのある感想文が書けるでしょう。
人間の複雑さと善悪では割り切れない現実
『正欲』は、人間の心理や社会問題に対して安易な答えを出さない作品です。
特に諸橋大也の物語は、単純な善悪では判断できない複雑さを描いています。
彼が抱える秘密や、それが引き起こす出来事について、皆さんはどのような感情を抱いたでしょうか。
おそらく、すっきりとした答えを見つけることができず、もやもやとした気持ちになった人が多いはず。
しかし、その「もやもや」こそが、この作品が投げかける重要なメッセージなのです。
感想文では、読後に感じた複雑な気持ちを素直に表現することが大切です。
「答えが見つからず困惑したが、それが現実の複雑さを教えてくれた」といった正直な感想を書きましょう。
また、日常生活で出会う様々な問題についても、この作品を読んだことで見方が変わった部分があるかもしれません。
白黒つけたがる自分の傾向に気付いたり、他者を安易に判断することの危険性を感じたりした経験があれば、それも重要な感想の材料になります。
物語の結末についても、明確な解決が示されないことで、読者一人ひとりが考え続けることの重要性を伝えている点に注目してください。
『正欲』の読書感想文のテンプレート
朝井リョウさんの小説『正欲』の読書感想文の書き方について、高校生向けにテンプレート化してみました。
これを参考に、あなたの感想を肉付けしていってください。
1. 導入:作品との出会いと第一印象
- 作品名と著者名を明記する。
- この本を手に取ったきっかけ(タイトルに惹かれた、話題になっていた、推薦されたなど)
- 読み始める前の正直な印象や期待(どんな物語だと思ったか、何を学びたいと思ったかなど)
例:「『正欲』というタイトルに漠然とした好奇心を抱いていました。」
例:「SNSで話題になっているのを見て、一体どんな物語なのだろうと興味を持ちました。」
2. 本文1:最も印象に残ったテーマや人物(「普通」と「多様な欲」)
この小説で最も強く感じたテーマやメッセージは何かを提示する。特に「普通」という概念の曖昧さや、多様な「欲」の存在に焦点を当てるのがおすすめです。
そのテーマを象徴する登場人物やエピソードを具体的に挙げる。
例:桐生夏月や佐々木佳道の「水フェチ」の描写について触れる。
具体的な描写が、自身の「普通」という感覚をどう揺さぶったか、どう気づきを与えたかについて書く。
「こんな風に感じる人もいるんだ」という発見や驚き。 自分の中にあった固定観念が崩れた感覚。 「性」や「欲望」に対する新たな視点を得られたことなど。
3. 本文2:もう一つの印象的なテーマや人物(「多様性」の現実と社会への問いかけ)
他に印象に残ったテーマや人物**について書く。「多様性」の理想と現実のギャップや、社会への問いかけに焦点を当てるのが良いでしょう。
そのテーマを象徴する登場人物やエピソードを具体的に挙げる。
例:寺井啓喜が息子の不登校や将来に悩む姿について触れる。
親としての葛藤、現代の親子関係や価値観の多様化について感じたこと。
例:神戸八重子と「ダイバーシティフェス」のエピソードについて触れる。
「多様性」という言葉の裏にある難しさや矛盾についてどう感じたか。 綺麗事だけでは済まされない現実への鋭い指摘についてどう考えたか。
4. 本文3:物語全体の構成と読後感
物語の構成(複数の視点、終盤の展開など)について、工夫されていると感じた点や、感銘を受けた点を書く。
例:「複数の視点が徐々に絡み合っていく構成が見事だった。」
例:「終盤の展開に良い意味で裏切られ、物語に引き込まれた。」
読後感について触れる。爽やかな読後感ではないこと、しかしそれがこの小説の魅力であることに言及する。
例:「読み終えてもモヤモヤとした気持ちが残ったが、それこそが大切だと思った。」
例:「簡単に答えが出ない問いを投げかけられたことで、深く考えさせられた。」
諸橋大也のエピソードなど、安易な善悪では判断できない人間の複雑さや社会の現実が描かれていることについて触れても良いでしょう。
5. 結論:この本から得たものとこれからの自分
この小説を読んで、最も心に残ったことや、学びになったことをまとめる。
この作品が、自分の価値観や考え方にどのような影響を与えたかを具体的に書く。
例:「自分の中の無意識の偏見に気づかされた。」
例:「他者を理解しようとする姿勢の大切さを改めて感じた。」
例:「『普通』とは何か、多様な『欲』とどう向き合うべきか、これからも考え続けていきたい。」
最後に、この本をどんな人に勧めたいか、あるいはもう一度読みたいかなど、今後の展望で締めくくる。
『正欲』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】「普通」って何だろう?
私は朝井リョウさんの小説『正欲』を読んで、今まで当たり前だと思っていた「普通」という言葉について深く考えるようになった。
この小説には、検事の寺井啓喜さん、ショッピングモールで働く桐生夏月さん、大学生の神戸八重子さんなど、様々な人が登場する。
最初は普通の人たちの普通の日常が描かれているのかと思ったが、読み進めるうちに、それぞれが抱える複雑な悩みや秘密が明らかになっていく。
特に印象的だったのは、夏月さんと佐々木佳道さんが持つ特殊な性的嗜好についての描写だった。
正直に言うと、最初は理解できなくて戸惑いを感じた。
しかし、二人の心の奥にある苦悩や孤独感を知ることで、「こんな風に感じる人もいるんだ」という新しい発見があった。
私は今まで、自分が普通だと思うことを無意識のうちに他の人にも当てはめていたのかもしれない。
この小説を読んで、「普通」という基準は人それぞれ違うということを痛感した。
また、寺井さんが息子の不登校に悩む姿も心に残った。
息子がYouTuberになりたいと言った時の寺井さんの複雑な気持ちは、私の親の気持ちと重なる部分があるように感じられた。
親は子どもに「普通」の道を歩んでほしいと願うものだが、その「普通」が子どもにとって本当に幸せなのかは分からない。
私自身も、親から期待される「普通の子ども」像と、自分がなりたい姿との間で悩んだことがある。
寺井さんの葛藤を読んで、親子関係の難しさについて改めて考えさせられた。
神戸八重子さんが企画する「ダイバーシティフェス」のエピソードも興味深かった。
多様性を受け入れようという素晴らしい取り組みなのに、八重子さん自身が兄への複雑な感情を抱えていることが分かる。
これを読んで、「多様性」という言葉を口にするのは簡単だが、本当に他者を理解し受け入れることは非常に難しいのだと気付いた。
私たちの学校でも「多様性を大切に」といった話をよく聞くが、実際に自分と違う考えや価値観を持つ人と接した時、素直に受け入れられているかと問われると、自信がない。
この小説は、そうした自分の中にある偏見や思い込みに気付かせてくれた。
物語の中で最も考えさせられたのは、諸橋大也さんの物語だった。
彼が抱える秘密については、簡単に善悪を判断することができない複雑さがある。
読んでいて正直、すっきりしない気持ちになったが、それこそが現実の複雑さなのだと思う。
私たちは普段、物事を白か黒かで判断しがちだが、実際の世界にはグレーゾーンがたくさん存在する。
『正欲』を読んで、そうした現実の複雑さから目を逸らさずに向き合うことの大切さを学んだ。
この小説を読み終えた時、明確な答えは見つからなかった。
しかし、それでいいのだと思う。
大切なのは答えを見つけることではなく、考え続けることなのかもしれない。
「正しい欲望って何だろう?」「普通って一体何なんだろう?」
こうした問いを持ち続けることで、私はもっと他者に優しくなれるような気がする。
朝井リョウさんが『正欲』を通して投げかけてくれたメッセージを、これからも大切にしていきたい。
『正欲』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】多様性の向こう側にあるもの
朝井リョウさんの小説『正欲』を読み終えた時、私は長い間本を閉じることができなかった。
この作品が提起する「普通とは何か」「多様性とは何か」という問いは、私たちが生きている現代社会の核心を突いているからだ。
物語は横浜の検事・寺井啓喜、広島のショッピングモール店員・桐生夏月、大学生・神戸八重子など、複数の登場人物の視点から描かれている。
最初はそれぞれ独立した日常が描かれているように見えたが、読み進めるうちに彼らの人生が複雑に絡み合っていく構成の巧妙さに驚かされた。
何より印象的だったのは、桐生夏月と佐々木佳道が抱える特殊な性的嗜好についての描写だった。
一般的には理解されにくいであろう「水フェチ」という性的指向について、朝井さんは一切の偏見を排除し、彼らの内面に真摯に向き合っている。
読み始めた当初、正直に言えば戸惑いを感じた。
しかし、二人の心の奥底にある孤独感や、社会から理解されない苦しみを知ることで、私の中にあった固定観念が少しずつ崩れていくのを感じた。
「こんな風に感じる人もいるんだ」という単純な驚きから始まり、やがて「私は無意識のうちに『普通』という枠を他者に当てはめていたのではないか」という自己省察に至った。
この経験は、多様性という言葉の本当の意味を考える大きなきっかけとなった。
また、検事である寺井啓喜が息子・泰希の不登校に悩む姿も強く心に残った。
息子がYouTuberになりたいという夢を持った時の啓喜の複雑な心境は、現代の親が直面する価値観の多様化を象徴している。
社会的に「まっとう」とされる道から外れることへの不安と、子どもの個性を尊重したいという気持ちの間で揺れ動く啓喜の姿は、私自身の親の姿と重なった。
私も進路選択において、親が期待する「普通」の道と自分の興味との間で葛藤した経験がある。
啓喜の悩みを通して、親子それぞれが持つ「普通」への期待や不安について、改めて深く考えさせられた。
神戸八重子が企画する「ダイバーシティフェス」のエピソードは、この小説の核心的なメッセージを含んでいる。
多様性を受け入れようという理想的な取り組みの裏で、八重子自身が兄への嫌悪感からくる異性恐怖症を抱えていることが明らかになる。
この矛盾した状況を読んで、私は「多様性」という言葉の持つ美しさと、それを実際に実現することの困難さについて深く考えるようになった。
私たちの高校でも「多様性の尊重」や「インクルーシブな社会」といった言葉をよく耳にする。
しかし、実際に自分と異なる価値観や生き方を持つ人と向き合った時、本当に心から受け入れることができているだろうか。
八重子の姿は、表面的な理解と真の共感の間にある深い溝を浮き彫りにしている。
私自身も、多様性について語る時に、どこか上から目線で「理解してあげている」という傲慢さがあったのではないかと反省させられた。
物語の中で最も考えさせられたのは、諸橋大也の存在だった。
彼が抱える秘密と、それが最終的に引き起こす出来事については、簡単に善悪を判断することができない複雑さがある。
読んでいて正直、すっきりしない気持ちになった。
明確な答えや解決策が示されず、むしろ問題の根深さや複雑さが浮き彫りになる。
しかし、その「もやもや」とした読後感こそが、この小説の最も重要な部分なのだと気付いた。
現実の世界には、白か黒かで割り切れない問題がたくさん存在する。
私たちは普段、物事を単純化して理解しようとしがちだが、人間の心理や社会の問題は本来、非常に複雑で多面的なものだ。
『正欲』は、そうした現実の複雑さから目を逸らさずに向き合うことの大切さを教えてくれる。
朝井リョウさんの筆力にも感服した。
複数の視点から物語を描きながら、それぞれのキャラクターの心理描写が非常にリアルで説得力がある。
特に、社会の「普通」から外れた人たちの内面を、偏見なく丁寧に描写する姿勢は素晴らしいと思った。
物語の構成も巧妙で、最初は別々に進んでいた各登場人物のストーリーが、徐々に絡み合っていく様子は見事としか言いようがない。
読み終えた今、私は「正しい欲望とは何か」「多様性とは何か」という問いを抱え続けている。
この小説は答えを与えてくれるのではなく、読者一人ひとりに深く考えることを促している。
そして、その考える過程こそが、真の多様性理解への第一歩なのかもしれない。
私は『正欲』を読んで、他者への想像力の大切さを改めて実感した。
自分とは異なる感性や価値観を持つ人たちの存在を認め、理解しようと努めること。
それが「あってはならない感情はない」というメッセージの本当の意味なのだと思う。
この読書体験は、私の今後の人間関係や社会との向き合い方に大きな影響を与えるだろう。
多様性という言葉を軽々しく使うのではなく、その向こう側にある複雑で深い人間の営みに思いを馳せながら、日々を過ごしていきたい。
振り返り
『正欲』の読書感想文について、重要なポイントから具体的な例文まで詳しく解説してきました。
この作品は「普通」という概念への問いかけや多様性の複雑さ、人間の心理の奥深さを描いた非常に考えさせられる小説です。
感想文を書く際は、物語のあらすじを説明するだけでなく、読んでいて心が動いた瞬間や考えさせられた場面について、自分なりの感想を具体的に書くことが大切。
今回紹介した3つの要点を参考に、皆さんも自分だけの感想文を書いてみてくださいね。
きっと読み手の心に響く、素晴らしい作品が完成するはずです。
※小説『正欲』のあらすじはこちらでご紹介しています。


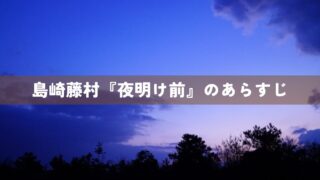




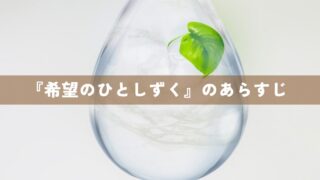


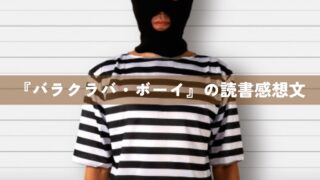




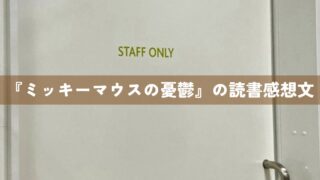
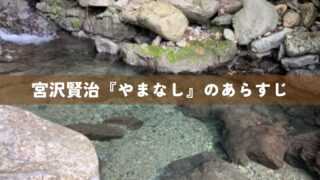


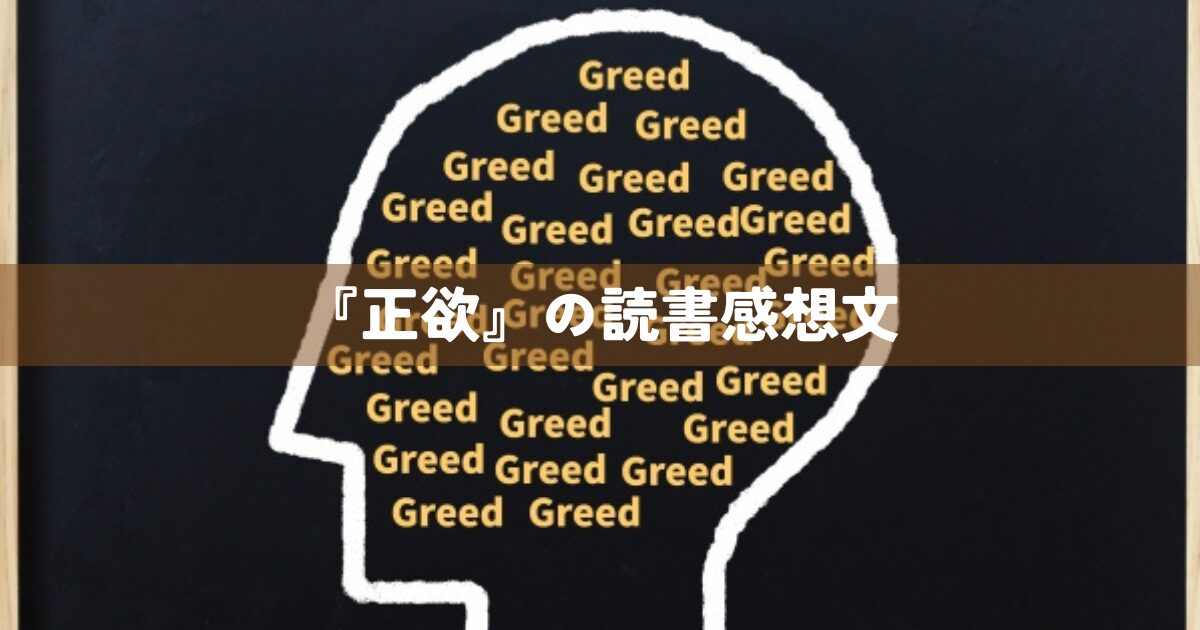
コメント