『人がつくった川・荒川』の読書感想文の書き方について、詳しく解説していきますよ。
『人がつくった川・荒川 水害からいのちを守り、暮らしを豊かにする』は長谷川敦さんが2022年に発表したノンフィクション作品で、第69回青少年読書感想文全国コンクール中学校の部の課題図書にも選ばれました。
荒川が流域に約1000万人が住む首都圏を貫き、江戸時代から洪水被害に対処しながら人々の暮らしと都市の発展を支えてきた歴史を、川の流れの変遷や治水工事の人々の努力を交えて紹介した作品です。
読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、『人がつくった川・荒川』の読書感想文の書き方を中学生・高校生の皆さんに分かりやすく説明していきます。
書き出しから題名の付け方、テンプレートやコピペ厳禁な例文まで、読書感想文作成のお手伝いをしますので、最後までお付き合いくださいね。
『人がつくった川・荒川』の読書感想文で触れたい3つの要点
『人がつくった川・荒川』の読書感想文を書く際に必ず触れてほしい重要なポイントは以下の3つです。
- 荒川が「人がつくった川」であることの歴史的意味
- 治水事業に携わった人々の努力と技術
- 現代の環境問題と未来への課題
これらの要点について読書中に「どう感じたか」をメモしておくことが、良い感想文を書く秘訣です。
メモの取り方としては、読書しながら付箋に「驚いた」「感動した」「疑問に思った」といった感情を書き込んでいくのがおすすめですよ。
「どう感じたか」が重要な理由は、読書感想文が単なる本の要約ではなく、あなた自身の心の動きを表現する文章だからです。
それでは3つの要点を詳しく見ていきましょう。
荒川が「人がつくった川」であることの歴史的意味
『人がつくった川・荒川』というタイトルから分かるように、荒川は自然のままの川ではありません。
江戸時代から現代に至るまで、人々が洪水被害を防ぎ、都市の発展を支えるために川の流れを変えてきた歴史があります。
特に徳川家康の時代に行われた荒川の流路変更は、江戸の繁栄に大きな影響を与えました。
この部分を読んだとき、あなたはどんなことを感じましたか?
「川の流れを変えるなんてすごい」「昔の人の知恵に驚いた」「自然を変えることの是非について考えた」など、様々な感想があると思います。
そうした素直な気持ちをメモしておくと、感想文を書くときに役立ちますよ。
治水事業に携わった人々の努力と技術
『人がつくった川・荒川』では、青山士(あおやまあきら)や伊那忠治(いなただはる)といった実在の人物が登場します。
青山士は明治時代の土木技師で、パナマ運河建設に携わった経験を活かして荒川放水路の設計・施工で中心的役割を果たしました。
伊那忠治は江戸時代に荒川の西遷事業を指揮した人物で、荒川の流れを変える大規模な土木工事の立役者でした。
こうした人々の功績について読んだとき、あなたはどう思いましたか?
「昔の技術でよくこんな大工事ができたな」「多くの人の協力があったからこそ今の安全があるんだ」といった感想を持った人もいるでしょう。
現代の私たちが当たり前に思っている安全な暮らしが、多くの先人たちの努力によって支えられていることに気づいたかもしれませんね。
現代の環境問題と未来への課題
『人がつくった川・荒川』は過去の話だけでなく、現代の水害対策や地球温暖化による大規模水害の増加についても触れています。
気候変動の影響で豪雨の頻度が増している現在、荒川の治水技術はますます重要になっています。
また、人工的に流れを変えたことで失われた自然環境についても考える必要があります。
この部分を読んで「自分たちにできることはないだろうか」「防災意識を高めなければ」「自然との共生について考えた」といった感想を持った人は多いと思います。
あなた自身が住んでいる地域の川と比較して考えてみるのも良いアプローチですね。
※『人がつくった川・荒川』のあらすじはこちらでご紹介しています。

『人がつくった川・荒川』の読書感想文のテンプレート
『人がつくった川・荒川』の読書感想文を楽に書けるように、ステップバイステップのテンプレートを用意しました。
以下の手順に従って空欄を埋めていけば、立派な感想文が完成しますよ。
ステップ1:書き出し(本との出会い)
『人がつくった川・荒川』というタイトルを最初に見たとき、私は_______と思った。川は自然のものだと考えていたので、「人がつくった」という表現に_______を感じた。
ステップ2:荒川の歴史について
この本を読んで最も驚いたのは、_______ということだった。江戸時代から現代まで、人々が_______のために川の流れを変えてきた歴史を知り、_______と感じた。
ステップ3:治水に携わった人々について
青山士や伊那忠治といった人物の功績を読んで、私は_______と思った。現代の私たちの安全な暮らしが_______によって支えられていることを知り、_______という気持ちになった。
ステップ4:現代の課題と自分の考え
地球温暖化による水害の増加について読んで、_______を感じた。私が住む地域でも_______について考える必要があると思う。これからは_______していきたい。
ステップ5:まとめ(未来への思い)
『人がつくった川・荒川』を読んで、_______ということを学んだ。自然と人間の関係について_______と考えるようになった。未来のために私たちは_______していく必要があると思う。
『人がつくった川・荒川』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】川と人間の共生について考える
『人がつくった川・荒川』というタイトルを見た時、私は疑問に思った。川は自然にできるものではないのか。なぜ「人がつくった」と言うのだろう。そんな気持ちでこの本を手に取った。
読み進めていくと、荒川が昔から「暴れ川」と呼ばれ、洪水で多くの被害をもたらしていたことが分かった。江戸時代の荒川は今とは全く違う場所を流れていて、大雨が降るたびに氾濫し、人々の生活を脅かしていたという。私が知っている荒川とは全然違う姿だった。
特に印象に残ったのは、徳川家康の時代に荒川の流路を変えた話だ。洪水被害を減らし、江戸の発展のために川の流れを人工的に変えるなんて、昔の人の知恵と技術の高さに驚いた。しかし、流れを変えることで一部の地域では逆に水害が増えてしまったという話を読んで、自然を変えることの難しさも同時に感じた。
明治時代の青山士という土木技師の話も興味深かった。パナマ運河の建設に参加した唯一の日本人として経験を積み、その技術を荒川放水路の建設に活かしたという。放水路の建設は多くの人の協力と長い時間が必要で、完成までには大変な苦労があったことがひしひしと伝わってきた。
写真や図を見ていると、昔の工事の様子がよく分かった。重機もない時代に、人の手でこれほど大規模な工事を行ったことに感動した。現在私たちが安全に暮らせているのは、こうした先人たちの努力があったからなのだと改めて思った。
しかし、人工的に川を整備することで失われたものもある。昔の荒川には豊かな自然があり、多くの生き物が住んでいたという。それが治水工事によってコンクリートで固められ、生態系が変わってしまった。人間にとっての安全を得る代わりに自然を犠牲にしたのだ。
私の家の近くにも大きな川が流れている。護岸工事がされていて、散歩道も整備されている。この本を読むまでは、これが当たり前だと思っていた。でも、この川も昔は違う姿をしていたのかもしれない。人の手が加えられて今の形になったのかもしれない。
最後に地球温暖化による水害の増加について書かれていた部分を読んで、これは現在の私たちの問題だと感じた。気候変動で異常な豪雨が増えている今、荒川の治水技術はますます大切になっている。でも、自然を壊さない方法も真剣に考えなければならない。
『人がつくった川・荒川』を読んで、川と人間の関係について深く考えるようになった。自然の力は恐ろしいけれど、完全に支配することはできない。私たちにできるのは、自然と共生しながら安全に暮らす方法を考えることだ。これからも防災について学び、身の回りの自然を大切にしていきたい。
『人がつくった川・荒川』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】自然と人間の共存を考える
『人がつくった川・荒川』という書名を見たとき、私は強い違和感を覚えた。川は自然の産物であり、山から海へと流れる水の道筋は自然の摂理によって決まるもの。それを「人がつくった」とはどういうことなのか。この疑問を抱きながら読み始めた本書は、私に人間と自然の関係について深く考えさせる機会を与えてくれた。
荒川の名前の由来は「荒れる川」である。かつての荒川は、現在の穏やかな流れとはほど遠い暴れ川だった。大雨が降れば瞬く間に水位が上がり、堤防を決壊させ、田畑や家屋を押し流していく。人々は常に洪水の恐怖と隣り合わせで生活していた。私は現代の整備された河川しか知らなかったため、この荒川の姿に大きな衝撃を受けた。
江戸時代、徳川家康は江戸の発展と洪水対策のために荒川の流路を大幅に変更した。これは単なる治水事業ではなく、都市計画の一環でもあった。川の流れを変えることで新田開発が進み、舟運が発達し、江戸は商業都市として繁栄した。人間が自然に働きかけることで文明が発達したという事実に、私は複雑な感情を抱いた。
しかし、流路の変更は新たな問題も生み出した。水の流れが変わったことで、これまで安全だった地域が水害に見舞われるようになったのだ。ある地域を守るために他の地域が犠牲になるという構図は、治水事業の宿命的な課題なのかもしれない。この部分を読んで、物事には必ず表と裏があることを改めて実感した。
明治時代に入ると、近代国家建設の一環として本格的な治水事業が開始された。中でも青山士という土木技師の存在は印象深い。彼は日本人として唯一パナマ運河建設に参加し、その経験を荒川放水路の建設に活かした。国際的な視野を持った技術者が日本の河川改修に取り組んだという事実に、明治時代の開放性と進取の精神を感じた。
荒川放水路の建設工事の写真を見ていると、当時の人々の並々ならぬ決意が伝わってくる。重機のない時代に、スコップと人力だけでこれほどの大工事を成し遂げたのだ。現在の私たちが享受している安全で快適な生活は、多くの先人たちの汗と努力の上に成り立っていることを痛感した。もし彼らの努力がなければ、今の都市の姿も大きく違っていたに違いない。
一方で、人工的な河川改修が自然環境に与えた影響についても考えさせられた。かつての荒川には豊かな湿地帯があり、多様な生物が生息していた。しかし、治水工事によってそれらの自然環境は失われてしまった。コンクリートで固められた河川は確かに安全だが、生物多様性という観点から見ると大きな損失である。人間の営みの裏で静かに失われていった自然の声にも、私たちは耳を傾ける必要があると感じた。
私の住む地域にも川が流れている。護岸工事が施され、遊歩道が整備された現在の姿しか知らなかったが、この本を読んでその川の歴史に興味を持つようになった。きっとこの川にも、人知れぬドラマがあったのだろう。地域の歴史を調べてみたいという気持ちが湧いてきた。自分が当たり前だと思っている風景にも、過去からの積み重ねがあると気づいたことは、大きな収穫だった。
現代の環境問題についての記述も印象深い。地球温暖化により豪雨の頻度と強度が増している今、従来の治水対策だけでは限界がある。近年の豪雨災害を見ていると、自然の力の前での人間の無力さを感じずにはいられない。これまで人間は自然をコントロールしようとしてきたが、これからは自然と共存する道を模索しなければならないのではないか。そのためには、過去の治水の歴史から学び、失敗や成功を次に活かす姿勢が求められる。
「グリーンインフラ」という言葉を本書で初めて知った。コンクリート主体の従来型インフラではなく、自然の機能を活用したインフラ整備という考え方である。これは人間と自然の新しい関係性を示唆しているように思える。完全に自然を支配するのでもなく、自然に翻弄されるのでもない、第三の道があるのかもしれない。人間の知恵と自然の力を両立させる仕組みづくりこそ、未来に向けての課題であり希望だと感じた。
『人がつくった川・荒川』を読んで、私は人間と自然の関係について多くのことを学んだ。人間は自然に働きかけることで文明を築いてきたが、その過程で多くのものを失ってもきた。これからの時代に求められるのは、過去の経験を踏まえた上で、持続可能な社会を構築することだろう。
荒川の歴史は、人間の英知と努力の記録であると同時に、自然との共生について考えさせる貴重な教材でもある。私たちの世代は、先人たちから受け継いだ知恵を活かしながら、次世代により良い環境を残していく責任がある。この本は、その重要性を改めて教えてくれた一冊だった。読み終えた今も、川の流れのように静かに問いかけが心に残り続けている。
振り返り
『人がつくった川・荒川』の読書感想文の書き方について、3つの要点からテンプレート、例文まで詳しく解説してきました。
この本は単なる河川の歴史書ではなく、人間と自然の関係について深く考えさせてくれる作品です。
荒川の治水に携わった人々の努力、現代の環境問題、そして未来への課題について、あなた自身の感想を織り交ぜながら書くことで、心に響く読書感想文が完成するはずです。
テンプレートや例文を参考にしながら、あなたらしい視点で『人がつくった川・荒川』について語ってみてくださいね。
きっと素晴らしい読書感想文が書けますよ。
■参考サイト:人がつくった川・荒川 – 株式会社旬報社


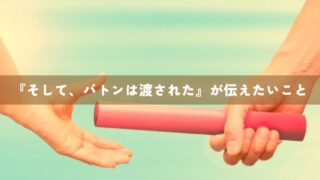


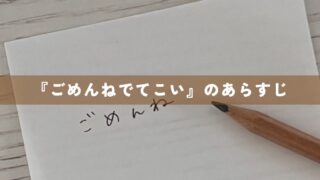

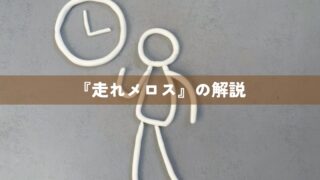




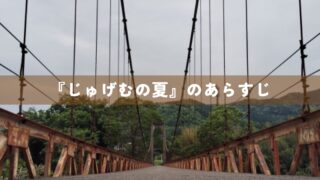



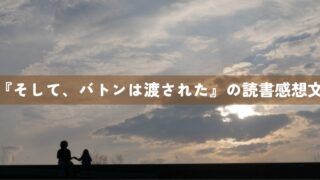


コメント