『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
山本悦子さんの『先生、しゅくだいわすれました』は、宿題を忘れた子どもたちが楽しい言い訳を考えて発表するという、ユーモアと想像力にあふれた物語ですね。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、小学生・中学生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文に書くべき3つのポイント
『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文を書く際に、絶対に触れておきたい重要なポイントが3つあります。
この3つのポイントを自分なりに感じたこととして書けば、深みのある感想文になりますよ。
まずは以下の3つのポイントを確認してみましょう。
- えりこ先生の教育方法のすばらしさ
- 子どもたちの創造性と表現力の成長
- 宿題の大切さを楽しく学ぶメッセージ
それぞれのポイントについて、物語を読みながら「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切です。
例えば「えりこ先生みたいな先生に教わりたい」「私もこんな面白い話を考えてみたい」「結局宿題はちゃんとやらないといけないんだな」といった素直な気持ちを書き留めておきましょう。
なぜこうしたメモが重要かというと、読書感想文は「本を読んで何を感じたか」を伝える文章だからです。
ただあらすじを書くだけでは感想文になりませんから、自分の心が動いた部分をしっかりと記録しておくことで、説得力のある感想文が書けるようになります。
えりこ先生の教育方法のすばらしさ
物語の中でえりこ先生は、宿題を忘れた子どもに対してただ叱るのではなく、「嘘をつくなら楽しい嘘をつきなさい」と言います。
この場面は、従来の厳しい教育とは全く違う、子どもの創造性を伸ばす新しい教育方法を表していますね。
えりこ先生の指導法は、子どもたちを萎縮させるのではなく、むしろ積極的に発言させ、想像力を育てることを重視しています。
皆さんもこの先生の教え方について、どう感じたかを考えてみてください。
「こんな先生がいたらいいな」と思ったか、それとも「やっぱり宿題は忘れちゃダメでしょ」と思ったか。
自分の学校の先生と比較してみるのもいいでしょうし、理想の先生像について考えてみるのも面白いですよ。
また、えりこ先生が子どもたちの話を最後まで聞いて、それを受け入れる姿勢についても注目してみましょう。
この寛容さが子どもたちの心を開かせ、クラス全体を明るくしていることがわかります。
現代の教育現場でも、このような子どもの気持ちに寄り添う指導が求められているのではないでしょうか。
子どもたちの創造性と表現力の成長
ゆうすけやりなが考える宿題を忘れた理由は、どれも想像力にあふれた楽しいものばかりです。
宇宙人に九九を教えた話、小さなねずみの家でパーティーをした話など、現実離れしているからこそ魅力的な物語になっています。
これらの話を通して、子どもたちは自分の想像力を存分に発揮し、クラスメイトの前で堂々と発表する表現力も身につけていきます。
皆さんも、もし宿題を忘れたときにこんな楽しい理由を考えられるか、想像してみてください。
きっと最初は難しいと感じるでしょうが、慣れてくると次々とアイデアが浮かんできそうですね。
この物語が伝えているのは、子どもたちの想像力は無限大だということ、そしてそれを表現する機会を与えることの大切さです。
普段の学校生活では、正解のある問題に答えることが多いですが、『先生、しゅくだいわすれました』では正解のない自由な発想が評価されています。
また、毎日誰かが新しい話を発表することで、クラス全体が楽しい雰囲気に包まれていることも重要なポイントです。
宿題の大切さを楽しく学ぶメッセージ
物語の最後で、ゆうすけは「宿題をさっさと終わらせる方が楽だ」と感じるようになります。
また、えりこ先生も自分が宿題を出さなかった理由を楽しい話で説明し、結果的に宿題の意味を子どもたちに伝えています。
この展開が示しているのは、楽しい言い訳を考えるよりも、実際に宿題をやってしまう方がずっと簡単だということです。
つまり、この物語は宿題を忘れることを推奨しているわけではなく、むしろ宿題の大切さを子どもたちに気づかせる工夫なのです。
皆さんも実際に宿題をやるのと、言い訳を考えるのと、どちらが大変か考えてみてください。
毎回創造的な話を考えるのは、実はとても頭を使う作業ですよね。
それならば最初から宿題をきちんとやってしまった方が、時間も労力も節約できると思いませんでしたか?
※『先生、しゅくだいわすれました』のあらすじはこちらで簡単にご紹介しています。

『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文のテンプレート
ここでは、『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文を簡単に書けるテンプレートを紹介します。
以下のステップに沿って空欄を埋めていけば、しっかりとした感想文が完成しますよ。
- 書き出し
『先生、しゅくだいわすれました』を読んで、私は( )と感じた。この物語は( )な話で、特に( )が印象的だった。 - えりこ先生について
えりこ先生の教え方は( )だと思った。なぜなら( )だからだ。私も( )な先生に教わりたいと思った。 - 子どもたちの想像力について
ゆうすけやりなが考える「宿題を忘れた理由」は( )で、私は( )と感じた。もし私が同じ立場なら( )な話を考えたいと思う。 - 宿題の大切さについて
物語の最後で、宿題をきちんとやることの大切さが( )という形で示されていた。私はこれまで宿題を( )と思っていたが、この本を読んで( )と考えるようになった。 - まとめ
この物語を通して、私は( )の大切さを学んだ。これからは( )を心がけて、( )な学校生活を送りたいと思う。
このテンプレートを使えば、重要なポイントを漏らすことなく感想文が書けます。
空欄には自分の素直な気持ちや体験を入れて、オリジナルの感想文を作り上げてくださいね。
『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】えりこ先生みたいになりたい
『先生、しゅくだいわすれました』を読んで、私は学校がもっと楽しい場所になればいいなと思った。
この本は、宿題を忘れた子どもたちが面白い話を作って先生に話すという、とてもユニークな物語だった。
読んでいる間、ずっと笑顔になってしまう素敵な本だった。
一番すごいと思ったのは、えりこ先生の教え方だった。
普通の先生なら宿題を忘れたら叱るはずなのに、えりこ先生は「楽しい嘘をつきなさい」と言ってくれた。
私の学校の先生も、もしかしたらこんな風に優しく指導してくれたら、もっと勉強が楽しくなるかもしれない。
えりこ先生みたいに、子どもの気持ちをわかってくれる大人になりたいと思った。
ゆうすけが宇宙人に九九を教えた話や、りなが小さなねずみと遊んだ話も、とても面白かった。
私も宿題を忘れた時に、こんな楽しい理由を考えられるだろうか。
きっと最初は難しいけれど、慣れれば次々とアイデアが浮かびそうだ。
想像力を使って物語を作るのは、勉強とは違った楽しさがあるのだと気づいた。
友達と一緒に面白い話を考え合うのも楽しそうだ。
でも、物語の最後で気づいたことがある。
ゆうすけは「宿題をやってしまう方が楽だ」と言っていたが、これはとても大切なメッセージだと思った。
毎日面白い話を考えるのは、実はとても大変なことなのだ。
それなら最初から宿題をきちんとやっておけば、こんなに苦労することもない。
私も今まで宿題を面倒だと思っていたが、この本を読んで考え方が変わった。
宿題は先生からの大切な贈り物で、それをきちんとやることで自分が成長できるのだと思う。
『先生、しゅくだいわすれました』を読んで、私は想像力の大切さと宿題の意味を同時に学ぶことができた。
これからは宿題を忘れないよう気をつけながら、えりこ先生やゆうすけたちみたいに、毎日を楽しく過ごしたいと思う。
そして将来は、えりこ先生のように子どもたちの気持ちをわかってあげられる大人になりたい。
『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】自由な発想が生むもの
『先生、しゅくだいわすれました』を読んで、今の学校や勉強について色々と考えた。この本は、宿題を忘れた子どもたちが面白い言い訳を発表するお話で、子どもの想像力を大切にする素敵な学校を描いている。山本悦子さんが書いたこの学校は、僕たちがいつも通っている学校とはまるで違う、やさしくて自由な場所だった。
主人公のえりこ先生の教え方には、今の学校に必要なことがたくさん詰まっていると思う。普通なら、宿題を忘れた生徒は怒られたり罰を受けたりするけれど、えりこ先生は全然違う。「楽しいうそをついてごらん」という言葉は最初は変だなと思ったけれど、実は子どもたちの想像力をのばす上手なやり方だった。
この方法のおかげで、子どもたちは怖がることなく、どんどん自分の考えを話すようになっている。僕の小学校生活を思い出してみると、こんなに自由に発想していい時間はあまりなかった。えりこ先生みたいな先生がもっといたら、たくさんの子どもたちが表現することが得意になるんじゃないかと思う。
ゆうすけやりなが考える宿題を忘れた理由は、どれもすごく面白くて想像力がいっぱいだった。宇宙人が来たとか、小さなねずみとパーティーをしたとか、現実にはありえない話だけど、聞いていてワクワクした。彼らはただの言い訳を考えているんじゃなくて、本当はすごい物語を作っているのだ。お話を考えて、みんなを楽しませて、クラスの前で堂々と発表する勇気も身につけている。これは国語や道徳の授業では学べない、とても大切な経験だと思う。
今の世の中では創造性や表現力がとても大事だと言われているけれど、この物語はそういう力を育てるのにぴったりの環境を教えてくれている。でも一番大切なメッセージは、最後の部分にあると思う。ゆうすけが「宿題をやった方が楽だ」と気づく場面は、この本が宿題をバカにしているわけじゃないことを表していた。創造的な言い訳をずっと考えるのは大変だということを体験して、子どもたちは自然と宿題の大切さが分かるようになる。これは口で説明するよりもずっと効果的な教え方だと感じた。
僕も中学生になって宿題が増えて、めんどくさいなと思うことがあるけれど、この本を読んで宿題に対する気持ちが変わった。宿題はただやらなければいけないことじゃなくて、自分の勉強のためになる大事なものなんだと改めて分かった。
それから、えりこ先生が自分も宿題を出し忘れた理由を楽しい話で説明する場面もとても印象に残った。先生と生徒が同じように創作を楽しんで、お互いの話をちゃんと聞き合う関係は理想的だと思う。こういう信頼できる関係があるから、子どもたちは安心して想像力を使えるんだと思う。
『先生、しゅくだいわすれました』は、学校での創造性と決まりごとのバランスをとても上手に描いた作品だった。この物語を読んで、僕は勉強に対する考え方や教育の本当の意味について色々なことを考えることができた。これからの学校生活では、宿題をきちんとやりながらも、えりこ先生や子どもたちのような想像力と表現力も大切にしていきたいと思う。
振り返り
『先生、しゅくだいわすれました』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つのポイントを押さえて、テンプレートを活用すれば、きっと皆さんも素晴らしい感想文が書けるはずです。
大切なのは、物語を読んで自分が本当に感じたことを素直に表現することです。
えりこ先生の教育方法に感動したのか、子どもたちの想像力に驚いたのか、宿題の大切さに気づいたのか。
そうした自分だけの気持ちを大切にして、オリジナルの感想文を完成させてくださいね。
皆さんの感想文が、きっと先生方にも届く心のこもった作品になることを願っています。
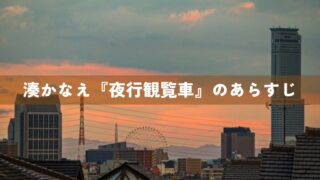



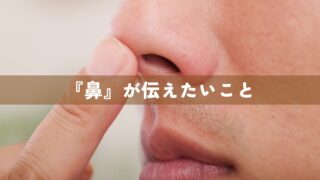
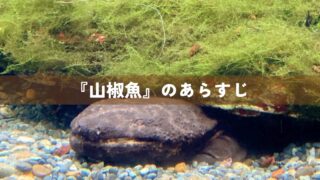




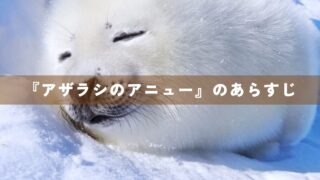

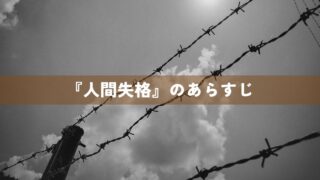


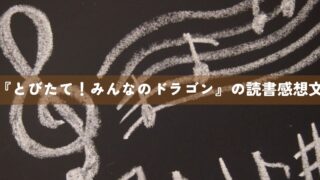
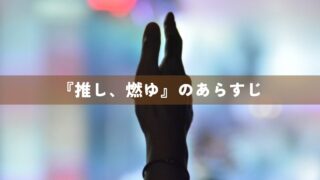

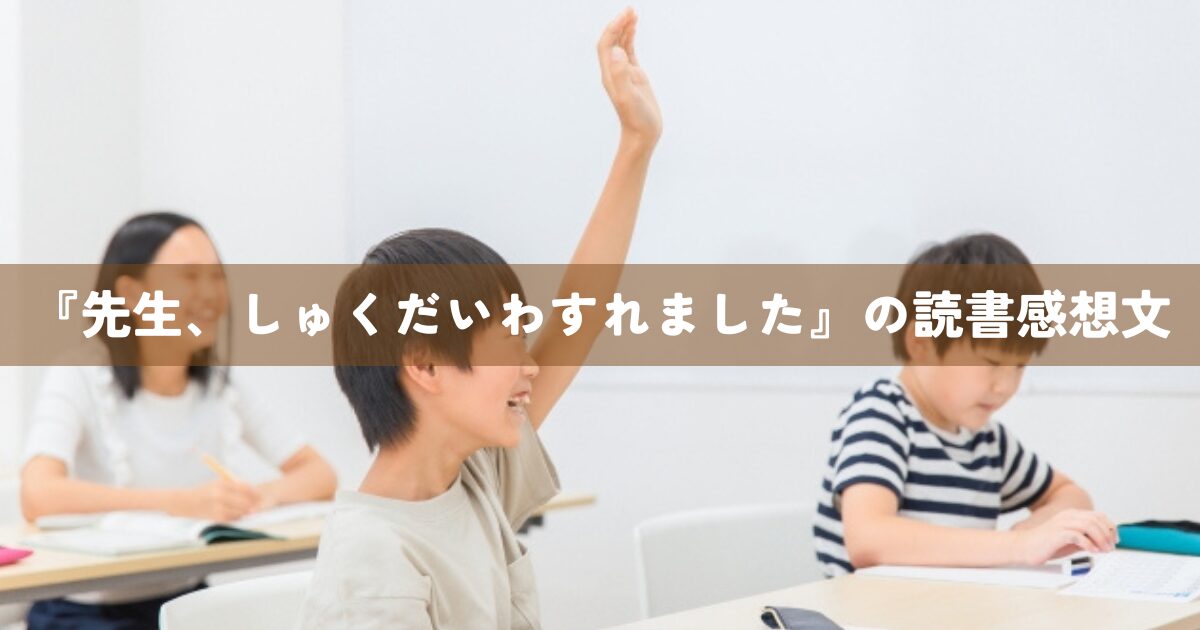
コメント