『エルマーのぼうけん』の読書感想文を書く予定の皆さん、お疲れさまです。
ルース・スタイルス・ガネット作の『エルマーのぼうけん』は、9歳の少年エルマーが捕らわれた竜の子どもを助けるために危険などうぶつ島へ向かう心温まる冒険物語ですね。
1948年にアメリカで出版されたこの作品は、日本でも1963年から福音館書店の「世界傑作童話」シリーズとして渡辺茂男さんの翻訳で親しまれ、多くの子どもたちに愛され続けています。
読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、小学生の低学年/高学年・中学生の皆さんに向けて、この作品の読書感想文の書き方や例文、題名の付け方、書き出しのコツまで詳しく解説していきますよ。
コピペではなく、皆さん自身の言葉で心に響く感想文が書けるよう、しっかりとサポートしていきますので、安心してお付き合いください。
『エルマーのぼうけん』の読書感想文で触れたい3つの要点
『エルマーのぼうけん』の読書感想文を書く際には、以下の3つの重要なポイントを押さえることが大切です。
これらの要点について、皆さんがどう感じたかをしっかりとメモしておくことをおすすめします。
- エルマーの勇気と知恵による問題解決
- 動物たちとの交流を通じて描かれる友情と思いやり
- 冒険を通じて広がる想像力とワクワク感
メモを取るときは、各場面を読みながら「なぜエルマーはこんなに勇敢なんだろう」「この場面で自分ならどうするだろう」「この動物の気持ちはどうだったのかな」といった疑問や感想を書き留めておくといいでしょう。
なぜ「どう感じたか」が重要なのかというと、読書感想文は単なるあらすじの紹介ではなく、あなた自身の心の動きや気づきを表現する文章だからです。
あなたの素直な気持ちこそが、読み手の心に響く感想文の核になるんですよ。
エルマーの勇気と知恵による問題解決
『エルマーのぼうけん』で最も印象的なのは、主人公エルマーが持つ並外れた勇気と機転の良さです。
エルマーは年老いた野良猫から竜の子どもが捕らわれているという話を聞くと、迷うことなく一人で危険などうぶつ島へ向かいます。
9歳の少年にとって、見知らぬ島での冒険は恐ろしいはずなのに、エルマーは困っている誰かを助けたいという純粋な気持ちで行動するのです。
さらに注目すべきは、エルマーが力ずくで問題を解決しようとしないことです。
トラにはチューインガムを与えて興味をそらし、サイには歯ブラシで角を磨いてあげ、ライオンにはくしとリボンでたてがみを美しく飾ってあげます。
これらは全て、相手の立場に立って何を求めているのかを理解し、自分の持っている道具を創意工夫で活用した結果なのです。
皆さんも日常生活で困ったとき、力や権力に頼るのではなく、相手の気持ちを考えて知恵を働かせることの大切さをエルマーから学べるのではないでしょうか。
また、エルマーが持参した道具の選び方も興味深いポイントです。
チューインガム、輪ゴム、歯ブラシ、虫眼鏡など、一見すると冒険には不要そうなものばかりですが、これらが全て重要な役割を果たします。
これは事前の準備と計画の大切さを教えてくれると同時に、身の回りにある何気ないものでも使い方次第で大きな力を発揮することを示しています。
読書感想文では、エルマーのこうした問題解決能力について、自分だったらどう行動するか、どんな道具を持参するかなど、具体的な例を交えて書くと良いでしょう。
動物たちとの交流を通じて描かれる友情と思いやり
『エルマーのぼうけん』のもう一つの魅力は、エルマーと様々な動物たちとの心温まる交流です。
最初は敵対関係にあった動物たちも、エルマーの優しさと思いやりに触れることで、次第に協力的な存在へと変わっていきます。
特に印象的なのは、エルマーが動物たちを騙したり脅したりするのではなく、彼らの悩みや困りごとを解決してあげることで信頼関係を築いていく点です。
サイは汚れた角に悩んでいて、ライオンはたてがみに絡まった木の枝に困っていて、ゴリラは体についたノミに悩まされています。
エルマーはこれらの問題を一つずつ解決し、動物たちの立場に立って行動することで、真の友情を育んでいくのです。
そして何より重要なのは、竜の子ども(ボリス)との関係です。
エルマーは最初から竜を助けることを目的としていましたが、実際に出会ってみると、単なる「助ける者」と「助けられる者」の関係を超えた深い友情が生まれます。
二人は困難を共に乗り越え、最後には竜の背中に乗って大空へ舞い上がるのです。
この場面は、真の友情とは一方的な助けではなく、お互いを支え合う関係であることを美しく描いています。
皆さんも友達との関係を振り返ってみて、困ったときに助け合った経験や、相手の気持ちを理解しようと努力した思い出があるのではないでしょうか。
読書感想文では、エルマーと動物たちの交流から学んだことを、自分の体験と照らし合わせて書くと、より深みのある内容になりますよ。
冒険を通じて広がる想像力とワクワク感
『エルマーのぼうけん』が多くの子どもたちに愛され続ける理由の一つは、読者の想像力をかき立てる魅力的な冒険の描写です。
どうぶつ島という不思議な場所、そこに住む個性豊かな動物たち、そしてエルマーが次々と遭遇する予想外の出来事は、読む人を物語の世界へと引き込んでいきます。
特に注目したいのは、作者が読者の想像力を大切にした描写を心がけている点です。
動物たちの外見や島の風景は詳細すぎず、読者一人ひとりが自分なりにイメージを膨らませられる余地を残しています。
これによって、同じ物語を読んでも人それぞれ異なる「自分だけのどうぶつ島」を頭の中に描くことができるのです。
また、エルマーの冒険は決して順調ではなく、次から次へと困難が現れます。
しかし、それぞれの困難が解決されるたびに読者は安堵し、同時に「次はどんなことが起こるのだろう」というワクワク感を味わうことができます。
このような起伏に富んだストーリー展開は、読書の醍醐味の一つでもありますね。
さらに、この物語は「空を飛ぶ」という多くの子どもたちが抱く夢を叶えてくれます。
竜の背中に乗って大空を飛ぶエルマーの姿は、読者に「自分も一緒に飛んでいるような気持ち」を与えてくれるでしょう。
読書感想文では、皆さんがこの物語を読みながら頭の中に描いた風景や、どの場面で一番ワクワクしたかなどを具体的に書いてみてください。
また、もし自分がエルマーの立場だったら、どんな冒険をしてみたいか、どんな動物と友達になりたいかなど、想像を膨らませて書くのも素敵ですよ。
『エルマーのぼうけん』の読書感想文の例文(800字/小学校低学年)
【題名】エルマーと一緒に飛んだ気持ち
私は『エルマーのぼうけん』を読んで、とてもワクワクした。
エルマーという9歳の男の子が、捕らわれた竜の子どもを助けるために一人でどうぶつ島に行く話だった。
私と同じくらいの年の子が、こんなに勇敢なのがすごいと思った。
一番すごいと思ったのは、エルマーがいろいろな道具を使って動物たちの問題を解決するところだった。
トラにはチューインガムをあげて、サイには歯ブラシで角を磨いてあげて、ライオンにはリボンでたてがみを飾ってあげた。
私だったら怖くて逃げてしまうと思うのに、エルマーは動物たちが何を困っているのかを考えて助けてあげるのがやさしいと思った。
特に心に残ったのは、17匹のワニを輪ゴムと棒付きキャンディーで一列にして橋にするところだった。
最初は「そんなことできるの?」と思ったけれど、読んでいるうちに「エルマーならできそう」という気持ちになった。
身の回りにある普通のものでも、アイデア次第でとても役に立つことを教えてもらった。
私も家にあるものを見回して、「これは何かの役に立つかな」と考えるようになった。
竜の子どものボリスと出会う場面も好きだった。
ボリスは捕らわれて悲しい思いをしていたけれど、エルマーに助けられてとても嬉しそうだった。
エルマーがジャックナイフで綱を切ってボリスを自由にしてあげるとき、私も一緒にいるような気持ちになった。
最後に二人が竜の背中で空を飛ぶところでは、私も一緒に飛んでいるような気分になって、とても気持ちよかった。
空を飛ぶのは私の夢でもあるので、エルマーがうらやましかった。
この本を読んで、困っている人がいたら助けてあげたいという気持ちが強くなった。
エルマーのように勇気を出して、相手の立場に立って考えることが大切だと分かった。
また、普段使っているものでも工夫次第でいろいろなことができることも学んだ。
私もエルマーのように、知恵と優しさを使って問題を解決できる人になりたいと思った。
そして、いつか本当に空を飛んでみたいと思った。
『エルマーのぼうけん』は、勇気と友情と冒険がいっぱい詰まった素晴らしい本だった。
『エルマーのぼうけん』の読書感想文の例文(1200字/小学校高学年)
【題名】小さな道具に込められた大きな知恵
私は『エルマーのぼうけん』を読んで、エルマーの勇気と知恵に感動した。
この物語は、9歳の少年エルマーが捕らわれた竜の子どもを助けるために危険などうぶつ島へ向かう冒険だが、いろいろな深いメッセージが込められていると思う。
最も心に残ったのは、エルマーの問題を解決する能力だ。
彼は力で動物たちを倒すのではなく、相手が何に困っているかを見抜き、持参した道具を使って解決していく。
トラにはチューインガムを与え、サイには歯ブラシで角を磨き、ライオンには櫛とリボンでたてがみを整えてあげる。
これらの行動は、相手の立場に立って考える思いやりの心から生まれたものだった。
私は普段、困った時に力で解決しようとしたり、誰かに頼ったりすることが多いが、エルマーのように相手の気持ちを理解して行動することの大切さを学んだ。
特に感心したのは、エルマーが持参した道具の選び方だ。
チューインガム、輪ゴム、歯ブラシ、虫眼鏡など、一見すると冒険には関係なさそうなものばかりだが、これらが大切な役割を果たす。
これは準備と計画の重要性を教えてくれると同時に、身の回りにあるものでも使い方次第で大きな力を持つことを教えてくれるようだった。
次に心を打たれたのは、エルマーと動物たちとの友情だ。
最初は敵対していた動物たちも、エルマーの優しさに触れることで協力的になっていく。
特に竜の子どものボリスとの関係は素晴らしかった。
エルマーは単にボリスを助けるだけでなく、彼の気持ちを理解して友情を育んでいく。
最後に二人が竜の背中で空を飛ぶ場面では、私も一緒に大空を舞っているような気持ちになった。
この場面から、真の友情とは一方的な助けではなく、お互いを支え合う関係であることを学んだ。
私にも困った時に助けてくれる友達がいるが、私も相手が困った時には支えてあげたいと強く思った。
また、この物語の魅力の一つは、読者の想像力をかき立てる描写だと思う。
どうぶつ島の風景や動物たちの姿は、読む人それぞれが自分なりに想像できるように描かれている。
私が頭の中に描いたどうぶつ島は、緑豊かで川が流れる美しい場所だった。
そこで繰り広げられるエルマーの冒険は、まるで映画を見ているようにワクワクした。
特に17匹のワニを輪ゴムと棒付きキャンディーで一列にして橋を作る場面は、最初は「本当にできるのかな」と思ったが、エルマーの機転の利いた発想に感心した。
この物語を読んで、私は三つの大切なことを学んだ。
一つ目は、困難に直面した時に諦めずに知恵を働かせることの重要性。
二つ目は、相手の立場に立って考え、思いやりの心を持って行動することの大切さ。
そして三つ目は、真の友情とは互いを支え合う関係であること。
エルマーのように、勇気と優しさと知恵を持った人になりたいと心から思った。
そして、いつか私も本当に空を飛んでみたいという夢を抱いた。
『エルマーのぼうけん』は、素晴らしい冒険小説であり、人生の大切な価値を教えてくれる貴重な物語だと思う。
『エルマーのぼうけん』の読書感想文の例文(1500字/中学生)
【題名】真の勇気とは何かを教えてくれた物語
『エルマーのぼうけん』を読んで、私は主人公のエルマーから多くのことを学んだ。
この作品は1948年に出版された古典的な児童文学だが、現代に生きる私たちにも通じる普遍的なメッセージが込められていると感じた。
物語の核心にあるのは、9歳の少年エルマーが見せる真の勇気である。
エルマーが竜の子どもを助けるために一人でどうぶつ島へ向かう決意には、単なる無謀さではない深い意味がある。
彼は困っている誰かを放っておけないという純粋な正義感から行動を起こすのだ。
現代社会では、「関わらない方が無難」「自分に被害が及ばないようにする」という考えが広まっているが、エルマーの姿勢はそれとは正反対である。
私自身も学校生活で困っている友達がいても、「余計なお世話かもしれない」と躊躇してしまうことがある。
しかし、エルマーの行動を見て、真の勇気とは危険を冒すことではなく、正しいと思うことを実行に移すことなのだと理解した。
また、エルマーの問題を解決する能力には目を見張るものがある。
彼は力ずくで動物たちを制圧するのではなく、相手が抱える問題を見抜き、創意工夫でそれを解決していく。
トラにはチューインガムを与えて気をそらし、サイには歯ブラシで角を磨いて自信を回復させ、ライオンには櫛とリボンでたてがみを美しく飾ってプライドを満たしてあげる。
これらの行動には、相手の立場に立って考える共感力と、限られた資源を最大限に活用する知恵が表れている。
現代社会でも、対立や問題の多くは互いの理解不足から生じている。
エルマーのように相手の本当の気持ちを理解し、お互いに利益をもたらす関係を築く姿勢は、私たち中学生にとっても見習えるところだろう。
私も友達との意見の相違があった時、相手の立場に立って考えることで解決策を見つけられるのではないかと思った。
さらに印象深いのは、エルマーと竜の子どものボリスとの友情である。
最初は「助ける者」と「助けられる者」の関係だった二人が、冒険を通じて対等な友達になっていく過程が美しく描かれている。
真の友情とは、一方的な施しではなく、互いを尊重し支え合う関係であることを物語は教えてくれる。
現代のSNS社会では表面的な「いいね」のやり取りが多いが、本当に困った時に支え合える関係こそが大切なのだと改めて感じた。
この作品のもう一つの魅力は、読者の想像力を刺激する描写である。
どうぶつ島の風景や動物たちの姿は、読む人それぞれが自分なりのイメージを膨らませられるように描かれている。
私が想像したどうぶつ島は、密林に覆われた神秘的な場所で、そこで繰り広げられるエルマーの冒険はまさに手に汗握るものだった。
特に17匹のワニを輪ゴムと棒付きキャンディーで一列につなぎ、橋として利用するアイデアには驚嘆した。
この場面は、思い込みにとらわれない柔軟な発想のお手本だと思う。
私たち中学生も受験勉強や部活動で困難に直面することがあるが、固定観念にとらわれずに新しい解決策を考える姿勢を持ちたいと思った。
『エルマーのぼうけん』は、表面的には子ども向けの冒険小説に見えるかもしれない。
しかし、その奥には人間関係の本質、問題解決の知恵、真の勇気とは何かといった深いテーマが込められている。
エルマーのように、困っている人を見過ごさない正義感、相手の立場に立って考える共感力、そして創意工夫で問題を解決する知恵を身につけたいと心から思った。
竜の背中で大空を飛ぶエルマーとボリスの姿は、私の心の中でいつまでも輝き続けるだろう。
振り返り
今回は『エルマーのぼうけん』の読書感想文について、詳しく解説してきました。
この記事では、感想文を書く際に押さえておきたい3つの重要なポイントから、小学生・中学生それぞれのレベルに合わせた例文まで紹介しましたね。
エルマーの勇気と知恵、動物たちとの友情、そして冒険を通じて広がる想像力という3つの要点を意識することで、きっと素晴らしい感想文が書けるはずです。
大切なのは、物語を読みながら皆さんが感じた素直な気持ちを大切にすることです。
「エルマーのこの行動がすごいと思った」「自分だったらどうするだろう」「この場面でワクワクした」といった皆さんの心の動きこそが、読み手に伝わる感想文の核となります。
今回紹介した例文は参考程度に留めて、ぜひ皆さん自身の言葉で『エルマーのぼうけん』への想いを綴ってください。
きっと先生や友達に皆さんの気持ちが伝わる、心温まる感想文が完成しますよ。
頑張って書き上げてくださいね。
※『エルマーのぼうけん』のあらすじはこちらで簡単に短くまとめています。


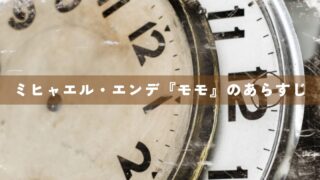
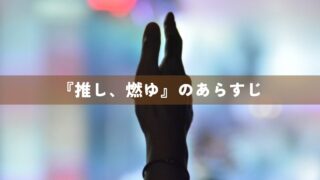
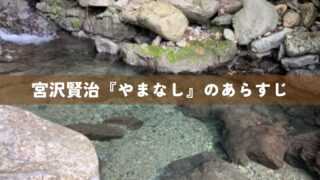
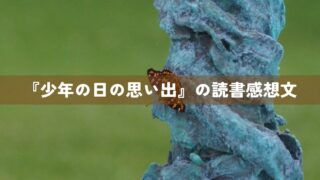


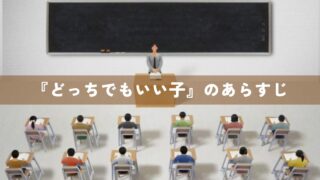
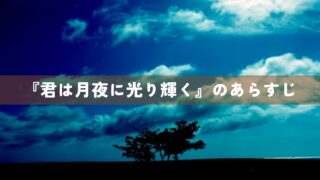


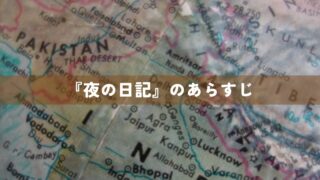
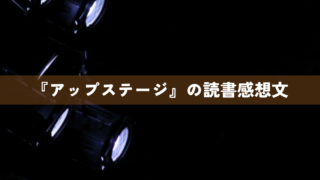


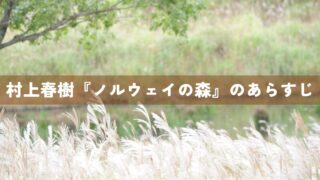

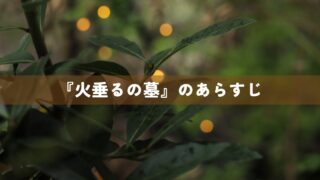

コメント