『オルタネート』の読書感想文を書く予定の中学生・高校生のみなさん、こんにちは。
加藤シゲアキさんが手がけた青春小説『オルタネート』の読書感想文について、詳しく解説していきますよ。
『オルタネート』は、高校生限定のマッチングアプリが普及した近未来を舞台にした群像劇です。
第164回直木三十五賞候補、第42回吉川英治文学新人賞受賞作品という輝かしい実績を持つ注目の作品ですね。
物語は東京の円明学園高校を中心に、3人の高校生の視点で進んでいきます。
調理部の部長でトラウマを抱える蓉、マッチングアプリを信奉する凪津、高校を中退して上京した尚志の3人が主人公です。
この記事では、年間100冊以上の本を読む私が『オルタネート』の読書感想文の書き方について、例文とともに丁寧に説明していきます。
中学生向けと高校生向けの例文も用意しているので、コピペではなく参考にして自分なりの感想文を書いてくださいね。
書き出しから題名の付け方まで、読書感想文のコツをしっかりお伝えしますよ。
『オルタネート』の読書感想文で触れたい3つの要点
『オルタネート』の読書感想文を書く際に押さえておきたい要点を3つご紹介します。
- デジタル時代における人間関係の変化と課題
- コンプレックスを抱える若者たちの心理と成長
- 群像劇として描かれる現代青春の多面性
これらの要点について、読書中や読後に「自分はどう感じたか」をメモしておくことが大切です。
感想文は単なるあらすじ紹介ではなく、あなた自身の心の動きや気づきを表現するものだからです。
メモを取るときは、「なぜそう感じたのか」「自分の体験と重なる部分はあるか」「登場人物の行動をどう思うか」といった視点で書き留めてください。
こうした感情の記録が、説得力のある感想文の土台になるんです。
それぞれの要点について詳しく見ていきましょう。
デジタル時代における人間関係の変化と課題
『オルタネート』の中心となるのは、高校生限定のマッチングアプリです。
AIが遺伝子レベルで相性を判断する「ジーンマッチ」機能まで登場する近未来的な設定ですね。
このアプリを通じて、現代の私たちが直面するSNSやデジタルコミュニケーションの問題が浮き彫りになります。
凪津がアプリのデータに依存して運命の相手を探す姿は、現実の私たちがスマートフォンやSNSに振り回される様子と重なります。
一方で、アプリを使えない尚志は、音楽を通じた偶然の出会いやリアルな人間関係を求めて行動します。
デジタルな繋がりの便利さと危険性、そしてアナログな関係の温かさについて、あなたはどう感じましたか。
現代を生きる私たちにとって、人と繋がるとはどういうことなのでしょう。
この要点について感想文で触れる際は、自分のSNS体験や友人関係と照らし合わせて考えてみてください。
コンプレックスを抱える若者たちの心理と成長
『オルタネート』の3人の主人公は、それぞれ深刻な悩みやコンプレックスを抱えています。
蓉は過去の料理コンテストでの失敗がトラウマとなり、自分の料理に自信を持てません。
凪津は母親との関係に軋轢があり、アプリを通じて理想の愛を求めますが、現実の人間関係から逃げている面もあります。
尚志は高校を中退したため、同世代とは違う立場に置かれ、居場所を探し続けています。
彼らの心の動きや葛藤は、多くの読者が共感できる普遍的なものです。
特に思春期の若者にとって、自分らしさを見つけることや他者との関係に悩むことは避けて通れない課題ですね。
登場人物たちがどのように自分の弱さと向き合い、成長していくかという点に注目してください。
あなた自身の経験や悩みと重なる部分があれば、それを感想文に盛り込むことで説得力が増します。
完璧でなくても、一歩ずつ前に進もうとする彼らの姿から、どんなメッセージを受け取ったでしょうか。
群像劇として描かれる現代青春の多面性
『オルタネート』は3人の視点で語られる群像劇です。
一見バラバラに進む3つの物語が、やがて一つの大きな流れに収束していく構成が印象的ですね。
異なる立場や境遇にある登場人物たちを多角的に描くことで、現代の高校生が置かれた状況の複雑さが浮かび上がります。
料理部での活動、マッチングアプリへの依存、音楽を通じた仲間探しなど、それぞれのエピソードが現代的なテーマを含んでいます。
文化祭を舞台に3人の運命が交錯する終盤は、群像劇ならではの醍醐味を味わえる場面です。
この構成によって、読者は登場人物それぞれの立場に立って物語を理解できます。
多様な価値観や生き方があることを認め合う大切さも描かれていますね。
あなたは3人の中で誰に一番共感しましたか。
それぞれの登場人物から学んだことや気づいたことを整理して、感想文に活かしてください。
現代を生きる若者の多様性と、それでも共通する悩みや願いについて、どう感じたかを書いてみましょう。
『オルタネート』の読書感想文の例文(中学生向け・約1200字/原稿用紙3枚分)
【題名】つながりの本当の意味
『オルタネート』を読んで、私は人と人がつながることの本当の意味について深く考えさせられた。
この物語には、高校生限定のマッチングアプリ「オルタネート」が登場する。
AIが遺伝子レベルで相性を判断する未来的な設定だが、現在の私たちの周りにあるSNSやアプリと本質的には変わらないと感じた。
主人公の一人である凪津は、このアプリを強く信じて運命の相手を探している。
しかし、彼女の行動を見ていると、本当は心の奥で孤独を感じているのではないかと思った。
アプリのデータに頼って相手を選ぶということは、自分の気持ちや相手の本当の姿を見ようとしていないということだからだ。
私も普段、LINEやInstagramを使って友達とやりとりしているが、画面越しのコミュニケーションでは伝わらないことがたくさんある。
顔の表情や声のトーン、その場の空気感など、実際に会って話すからこそ分かることがあるのだ。
調理部部長の蓉は、過去の失敗から料理に自信を失っている。
彼女の気持ちは私にもよく分かる。
一度失敗すると、また同じことが起こるのではないかと不安になってしまうからだ。
でも、蓉が再び料理コンテストに挑戦しようとする姿を見て、大きな勇気をもらった。
失敗を恐れていては何も始まらないし、大切なのは諦めずに続けることなのだと教えられた。
高校を中退した尚志は、規約でアプリを使うことができない。
最初は可哀想だと思ったが、読み進めるうちに、彼だからこそ得られる出会いや経験があることに気づいた。
音楽を通じて人とつながろうとする尚志の姿は、とても自然で温かい。
デジタルな手段に頼らなくても、共通の趣味や価値観を通じて深い関係を築くことができるのだ。
物語の終盤で、3人の運命が文化祭で交錯する場面は特に印象的だった。
バラバラだった物語が一つにつながる瞬間は、まさに奇跡のように感じられた。
これは偶然ではなく、それぞれが自分なりに努力し、人とのつながりを大切にしてきた結果なのだと思う。
この本を読んで、私は本当のつながりとは何かを考えるようになった。
スマートフォンやSNSアプリは便利な道具だが、それだけに頼っていては表面的な関係しか築けない。
相手の気持ちを理解しようとする努力や、自分の本当の気持ちを伝える勇気が必要なのだ。
また、完璧である必要はないということも学んだ。
蓉のように失敗を恐れたり、凪津のように理想を追い求めすぎたりすることもあるだろう。
それでも、自分らしく生きようとする気持ちを持ち続けることが大切だと感じた。
『オルタネート』は、現代を生きる私たちに多くのことを教えてくれる作品だった。
人とのつながりを大切にし、自分自身と向き合う勇気を持って、これからの学校生活を送っていきたいと思う。
『オルタネート』の読書感想文の例文(高校生向け・約2000字/原稿用紙5枚分)
【題名】デジタル社会に生きる私たちの選択
『オルタネート』を読み終えた今、私は自分自身の人間関係や価値観について深く考えさせられている。
加藤シゲアキ氏が描く近未来の高校生たちの物語は、フィクションでありながら、現実の私たちが直面している問題を鋭く映し出していた。
高校生限定のマッチングアプリ「オルタネート」が当たり前の世界は、もはや遠い未来の話ではないだろう。
現在でもSNSやマッチングアプリが若者の人間関係に大きな影響を与えているからだ。しかも、その影響は年々大きくなっており、私たちは日々、情報の海の中で自分の立ち位置を探している。
物語の中で最も印象的だったのは、3人の主人公それぞれが抱える現代的な悩みと、それに対する向き合い方の違いである。
凪津がアプリのデータに依存して運命の相手を探す姿は、現代の私たちがデジタル情報に振り回される様子と重なった。
彼女は母親との関係に問題を抱え、理想的な愛を求めてアプリにのめり込んでいく。
この行動の背景には、現実の人間関係で傷つくことを恐れる気持ちがあるのではないかと感じた。
データで相性が保証されていれば、傷つくリスクを減らせると考えているのかもしれない。
しかし、そこには大きな矛盾がある。
本当の愛や友情は、リスクを取って相手と向き合うからこそ生まれるものだからだ。
私自身も、SNSで「いいね」の数を気にしたり、相手の反応を予測してメッセージを送ったりすることがある。
凪津の行動を見て、自分もデジタルな安心感に逃げている部分があることに気づかされた。
一方で、調理部部長の蓉の心境には深く共感した。
過去の失敗がトラウマとなり、自分の能力に自信を持てない彼女の気持ちは、多くの高校生が経験することだろう。
私も部活動や勉強で失敗したとき、同じような気持ちになったことがある。
特に、他人と比較されたり評価されたりする場面では、自分の価値を見失いそうになることがある。
それでも、蓉が料理コンテストに再挑戦しようとする姿は、そんな私に勇気を与えてくれた。
完璧でなくても、失敗を恐れずに挑戦し続けることの大切さを教えられた。
彼女の奮闘は、自分に足りない勇気や情熱に気づかせてくれるものであり、自分自身もまた、少しずつ前を向いて努力していこうという気持ちになった。
高校を中退した尚志の立場は、他の二人とは大きく異なる。
アプリを使えない彼は、音楽という共通言語を通じて人とのつながりを求めている。
最初は不利な立場にあるように思えたが、読み進めるうちに、彼だからこそ得られる本質的な出会いがあることが分かった。
デジタルツールに頼らない分、相手の人間性や内面をより深く理解しようとする姿勢が印象的だった。
彼が紡ぐ言葉やメロディには、誰かとつながりたいという切実な願いが込められていて、胸を打たれた。
尚志の存在は、私たちがデジタル社会で失いつつあるものを象徴しているように感じる。
偶然の出会い、直感的な判断、時間をかけて築く信頼関係など、効率性とは対極にある価値を大切にしている。
この物語が群像劇として構成されていることも重要な意味を持っている。
3人の異なる視点を通じて、現代の高校生が置かれた状況の複雑さが浮き彫りになる。
一つの正解があるわけではなく、それぞれが自分なりの方法で課題に向き合っているのだ。
私たちの世代は、前の世代が経験したことのないデジタル社会で青春を過ごしている。
SNSでの人間関係、オンライン学習、デジタルネイティブとしての責任など、新しい課題に直面している。
それらにどう向き合い、自分らしく生きるのかは、私たち一人ひとりに委ねられている。
『オルタネート』は、そんな私たちに一つの道標を示してくれる作品だった。
物語の終盤で3人の運命が交錯する場面は、偶然ではなく必然だったと感じる。
それぞれが自分なりに努力し、人とのつながりを大切にしてきた結果として、奇跡的な出会いが生まれたのだ。
これは現実の私たちにも当てはまることだろう。
表面的な関係だけでなく、時間をかけて築く深いつながりを大切にすることで、人生は豊かになるのだ。
この作品を読んで、私は自分の人間関係を見直すきっかけを得た。
便利なデジタルツールを活用しながらも、それに依存しすぎないバランス感覚が重要だと感じる。
相手の顔を見て話すこと、時間をかけて理解し合うこと、失敗を恐れずに挑戦することの価値を改めて認識した。
そして、情報や効率だけでは測れない「人と人とのあたたかいつながり」の尊さを強く感じた。
『オルタネート』は、現代を生きる私たちに多くの示唆を与えてくれる優れた青春小説である。
デジタル社会の恩恵を受けながらも、人間らしさを失わない生き方を模索していきたいと思う。
振り返り
『オルタネート』の読書感想文について詳しく解説してきました。
この記事で紹介した3つの要点と例文を参考にすれば、きっと素晴らしい感想文が書けるはずです。
大切なのは、物語のあらすじを説明するのではなく、あなた自身がどう感じたかを正直に表現することです。
登場人物の心情に共感した部分や、現代社会への気づきなど、あなたの心に響いた部分を中心に書いてくださいね。
読書感想文は、本と向き合った証であり、あなた自身の成長の記録でもあります。
完璧を求めすぎず、等身大の感想を大切にして、自分らしい文章を書いてください。
きっと読み手の心に響く、素敵な感想文が完成するでしょう。
※『オルタネート』のあらすじはこちらでご紹介しています。


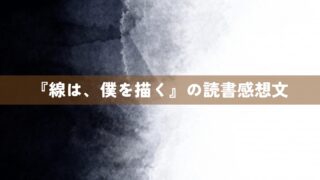
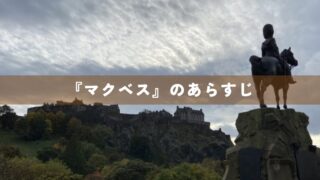
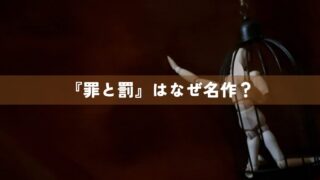


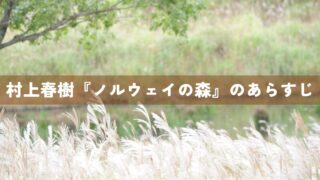
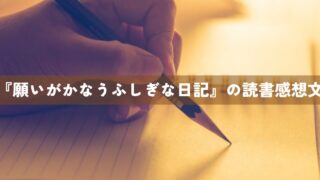
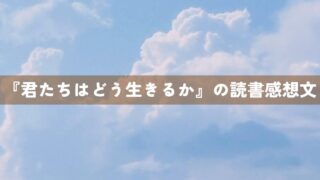




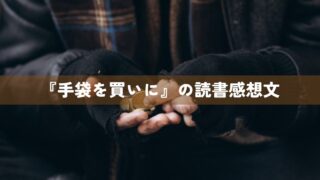
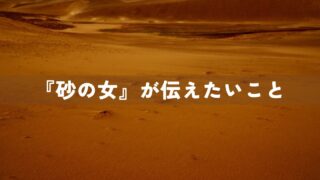


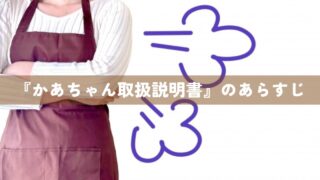

コメント