『吾輩は猫である』の読書感想文を書く予定の学生さんたちに向けて、書き方や例文をご紹介していきますよ。
夏目漱石の代表作『吾輩は猫である』は、名前のない一匹の猫が語り手となって明治時代の人間社会を観察し、痛烈に風刺した長編小説。
今回は読書が趣味で年間100冊以上の本を読む私が、中学生や高校生の皆さんが読書感想文を書く際に役立つよう、書き出しから題名の付け方まで、具体的な例文とともにコピペできるレベルで詳しく解説していきます。
テンプレートもご用意したので、ぜひご活用ください。
『吾輩は猫である』の読書感想文で触れたい3つの要点
『吾輩は猫である』の読書感想文を書く際に押さえておきたい重要なポイントを3つご紹介しますね。
- 猫の視点から描かれる人間社会への風刺とユーモア
- 明治時代の知識人たちの生活と価値観の描写
- 存在の意味や生きることへの哲学的な問いかけ
これらの要点について「自分はどう感じたか」をメモしながら読み進めることをおすすめします。
感想文を書く前に、付箋やノートを使って「面白いと思った場面」「疑問に思ったこと」「共感できた部分」などを書き留めておくと、後で文章にまとめる際にとても役立ちますよ。
なぜメモが重要かというと、読書感想文で最も大切なのは「あなた自身の感想や考え」だからです。
あらすじを長々と書くのではなく、あなたがこの作品を読んでどんなことを感じたかが評価されるポイントなんです。
それでは、この3つの要点について詳しく見ていきましょう。
猫の視点から見た人間観察
この小説の最大の魅力は、猫という「第三者の視点」から人間社会が描かれている点です。
名前もない一匹の猫が、飼い主である珍野苦沙弥先生をはじめとする人々の言動を、時にユーモラスに、時に鋭く観察しています。
猫だからこそ気づく人間世界の矛盾や不思議な習慣について、どのように感じたかメモしておくと良いでしょう。
例えば、人間が二本足で歩くことの不安定さや、わざわざ髪を整える習慣など、当たり前だと思っていることを猫の目線で見直すと新鮮な発見がありますよね。
この「異なる視点からの観察」について、あなた自身の経験と重ね合わせて考えてみてください。
普段気づかない家族の癖や、学校での友達の行動など、猫のような客観的な目で見ると面白い発見があるかもしれません。
明治時代の知識人社会
作品には苦沙弥先生やその友人である迷亭、寒月、東風などの知識人たちが登場します。
彼らの会話や行動を通して、明治時代の教養人たちの生活や考え方が詳細に描かれています。
特に注目したいのは、彼らが持つプライドや見栄、そして時に見せる滑稽な一面です。
現代の私たちから見ても共感できる部分や、逆に「時代が違うな」と感じる部分があるでしょう。
金田夫婦のような成金趣味への批判や、知識人たちの理屈っぽい議論など、人間の本質的な部分は今も昔も変わらないことに気づくはずです。
あなたの周りにいる大人たちと比較してみると、感想文に深みが出ますよ。
先生や親の言動で「なんだか苦沙弥先生みたい」と思った経験があれば、それも立派な感想になります。
存在と生きることへの問い
この作品では、猫が自分の存在意義について深く考える場面が多く登場します。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い」という有名な冒頭からも分かるように、アイデンティティの問題が重要なテーマの一つです。
猫は人間社会を観察しながら、「生きるとはどういうことか」「自分とは何者か」といった哲学的な問いを投げかけます。
これは現代の私たちにも通じる普遍的なテーマですよね。
中学生や高校生の皆さんも、将来への不安や自分らしさについて悩むことがあるでしょう。
猫の思索を読みながら、あなた自身が感じている疑問や不安と重ね合わせてみてください。
「名前がない」ということの意味や、所属する場所がないことの寂しさなど、現代の若者が抱える問題とも共通点があります。
また、物語の終盤で描かれる猫の運命についても、生命の尊さや人生の儚さについて考えさせられる内容になっています。
※夏目漱石が『吾輩は猫である』で伝えたいことはこちらで考察しています。

『吾輩は猫である』の読書感想文のテンプレート
『吾輩は猫である』の読書感想文のテンプレート(書き方の型)を以下にまとめます。
自分の感想や思ったことをこの流れにそって書くと、バランスの良い感想文になります。
– 「この本を読もうと思った理由」や「読む前の印象」を簡単に書く。
– 例:「学校の課題で読むことになりました。」/「猫が主人公ということで、どんな話か興味がありました。」
– 物語のおおまかな内容や主人公について簡潔にまとめる。
– 例:「名もない猫が語り手となり、人間社会を観察したり、飼い主の苦沙弥先生たちの日常をユーモアを交えて描いています。」
– 特に心に残ったシーンや、面白い、驚いた点を取り上げる。
– 例:「猫が人間のことを皮肉交じりに語る場面が面白かったです。」
– 作品で伝わってくる大きなテーマやメッセージについて自分の考えを述べる。
– 例:「猫の目から見ることで人間社会の愚かさがよく分かりました。」
– 「生きることや自分の存在について考えさせられました。」
– 物語や猫の考え方が、自分の生活や社会にどうつながるかを書く。
– 例:「普段何気なく過ごしているけど、別の視点で見ることで新しい発見があると思いました。」
– 感想のまとめや今後に活かしたいことなどで締めくくる。
– 例:「この本を通して、日常を違った目線で見てみようと思いました。」
– 「これからもいろいろな本を読んで、自分なりの考えを持ちたいです。」
この流れにそって、自分なりの気づきや感想を言葉にしていくと、説得力ある読書感想文になります。
テンプレート例文
1. 『吾輩は猫である』を読みました。最初は猫が主人公という点が不思議で興味を持ちましたが、読み進めるうちに人間社会のユーモアや風刺がたくさん詰まっていることに気づきました。
2. 物語は、名もない猫が人間の家で暮らし、その日常や人間たちの行動を観察している内容です。特に、飼い主の苦沙弥先生や周りの人たちの会話がとても面白かったです。
3. 私が印象に残ったのは、猫が時々「生きるってなんだろう」と考える姿でした。普段は気にしないようなことも、猫の視点で見るととても新鮮でいろいろなことを考えさせられました。
4. このお話を通して、生きる意味や自分の存在について考える大切さを学びました。人は時々立ち止まって、生活をちょっと違う目で見てみると新しい発見があると思いました。
5. 今後は、日常の出来事にも好奇心や疑問を持ちながら生活してみたいです。そして、これからも色々な本を読んで自分なりの視点を大切にしたいと思いました。
『吾輩は猫である』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】猫の目で見た人間の不思議
私は『吾輩は猫である』を読んで、普段当たり前だと思っていることを違う角度から見ることの面白さを知った。
この小説は、名前のない一匹の猫が語り手となって、飼い主の苦沙弥先生やその周りの人々を観察する物語だ。
最初は猫が人間の言葉を話すなんて変だと思ったが、読み進めるうちに猫だからこそ見える人間の滑稽さや矛盾に気づかされた。
特に印象に残ったのは、猫が人間の習慣を不思議がる場面だった。
例えば、人間が二本の足で歩くことを「不安定で危険」だと表現したり、わざわざ髪を整える習慣を「無駄な労力」だと批判したりする。
私たちにとっては当然のことでも、猫の視点から見ると確かにおかしな行動に見えるのかもしれない。
これを読んで、私も家族の行動を猫の目線で観察してみた。
父が毎朝鏡の前で髪をセットしている姿や、母が天気予報を見ながら洗濯物を干すタイミングを計っている様子など、改めて見ると確かに不思議な光景だった。
また、苦沙弥先生とその友人たちの会話も面白かった。
迷亭という美学者の友人は、いつも大げさな話をして周りの人を困らせる。
寒月という理学士は真面目だが、時々とんでもないことを言い出す。
彼らの議論は難しい内容だったが、猫が「人間は無駄な議論ばかりしている」と冷静にツッコミを入れるのが可笑しかった。
私の周りにも、授業中に先生が難しい話をしているときに、友達同士でこっそり「何を言っているか分からない」と顔を見合わせることがある。
猫の立場から人間を見ると、私たちも同じように滑稽に見えるのだろう。
この作品を読んで一番考えさせられたのは、猫が自分の存在について悩む場面だった。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い」という冒頭の言葉からも分かるように、この猫には名前がない。
名前がないということは、誰からも特別な存在として認められていないということだ。
私は今まで自分の名前があることを当たり前だと思っていたが、名前があるということは家族や友達から大切にされている証拠なのだと気づいた。
猫は人間社会を観察しながら、自分がこの世界でどんな意味を持っているのかを考え続ける。
私も中学生になって、将来のことや自分らしさについて悩むことが増えた。
猫の思索を読みながら、「自分とは何者か」という問いについて一緒に考えることができた。
明治時代と現代では生活環境は大きく変わったが、人間の基本的な性格や悩みはあまり変わっていないのだと感じた。
苦沙弥先生のノイローゼ気味な性格や、金田夫婦の見栄っ張りな態度など、現代にも似たような人がいる。
猫の鋭い観察眼によって、時代を超えて変わらない人間の本質が描かれているのだと思う。
『吾輩は猫である』を読んで、物事を多角的に見ることの大切さを学んだ。
普段の生活でも、猫のように少し距離を置いて周りを観察してみると、新しい発見があるかもしれない。
また、自分自身についても客観的に見つめ直すきっかけをもらった。
この作品が100年以上前に書かれたとは思えないほど、現代の私たちにも通じる内容だった。
『吾輩は猫である』の読書感想文の例文(2000字の高校生向け)
【題名】猫が映し出す人間社会の真実
夏目漱石の『吾輩は猫である』を読み終えて、私は人間社会を客観視することの重要性と、存在することの意味について深く考えさせられた。
この作品は、名前を持たない一匹の猫の視点から明治時代の人間社会を描いた風刺小説だが、そこに込められたメッセージは現代の私たちにも強く響くものがある。
最初にこの小説の独創性に驚かされた。
猫という人間ではない存在を語り手にすることで、人間社会の矛盾や滑稽さを容赦なく暴き出している。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い」という冒頭の一文からして、この猫が社会の周縁に位置する存在であることが示されている。
名前がないということは、誰からも特別な関心を向けられていないということであり、それゆえに冷静で客観的な観察が可能になっているのだろう。
私自身も高校生として、時々大人たちの行動や社会の仕組みに疑問を感じることがある。
しかし、それを直接批判することは難しい。
この猫のように、少し距離を置いた立場から物事を見ることで、より本質的な問題が見えてくるのかもしれない。
作品に登場する苦沙弥先生とその友人たちの描写は、明治時代の知識人たちの実態を鋭く捉えている。
苦沙弥先生は中学校の英語教師でありながら、神経質でノイローゼ気味な性格をしている。
友人の迷亭は美学者として教養をひけらかすが、その実態は人をからかって楽しむだけの軽薄な人物だ。
寒月は理学士として科学的な知識を持ちながら、時として非現実的な発想に走る。
彼らの会話は一見高尚に聞こえるが、猫の冷静な観察によってその空虚さが暴露される。
これらの人物描写を読みながら、私は現代の知識人や教育者たちにも同様の傾向があることに気づいた。
学校の先生の中にも、知識はあるが実生活では非常識な人がいる。
テレビに出る評論家たちも、もっともらしいことを言いながら、実際には世間知らずな発言をすることがある。
知識と人間としての成熟は必ずしも一致しないということを、この作品は教えてくれる。
また、金田夫婦のような成金的な人物への批判も印象的だった。
金田は実業家として成功しているが、その成功は必ずしも人間的な価値とは結びついていない。
妻の鼻子は巨大な鼻の持ち主として戯画化され、娘の富子はわがままな令嬢として描かれている。
彼らの行動は常に自分の利益や見栄を優先しており、他者への配慮に欠けている。
現代社会でも、経済的成功と人間的な価値は別物であることを実感する場面は多い。
SNSで自分の豊かさを誇示する人々や、ブランド品に執着する同世代の友人たちを見ていると、金田一家と重なる部分がある。
真の豊かさとは何かということを、この作品は問いかけているように感じた。
しかし、この作品で最も深く考えさせられたのは、猫の存在そのものが持つ哲学的な意味だった。
猫は人間社会を観察しながら、常に自分の存在意義について思索を巡らせている。
名前がないということの寂しさ、所属する場所の曖昧さ、そして自分が何者であるかという根本的な疑問。
これらは現代の若者が抱える問題と深く通じている。
私たち高校生も、将来への不安や自分らしさの追求という課題を抱えている。
進路選択を迫られる中で、「自分は本当に何をしたいのか」「社会の中でどんな役割を果たせるのか」といった疑問を持つことは珍しくない。
猫の思索を読みながら、これらの疑問は決して個人的なものではなく、存在するということの根本的な問題なのだと理解した。
また、猫が三毛子という雌猫に恋をするエピソードも印象深かった。
三毛子の死によって、猫は愛するものを失う悲しみを経験する。
この体験を通して、猫は生きることの儚さと同時に、愛することの尊さを学ぶ。
人間関係においても、失うことの痛みがあるからこそ、今ある関係の大切さが分かるのだろう。
私も友人との別れや家族との衝突を経験する中で、人とのつながりの複雑さと重要性を実感している。
猫の体験を通して、人間関係の本質について改めて考えることができた。
作品全体を通して感じたのは、漱石の人間に対する愛情深い眼差しだった。
猫は人間を厳しく批判するが、それは憎しみからではなく、より良い存在になってほしいという願いから生まれているように思える。
風刺の背後にある温かさこそが、この作品を単なる皮肉な観察記録以上のものにしている。
現代社会も多くの問題を抱えているが、それらを批判するだけでなく、どうすれば改善できるかを考えることが大切だと感じた。
猫のような客観的な視点を持ちながら、同時に人間への愛情を失わないこと。
これが真の批判精神なのかもしれない。
『吾輩は猫である』は、明治時代の作品でありながら、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれる。
人間社会の矛盾を見つめる冷静さと、存在することの意味を問い続ける姿勢。
そして何より、他者への温かい関心を失わないこと。
この作品から学んだこれらの教訓を、これからの人生に活かしていきたいと思う。
振り返り
『吾輩は猫である』の読書感想文について、書き方のポイントから具体的な例文まで詳しくご紹介してきました。
この記事で紹介した3つの要点を押さえれば、あなたも必ず印象的な感想文が書けるはずです。
中学生向けと高校生向けの例文も参考にしながら、あなた自身の言葉で作品への感想を表現してみてください。
大切なのは、猫の視点から見た人間社会について「あなたがどう感じたか」を正直に書くことです。
漱石が描いた明治時代の世界と現代を比較したり、登場人物たちと身近な人々を重ね合わせたりすることで、きっと素晴らしい感想文が完成しますよ。
※『吾輩は猫である』の読書感想文の作成に役立つ記事がこちら。



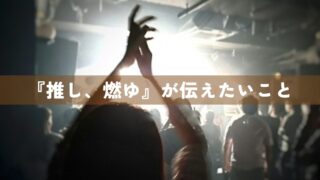


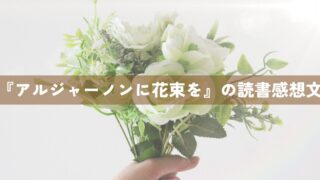
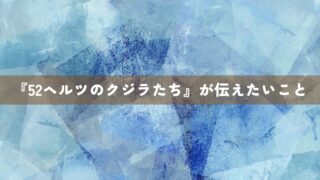



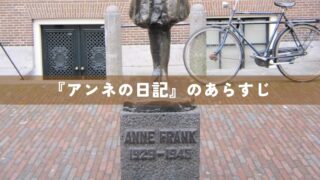
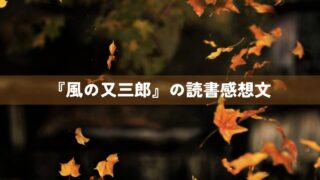
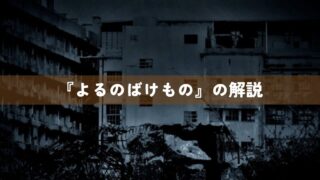

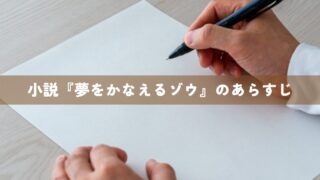
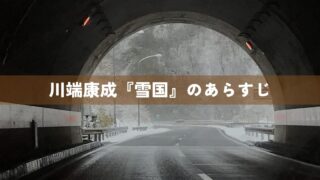


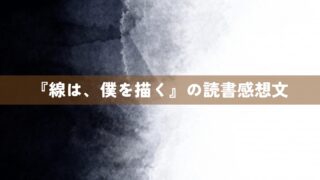

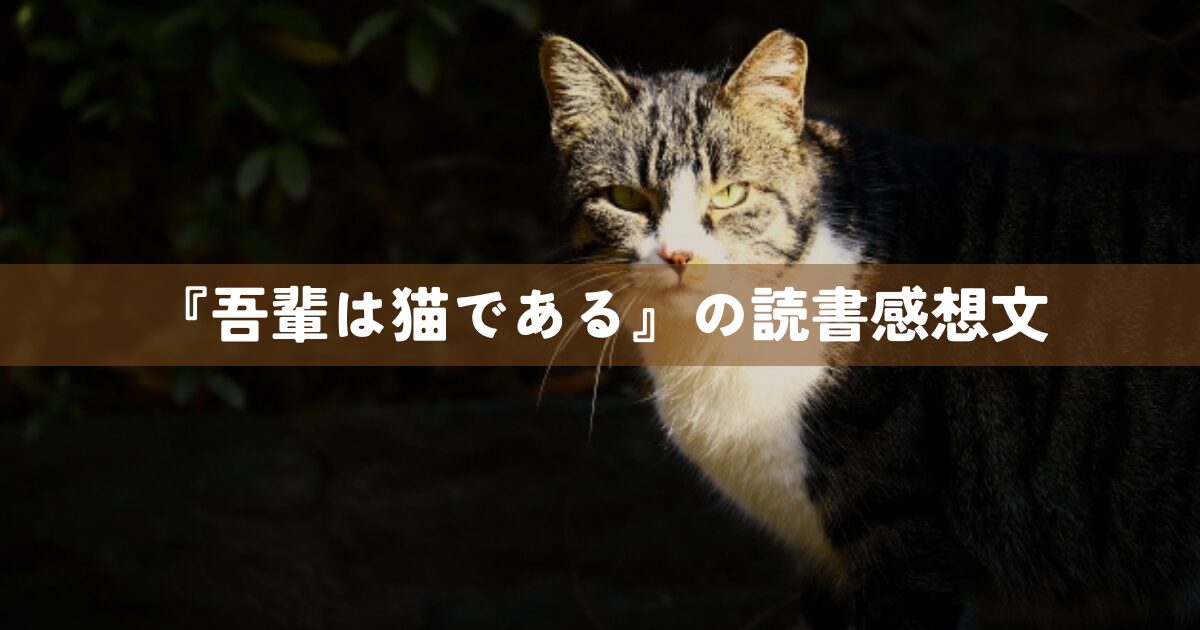
コメント