『君の膵臓をたべたい』の読書感想文を書く予定のみなさん、こんにちは。
この作品は住野よるさんによる青春小説で、略称は「キミスイ」として多くの読者に愛されています。
友人や恋人との関わり合いを持たない内向的な主人公「僕」が、膵臓の病気で余命わずかな山内桜良との出会いを通じて成長していく物語です。
アニメ化や実写映画化もされた話題作で、読書感想文の定番として小学生・中学生・高校生を問わず多くの学生が取り組んでいますね。
年間100冊以上の本を読む私が『君の膵臓をたべたい』の読書感想文の書き方について、800字・1200字・2000字の例文や題名まで、徹底的に解説していきますよ。
この記事を読めば、きっと素晴らしい読書感想文が書けるようになるでしょう。
それでは早速進めていきましょう。
『君の膵臓をたべたい』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
『君の膵臓をたべたい』の読書感想文を書く際に、必ず触れておきたい重要なポイントがあります。
この作品は表面的な恋愛小説ではなく、生きることの意味や人とのつながりについて深く考えさせる作品なんですね。
感想文では以下の3つのポイントを中心に書くと、より深みのある内容になりますよ。
- 「生きる意味」と「死」との向き合い方
- 登場人物の成長と「人とのつながり」
- タイトルの意味と「共病文庫」の存在
これらのポイントを押さえることで、単なるあらすじの要約ではなく、作品が持つ深いテーマやメッセージについて自分なりの考えを表現できる読書感想文が完成します。
それでは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
「生きる意味」と「死」との向き合い方
この作品の最も重要なテーマが「限られた命をどう生きるか」という問いです。
桜良は膵臓の病気により余命1年という現実と向き合いながらも、その事実を恨むことなく前向きに生きようとします。
彼女が日記のタイトルを「闘病日記」ではなく「共病文庫」と名付けた理由からも、病気と共に歩む覚悟や生きることへの強い意志が感じられるでしょう。
一方で「僕」は桜良との出会いを通じて、それまで無関心だった「生きること」の意味について深く考えるようになります。
感想文では、桜良の生き方や「僕」の変化から、あなた自身が「生きること」についてどのような気づきを得たかを書くことが重要です。
「もし自分が桜良の立場だったらどうするか」「限りある時間をどう過ごしたいか」といった具体的な問いに対するあなたなりの答えを含めると、より説得力のある感想文になりますよ。
登場人物の成長と「人とのつながり」
物語の核心は、正反対の性格を持つ「僕」と桜良の心の交流です。
「僕」は最初、友人や恋人との関わり合いを必要とせず、人間関係を自己完結させる内向的な性格でした。
しかし桜良との出会いにより、人を認め、人と関わり合う努力を始めるようになります。
桜良もまた、「僕」が初めて関わり合いを持ちたいと思った相手として自分を選んでくれたことで、「初めて私自身として必要とされている」と感じるのです。
この相互の成長過程は、読者にとって非常に感動的な部分ですね。
感想文では、二人がどのように変化していったか、そしてその変化があなたにどのような影響を与えたかを具体的に書きましょう。
「人とつながることの大切さ」「お互いに欠けている部分を補い合う関係」「心を開くことの勇気」といったテーマについて、あなた自身の体験や考えと重ね合わせて書くと良い感想文になります。
タイトルの意味と「共病文庫」の存在
「君の膵臓をたべたい」という印象的なタイトルは、作品を読み進めるにつれてその深い意味が明らかになります。
これは古い迷信に基づく表現で、「君ともっと深くつながりたい」「君の一部になりたい」という切実な願いが込められています。
また「共病文庫」は桜良が病気と共に歩むことを受け入れ、その体験を記録した特別な日記です。
この日記を通じて「僕」と桜良は秘密を共有し、特別な関係を築いていきます。
感想文では、これらのシンボリックな要素があなたにどのような印象を与えたかを書くことが重要です。
「タイトルを初めて見たときの印象と、読後の印象の変化」「共病文庫が二人の関係にどのような意味を持っていたか」について、あなたなりの解釈を含めて書きましょう。
また、桜良が「僕」に託したメッセージからどのような感動や気づきがあったかも、感想文の重要な要素になります。
※『君の膵臓をたべたい』が伝えたいことや面白い点はこちらで考察しています。


より良い読書感想文を書くために『君の膵臓をたべたい』を読んだらメモしたい3項目~桜良と「僕」に対してあなたが感じたこと~
読書感想文を書く際に最も重要なのは、作品を読んであなたが何を感じたかということです。
『君の膵臓をたべたい』を読みながら、以下の3つの項目について具体的にメモを取ることをおすすめします。
これらのメモがあることで、感想文を書く際に自分の気持ちを正確に表現でき、より説得力のある文章が書けるようになりますよ。
- 感情の揺れ動きと、そのきっかけとなった場面やセリフ
- 登場人物の行動や考え方に対する共感や驚き
- 「生きること」や「死ぬこと」について考えさせられた瞬間
感想文は作品のあらすじを書くものではなく、あなたの心がどう動いたかを表現するもの。
だからこそ、読書中に感じた素直な気持ちを記録しておくことが何より大切なのです。
それでは、それぞれの項目について詳しく説明していきましょう。
感情の揺れ動きと、そのきっかけとなった場面やセリフ
物語を読み進める中で、あなたの心がどのように動いたかを具体的にメモしておきましょう。
桜良の明るさに心が軽やかになった瞬間、「僕」の不器用さにもどかしさを感じた場面、物語の展開に驚いた箇所など、様々な感情の変化があったはずです。
特に重要なのは、その感情がどの場面で、誰のどのような言葉や行動によって引き起こされたかを特定することです。
例えば「桜良が『うわははっ』と笑う場面で、彼女の強さと同時に切なさを感じた」「『僕』が桜良の病気を知った時の戸惑いに共感した」といった具体的な記録が役立ちます。
このようなメモがあることで、感想文を書く際に「なぜそう感じたのか」という理由も含めて説明できるようになり、読み手に伝わりやすい文章が書けるわけです。
感情の変化は人それぞれ異なるものですから、あなただけの独特な感じ方を大切にしてくださいね。
登場人物の行動や考え方に対する共感や驚き
「僕」や桜良の行動や考え方について、あなたがどのように感じたかをメモしておきましょう。
共感した部分、理解できなかった部分、驚いた行動、感動した言葉など、登場人物に対するあなたの率直な反応が感想文の核となります。
「僕」の内向的な性格に自分を重ね合わせた人もいれば、桜良の前向きな生き方に憧れを感じた人もいるでしょう。
また、隆弘の行動に腹立たしさを感じたり、恭子の友情に心を打たれたりした場面もあったかもしれません。
これらの感情は、あなた自身の価値観や経験と深く関わっています。
感想文では「なぜそう感じたのか」という理由も含めて書くことで、あなたの人柄や考え方が表現された個性的な文章になります。
登場人物の行動から学んだことや、自分も見習いたいと思った点があれば、それも重要なメモの内容ですね。
「生きること」や「死ぬこと」について考えさせられた瞬間
この作品の最も深いテーマである「生きること」と「死ぬこと」について、あなたが考えさせられた場面をメモしておきましょう。
桜良の病気、彼女の生き方、物語の結末など、様々な場面で重いテーマについて考える機会があったはずです。
「もし自分が桜良の立場だったらどうするか」「限りある命をどう生きたいか」「大切な人を失うということはどういうことか」といった問いについて、あなたなりの答えや考えをメモしてください。
これらの深い思考は、読書感想文を単なる感情の記録から、哲学的で意味深い文章へと昇華させてくれます。
また、この作品を読んで「日常生活で大切にしたいと思うようになったこと」「人との関わり方について見直したいと思ったこと」があれば、それも重要なメモの内容です。
読書は知識を得るだけでなく、人生について深く考える機会を与えてくれるものですから、そうした気づきを大切にしてくださいね。
※『君の膵臓をたべたい』のあらすじはこちらでご紹介しています。
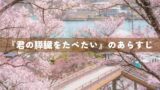
『君の膵臓をたべたい』の読書感想文の例文(800字の小学生向け)
【題名】大切な人とのつながり
私は『君の膵臓をたべたい』を読んで、人とのつながりがどんなに大切かということを学んだ。
最初は変なタイトルだと思ったけれど、読み終わった時にはこのタイトルがとても深い意味を持っていることが分かった。
物語の主人公である「僕」は、私と同じように友達を作るのが苦手な人だった。
いつも一人で本を読んでいて、他の人と関わろうとしない。
私もクラスでは静かにしていることが多いので、「僕」の気持ちがよく分かった。
でも桜良という女の子と出会って、「僕」は少しずつ変わっていく。
桜良は膵臓の病気で、あまり長く生きることができない。
それなのに彼女はいつも明るくて、「うわははっ」という面白い笑い方をする。
私は桜良のような人になりたいと思った。
辛いことがあっても前向きに頑張る桜良は、とてもかっこいい。
「僕」が桜良と一緒にいろいろな場所に行ったり、やりたいことをしたりする場面を読んで、友達がいるっていいなと思った。
一人でいる時間も大切だけれど、誰かと一緒に過ごす時間はもっと楽しいのかもしれない。
桜良が「共病文庫」という日記を書いていたことも印象的だった。
病気と一緒に生きていくという意味で「共病文庫」と名付けたということを知って、桜良の強さに感動した。
私だったら病気になったらきっと悲しくて泣いてしまうと思う。
でも桜良は病気を恨まずに、残された時間を大切に過ごそうとしていた。
物語の終わり方は悲しかったけれど、桜良が「僕」に残してくれたメッセージはとても温かかった。
「僕」が桜良との思い出を大切にして、これからは他の人とも関わっていこうと決心する場面では涙が出た。
この本を読んで、私も友達を作る努力をしてみようと思った。
「僕」と桜良のように、お互いにないものを補い合える関係を築けたら素敵だ。
毎日を当たり前だと思わずに、一日一日を大切に生きていきたい。
そして周りの人に優しくして、桜良のように人を笑顔にできる人になりたいと思う。
『君の膵臓をたべたい』の読書感想文の例文(1200字の中学生向け)
【題名】限りある時間を生きるということ
『君の膵臓をたべたい』というタイトルを初めて見た時、私は正直気持ち悪いと思った。しかし物語を読み終えた今、このタイトルには深い愛情と切ない思いが込められていることが分かる。この作品を通して、私は生きることの意味や人とのつながりについて考えるようになった。
物語の主人公「僕」は、私と同年代でありながら内向的で、人間関係を避けて生きている。彼が太宰治を愛読しているという設定は、文学的な感性を持ちながらも現実逃避をしている複雑な人物像を表している。私も人とのコミュニケーションが得意ではないため、「僕」の心境には共感する部分が多かった。
一方で桜良は、膵臓の病気により余命1年という過酷な現実と向き合いながらも、驚くほど前向きに生きている。彼女が日記のタイトルを「闘病日記」ではなく「共病文庫」と名付けた理由を知った時、私はその精神的な強さに圧倒された。病気と共に生きていくという発想は、中学生の私には思いつかないものだった。
物語で印象的だったのは、「僕」と桜良が互いに自分にない部分に憧れを抱く場面である。内向的な「僕」は桜良の社交性と明るさに、桜良は「僕」の深く考える能力と独立した精神に魅力を感じている。この相互の憧れは、人間関係の本質を表していると思う。私たちは自分にないものを他者に求め、そうすることで成長していくのだ。
桜良の「うわははっ」という特徴的な笑い方は、最初は個性的な表現だと思っていたが、物語が進むにつれて、彼女の強がりであり本心からの明るさでもあることが分かってくる。自分の境遇を悲観せず、周囲に心配をかけまいと笑顔を保つ彼女の健気さに、私は何度も胸が熱くなった。
「僕」が桜良との交流を通じて変化していく過程も素晴らしい。人を認め、関わろうとする彼の決意は、私にとって大きな励みになる。私も「僕」のように、もっと人とのつながりを大切にしたいと思うようになった。
物語の結末はショッキングだった。桜良が意外な形で命を落とすという展開は、人生の不条理さを強く印象づける。しかしだからこそ、今この瞬間を大切に生きなければならないのだと感じた。
桜良が「僕」に残した最後のメッセージは、思いやりと愛情に満ちていた。「君の膵臓をたべたい」という言葉の真意を知った時、私は涙を抑えることができなかった。古い迷信に基づくこの表現は、「君ともっと深くつながりたい」という純粋な願いを表している。桜良の「僕」への愛情は、恋愛感情を超えた深い絆だった。
この作品を読んで、私は日常生活の中で多くのことを見直したくなった。友達や家族との時間をもっと大切にし、相手の気持ちを理解しようと努力したい。
また桜良のように、困難な状況でも前向きに生きる強さを身につけたい。限りある時間を無駄にせず、一日一日を精一杯生きていこうと決意を新たにした。
『君の膵臓をたべたい』の読書感想文の例文(2000字/原稿用紙5枚の高校生向け)
【題名】生きることの意味を問い直す青春小説
『君の膵臓をたべたい』というタイトルを最初に見たとき、正直言って気持ち悪いと思った。なんでこんなタイトルなんだろうと理解できなかった。しかし、この物語を読み終えた今、このタイトルには想像以上に深い愛情と切ない思いが込められていることが分かる。この作品を通して、僕は生きることの意味や人とのつながりについて真剣に考えるようになった。
物語の主人公である「僕」は、僕と同じ高校生でありながら、極めて内向的で人間関係を避けて生きている人物として描かれている。彼が太宰治を愛読しているという設定は、文学的な感性を持ちながらも現実逃避をしてしまう複雑な人物像を巧みに表現していると思う。僕自身も人とのコミュニケーションが得意ではないため、「僕」の心境には深く共感した。クラスメイトとの距離感や、一人でいることを好む性格など、まるで自分を見ているような気持ちになることが何度もあった。特に図書館で静かに本を読んでいる彼の姿は、僕自身の日常と重なって見えた。
一方で、桜良は膵臓の病気により余命わずか1年という過酷で残酷な現実と向き合いながらも、驚くほど前向きに生きている。彼女が日記のタイトルを「闘病日記」ではなく「共病文庫」と名付けた理由を知ったとき、僕はその精神的な強さと深さに圧倒された。病気と闘うのではなく、病気と共に生きていくという発想は、高校生である僕には到底思いつかないような深い洞察だった。
桜良の「うわははっ」という特徴的な笑い方は、最初は単なる個性的な表現だと思っていたが、物語が進むにつれて、それが彼女の強がりでもあり本心からの明るさでもあることが分かってきた。自分の置かれた厳しい境遇を悲観せず、周囲に心配をかけまいと笑顔を保ち続ける彼女の健気さに、僕は何度も胸が熱くなり、感動を覚えずにはいられなかった。
物語の中で特に印象深く、そして美しいと感じたのは、「僕」と桜良が互いに自分にはない部分に強い憧れを抱く場面である。内向的で人付き合いが苦手な「僕」は、桜良の持つ自然な社交性と屈託のない明るさに憧れを感じている。反対に桜良は、「僕」の物事を深く考える能力や、他人に依存しない独立した精神に魅力を感じているのだ。この相互の憧れの構造は、人間関係の本質的な部分を見事に表現していると僕は思う。僕たち人間は、自分にないものを他者に求め、そしてそうすることによって互いに成長し、より豊かな人間になっていくのではないだろうか。この気づきは僕にとって非常に大きな意味を持つものだった。
「僕」が桜良との交流を通じて少しずつ変化し、成長していく過程も本当に素晴らしいと感じた。最初は人を避け、関わることを恐れていた彼が、徐々に人を認め、積極的に関わろうとする決意を固めていく姿は、僕にとって大きな励みとなった。僕自身も「僕」のように、もっと積極的に人とのつながりを大切にし、育んでいきたいと強く思うようになった。人とのコミュニケーションは確かに難しく、時として傷つくこともあるが、それ以上に得られるものの方がはるかに大きいということを、この物語は教えてくれたように思う。
物語の結末は、僕にとって非常にショッキングで、しばらく言葉を失うほどだった。桜良が病気ではなく、全く予想もしなかった意外な形で命を落とすという展開は、人生の理不尽さや不条理さを強烈に印象づけるものだった。しかし、だからこそ僕たちは今この瞬間、この時間を本当に大切に生きなければならないのだということを、心の底から実感することができた。
桜良が「僕」に残した最後のメッセージは、思いやりと深い愛情に満ち溢れていた。「君の膵臓をたべたい」という言葉の真の意味を知ったとき、僕は涙を抑えることができなかった。古い迷信に基づくこの一見奇妙な表現は、「君ともっと深くつながりたい」「君の一部になりたい」という純粋で美しい願いを表現していたのだ。桜良の「僕」への愛情は、単純な恋愛感情を遥かに超えた、もっと深い次元での絆だったと分かり胸に迫るものがあった。
この作品を読み終えて、僕は自分の日常生活の中で多くのことを見直したいと思うようになった。友達や家族との何気ない時間をもっと大切にし、相手の気持ちを理解しようと真剣に努力したいと思う。また、桜良のように、どんなに困難で厳しい状況に置かれても前向きに生きる強さを身につけたいと心から願うようになった。僕たちに与えられた時間は決して無限ではない。限りある貴重な時間を無駄にすることなく、一日一日を精一杯、後悔のないように生きていこうと決意を新たにした。
『君の膵臓をたべたい』は、最初の印象とは全く異なる、深い愛と生きることの意味を問いかける素晴らしい作品だった。この物語を通して学んだことを胸に刻み、これからの高校生活、そしてその先の人生をより豊かに歩んでいきたいと思っている。
振り返り
今回は『君の膵臓をたべたい』の読書感想文の書き方について、詳しく解説してきました。
この作品が持つ深いテーマや感動的なメッセージを理解することで、きっと素晴らしい読書感想文が書けるはずです。
重要なのは、作品のあらすじを要約することではなく、あなた自身が感じたことや考えたことを正直に表現することです。
「生きることの意味」「人とのつながりの大切さ」「限りある時間をどう過ごすか」といったテーマについて、あなたなりの答えを見つけてください。
小学生・中学生・高校生それぞれのレベルに応じた例文も紹介しましたが、これらはあくまでも参考例です。
コピペするのではなく、あなた自身の言葉で書き上げることが何より大切ですよ。
800字でも1200字でも2000字でも、文字数に関係なく心のこもった感想文を書けば、必ず読み手の心に届きます。
この記事を参考にして、ぜひ素晴らしい読書感想文を完成させてくださいね。
あなたにも必ずいい感想文が書けるはずです。
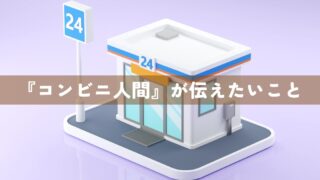

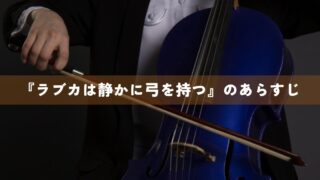
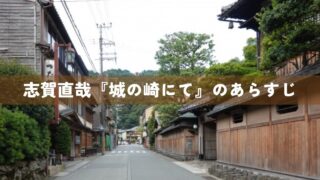





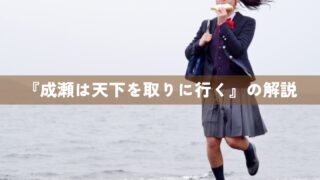
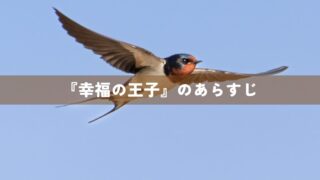
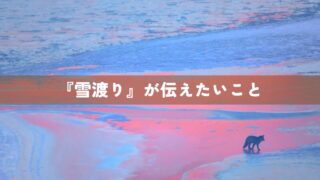

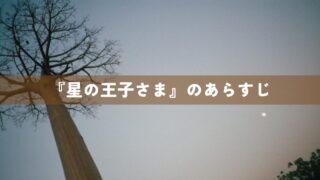
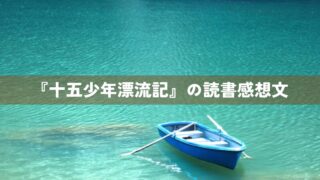



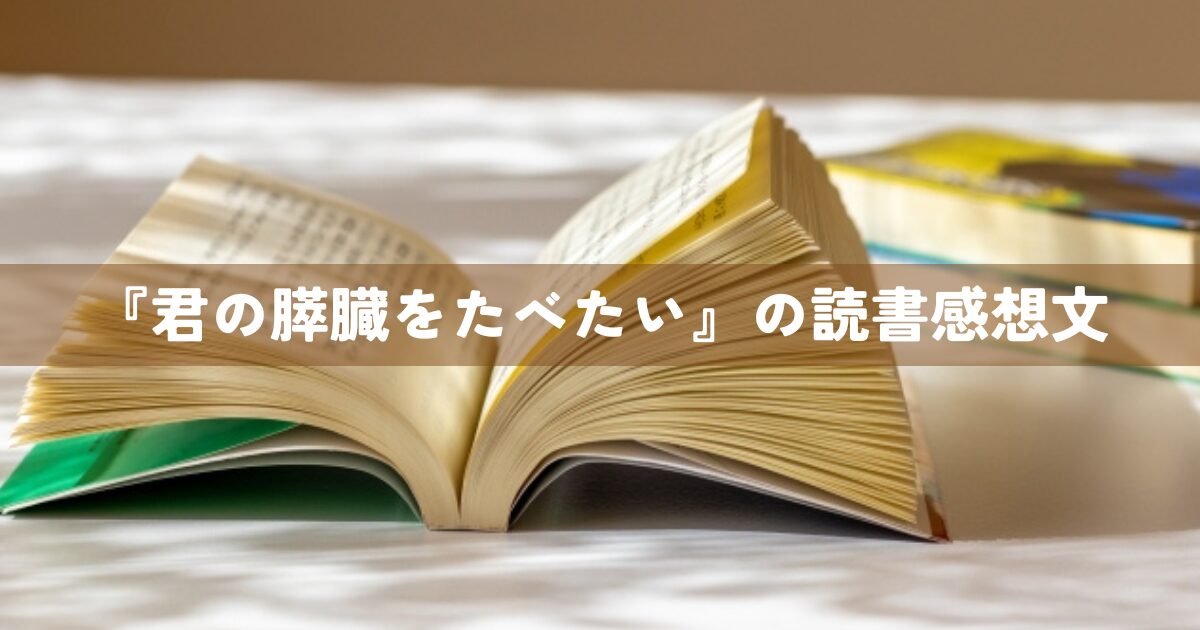
コメント