『さようならプラスチック・ストロー』のあらすじを簡単に、そして詳しくご紹介していきますね。
この作品は、身近なプラスチック・ストローを通じて環境破壊の問題とその解決への道を学べる、SDGsに結びついた教育的価値の高いノンフィクション絵本です。
作者はディー・ロミートさんで、2023年に光村教育図書から出版されました。
私は年間100冊以上の本を読む読書家で、児童書も多数読んできましたが、『さようならプラスチック・ストロー』は子どもたちに環境意識を育てる素晴らしい作品だと感じています。
読書感想文を書く予定の皆さんの力になれるよう、短くて簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、ネタバレなしで丁寧に解説していきますよ。
ディー・ロミート『さようならプラスチック・ストロー』のあらすじを短く簡単に
ディー・ロミート『さようならプラスチック・ストロー』のあらすじを詳しく
この絵本は、ストローの歴史と環境のことをわかりやすく教えてくれます。物語は約5000年前に、古代シュメール人が草(葦/あし)を使ったストローを発明したところから始まります。その後も時代ごとに工夫がされ、1800年代には紙のストローが生まれ、1937年には曲がるストローが作られました。そして1960年代からは、使い捨てのプラスチックストローが世界中で広く使われるようになりました。
しかし便利なプラスチックストローは、使い終わるとすぐにゴミとなり、自然に戻らないために大きな問題を引き起こしています。海に流れ出ると細かくくだけてマイクロプラスチックとなり、魚やカメなどの生き物が食べてしまい、命を落とすこともあります。海や自然がどんどん汚れていく様子が、この絵本ではしっかりと描かれています。
同時に、この本では解決のための工夫も紹介されています。たとえば、紙や金属など再利用できるストローを使うこと、使い捨てを減らすことなどです。また、アメリカの9歳の子ども、マイロ・クレスが始めた「ストローを減らそう」という活動も紹介されています。小さな子どもでもできることがあり、それが社会を動かす力になるのだと教えてくれます。
最後に、環境を守るための大切な考え方「4つのR」も紹介されています。リデュース(減らす)、リユース(くり返し使う)、リサイクル(再び使う)、リフューズ(いらないと断る)の4つです。この本を読むことで、私たち一人ひとりができることを考え、行動にうつす大切さを学べるようになっています。
『さようならプラスチック・ストロー』のあらすじを理解するための用語解説
『さようならプラスチック・ストロー』を読む上で知っておきたい重要な用語をまとめました。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 古代シュメール | 約5,000年前、メソポタミア地方に栄えた文明。 世界最古のストローが発明されたとされる。 |
| 生分解性 | 自然の微生物などによって分解される性質のこと。 プラスチックはほとんど生分解性がなく、 長期間自然界に残る。 |
| 海洋プラスチックごみ | 海や海岸に捨てられたプラスチック製品のごみ。 海の生きものが誤って飲み込んだり 絡まったりして命を脅かす。 |
| 4つのR | 環境保護のための行動指針。 ・リデュース(減らす) ・リユース(繰り返し使う) ・リサイクル(再利用) ・リフューズ(断る) |
これらの用語を理解することで『さようならプラスチック・ストロー』が伝える環境問題の重要性がより深く分かるでしょう。
『さようならプラスチック・ストロー』の感想
『さようならプラスチック・ストロー』を読んで、まず感じたのは「こんなにも身近な問題だったのか」という驚きでした。
正直に言うと、私も普段何気なくプラスチック・ストローを使っていて、それがこれほど深刻な環境問題につながっているなんて考えたことがありませんでした。
ストローの歴史から始まる構成が本当に巧妙で、古代シュメール人の葦のストローから現代のプラスチック・ストローまでの流れが自然に頭に入ってくるんですね。
「へえ、ストローってこんなに長い歴史があるんだ」と興味深く読み進めているうちに、いつの間にか環境問題の核心に迫っている構成になっていました。
特に感動したのは、9歳のマイロ・クレス君のエピソードです。
たった9歳の子どもが「ストローをなくそう」というキャンペーンを始めたという話を読んで、頭が下がる思いでしたね。
子どもだからこそ持っている純粋な正義感と行動力に、大人の私が学ばされた気持ちになったんです。
「自分にも何かできることがあるはず」と強く思わせてくれる、そんな力がこの絵本にはありますね。
イラストも本当に美しくて、海の生き物たちの描写は見ているだけで心が痛くなるほどリアルでした。
でも、ただ悲惨な現実を突きつけるだけじゃなく、代替品の紹介や4つのRの説明など、前向きな解決策もしっかりと示されているのが素晴らしいと思います。
読み終わった後、すぐにマイボトルを持参するようになりましたし、コンビニでストローをもらうのをやめました。
小さな変化かもしれませんが、この絵本のおかげで環境に対する意識が確実に変わったんです。
子ども向けの絵本というカテゴリーを超えて、大人にも深い気づきを与えてくれる『さようならプラスチック・ストロー』。
環境問題を身近な問題として捉え直すきっかけになる、本当に価値のある作品ですよ。
※『さようならプラスチック・ストロー』の読書感想文の書き方と例文はこちらにまとめています。

『さようならプラスチック・ストロー』の作品情報
『さようならプラスチック・ストロー』の基本的な作品情報をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | ディー・ロミート(文) ズユェ・チェン(絵) 千葉茂樹(訳) |
| 出版年 | 2023年9月 |
| 出版社 | 光村教育図書 |
| 受賞歴 | 記載なし(著者はクリスタルカイト賞受賞者) |
| ジャンル | 児童文学、環境問題・海洋廃棄物に関する絵本 |
| 主な舞台 | 海洋環境をテーマに、プラスチックごみ問題を描く |
| 時代背景 | 古代シュメール時代から現代まで |
| 主なテーマ | 環境保護、SDGs、プラスチック問題 |
| 物語の特徴 | ノンフィクション、教育的価値が高い |
| 対象年齢 | 小学校低学年から |
| 青空文庫の収録 | 収録なし |
『さようならプラスチック・ストロー』の登場人物
『さようならプラスチック・ストロー』に登場する重要な人物をご紹介します。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| マイロ・クレス | 2011年に「ストローをなくそう」という キャンペーンを始めた9歳の男の子。 実在の子ども環境活動家として 本書で紹介されている。 プラスチックストローの大量消費問題に気づき 行動を起こした代表例。 |
この作品はノンフィクション絵本のため、特定のキャラクターや主人公は設定されていませんが、マイロ・クレス君が実例として重要な役割を果たしています。
『さようならプラスチック・ストロー』の読了時間の目安
『さようならプラスチック・ストロー』の読書にかかる時間をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総ページ数 | 32ページ |
| 文字数 | 不明 |
| 読了時間(大人) | 5~10分 |
| 読了時間(小学生) | 10分前後 |
絵本形式で文字も大きく、イラストも豊富なので、小学生でも10分程度で読み終えることができるでしょう。
内容が分かりやすく構成されているため、何度も読み返して理解を深めることもおすすめです。
『さようならプラスチック・ストロー』はどんな人向けの絵本か?
『さようならプラスチック・ストロー』がおすすめな人のタイプをまとめました。
- 小学校中学年(9歳頃)からの子どもたち – 環境問題について基礎から学びたい年齢層にぴったり
- 環境問題やSDGsに興味を持ち始めた人 – ストローという身近なものから地球環境を考えるきっかけになる
- 家族で環境について話し合いたい人 – 大人も子どもも一緒に読めて、家庭での環境教育の材料として最適
一方で、すでに環境問題について深い知識を持っている大人には物足りないかもしれません。
ただし、子どもと一緒に読む機会があれば、その教育的価値の高さを実感できるはずです。
あの本が好きなら『さようならプラスチック・ストロー』も好きかも?似ている絵本3選
『さようならプラスチック・ストロー』と同じように環境問題を扱った素晴らしい絵本をご紹介しますね。
どれも子どもたちに環境意識を育てるのに役立つ作品です。
ミシェル・ロード『プラスチックのうみ』
人間の生活から出たプラスチックごみが海に流れ込み、海の生き物にどんな影響を与えているのかを描いた絵本です。
『さようならプラスチック・ストロー』と同じく、プラスチック汚染の問題を子どもにも分かりやすく伝えている点が似ています。
美しい海を守るために今できることを考えるきっかけになる作品ですね。
真珠まりこ『もったいないばあさん』
「もったいない」の気持ちを大切にし、資源やごみ、環境にやさしい暮らしの大切さを伝えるロングセラー絵本です。
4つのRの精神と共通する「無駄をなくす」という考え方が『さようならプラスチック・ストロー』と重なります。
小さな子にもごみを減らす意識を育てる点で類似している作品です。
ミランダ・ポール『ポリぶくろ、1まい、すてた』
アフリカに住む女の子が、ポリ袋による環境問題に気づき、解決のために行動するストーリーです。
実在の女性がモデルのノンフィクションで、子どもが環境問題解決のために立ち上がる点が『さようならプラスチック・ストロー』のマイロ・クレス君のエピソードと似ています。
ストーリー仕立てで環境問題が学べる構成も共通していますね。
振り返り
『さようならプラスチック・ストロー』は、身近なストローを通じて環境問題を考える優れた教育絵本でした。
古代から現代までのストローの歴史をたどりながら、プラスチック汚染の深刻さと解決策を分かりやすく伝える構成が見事です。
特にマイロ・クレス君の実例が示すように、子ども一人一人にもできることがあるというメッセージが心に響きます。
小学生にとって環境問題について考える良いきっかけになる作品だと思いますよ。


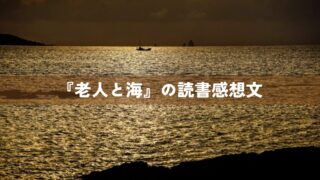


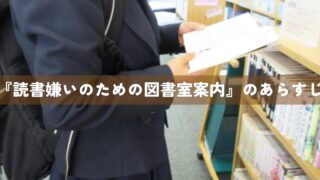






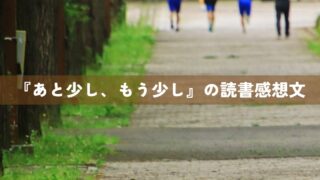
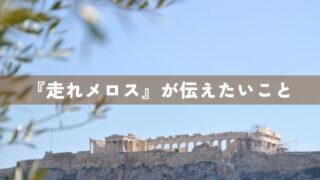




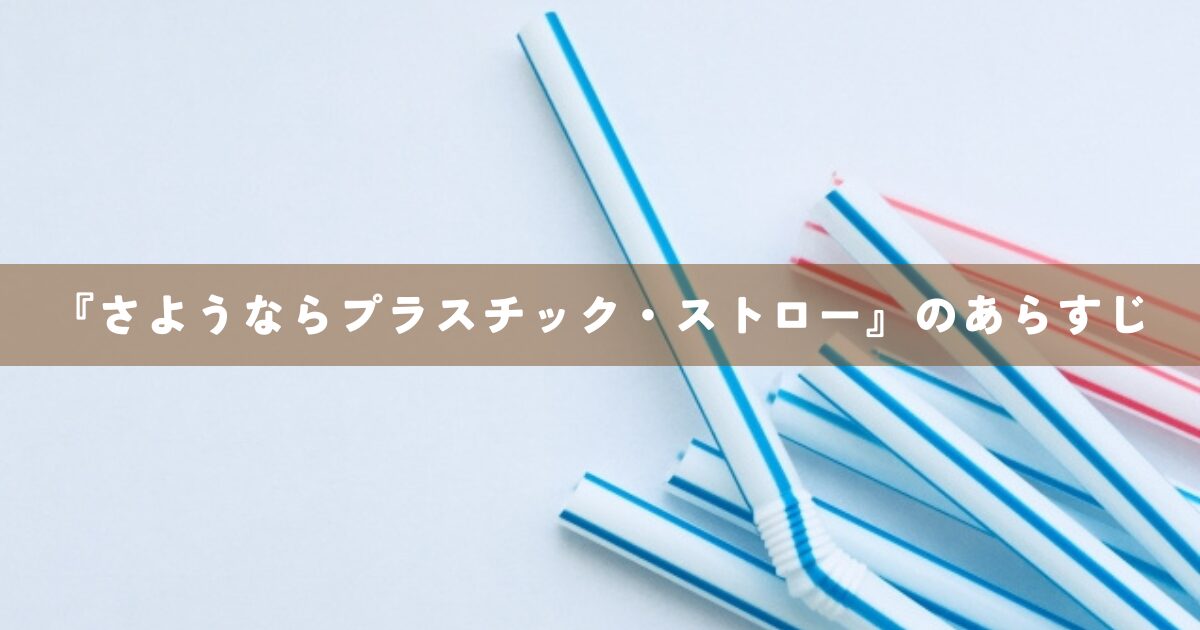
コメント