『平和のバトン』のあらすじと内容を簡単に短く、かつ詳しく解説します。
『平和のバトン 広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶』は、広島市立基町高校の高校生たちが被爆者の証言を聞き取り、それを油絵として描く「次世代と描く原爆の絵」プロジェクトを描いたノンフィクション作品です。
この記事では年間100冊以上の本を読む私が、広島の高校生たちが被爆者の証言を絵に描く感動的な『平和のバトン』のあらすじを要約して、読書感想文を書く予定の皆さんに向けて分かりやすく紹介していきますね。
弓狩匡純『平和のバトン』のあらすじ(内容と要約)
弓狩匡純『平和のバトン』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
広島市立基町高校の創造表現コースに通う高校生たちのもとに、広島平和記念資料館から特別なプロジェクトの依頼が舞い込んだ。
それは被爆者の証言を聞き取り、その記憶を油絵として描く「次世代と描く原爆の絵」という活動だった。
被爆体験者たちは高齢となり、「このままでは原爆のことが忘れられてしまう」という強い危機感を抱いていた。
そこで勇気を出して自身の体験を若い世代に語り継ぐことを決意したのである。
戦争や原爆の実態を直接経験したことのない高校生たちにとって、証言者の言葉だけでその記憶を理解することは容易ではなかった。
しかし彼らは証言者と密接に交流し、資料館や図書館で徹底的に調査を行った。
「ゲートル」と呼ばれる戦時中の足布の意味を調べたり、当時の服装や道具、街の様子を詳しく学んだりしながら、リアルな情景を理解していく。
一年という長い時間をかけて、高校生たちは証言者の記憶を自分たちの手で形にしていく。
このプロジェクトは単なる絵の制作を超え、戦争や原爆の記憶を次世代へつなぐ「平和のバトン」として位置づけられる重要な活動となった。
『平和のバトン』のあらすじを理解するための用語解説
この作品を読む上で重要な用語について、以下の表で分かりやすく説明する。
戦争や平和に関する専門的な言葉が多く登場するため、しっかりと理解しておきましょう。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 被爆者 | 1945年8月6日の 広島への原子爆弾投下で被害を受けた人々。 戦争の悲惨な体験を語り継ぐ重要な存在 |
| 次世代と描く原爆の絵プロジェクト | 広島の基町高校の生徒が 被爆者の証言を聞き絵画制作を通じて 被爆体験の継承と平和教育を行う活動 |
| 平和のバトン | 戦争や原爆の記憶を次の世代に 伝え続ける責任や使命の比喩。 被爆者と若い世代との共有を象徴する概念 |
| 原爆の絵 | 高校生たちが被爆者の証言をもとに描く油絵。 記憶を視覚的に表現し戦争の悲惨さと 平和の尊さを後世に伝える役割を持つ |
『平和のバトン』の感想
『平和のバトン』を読み終えた私は重い責任感を感じずにはいられませんでした。
この作品は単なる戦争体験談ではなく、記憶を継承することの大切さと困難さを丁寧に描いた秀作ですね。
特に印象的だったのは、高校生たちが被爆者の証言を聞いて絵を描く過程での真剣な取り組みです。
「ゲートル」という戦時中の足布について調べるエピソードなんて、本当に細かい部分まで理解しようとする姿勢が伝わってきて、すごく感動しました。
最初は戦争なんて遠い昔の話だと思っていた高校生たちが、被爆者の生の声を聞くことで徐々に当事者意識を持っていく様子が丁寧に描かれています。
私自身、40代になってから戦争について考える機会が増えたのですが、この本を読んで改めて平和の尊さを実感しましたよ。
被爆者の方々が高齢になり、直接体験を語れる人が少なくなっている現状も切実に感じました。
だからこそ、こうした継承活動がいかに重要かということが心に響きます。
ただ正直に言うと、読み物としてのエンターテインメント性を求める人には少し物足りないかもしれません。
絵の制作過程やインタビューの記録が詳細に書かれているので、ドラマチックな展開を期待している読者には向かないでしょうね。
でも、それこそがこの作品の価値だと私は思います。
派手な演出や作り話ではなく、リアルな記録として残された貴重な証言なんですから。
『平和のバトン』を読んでいて特に泣けたのは、被爆者の方が「忘れられてしまうのではないか」という不安を抱きながらも、勇気を出して体験を語る場面でした。
自分の辛い記憶を若い世代に託すということの重さを、読んでいて強く感じましたね。
高校生たちも最初は戸惑っていたけれど、だんだんと責任の重さを理解していく過程が丁寧に描かれていて、読者としても一緒に成長していく気持ちになりました。
この作品を読んで、私たち大人も戦争の記憶を次世代に伝える責任があることを改めて実感しています。
『平和のバトン』は確実に読者の心に残る作品だと断言できますよ。
※『平和のバトン』の読書感想文の書き方と例はこちらにまとめています。

『平和のバトン』の作品情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作者 | 弓狩匡純(著) 広島平和記念資料館(協力) |
| 出版年 | 2019年 |
| 出版社 | くもん出版 |
| 受賞歴 | 特定の受賞歴はなし(平和教育関連の注目作) |
| ジャンル | 児童書、ノンフィクション、平和学 |
| 主な舞台 | 広島市、広島平和記念資料館、広島市立基町高校 |
| 時代背景 | 現代(2010年代後半) |
| 主なテーマ | 戦争の記憶継承、平和教育、世代間交流 |
| 物語の特徴 | 実話に基づくノンフィクション、教育的価値の高い内容 |
| 対象年齢 | 小学高学年から(13歳以上推奨) |
| 青空文庫収録 | なし |
『平和のバトン』の主要な登場人物と簡単な説明
『平和のバトン』に登場する主要な人物や団体について、以下の表で整理しておきますね。
実話に基づいているため、個人名よりも集団や役割での紹介が中心となります。
| 人物・団体 | 説明 |
|---|---|
| 広島市立基町高校の高校生たち | 本書の中心人物で美術を学ぶ高校生グループ。 被爆者の証言を受けて 「原爆の絵」を描く活動に取り組む |
| 被爆体験証言者たち | 広島で被爆しその体験や記憶を 高校生に語る高齢の被爆者たち。 自分たちの記憶を次世代に伝えるべく 勇気をもって体験を共有する |
| 弓狩匡純 | 作家・ジャーナリスト。 高校生と被爆者の交流を密に取材し 『平和のバトン』を執筆した |
| 広島平和記念資料館 | 活動の依頼者として証言者の記憶を 記録する場や支援者として登場 |
これらの人物や集合体が中心となって、戦争や原爆の記憶を次世代に伝える取り組みを描いています。
『平和のバトン』の読了時間の目安
『平和のバトン』を読むのにかかる時間について、以下の表でまとめておきますね。
読書感想文を書く予定がある人は、スケジュールの参考にしてください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 総ページ数 | 160ページ |
| 推定文字数 | 約96,000文字 |
| 読了時間(集中して読んだ場合) | 約3時間12分 |
| 1日1時間読書の場合 | 約3〜4日で読了 |
| 週末にまとめて読む場合 | 1日で読了可能 |
『平和のバトン』は児童書ということもあり、比較的読みやすい文章で書かれています。
中学生や高校生なら集中すれば一日で読み切ることも十分可能ですよ。
『平和のバトン』はどんな人向けの小説か?
『平和のバトン』は特に以下のような人におすすめできる作品です。
読書感想文を書く予定の学生さんや、平和教育に関心のある人にぴったりの内容となっていますね。
- 戦争や原爆の歴史を若い世代の視点で理解したい人
- 平和教育や社会問題に関心がある学生や教師
- 芸術(絵画)を通して社会問題に取り組む姿勢に興味がある人
一方で、エンターテインメント性を重視する読者や、軽い読み物を求めている人には少し重いかもしれません。
でも、真剣に平和について考えたい人にとっては、非常に価値のある一冊だと思います。
『平和のバトン』と似たテーマの作品2選
『平和のバトン』と同じように戦争や平和をテーマにした作品の中から、特におすすめの2作品を紹介しますね。
どれも若い読者にも読みやすく、深いメッセージが込められた優秀な作品です。
汐見夏衛『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
この作品は戦争の悲惨さと家族や友情の絆を繊細に描いた小説です。
『平和のバトン』と同様に、若い読者にも読みやすい文体で書かれており、戦争の記憶と平和の大切さを伝えています。
特に世代を超えた人間関係の描写が共通しており、戦争体験を現代に生きる私たちがどう受け継ぐべきかという問題意識も似ています。

原民喜『夏の花』
広島で被爆した作家が自身の体験を描いた代表的な作品です。
『平和のバトン』が現代の高校生の視点から被爆体験を扱っているのに対し、『夏の花』は実際の被爆者による直接的な証言文学となっています。
戦争の悲惨さと人間の苦悩を詩的に表現し、平和への願いを深く訴える点で共通しており、併せて読むことで理解がより深まるでしょう。
振り返り
『平和のバトン』のあらすじから感想まで詳しく紹介してきました。
この作品は広島の高校生たちが被爆者の証言を絵に描くプロジェクトを通じて、戦争の記憶を次世代に継承する大切さを描いたノンフィクションです。
簡単なあらすじから詳しい内容、そして私自身の読後感想まで、読書感想文を書く際の参考になる情報をお伝えできたと思います。
160ページと比較的短い作品ながら、平和について深く考えさせられる貴重な一冊ですので、ぜひ手に取って読んでみてくださいね。
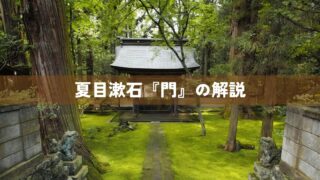
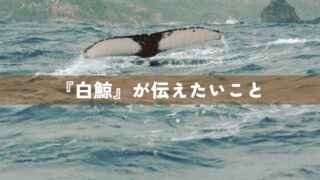
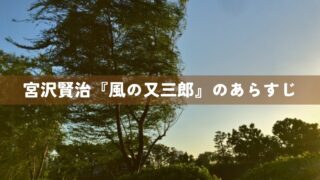
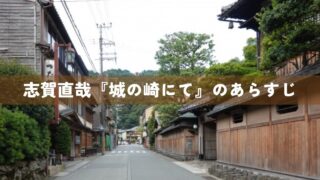



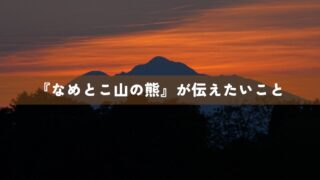
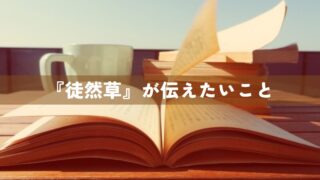

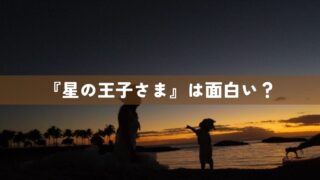
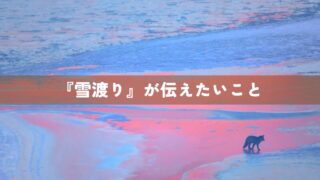






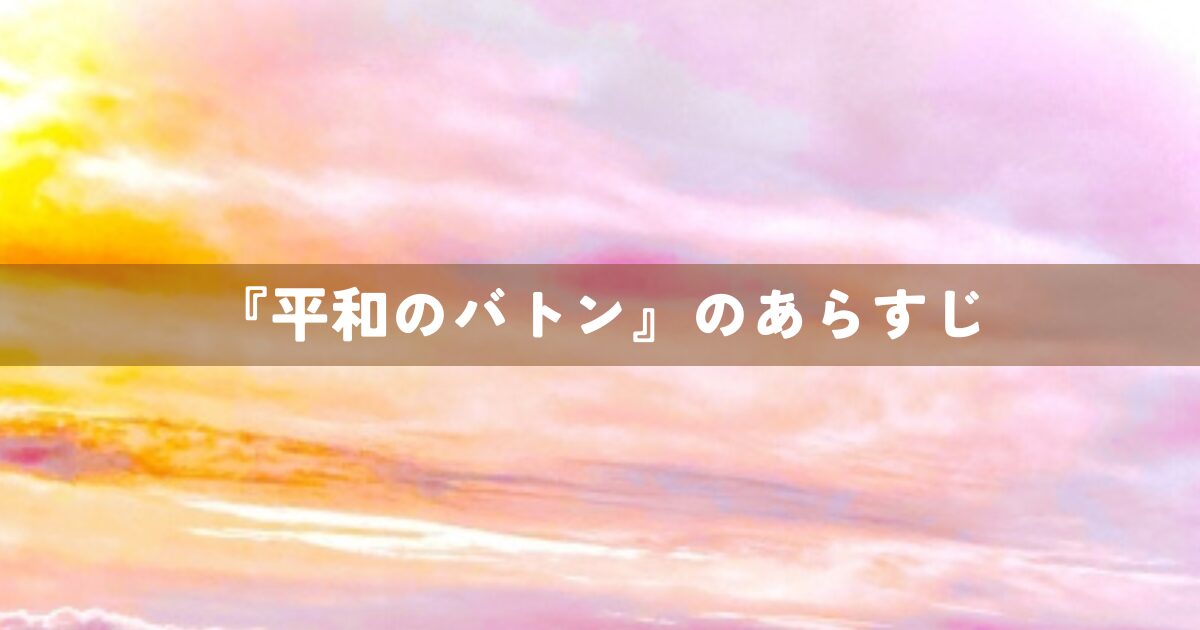
コメント