『ドアのむこうの国へのパスポート』のあらすじを簡単に・短く・詳しく・ネタバレなしでご紹介していきますね。
この作品はオランダの児童文学作家トンケ・ドラフトとリンデルト・クロムハウトによる共著で、2023年に岩波書店から出版された心温まる成長物語です。
特別支援を必要とする子どもたちが、謎のドアの向こうにある不思議な国への旅を通して自己理解を深めていく、深いテーマを持った児童文学。
年間100冊以上の本を読む私が、読書感想文を書く予定の皆さんに向けて、この素晴らしい『ドアのむこうの国へのパスポート』の魅力を余すところなくお伝えします。
作品の核心から登場人物の心情まで、丁寧に解説していきますよ。
『ドアのむこうの国へのパスポート』のあらすじを短く簡単に
『ドアのむこうの国へのパスポート』のあらすじを詳しく(ネタバレなし)
『ドアのむこうの国へのパスポート』のあらすじを理解するための用語解説
物語に登場する重要な用語をわかりやすく解説していきますね。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| コスモポリタン連邦 | ラヴィニアの家にある 閉ざされたドアの向こうに広がる 特別な国たちの集まり。 パスポートとビザがないと 入ることができない不思議な世界。 |
| パスポート・ビザの申請書 | ラヴィニアから送られてくる書類で 子どもたちの成長のきっかけとなる課題。 これに答えることで自分自身や仲間への理解を深めていく。 |
| 手のかかる子どもたち | 物語の舞台となるクラスにいる 特別な支援を必要とする子どもたちのこと。 それぞれが自身の困難と向き合っている。 |
| 閉ざされたドア | ラヴィニアの家にある鍵のかかったドアで 「コスモポリタン連邦」への入口。 子どもたちの精神的成長の象徴として描かれている。 |
これらの用語を押さえることで、『ドアのむこうの国へのパスポート』の象徴的な世界観がより深く理解できるはずです。
『ドアのむこうの国へのパスポート』を読んだ感想
『ドアのむこうの国へのパスポート』を読み終えて、正直に言うとすこし戸惑いました。
児童書らしいファンタジックな導入でありながら、実際にはとても深いテーマを扱った作品だったからです。
でも読み進めるうちに、この作品の本当の魅力がじわじわと心に染み込んできました。
特に印象的だったのは、ラウレンゾーという少年の心の動きですね。
転校生として新しい環境になじめずにいる彼の不安や戸惑いが、とてもリアルに描かれています。
私自身も子どもの頃に転校を経験したので、彼の気持ちがすごく理解できました。
そして何より心を打たれたのが、子どもたちがパスポートとビザの申請書に向き合う場面です。
これが単なる書類ではなく、自分自身と向き合うための手段として使われているのが秀逸でした。
ラウレンゾーが3年前に出て行った父親への手紙を書くかどうか悩む場面では、思わずもらい泣きしそうになりましたよ。
子どもの心の中にある複雑な感情を、これほど丁寧に描いた作品はなかなかありません。
作者のトンケ・ドラフトとリンデルト・クロムハウトは、特別支援を必要とする子どもたちの世界を美化することなく、でも温かい眼差しで描いています。
クラスメイトたちがそれぞれの困難を抱えながらも、お互いを支え合っていく様子がとても自然で、作り物っぽさがまったくないんです。
ただ、正直に言うと理解しにくい部分もありました。
物語の結末、つまり「コスモポリタン連邦」の正体については、子どもによっては期待していたものと違うと感じるかもしれません。
私も最初は「あれ?魔法の世界じゃないの?」と少し肩透かしを食った気分になりました。
でも考えてみると、この作品の真の魅力はファンタジーの部分ではなく、子どもたちの内面の成長にあるんですね。
鏡に映った成長した自分たちの姿を見る場面では、読んでいる私も一緒に成長を実感できたような気がしました。
トム先生の子どもたちへの接し方も素晴らしくて、教育に携わる人にとってもヒントになる作品だと思います。
本を読む時間を大切にする先生の姿勢からは、読書がいかに子どもたちの心を育むかが伝わってきました。
翻訳も西村由美さんの手によるもので、オランダ語の原文の雰囲気を上手く日本語に移していると感じます。
『ドアのむこうの国へのパスポート』は、表面的には児童書ですが、実際には大人が読んでも深く考えさせられる作品でした。
『ドアのむこうの国へのパスポート』の作品情報
『ドアのむこうの国へのパスポート』の基本的な情報をまとめましたよ。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作者 | トンケ・ドラフト、 リンデルト・クロムハウト(共著) リンデ・ファース(絵) 西村由美(訳) |
| 出版年 | 2023年4月27日 (書店発売日2023年5月1日) |
| 出版社 | 岩波書店 |
| 受賞歴 | 情報なし |
| ジャンル | 児童文学、児童書 |
| 主な舞台 | 作家の家、特別支援学校のクラス、コスモポリタン連邦 |
| 時代背景 | 現代 |
| 主なテーマ | 自己理解、仲間との関係、成長 |
| 物語の特徴 | ファンタジー要素を含む現実的な成長物語 |
| 対象年齢 | 小学校中学年から高学年向け |
| 青空文庫の収録 | 収録なし |
『ドアのむこうの国へのパスポート』の主要な登場人物とその簡単な説明
物語に登場する重要な人物たちを紹介しますね。
| 人物名 | 紹介 |
|---|---|
| ラウレンゾー | 小学4年生で物語の主人公。 「手のかかる子どもたち」のための学校に通っている転校生。 活発な性格で、先生が本を読む時間を楽しみにしている。 |
| トム先生 | ラウレンゾーたちの担任の先生。 クラスの子どもたちに本を読んだり 支えたりする優しい教師。 |
| ラヴィニア・アケノミョージョ | 児童文学作家で、謎のドアの持ち主。 子どもたちを家に招待し コスモポリタン連邦について教える。 手紙を通じて子どもたちの成長を導く重要な人物。 |
| テヤ | ラウレンゾーのクラスメイトの一人。 ラヴィニアの家に一緒に招待される。 |
| 大使 | パスポート発行のためにさまざまな質問をする役割。 子どもたちが自己理解を深めるきっかけを作る存在。 |
これらの登場人物が織りなす『ドアのむこうの国へのパスポート』の世界をぜひ楽しんでくださいね。
『ドアのむこうの国へのパスポート』の読了時間の目安
この本をどのくらいの時間で読めるか、目安をお伝えしますね。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ページ数 | 206ページ |
| 推定文字数 | 約123,600文字 |
| 読書時間(500文字/分) | 約247分(約4時間7分) |
| 1日30分読書の場合 | 約8日で完読 |
| 1日1時間読書の場合 | 約4日で完読 |
『ドアのむこうの国へのパスポート』は児童書なので比較的読みやすく、集中すれば一日で読み切ることも可能です。
読書感想文を書く予定なら、じっくりと味わいながら読むのがおすすめですよ。
『ドアのむこうの国へのパスポート』はどんな人向けの小説か?
この『ドアのむこうの国へのパスポート』は、特に以下のような人におすすめします。
- 自分の気持ちや個性について考えたい小学生から中学生の子どもたち
- 学校生活や友人関係で悩みを抱えている子どもとその保護者
- 教育現場で子どもたちの成長を支援したい先生や教育関係者
特に自己理解や仲間との関係を深めたいと思っている子どもには、きっと心に響く作品になるでしょう。
ただし、わくわくするような冒険ファンタジーを期待している読者には、少し物足りなく感じるかもしれません。
この作品の真の魅力は、子どもたちの内面の成長にあるのです。
あの本が好きなら『ドアのむこうの国へのパスポート』も好きかも?似ている小説3選
『ドアのむこうの国へのパスポート』が気に入った方には、以下のような作品もおすすめですよ。
どれも自己発見や成長をテーマにした、心温まる物語です。
『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治)
主人公のジョバンニが親友のカムパネルラと夜の銀河鉄道で旅をする幻想的な物語。
命や友情の意味、他者のために生きる「ほんとうの幸い」をめぐる自己発見の名作です。
『ドアのむこうの国へのパスポート』と同じく、不思議な世界への旅を通して主人公が成長していく点で共通しています。
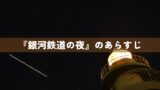
『霧のむこうのふしぎな町』(柏葉幸子)
一人旅に出た少女リナが、霧の谷の不思議な町で人々や出来事に出会い、自分と向き合いながら成長していくファンタジー。
映画『バースデー・ワンダーランド』の原作にもなった作品です。
主人公が不思議な世界で自分自身を見つめ直す構造が、『ドアのむこうの国へのパスポート』と非常によく似ています。
『コロボックル物語1 だれも知らない小さな国』(佐藤さとる)
コロボックルという小さな人々と人間の交流を優しく描いた日本ファンタジーの古典。
主人公の少年が秘密の世界に足を踏み入れて成長していく物語です。
特別な世界への入口という設定や、子どもの純粋な心が描かれている点で、『ドアのむこうの国へのパスポート』と共通する魅力を持っています。
振り返り
『ドアのむこうの国へのパスポート』は、表面的にはファンタジーでありながら、実際には子どもたちの心の成長を丁寧に描いた深い作品でした。
特別支援を必要とする子どもたちの世界を温かく描き、自己理解と仲間との関係の大切さを教えてくれる素晴らしい児童文学。
読書感想文を書く際は、ラウレンゾーの心の変化や、パスポート申請という課題が持つ象徴的な意味に注目すると、きっと深い感想が書けるはずです。
この記事が皆さんの読書体験のお役に立てれば嬉しいですね。
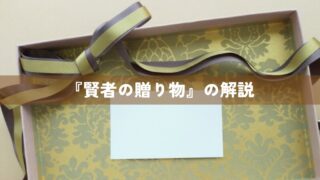


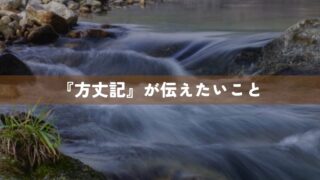
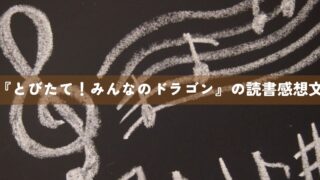


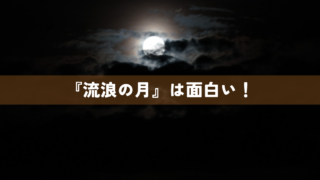
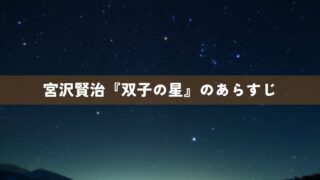





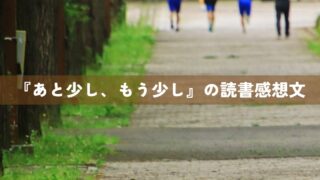


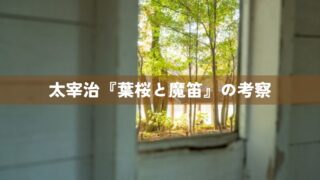
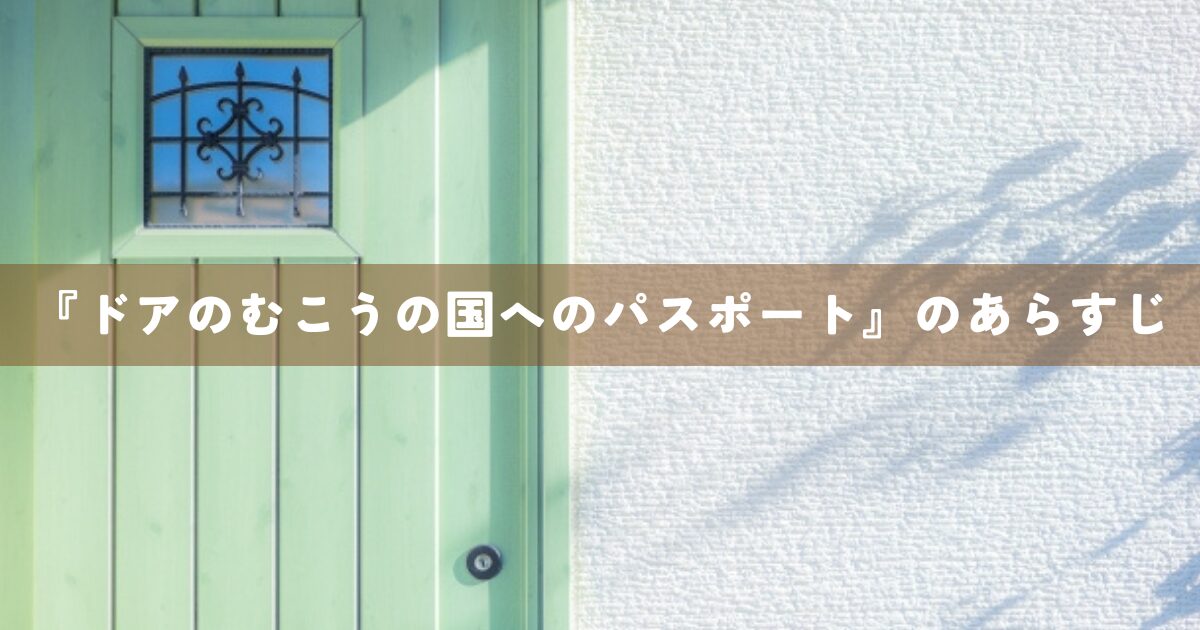
コメント