読書が大好きで年間100冊以上の本を読む私が、今回は世界文学の傑作のひとつ『フランケンシュタイン』についてご紹介します。
この作品はイギリスの作家メアリー・シェリーが1818年に発表した小説。
多くの人が誤解している「フランケンシュタイン」という名前は実は怪物ではなく、その創造主である「科学者の名前」なんですよ。
読書感想文を書く予定の皆さんのお役に立てるように、簡単なあらすじから詳しいあらすじまで、登場人物の紹介や読書感想文を書く際のポイントなど、たっぷりと解説していきますね。
それではさっそく『フランケンシュタイン』の世界に飛び込んでいきましょう!
『フランケンシュタイン』の簡単なあらすじ
『フランケンシュタイン』の中間の長さのあらすじ
『フランケンシュタイン』の詳しいあらすじ
北極探検中の船長ロバート・ウォルトンは、氷原で衰弱したヴィクター・フランケンシュタインを救助する。死を目前にしたフランケンシュタインは、自らの壮絶な人生をウォルトンに語り始めた。
スイスの裕福な家庭に生まれたフランケンシュタインは、自然科学に魅了されてインゴルシュタット大学で学ぶ。彼はパーツを組み合わせて新たな生命を創造する実験に没頭し、ついに成功を収める。しかし生み出された怪物はあまりにも醜く、恐怖したフランケンシュタインは逃げ出してしまう。
捨てられた怪物は独学で言葉を覚え、思考し、感情を持つようになるが、その醜い外見から人間社会に受け入れられず深い孤独に苦しむ。怪物は創造主に伴侶となる女性の怪物を作るよう要求するが、フランケンシュタインはさらなる災いを恐れて拒否。復讐を誓った怪物はフランケンシュタインの弟や親友、そして新婚の妻までも手にかけてしまう。
絶望と怒りに駆られたフランケンシュタインは怪物を追って北極まで追跡するが、極寒の地で力尽きてウォルトンに救助されたのだった。物語の最後、フランケンシュタインの死を知った怪物は深い後悔と悲しみを表し、自らも薪の山で我が身を燃やすと宣言して北極の闇へと消えていった。
『フランケンシュタイン』の概要
『フランケンシュタイン』の詳細情報をまとめました。
この小説がどのような背景で書かれ、どんな特徴を持っているのか、ひと目で分かりますよ。
| 作者 | メアリー・シェリー |
|---|---|
| 出版年 | 1818年(初版)、1831年(改訂版) |
| 受賞歴 | 特になし(ただし文学史上の重要作品として評価されている) |
| ジャンル | ゴシック小説、ロマン主義小説、SF小説 |
| 主な舞台 | スイス(ジュネーヴ)、ドイツ、イギリス、北極海 |
| 時代背景 | 18世紀末〜19世紀初頭(産業革命と科学の発展期) |
| 主なテーマ | 科学と倫理、創造と責任、孤独と疎外、自然と人工 |
| 物語の特徴 | 書簡体小説の形式を取り、入れ子構造の語りで展開する |
| 対象年齢 | 高校生以上(複雑なテーマと描写を含むため) |
『フランケンシュタイン』の主要な登場人物とその簡単な説明
『フランケンシュタイン』には魅力的な登場人物がたくさん登場します。
物語を理解するうえで特に重要な人物たちをご紹介しますね。
キャラクターの関係性を把握すると、小説がより深く理解できますよ。
| 人物名 | キャラクター紹介 |
|---|---|
| ヴィクター・フランケンシュタイン | スイス人の若き科学者。生命の謎を解明し「理想の人間」を創造するが、その結果に責任を持てず逃げ出してしまう |
| 怪物 | フランケンシュタインが創造した存在。知性と感受性を持つが、その醜い外見から社会から拒絶され、深い孤独に苦しむ |
| ロバート・ウォルトン | 北極探検家。フランケンシュタインを救助し、彼の物語を聞く語り手の一人 |
| エリザベス・ラヴェンツァ | フランケンシュタインの義妹であり婚約者。純粋で優しい女性 |
| アルフォンス・フランケンシュタイン | ヴィクターの父親。家族思いの人格者 |
| ヘンリー・クラーヴァル | ヴィクターの親友。文学と自然を愛する青年 |
| ウィリアム・フランケンシュタイン | ヴィクターの末の弟。 |
| ジュスティーヌ・モーリッツ | フランケンシュタイン家の使用人。 |
| ド・ラセーの一家 | 怪物が隠れて観察し、言語や感情を学ぶきっかけとなる家族 |
| マーガレット・サヴィル | ウォルトンの姉。ウォルトンの手紙の受取人 |
これらの登場人物たちがそれぞれの思いを抱えながら、物語の中で複雑に絡み合っていきます。
特に主人公のフランケンシュタインと彼が創造した怪物との関係性が、この物語の核心となっていますよ。
『フランケンシュタイン』の文字数と読むのにかかる時間(読了時間)
『フランケンシュタイン』を読む前に、どのくらいの時間がかかるのか気になりますよね。
ここでは文字数と読了時間の目安をまとめました。
自分のペースで計画的に読むための参考にしてくださいね。
| 文字数 | 約195,000文字 |
|---|---|
| 読了時間の目安 | 約6.5時間(1分あたり500文字で計算) |
| 1日2時間読んだ場合 | 約3日で読み終える計算 |
| 難易度 | やや高め(哲学的な内容と複雑な構成のため) |
実際の読書スピードは人によって異なりますので、あくまで目安としてください。
じっくりと考えながら読みたい本なので、余裕を持ったスケジュールで読むことをおすすめします。
『フランケンシュタイン』の読書感想文を書くうえで外せない3つの重要ポイント
読書感想文を書く際には、作品の本質に迫るポイントを押さえることが大切です。
『フランケンシュタイン』は深いテーマを持つ作品なので、以下の3つの重要ポイントを中心に考察すると、説得力のある感想文が書けますよ。
- 科学技術の発展と倫理的責任の問題
- 孤独と愛情の必要性
- 外見による偏見と内面の価値
それでは、この3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
科学技術の発展と倫理的責任の問題
『フランケンシュタイン』の中心テーマの一つは、科学技術の進歩がもたらす倫理的な問題。
ヴィクター・フランケンシュタインは科学への情熱から、新たな生命を創造することに成功します。
しかし、彼はその成功に恐れをなし、自らの創造物に対する責任を放棄してしまいます。
この物語は、科学技術の発展それ自体は素晴らしいことですが、そこに倫理的な判断が伴わないと悲劇を招く可能性があることを強く示唆していますね。
フランケンシュタインは「できること」と「すべきこと」の違いを考えずに行動し、その結果、取り返しのつかない事態を引き起こしました。
現代社会では、AI技術や遺伝子操作など、人間の能力を超えるような科学技術が次々と生まれています。
こうした技術の発展に対して、私たちはどのような倫理観を持つべきなのか。
『フランケンシュタイン』は約200年前に書かれた小説ですが、現代の私たちにも深い問いかけをしているのですね。
感想文では、フランケンシュタインの行動と現代の科学技術の発展を結びつけて考察すると、説得力のある内容になりますよ。
孤独と愛情の必要性
『フランケンシュタイン』のもう一つの重要なテーマは、孤独と愛情の必要性。
怪物は生まれた瞬間から創造主に拒絶され、その後も醜い外見から人間社会に受け入れられることはありませんでした。
物語の中で怪物は次第に言葉を覚え、思考し、感情を持つようになります。
彼は人間の家族を密かに観察しながら、愛情や絆の大切さを学びます。
しかし、自分自身はそうした愛情を得ることができず、深い孤独に苦しむことに……。
怪物が最終的に復讐に走ったのは、単なる悪意からではなく、愛情と理解を求めても拒絶され続けた絶望からでした。
彼が創造主に求めたのは、自分と同じ姿を持つ伴侶—つまり、孤独を分かち合える存在でした。
この側面から、人間にとって愛情や理解がいかに重要であるか、また孤独が人の心をどのように変えてしまうかについて考察することで、読者の共感を得られる感想文になるでしょう。
外見による偏見と内面の価値
『フランケンシュタイン』の三つ目の重要なテーマは、外見による偏見と内面の価値。
怪物は恐ろしい外見を持っていますが、その内面は知性と感受性に富んでいました。
彼は文学を学び、美しい自然に感動し、人間の家族の絆に憧れる繊細な心を持っていたのです。
しかし、人々は彼の醜い外見だけを見て、内面を知ろうとはしませんでした。
怪物が最初に親切にした少女さえも、彼の姿を見た瞬間に恐怖で逃げ出してしまいます。
この経験が、怪物の心に深い傷を残していきました。
この物語は、私たちが他者を外見だけで判断することの危険性と、内面の価値を理解することの大切さを教えてくれます。
現代社会でも、外見や第一印象で人を判断しがちな傾向がありますが、本当に大切なのは内面ではないでしょうか。
感想文では、怪物の悲劇的な運命と私たちの日常における「見た目」の影響について関連づけて考察すると、読み手に新たな気づきを与える内容になるでしょう。
※『フランケンシュタイン』が伝えたいことは、以下の記事で考察しています。

『フランケンシュタイン』の読書感想文の例(原稿用紙4枚/約1600文字)
私は今回メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を読んだ。この小説は1818年に書かれたとは思えないほど現代的なテーマを持っていて、読み進めるうちにどんどん引き込まれていった。最初は単なるホラー小説かと思っていたが、実際には科学の倫理、人間の本質、孤独の苦しみなど、深いテーマを扱った作品だった。
まず驚いたのは、多くの人が「フランケンシュタイン」を怪物の名前だと勘違いしていることだ。実際には科学者の名前であり、彼が作り出した怪物には名前すら与えられていない。この「名前がない」という設定自体が、怪物の孤独と疎外感を象徴していると感じた。
物語の中で一番心に残ったのは、怪物の孤独だ。彼は生まれた瞬間から創造主に拒絶され、その後も社会から排除され続ける。怪物が森の中で一家を観察しながら言葉や感情を学んでいく場面は特に印象的だった。彼らの温かさに触れながらも、自分はその輪の中に入れないという現実。その描写を読んでいると、胸が締め付けられるような気持ちになった。
「人は見た目が9割」なんて言葉があるけど、この物語はまさにそれを批判している。怪物は知性があり、感受性も豊かで、最初は善良な心を持っていた。それなのに、その醜い外見だけで人々は彼を拒絶する。もし誰かが彼の内面を見ようとしていたら、物語は全く違う展開になっていたかもしれない。これは現代の私たちにも当てはまる問題で、SNSの普及で外見がより重視される社会になっているからこそ、考えさせられた。
もう一つ考えさせられたのは、科学技術の発展と倫理の問題だ。フランケンシュタインは「できること」と「すべきこと」の違いを考えずに行動し、その結果、取り返しのつかない悲劇を招いた。今の時代、AI技術や遺伝子操作など、人間の能力を超えるような科学技術が次々と生まれている。こうした技術の発展に対して、私たちはどのような倫理観を持つべきなのか。200年前に書かれた小説が、現代の問題にもつながっていることに驚いた。
物語の中でフランケンシュタインが怪物を作った後、責任から逃げ出す場面がある。彼は自分の創造物に恐れをなし、放棄してしまう。この行動は「フランケンシュタイン・コンプレックス」と呼ばれるようになったと聞いた。これは創造主が自分の創造物を恐れ、拒絶することを意味する。親が子どもに対して抱く感情や、最近のAI技術に対する恐れなども、この概念で説明できるのかもしれない。
この物語を読んで特に考えさせられたのは「責任」の重さだ。フランケンシュタインは生命を創造することには成功したが、その後の責任を果たせなかった。もし彼が怪物を受け入れ、教育し、社会に適応できるよう導いていたら…。そう考えると、私たち一人一人が持つ「責任」について改めて考えさせられる。自分の行動の結果に対して、どこまで責任を持つべきなのか。
また、作者のメアリー・シェリーがこの小説を書いたのは19歳の時だと知って驚いた。若い女性が当時の男性中心の文学界で、こんな深遠なテーマを扱った作品を書いたことに感銘を受けた。彼女自身の人生も波乱に満ちていたらしく、そうした経験が作品に反映されているのかもしれない。
『フランケンシュタイン』は200年以上前に書かれた小説だが、その問いかけは現代にも通じるものがある。科学技術の発展と倫理、外見と内面の価値、孤独と愛情の必要性など、普遍的なテーマを持つ作品だ。読み終えた今でも、怪物の最後の言葉が頭から離れない。彼は息を引き取った創造主の前で自らの運命を嘆き、北極の氷の上で自ら命を絶つ決意をする。その姿には悲しさと同時に、どこか崇高さも感じられた。
この物語は単なるホラー小説ではなく、人間の本質や社会の問題を深く掘り下げた作品だ。古典文学に興味がなかった私でも、引き込まれるほどの魅力を持っていた。これからも、こうした深いテーマを持つ古典作品に触れていきたいと思う。
『フランケンシュタイン』はどんな人向けの小説か
『フランケンシュタイン』は単なるホラー小説ではなく、深い哲学的テーマを持つ作品です。
どんな人にこの小説をおすすめできるか、考えてみました。
- 科学技術の発展と倫理について考えたい人
- 人間の本質や内面と外見の関係について興味がある人
- 孤独や疎外感といったテーマに共感できる人
- ゴシック小説やロマン主義文学に興味がある人
- SFの源流となった作品を読みたい人
- 現代社会の問題を古典文学を通して考えたい人
『フランケンシュタイン』は200年以上前に書かれた作品ですが、その問いかけは現代にも通じるものがあります。
科学技術の進歩に対する警鐘や、人間の内面の価値についての考察など、普遍的なテーマを持っています。
特に、AIや遺伝子操作などの最先端技術が進化する現代において、「できること」と「すべきこと」の境界について考えるきっかけになるでしょう。
この小説は読者に深い思索を促す力があるんですよ。
『フランケンシュタイン』と類似した内容の小説3選
『フランケンシュタイン』が提起するテーマは現代文学にも大きな影響を与えています。
同様のテーマを扱った作品を知ることで、より深く『フランケンシュタイン』の意義を理解できるでしょう。
ここでは、類似したテーマを持つ小説を3つご紹介します。
『モロー博士の島』by H.G.ウェルズ
H.G.ウェルズの『モロー博士の島』は、孤島で動物を人間に改造する実験を行う科学者モロー博士の物語です。
この作品も科学の倫理的境界に挑戦し、科学者の責任を問うている点で『フランケンシュタイン』と共通しています。
モロー博士の創り出した獣人たちも、フランケンシュタインの怪物のように、自分たちの存在の意味や創造主への疑問を抱えています。
科学の名のもとに行われる残酷な実験と、その結果生まれた存在の苦悩を描いた作品で、『フランケンシュタイン』と同様、科学の進歩に警鐘を鳴らしています。
『未来のイヴ』by ヴィリエ・ド・リラダン
19世紀末にフランスで書かれた『未来のイヴ』は、「アンドロイド」という言葉が初めて使われた作品として知られています。
エジソン(実在の発明家をモデルにしています)が、友人のために理想的な女性アンドロイドを作り出すという物語。
人工的に創られた美しい女性アンドロイドとそれを創造する科学者の関係性は、『フランケンシュタイン』と通じるものがあります。
特に、人間の感情や魂を機械に宿すことの可能性と限界について考察している点が類似しています。
人工生命の創造というテーマで『フランケンシュタイン』の系譜に連なる作品と言えるでしょう。
『ボッコちゃん』by 星新一
日本の作家・星新一の短編集『ボッコちゃん』に収録されている表題作は、バーテンダーとして働くアンドロイド「ボッコちゃん」の物語。
人間そっくりなボッコちゃんは、プログラミングされた通りに行動しますが、それが思わぬ結果を招くという展開は、創造されたものが創造主の意図を超えて独自の行動をとる『フランケンシュタイン』と共通するテーマを持っています。
短編ながらも人工知能や人造人間が持つ可能性と危険性を鋭く描いており、『フランケンシュタイン』が提起した問題が現代にも続いていることを示す作品です。
振り返り
『フランケンシュタイン』は200年以上前に書かれた小説ですが、その深いテーマ性はいまだに私たちの心に響きます。
科学技術の発展と倫理、孤独と愛情の必要性、外見による偏見と内面の価値など、現代社会でも議論される普遍的なテーマが詰まった作品ですね。
読書感想文を書く際には、ぜひ本記事で紹介した3つの重要ポイントを中心に、自分なりの考察を加えてみてください。
また、『フランケンシュタイン』の真の恐ろしさは、怪物そのものではなく、責任から逃げ出した科学者の行動や、愛情を求めてもかなわない怪物の絶望など、人間の心の闇にあるのかもしれません。
メアリー・シェリーがわずか19歳でこの傑作を書いたことも驚きですが、彼女自身の複雑な人生経験が作品に反映されていると考えると、より深く作品を理解できるでしょう。
この記事が『フランケンシュタイン』を理解する手助けとなり、読書感想文を書くきっかけになれば幸いです。良い読書体験を!
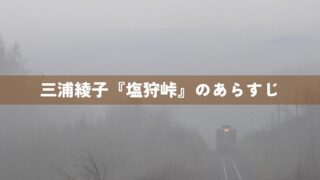


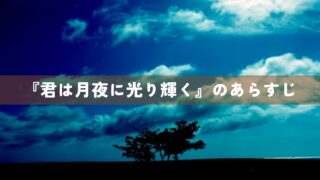
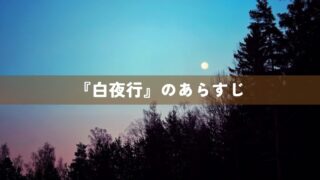


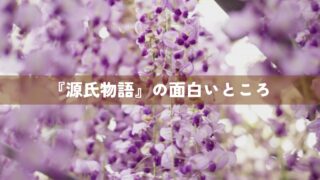

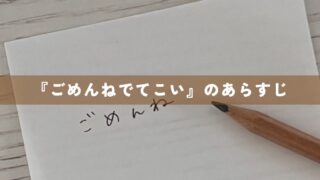

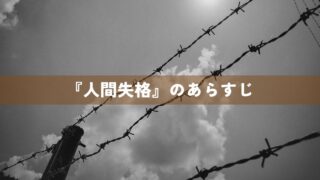

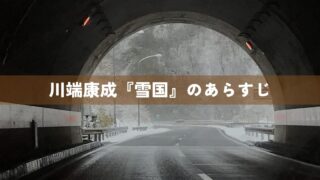
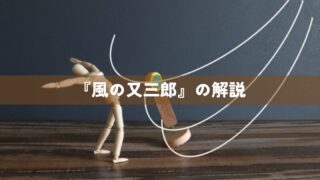



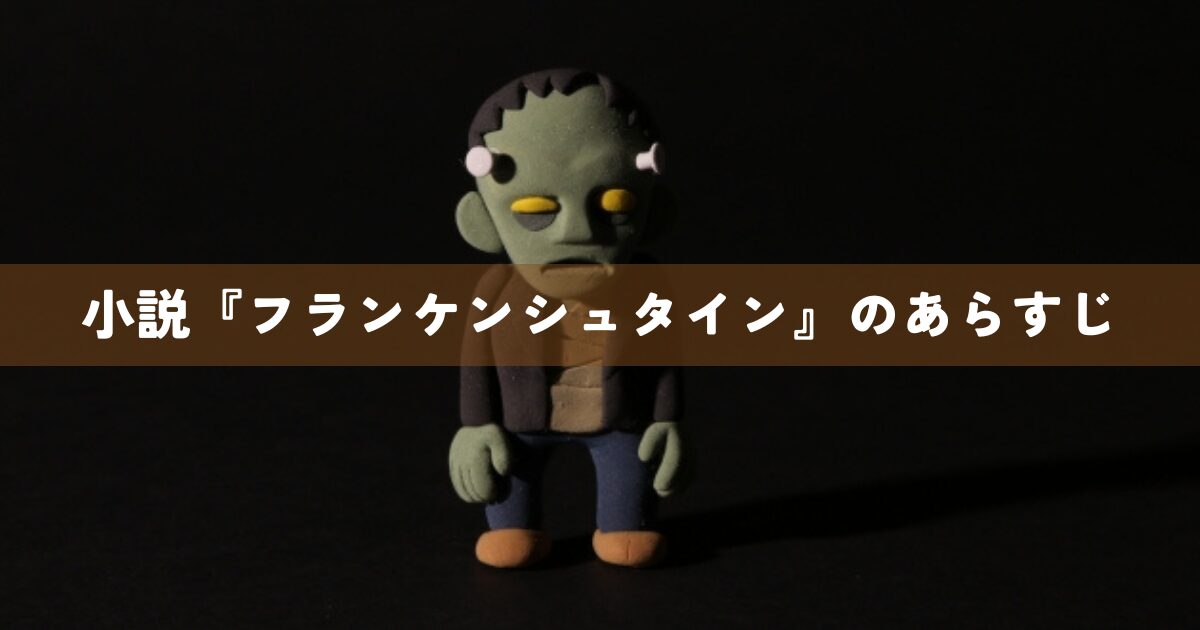
コメント